習近平はなぜ、独裁体制を確立できたのか?「腐敗撲滅運動」に隠された野望
精神上の支配においても「教祖様」に
こうしたなかで2017年10月、共産党第19回党大会が開催されたが、この大会は結局、習近平の個人独裁体制を確立するための重要会議となった。
まず、この党大会では党の規約が改定され、習近平の名前を冠とする「習近平思想」なるものが新しい規約に盛り込まれて、マルクス主義や毛沢東思想と並べて中共政権の指導的思想理念として掲げられた。
これで習近平は、たんなる政治上の独裁者として政権に君臨するのではなく、思想上・精神上の支配においても共産党の「教祖様」となった。その一方、党の最高指導部である共産党政治局は習近平派によって固められることとなった。
19回党大会閉幕の翌日、共産党中央委員会の第19期1中全会が開催され、党中央政治局員のメンバーが選出された。新しい政治局のメンバー25人のうち、新任されたのは15人であるが、そのうち、いわゆる習近平の子分、中国語でいう「習家軍」は私が数えたところでは9人であり、その多くがかつての部下・幼馴染み・同級生で占められていた。
その結果、25名からなる政治局には、留任の習近平派を含めて習の子分・お友だちが12名となっている。それに対して、共産党前総書記の胡錦濤が率いる胡錦濤派(すなわち共産主義青年団派)は3名、他の10名はいずれも派閥色のない一匹狼のような存在で、何の政治勢力も成していない。
四人組どころではなく「十一人組」
このように、習近平派は政治局において圧倒的な勢力をもつ派閥となっており、共産党政治局はある意味で、習近平の側近や取り巻きによって乗っ取られている状況といえる。独裁体制の中国共産党の歴史上においても、それはまさに前代未聞の異常事態なのである。
党中央政治局における習近平派が12人も占めるような状況は、じつは現代中国の「初代皇帝」であり、絶対的個人支配を誇った毛沢東の時代ですらなかった。毛沢東時代の大半を通して、党主席の毛沢東自身は絶大な権威と権力を持ちながらも、党内の力関係においてはライバル派閥の劉少奇派や周恩来派がおり、毛沢東の権力をつねに牽制している状況であった。
中央指導部が毛沢東派一辺倒となったのは、1966年からの文化大革命で劉少奇一派が一掃されたあとである。当時、共産党政治局には毛沢東の妻や側近である江青、張春橋(ちょう しゅんきょう)、王洪文、姚文元(よう ぶんげん)が入り、毛沢東の側近政治を支える「四人組」を形成していた。
しかし今、政治局のなかの習近平派は四人組どころではなく、「九人組」あるいは習近平を除いた「十一人組」となっているのである。しかも実績があって昇進したのではなく、習近平の友人や子分だから抜擢されたことは明らかだ。今の習近平はかつての毛沢東以上の側近政治をほしいままに行ない、中国共産党は半ば「習近平の党」となっている有様である。
本書が刊行された2022年はちょうど、辛亥革命による清王朝皇帝退位から110周年の節目の年である。しかしよく考えてみれば、この110年にわたる中国の近現代史はしょせん、毛沢東や習近平のような「新皇帝」を生み出す歴史にすぎない。
この110年間、中国の経済・文化・社会などでは大きな変貌が起きているものの、政治の根本は一向に変わらない。秦の始皇帝以来の皇帝政治は依然として中国という国を支配しており、中国という国は、旧態依然の「皇帝の時代」からどうしても脱出できないままである。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月04日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 習近平の「暗殺未遂数」は歴代トップクラス
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- 「トランプは中国との関係改善を望んでいる」 米中関税戦争の休戦に合意した理由

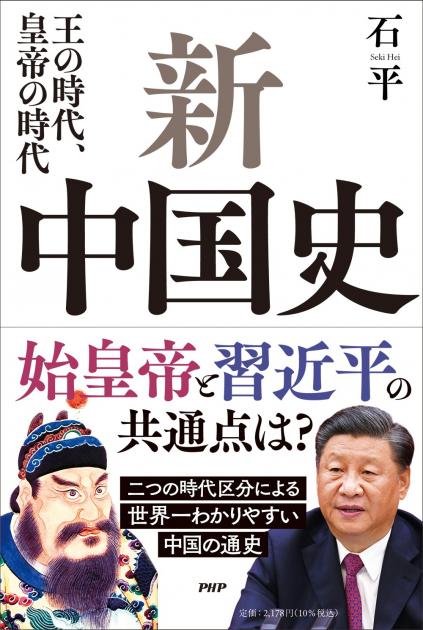

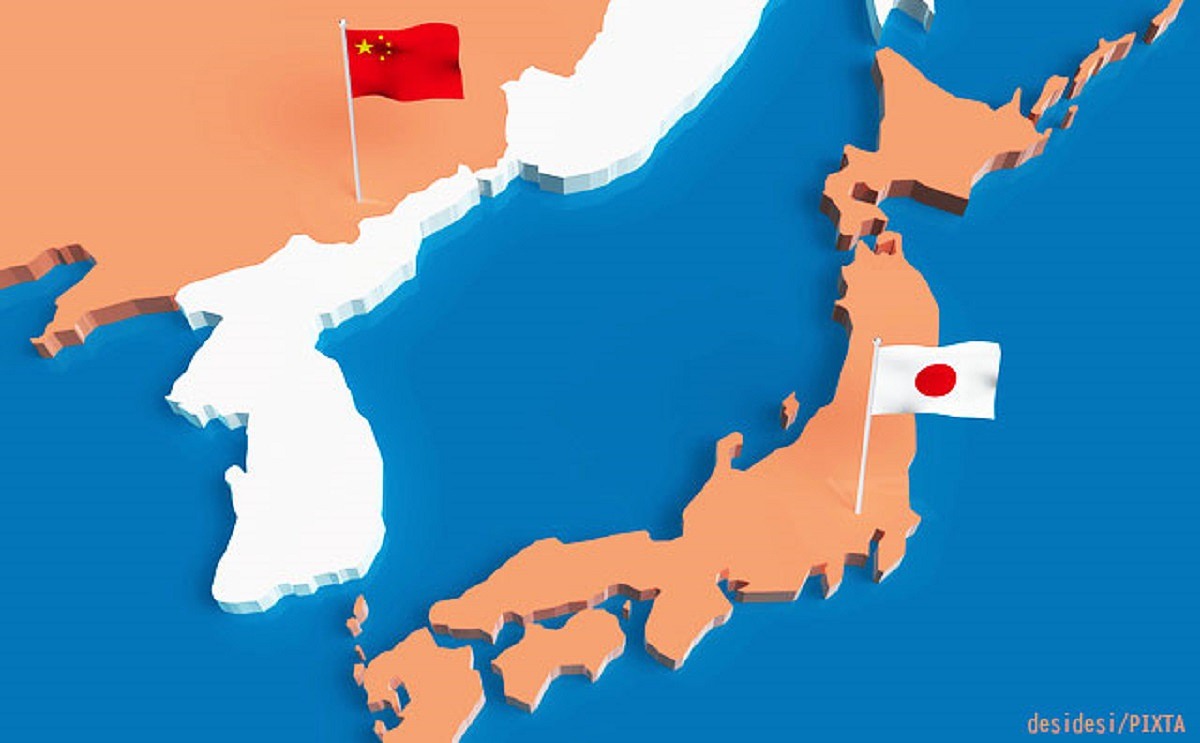

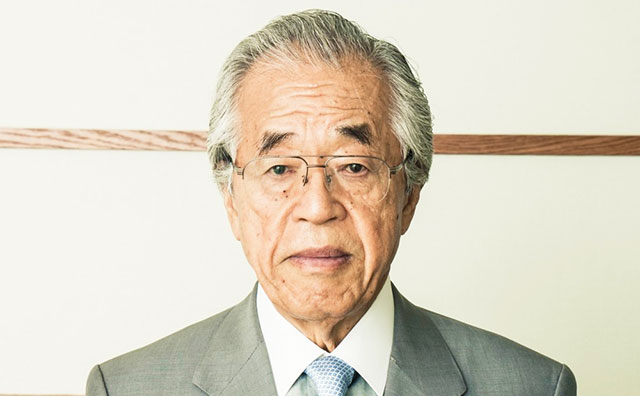

.jpg)
