「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
2018年08月09日 公開
2024年12月16日 更新
2018年7月6日朝、オウム真理教の教祖・麻原彰晃と元幹部六人の死刑が執行された。26日に残された6人の死刑が執行され、オウム真理教事件の死刑囚13人全員が処刑されたわけだが、これでオウム真理教事件が終わったわけではない。
いまだ解決されない多くの謎が残されており、またオウム復活の兆候も見え隠れしているというのだ。平成最大の国内テロ事件といわれる、オウム事件の首謀者麻原彰晃とは一体何者だったのか? 当事件の真相に迫る一橋文哉著『オウム真理教事件とは何だったのか?』が、PHP新書から7月末に緊急発刊されたので、その内容から一部を抜粋して紹介したい。
麻原彰晃、死す!
あの男が、ついに死んだ。
たとえ、どんな目に遭わされようとも、絶対に死ぬことなどないと思われた「怪物」のような男だっただけに、俄には信じられない思いもする。
あの男とは、麻原彰晃(本名・松本智津夫)。一九八四年二月、「オウムの会(後にオウム神仙の会)」として設立し、八七年七月に「オウム真理教」に改称した教団の教祖として、また八八年頃から信者殺害・遺体焼却を皮切りに、坂本堤弁護士一家拉致・殺害、そして松本サリン、地下鉄サリン……など一連のテロ事件の首謀者として暗躍した人物である。
九五年五月に逮捕された麻原は、元教団幹部十二人とともに死刑判決を言い渡され、後に死刑が確定。二〇一八年七月六日、麻原と元幹部六人の死刑が執行されたのだ。
その日、麻原はいつもの通り午前七時(土・日曜日は七時半)に起床した。
通常は午前七時十五分に点検(刑務官が死刑囚の様子を見回る作業)を受けた後、同二十五分に朝食、同十一時五十分に昼食、午後四時二十分に夕食が配膳され、あっと言う間に食べ終えて午後四時四十分に点検を受けると、後は何もやることがない。消灯時間は午後九時だが、死刑囚の中には午後五時を過ぎたら早々と横になる者もいるらしい。
身体をほとんど動かさないため、毎日のように四十分前後、厳重に塀と金網が張り巡らされた狭いスペースで刑務官の監視を受けながら、一人で体操したり縄跳びしたりする戸外活動時間があるし、希望すれば軽作業をさせてもらえ、わずかばかりだが報酬を得て、自分の衣類や菓子などを買える。入浴は週二回(夏は三回)で、入浴時間は十五分ながら単独で入ることができる。
暇を持て余すとろくなことを考えないので、本を借りて読んだり、毎週一、二回の割合で大河ドラマや歌番組、映画のVTRなどのテレビ鑑賞をすることも可能だ。
かつては一度に大勢の死刑囚に死刑を執行する集団処遇の時期があり、一九一一(明治四十四)年に大逆事件で一度に十二人の死刑が執行されたり、一九一五(大正四)年の年間九十四件を筆頭に、年五十件以上の死刑執行が当たり前のように行われていた。
戦後に入っても一九五七(昭和三十二)年と一九六〇(昭和三十五)年の三十九件をはじめ二十~三十件の執行が続いたが、一九七七(昭和五十二)年以降はヒトケタの執行が続き、一九九〇~九二年は三年連続で一件も執行されなかった。
その結果、死刑囚が拘置所に入所してから刑が執行されるまでの期間は十五~二十年と長くなった。
そのため確定死刑囚もそう毎日ビクビクしながら生活しなくてもいいはずなのだが、いつお迎えが来るか分からない恐怖心は相当に重いもので、朝食が取れなかったり、一睡もできない者も決して少なくない。
以前のように事前に死刑執行を通告したり、家族に連絡が行くことはないのだが、死刑囚たちは刑務官の言動や食事の内容、拘置所内の雰囲気などから、何となく「次は自分だ」と感じ取り、緊張感を高めているようである。刑務官がいつもと違う言動を取ろうものならパニックに陥る死刑囚もいるほどだ。
精神に異常を来たした様子を見せていた(刑務官の中には精神異常者を装っていると見ている者が多いが……)麻原彰晃は、二人の刑務官が両側から腕を取って持ち上げるようにして支えないと、立つこともできない有り様だ。
拘禁反応に加え便秘症状に苦しんでいたが、運動も他の死刑囚と違い、警備担当者四、五人に囲まれ、別の運動場に行き、ほとんど空気を吸うだけで終わる。
入浴も一人ではできず、身体を洗うことはもとより、麻原が備え付けのトイレを使わないため着用させられているオムツの交換を含めて着替えをすることも、すべて刑務官に手伝ってもらわなければ何一つできないのが実情だった。
食欲はあまり落ちていないようだが、体重は激減していてかなり痩せており、精神のバランスを欠いているように見える。何しろ、運動や入浴時間以外は独居房の中でブツブツ言いながら壁にもたれて座り、一日中過ごしているというのだ。
刑務官の日報によると、麻原が呟いている言葉は何かよく分からない梵語のような文言であったり、「ショーコー、ショーコー」と自らの名前を連呼して歌っていることもあるといい、「本当に精神に異常を来したのかと思わざるを得ない素振りだった」(死刑囚舎房担当の刑務官)ようである。
「チクショー。やめろ」
拘置所関係者の話に基づき、六日の様子を再現すると、午前七時半過ぎ、麻原の独居房の出入り口にある窓ごしに、いつもと違う刑務官が「出房だ」と声をかけた。
大抵の死刑囚はこの見慣れぬ顔と声で自分の運命を悟り、顔面を蒼白にしてうなだれながら刑務官の指示に従うか、大声を出したり暴れたりして抵抗するか、いずれもいつもと違う行動に出る。
麻原は二人の刑務官に両腕を抱えられ、「チクショー。やめろ」と叫びながら独居房から出ると、三人の警備担当者に身体を押されるように両側に独居房が並ぶ死刑囚舎房の通路を歩き、長く薄暗い渡り廊下を通って、何の表示も出ていない部屋の前に到着した。
そこで待機していた刑務官二人の手でギギッと妙に響く音を立てて扉が開けられると、その前には分厚いカーテンがかかった狭い通路があり、カーテンに沿って先に進むと急な階段が現れ、上で別の刑務官ら大勢の人が待っている気配が伝わってくる。
ここまで来ると、この先に何があるのか察する死刑囚が多いのだが、麻原はブツブツと小声で何か言うだけで、四人の刑務官に押されるように階段を上がった。
カーテンの下から流れる冷たい風が頬を撫でたか、麻原はブルッと身体を震わせた。実はカーテンの向こう側は刑場の地下室、つまりロープで吊り下がった遺体を処理する場所であり、冷たく血なまぐさい風が吹くのも当然なのかも知れない。
階段を上がった横にある部屋には、五人の男たちが待っていた。
麻原には誰が誰か分からなかったが、正面に拘置所長、その後ろに検事や総務部長ら拘置所幹部がいて、横には祭壇が設けられ、教誨師の僧侶も立っていた。
「松本智津夫君。残念だが、法務大臣から刑の執行命令が来た。お別れだ」
(本稿は、一橋文哉著『オウム真理教事件とは何だったのか?』〈PHP新書〉を一部抜粋、編集したものです)
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月09日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点
- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」
- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景


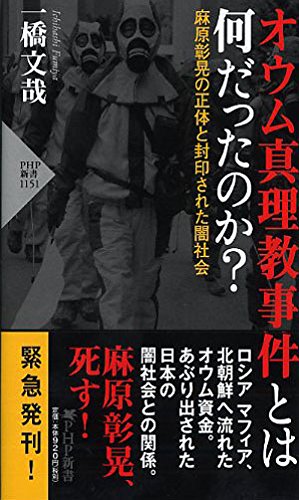



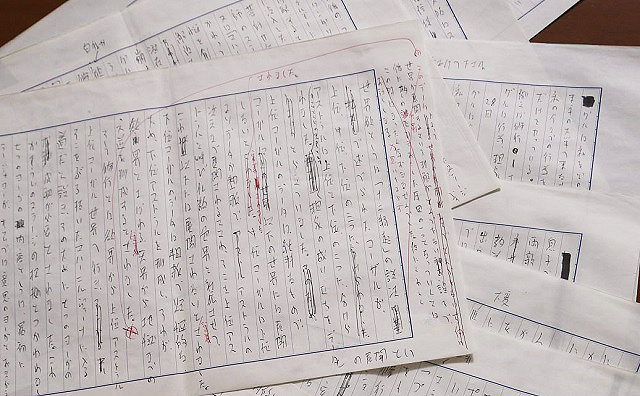

.jpg)
