【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第3回)

米中をはじめとする文明的大国が自己主張を強め、同時にデジタル化やビッグデータを軸にした技術革新が起きているなど、私たちはいま劇的な世界の変化を経験しています。このような状況下では、環境変化の圧力や不確実性に翻弄されるばかりでは十分ではなく、日本のあり様や世界のなかでの位置づけを問い直していく必要があるはずです。
「日本文明研究会(委員:河野有理、藤本龍児、三宅香帆)」では、日本の文明的な性格がいかなるものかを、思想・宗教、文化文芸から家族、組織原理、政治、経済社会にいたるまで多角的な視点で検討し、顕在知として表出していくことをめざします。近代の日本においてリベラル・デモクラシーの政治制度が採用され、定着するに至った、その文明史的な背景について、苅部直氏が4回にわたって概観します。(構成:藤橋絵美子)
日本が「国家」の概念を受容した背景とは
前回、前々回に見てきたような、リベラル・デモクラシーをめぐる議論の現代における動向を念頭に置きながら、近代の日本においてリベラル・デモクラシーの政治制度が採用され、定着するに至った、その文明史的な背景を概観してみましょう。
先にふれたリチャード・タックの議論は、近代に主権国家が登場したとき、それを説明する理論が含んでいた「主権」と「統治」との区別という発想に、新たに光をあてるものでした。そうすると、西洋近代の文化産物である主権国家の概念を、19世紀に日本が受容した基礎にあったものは何か。そのことがまず問題になります。
拙稿「日本が『国家』になったとき」(『アステイオン』90号、2019年5月)で詳しく書いていますが、日本の文化史・思想史においては、主権国家の概念を受け入れやすい素地が、すでに中世からできつつありました。村井章介(『アジアのなかの中世日本』校倉書房、1988年)や黒田日出男(『龍の棲む日本』岩波新書、2003年)の歴史研究が明らかにしたように、日本列島を結ぶ海運の発達を背景として、列島全体を一つの「日本」の空間ととらえ、その外側と区別する意識が、13世紀ごろから庶民にまで広がり、確立しています。当時になって初めて登場した日本の列島全図が、「日本」を取り囲んでその内と外とを区別する境界を、巨大な龍や蛇によって表現しているのが、その好例です。
ただし中世においては、「日本」の内側がすべて均質な空間として思い描かれていたわけではありません。さまざまな地域・都市を結ぶ線が走っているという空間像だったと思われます。これが面として広がった国土のイメージに変わってゆくのは、徳川時代に作られた各地方の「国絵図」によって、広い範囲の空間が画像として描かれるようになったのちのことだと考えられます(新田一郎『中世に国家はあったか』山川出版社、2004年を参照)。
さらに徳川時代には、参勤交代をはじめとする武士の長距離移動や商業の発展によって、全国を結ぶ交通網が発達します。したがって出版文化の隆盛とともに、書物の流通も全国に広がってゆく。文化史家の守屋毅が『村芝居』(平凡社、1988年)で明らかにしたことですが、各地の村で祭のさいに村人たちが上演する芝居の脚本は、全国共通です。つまり、話し言葉は地方によってさまざまであっても、書き言葉や、物語の背景をなす文化的な素養は、庶民まで含めて全国共通のものになっていたのです。
言語の共有によって支えられた、人と情報の交通ネットワークの全国大での確立。この状況を指して、日本は18世紀にはすでに「近代」に突入していたという見解があります(加藤秀俊『メディアの展開』中央公論新社、2015年)。「近代」の定義に関しては異論もあるでしょうが、納得できる説だと思います。
国家を「一つの人体」にたとえる発想
徳川時代の日本においては、列島全体を一つの「日本」という空間としてとらえる意識に加えて、そこに住む日本人が共通の言語と文化を共有しているという感覚も、社会の広い層にわたって共有されていたと思われます。おそらくそうした感覚を基盤として、日本という国の全体を、一つの人体のようにとらえる発想が生まれてきます。
それが明確に現れているのは、水戸学の思想の代表的な著作とされる、會澤正志斎による『新論』(文政8年・1825年執筆)の巻頭にある「緒言」の冒頭の一節です。そこでは、日本は「太陽の出づる所、元気の始まる所(太陽の昇る所、生命の源が発生する所)」であると述べ、これを「大地の元首」と呼び直しています。文字どおり、人間の頭部にあたる国ということになる。さらに、西洋諸国は卑賤な「脛足」「股脛」であるがゆえに海上交通を発達させアジアにまで進出してきたと述べ、アメリカは「背後」すなわち背中にあたると語ります。
つまりこれは、当時に西洋から輸入された両半球世界図で日本が一番東に位置しているのを見て、ユーラシア大陸の全体を一つの人体にたとえているのでしょう。そういう論理で、頭部である日本こそが、世界でもっとも優れて道徳的な国だという自己賛美を基礎づけたのでした。
會澤のこの著作は、「國體」という言葉を強調し、しかもそれを「国のありさま」「国の体面」といった一般的な言葉ではなく、天皇が代々その国を治めており、王朝交代が起こらないという日本独特の特質を示す言葉として意味づけし直すものでした。これが徳川末期に広く読まれて尊王攘夷論の隆盛を支え、「國體」の概念が近代の国民道徳論や治安維持法体制に継承されてゆくのですが、會澤がこの言葉を記したときは、文字どおり「日本の国という人体」の独自の個性という感覚をもっていたのではないでしょうか。
この人体のイメージが、西洋の主権国家の概念を受容するのに役立った。そう見ることもできるでしょう。ホッブズの『リヴァイアサン』は冒頭で、主権国家を巨大な「人工人間(artificial Man)」にたとえていますし、国家を一つの有機体(organization)にたとえるのは、19世紀の西洋思想にしばしば見られる論法です。
そして、「主権」の国法理論を日本に初めて紹介した書物、津田真道による『泰西国法論』(慶應4年・1868年)の第1篇第1章には、「国家は幹なり国民は支なり」という言い回しが見えます。「幹」「支」は木の幹と枝のことでしょうが、人体の体幹と手足も想起させます。また津田は、『明六雑誌』第2号(1874年)に寄稿した「学者職分ノ論」では、より明確に「政府ハ猶精神ノ如ク人民ハ猶体骸ノ如クナリ」と語ります。これは、すでにあった人体としての国家観とつながるものとして、西洋の主権理論を理解し導入した跡ではないでしょうか。
「公論による政治」の意識が早くから定着
19世紀の日本においては、やがて主権理論の受容につながるような、一つの人体としての国家のイメージが育ちつつあった。政治学の用語で言う国家建設(state-building)の日本独特の形と呼ぶこともできるでしょう。しかもこれと並行して、のちに議会制度の受容につながるような政治構想が、西洋思想ではなく朱子学を基盤にして登場したことが重要です。
そうした動向の先駆者と言える思想家が、熊本の朱子学者・横井小楠です。もともと朱子学には、実現すべき「理」について、師と弟子たちとが対等に論じあう「講論」の方法論があり、徳川時代の儒者による私塾や学校では、そうした対等な討論としての「会読」が普及していました。小楠はそれを政治制度に転用し、身分をこえて幅ひろい主体が参加する「公論」を活発に行なうことが、一国における「理」の発見と実践につながると唱えたのでした。
やがてこの発想は、西洋の政治制度に関する知識を得たことによって、徳川末期における議会導入論、すなわち「公議」による政治の提唱へと展開します。
こうした「公論」「公議」による政治という体制構想が、徳川政権と薩摩・長州の両者に受容された結果、明治政府による「公議」機関の設置、さらには府県会、帝国議会の開設へとつながってゆきます。政治決定は「公論」によって行なわれなくてはいけないという方針は、明治政府と自由民権運動とが、ともに最初から共有したものでした(鳥海靖『日本近代史講義』東京大学出版会、1988年を参照)。そもそも王政復古の直後に発せられた施政方針である、五箇条の「御誓文」の第一条は、「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」。この文書の起草には、かつて横井小楠ともに福井藩の藩政改革を実行した由利公正が、新政府の参与として関わっていました。
もちろん、結果としてできあがった帝国議会の権限が必ずしも大きくなかったことが、立憲体制としては不十分だったという批判も、早くからありました。しかし近代の日本が1890(明治23)年に帝国議会を開設して以降、昭和の戦争期も含めて一度も議会を停止していないことは、注目に値するでしょう。
主権国家という発想が早く定着したのと並行して、議会による政治が正しい政治制度だという感覚もまた早期に生まれ、日本人の意識にしっかりと定着しているのだろうと思います。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月09日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点
- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」
- なぜモテない? 「パートナー探しが無理ゲー」になった進化論的背景




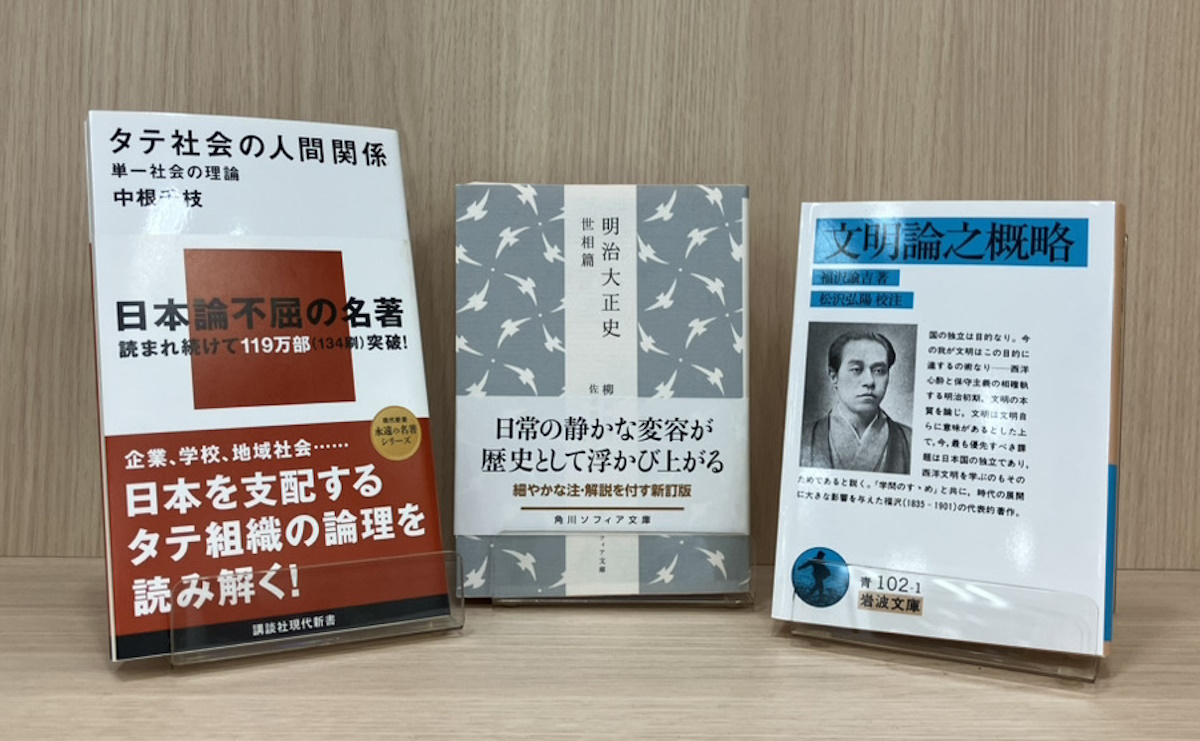

.jpg)
