【日本文明研究会・第3回】「1つの文明圏」としての日本、受け継がれている精神性

米中をはじめとする文明的大国が自己主張を強め、同時にデジタル化やビッグデータを軸にした技術革新が起きているなど、私たちはいま劇的な世界の変化を経験しています。このような状況下では、環境変化の圧力や不確実性に翻弄されるばかりでは十分ではなく、日本のあり様や世界のなかでの位置づけを問い直していく必要があるはずです。
「日本文明研究会」では、日本の文明的な性格がいかなるものかを、思想・宗教、文化文芸から家族、組織原理、政治、経済社会にいたるまで多角的な視点で検討し、顕在知として表出していくことをめざします。同研究会の委員が、日本文明を検討するにあたって必読の3冊を紹介します。(構成:藤橋絵美子)
疑われ始めている「普遍的な価値観」
ここ最近、「グローバリズムの終焉」や「リベラル・デモクラシー(自由民主主義)の衰退」といった話題を耳にする機会が増えてきました。1989年に東西冷戦が終わってからというもの、盛んに「世界はグローバル化して一体になる」とか「リベラル・デモクラシーが世界を覆う」などと西側諸国で言われてきました。ところが近年になって、その普遍的な世界観が疑われ始めています。
国際政治や歴史、文明などについて見方がガラッと変わる時期にあるのではないか。また、それにともなって、「日本とは何なのか」を見つめ直す時期にあるのではないか、と思います。
ハンチントンの「文明の衝突」は正しかった?
このことを考えるためにはまず、サミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』(1993年)を挙げたいと思います。この本の意義は、その前に出された国際政治学者フランシス・フクヤマの論文「歴史の終わり」(1989年)と並べることで見えやすくなります。
先に「リベラル・デモクラシーが世界を覆う」という展望を紹介しましたが、それを示すのが「歴史の終わり」という概念です。人類は、自由を目指してイデオロギーを戦わせることで進歩してきた。しかし東西冷戦は、間もなくアメリカを代表とする西側の勝利で終わるだろう。となれば「西洋の自由民主主義」が普遍化することによって「歴史は終わる」と言える。フクヤマはそういうふうに論じたのです。
実際、「歴史の終わり」論が発表されてすぐに東側が崩壊したため、この概念は非常に有名になりました。もちろん「世界を楽観視している」「複雑な世界を単純化している」などの批判はありました。しかし、端的にいってフクヤマが示したのは、自由と民主主義、法の支配、市場経済といった政治経済体制がグローバル化するだろう、という展望です。
それらのほかにめざすべき理念や政治経済体制が思い当たらないのであれば、フクヤマに賛成するか否かにかかわらず、基本的には「歴史の終わり」の展望を共有していることになります。その意味で「歴史の終わり」論は、冷戦後の世界をたしかに覆っていました。ところがいまや、それが疑われ始めたわけです。
その代わりに見直されているのが『文明の衝突』にほかなりません。ハンチントンは世界的に有名な国際政治学者であり、フクヤマの師でもありますが、対照的なヴィジョンを打ち出しました。
ハンチントンの議論の特徴は、国際政治をみるのに「文明」という観点を持ち込んだところにあります。冷戦後の世界では「文明」が、国際政治を動かす中心的な役割を果たすことになる。世界は、西欧文明、イスラーム文明、中華文明、ヒンドゥー文明、ロシア正教会文明、ラテンアメリカ文明、日本文明、アフリカ文明といったように分かれて争われる。
こうしたハンチントンの議論は、当初から学者や専門家にさんざん叩かれてきました。たとえば「文明という概念が曖昧である」「そういう見方や議論そのものが、対立を生じさせてしまう」といった批判です。
しかし、もし「文明の衝突」論が意味のない議論であれば、すぐに忘れ去られたでしょう。にもかかわらず、今世紀に入ってもずっと批判され続けました。ということは、多くの人がそれなりに何か思い当たることがあったのだと考えられます。
「文明」とは、「人のもつ文化的アイデンティティの最も広いレベルのことだ」とハンチントンは言います。たとえばローマ人であれば、ローマ市民、イタリア人、カトリック教徒、キリスト教徒、ヨーロッパ人、西洋人、といったようにさまざまなレベルで自分を規定します。
文明は「われわれ」と呼べる最大の分類なのです。たしかに、曖昧な概念ではあります。ただ、9.11テロからロシアのウクライナ侵攻までをふり返ってみて、次第に「ハンチントンの言っていたことには一理ある」と思われるようになりました。経済などの合理的な要素では説明できない国際政治の動きに、何がしか「文明」の要素が入っている、と考えられるようになったわけです。
「日本の愛国心」とアンパンマン
ハンチントンは、こんなに小さな国にもかかわらず、日本を1つの文明圏として考えました。では、日本はどのような文明なのでしょうか? これはとても大きな問いですが、ここでは佐伯啓思『日本の愛国心』(2008年)を挙げたいと思います。今年は終戦から80年目にあたり、本書は「先の戦争」の問題を題材にしながら、日本文明の核となる「日本人のこころ」を考えているからです。著者は「愛国心」という言葉へのアンヴィヴァレントな感情を吐露するところから始めています。
三島由紀夫は「愛国心」という言葉が嫌いだったそうだが、私も、正直にいえば、愛国心という言葉は決して好きではない。そもそも私のような一介の平凡な人間が「国」を愛するとか愛さないなどというだいそれたことをいえるのか、という気にもなる。私の「愛」の対象は、せいぜい、身近な家族や友人や同僚程度のことで、それさえも適切に処遇できない者が「愛国」などといえたものではない、という思いがある。
こういう感情をもとにして議論が展開されていきます。そして、「日本の愛国心」について考える場合、どうしても「先の戦争」にたいする評価が大きく関わってくる。著者が述べるように、日本の愛国心は、先の戦争で亡くなった人びとに対する負い目を抜きにしては語れません。とくに特攻隊についての想いは、人によってするどく分かれます。
こうした問題を、身近なことから考えるにはどうしたらよいでしょうか。今年はとくに「アンパンマン」が格好の作品だと思います。作者であるやなせたかしさんの弟は、特殊潜航艇の乗組員でした。やなせさん自身も戦争でつらい体験をされ、「戦争なんて大嫌い」と言う。そうした経験から描き出されたのが「アンパンマン」です。
困っている子がいれば、すぐに飛んでいき、お腹を空かせている子には自分の顔を食べさせる。どんなヒーローでも、何かしら自己犠牲の精神をもっているでしょうが、自分の顔を食べさせるヒーローなんて海外ではまず見られません。しかし日本では、自然と受け入れられている。やなせさんが作詞した「アンパンマンのマーチ」は、いまも子どもたちに親しまれている歌です。これを、やなせさんの戦争への思いや、弟さんへの想いをふまえて聴いてみてもらいたいですね。
「令和の精神」はあるのか?
3冊目は、日本の精神性を考えるための本として、いわずと知れた国民文学の代表作、夏目漱石の『こころ』(1914年)です。
この小説は、語り手の「私」と、私が鎌倉で出会った謎めいた人物である「先生」、そして先生の親友「K」など、さまざまな登場人物の孤独や愛情、裏切りなどが掘り下げられています。とうてい語り尽くせない作品ですが、最後のほうで「明治の精神」という文言が出てきます。
私は殉死という言葉をほとんど忘れていました。平生使う必要のない字だから、記憶の底に沈んだまま、腐れかけていたものとみえます。妻の冗談を聞いてはじめてそれを思い出した時、私は妻に向かってもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死するつもりだと答えました。私の答もむろん冗談に過ぎなかったのですが、私はその時なんだか古い不要な言葉に新しい意義を盛りえたような心持ちがしたのです。
この「明治の精神」とは何なのか。そして「明治の精神に殉死する」とはどういうことなのか。思想をはじめ歴史、社会、政治、教育、経済など、幅広い領域にわたって考えなければ、漱石の言わんとする「明治の精神」に近づくことはできません。
これを現代で考えるとどうでしょう。たとえば、この春に映画化された人気漫画に『かくかくしかじか』があります。この作品は東村アキコさんの自伝的漫画で、絵を「かく」ことを通じてつながる「先生と私」が描かれています。絵の道に殉じる先生、すこし違う道を進みながらも「かく」ことを通じてその精神を受け継ぐ私。すれ違いながら「かく」ことで共鳴し、古いものが受け渡され、新しい「絵」が描かれていく。
私は原作を読んだときに『こころ』に通じるものがあると思いました。もちろん、この2つの作品は一見かけ離れています。ただ、「明治の精神」とは言わないにしても、「昭和の精神」にはつながっている、と言っていいかもしれません。いま『こころ』や『かくかくしかじか』を読んで感動するとすれば、そこに令和の現在にも受け継がれている日本の精神性がある、と言えないでしょうか。
*この連載は政策シンクタンクPHP総研が主宰する「日本文明研究会」での議論を記事化したものです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月19日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算


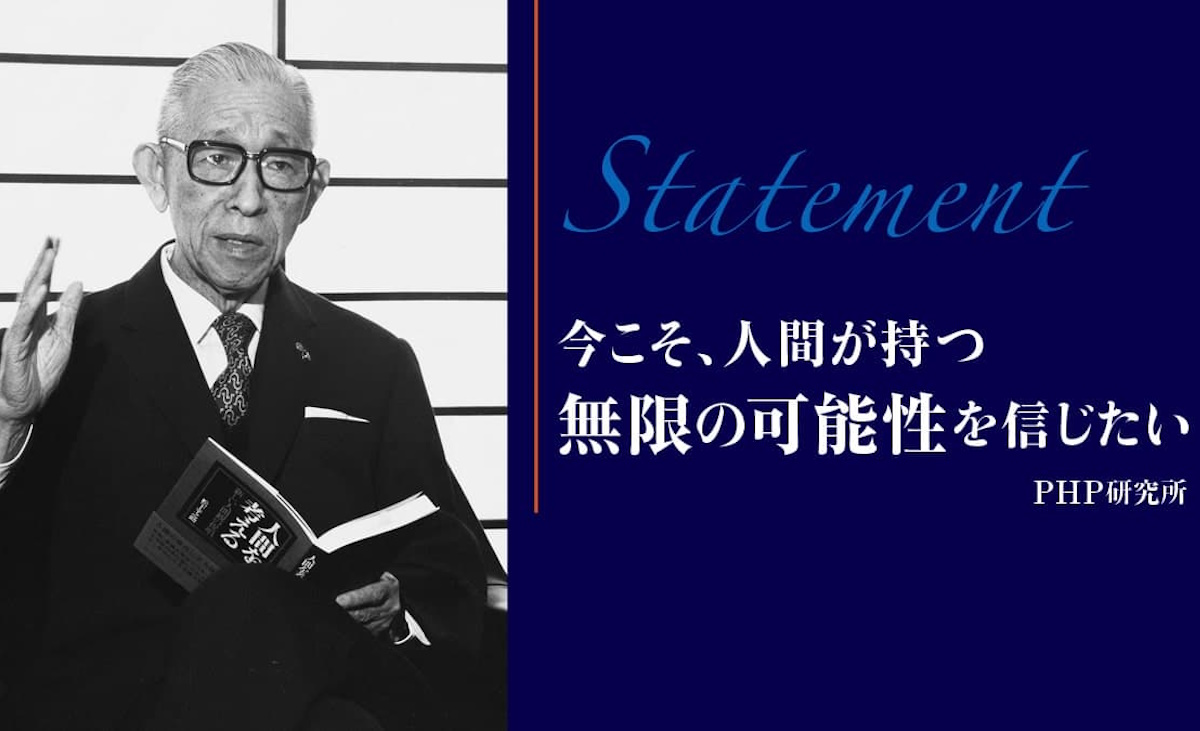



.jpg)
