【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)

米中をはじめとする文明的大国が自己主張を強め、同時にデジタル化やビッグデータを軸にした技術革新が起きているなど、私たちはいま劇的な世界の変化を経験しています。このような状況下では、環境変化の圧力や不確実性に翻弄されるばかりでは十分ではなく、日本のあり様や世界のなかでの位置づけを問い直していく必要があるはずです。
「日本文明研究会(委員:河野有理、藤本龍児、三宅香帆)」では、日本の文明的な性格がいかなるものかを、思想・宗教、文化文芸から家族、組織原理、政治、経済社会にいたるまで多角的な視点で検討し、顕在知として表出していくことをめざします。近代の日本においてリベラル・デモクラシーの政治制度が採用され、定着するに至った、その文明史的な背景について、苅部直氏が4回にわたって概観します。(構成:藤橋絵美子)
「ルソー的近代」を理想とした日本の戦後民主主義
前回のジョン・グレイ、リチャード・タックの議論を「ホッブズ的近代」の再評価と呼ぶならば、いわゆる日本の戦後民主主義の思想が理想としてきたのは、「ロック、ルソー的近代」とでも言うことができるのではないでしょうか。ジョン・ロックについては、日本国憲法の前文に「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて」とあり、ロックが『統治二論』で展開した「信託(trust)」の理論を参照して起草されたことが明らかですし、前文と第1条が掲げる国民主権に関しては、それを説いた政治思想の古典の代表としてジャン=ジャック・ルソーの『社会契約論』がしばしばとりあげられます。
さしあたりジョン・ロックは措いておくとして、ホッブズとルソー、この2人の政治思想については、法哲学者の長尾龍一が「学内行政の法哲学」(1993年初出、『純粋雑学』信山社、1998年所収)というエッセイでおもしろい比較を試みています。そこでは、大学教員の2つの類型という形で、「ホッブズ主義」と「ルソー主義」とを対比して説明しています。
ルソーは、あらゆる政治秩序の根源には、社会契約によって設立された市民(citoyen)の共同体があると論じています。そうした原初の共同体においては、「各構成員は自分の持ついっさいの権利とともに、自分を共同体全体にたいして完全に譲渡する」(『社会契約論』第一篇第六章、平岡昇・根岸国孝訳、角川文庫、1965年、28頁)とされます。すなわち、一つの意志によって結ばれた緊密な共同体が生まれ、各人はその総体の力すなわち主権をともに行使し、他面でともに義務を負う。
したがって全体の生存を確保するために、戦争に参加し生命を献げるのも、また重大な罪を犯した場合は死刑に処されるのも当然ということになります。これと同じように大学行政において、書類作成や会議で忙殺される管理職の仕事を進んで引きうけ、自分の研究を犠牲にすることを厭わないのが「ルソー的教師」です。
ルソーとは対照的に、ホッブズは『リヴァイアサン』の第21章で、「人間が自らを保護するために本来的に有している権利は、他の誰も彼を保護しえない場合には、いかなる信約によっても廃棄されえない」(加藤節訳『リヴァイアサン』上巻、ちくま学芸文庫、2022年、349頁)と説いています。したがって、主権者が人民に兵役に就くよう命じた場合、臣民(subject)の側がそれを拒否して代役を立てる行為も不正ではないということになります。
そのとき、主権者は臣民の生命と身体の安全を保護するという約束を果たしていないので、臣民も命令に従う義務はなくなる。長尾はこの議論を敷衍して、大学行政の仕事を極力さぼり、管理職になるのを避けることで自分の時間を確保し、すぐれた研究業績を積み重ねる大学教員を「ホッブズ的教師」と呼んでいます。
市民の一人ひとりが主体的に政治秩序の運営を担うことを推奨するルソー。それに対して、主権国家が成立したあとは、そこに暮らす人々は秩序を破壊するような行動をとらない限り自由とする(ただし先にふれたように、宗教の問題を度外視する限りのことですが)ホッブズ。
もっともルソーの議論は、原初の市民の共同体が最初の立法権を行使したのち、執行権を委ねる対象としては、市民全員(民主政)、代表議会も含む少数者(貴族政)、一人(君主政)と3つの場合があるというもので、現実の政治制度として直接民主政を推奨したわけではありません(熊谷英人『ルソーからの問い、ルソーへの問い』吉田書店、2023年、317-321頁を参照)。しかし、社会契約と市民の共同体について語る箇所に注目するかぎり、市民の直接参加という理想像を読者の心のなかに喚起する著作であることは否定できないでしょう。
日本の「国民主権」は本音と建前が分離している?
終戦直後における政治・社会の改革に始まる、いわゆる「戦後民主主義」の思想潮流は、長尾の言う「ホッブズ主義」と「ルソー主義」との対比に即して言うならば、明確に「ルソー主義」の色彩の強いものだったと言えるでしょう。
『国史大辞典』(吉川弘文館)の項目「近代」のなかで、思想史家の鹿野政直は「戦後民主主義」を以下のように説明しています。「丸山真男・大塚久雄・桑原武夫らによって、近代日本の封建遺制をするどくつく論議が展開される一方、竹内好のようにアジアの変革から学ぼうとする論議もあらわれた。また、教育における社会科の設置や、生活重視の視点の登場や、広汎な民衆運動の勃興や戦争責任論・天皇制論の展開など」。
「アジアの変革から学ぼうとする論議」を主要な特徴として挙げるのは、「アジアの変革」が1949年の中国の共産革命のことを指しており、終戦直後からあった動向ではないことを考えればやや疑問ですが、それ以外の諸点に関しては、「戦後民主主義」と聞かされた場合、普通に想起する内容を拾いあげていると言えるでしょう。ここで「教育における社会科の設置」が挙がっていることが、いかにも戦後日本らしい特徴です。
その社会科が始まった年、1947(昭和22)年の8月に刊行された中学生用の社会科教科書(パンフレット)として、『あたらしい憲法のはなし』という有名な一冊があります。文部省による発行で、施行されたばかりの日本国憲法の趣旨を解説した本ですが、憲法学者の浅井清が委嘱を受けて執筆したことが、現在では明らかになっています。
この本の「主権在民主義」に関する説明は、以下のようなものでした。
「こんどの憲法は、民主主義の憲法ですから、国民ぜんたいの考えで国を治めてゆきます。そうすると、国民ぜんたいがいちばん、えらいといわなければなりません」(髙見勝利編『あたらしい憲法のはなし 他二篇』岩波現代文庫、2013年、37頁)。
この文章をよく読むと、「国を治めてゆきます」の主語がありません。「国民ぜんたい」が主語になってもよさそうなのに、そうなってはいない。
前回ふれた、リチャード・タックによるボダンとホッブズに関する理解、また政治体制をめぐるルソーの議論の二重構造を念頭において読み直すと、これはまさしく、「主権」と「統治」の区別、ルソーの言う市民の共同体と具体的な政治体制との関係を念頭においた、国民主権の説明だということがわかります。
日本国憲法では、主権が国民にあると規定されてはいても、一つ一つの立法に関して国民がみずから関与する制度にはなっていません。まして行政、司法に関して、その意志が直接に反映されることもない。統治の実態においては国民の意向を直接に実現する制度になっていない状態を前提として、「国民主権」をどのように説明すればいいのか。それを考えた末の苦肉の策だったのでしょう。
戦後の日本においてはずっと、初等・中等教育において、また大学の憲法の授業でも、日本国憲法の三大原理が必ず説明され、その第一に国民主権が挙げられています。金子宏ほか編『法律学辞典』第3版(有斐閣、1999年)によれば、それは「国の政治のあり方を終局的に決定する力(主権)が一般国民にあるという原理」と説明されます。「終局的に」という留保が微妙ですが、さしあたりこういう説明を聞くと、普通の読者は「一般国民」がみずから参加して政治を「決定」する直接民主政を思い描くでしょう。
しかし、国会で展開する立法過程や、さらにそれ以前に法案が政府与党と行政官庁の内部で練り上げられてゆく過程に、国民が参加しているわけではない。地方自治体において、個別の案件に関して住民投票が例外的に行なわれる場合くらいしか、実効性をもった直接参加の機会はありません。国民主権という原理を強調してとらえる限り、日本のリベラル・デモクラシーは、建前と本音とが分離した状態で運営され続けているのです。
「議会制民主主義」の価値が低く見積もられる日本
「国民ぜんたいの考えで国を治めてゆきます」というデモクラシーに関するイメージは、終戦直後の「戦後民主主義」全盛期をこえて、現在に至るまで一般社会には根強く普及しているように思えます。現実の政治を論じるさいに、どんな問題の場合でも、「市民の声が反映されていない」という批判や、「市民参加のいっそうの活性化が望まれる」といったひとことで話を結んでしまう。そうした傾向が、ジャーナリズムにおける報道にも、知識人による評論やSNS上の投稿にも、しばしば見られます。
もちろん、デモクラシーの政治制度をしいている限り、何らかの形で国民の意向が政治に反映されることが不可欠ですから、そうした結論を述べるのもおかしなことではありません。しかし、人々の共有している理想像が著しく直接民主政のイメージに傾いている結果、先にふれた政治的決定の現実のありさまに直面することで、人々に深い失望を呼びおこしてしまう。そうした負の影響関係が生じていないでしょうか。いわゆる「政治的無関心」や投票率の低下には、そんな要因も働いているような気がします。
東京大学法学部「現代と政治」委員会編『東大政治学』(東京大学出版会、2024年)という本の第8章でも詳しく紹介したことですが、こうした直接民主政への素朴な憧れは、高校の「公共」科目の検定教科書にも、しばしば見られます。文部科学省で定めている学習指導要領は、「公共」で現代日本の政治制度について説明するさいに「議会制民主主義」についての記述を盛り込むように指定しています。
ところが、これに即して作成された教科書のなかには、直接民主政についてまず紹介し、その次に議会制民主主義についてふれ、しかも後者を「間接民主政(制)」というもう一つの名前で呼び直している例が見られます。
たとえばある教科書(2021年検定版)は、古代ギリシアのポリスにおける「直接民主制」をとりあげ、こちらが「民主政治のあり方としては理想的であるが、国土・人口の規模が大きい近代以降の国家では、その実施は困難である」と説明した上で、いわばその代替措置として現代の諸国では「議会制民主主義」を採っていると説明し、「間接民主制」という名称を付け加えています。直接民主政が理想だが、国家の大きさという事情のせいでやむなく採用した制度。そういう意味あいが、「間接」(directに対するindirect)という表現から感じられます。
しかしたとえば、英国で刊行された全8巻の『Encyclopedia of Political Thought(政治思想大辞典)』(Willey Blackwell, 2015)のindirect democracyという項目の説明に見えるのは、現代では「直接」民主政よりも「間接」民主政のほうが、自由を旨とする統治体制(a free government)において、より安定した公正なしくみを提供できるという理解です。広い国土に対応するための便宜上の手段として、代表民主政(議会制民主主義)を意味づけているわけではありません。
リチャード・タックもまた、先に挙げた『眠れる主権者』において、代表民主政は決して直接民主政の代替手段ではなく、そこでは代表議会それ自体が法を定め政府構成員の人選を行なう権限をもっているという点で、「統治」でなはなく「主権」の位置にあると論じています。
高校教科書の執筆者が、学習指導要領にはない「間接民主政(制)」という言葉を追加して、日本国憲法が定めた「議会制民主主義」の価値を低く見積もるような記述を付け加えているのです。おそらくそのような説明が、戦後はずっと、多くの高校の教室で行なわれてきたのでしょう。
戦後の左派知識人の影響が教育に残っている
私見では、この傾向は日本国憲法の制定よりもずっと前の時代、1930年代の政治学に由来しています。
昭和戦前期に刊行された『法律学辞典』の第3巻(岩波書店、1936年)には「デモクラシー」という大項目があり、当時は東京帝国大学法学部の教授として政治学(政治原論)の講義を担当していた矢部貞治が執筆しています。そこで強調されているのは、同時代の欧米諸国と日本における「デモクラシーの危機」の動向です。
従来の「自由的・議会的デモクラシー」すなわち「議会・政党による間接政」が機能不全に陥り、それに代わって議会の機能の縮小もしくは廃止を唱え、代表制を介さない人民の直接参加を標榜する「ファシズム」と「ボルシェヴィズム」の政治勢力が左右から擡頭し、現実にイタリア、ドイツ、ソヴィエト連邦で政治体制を変革した時代。その空気のなかで、従来のリベラル・デモクラシーの体制を「間接」民主政として批判する論法が登場したのです。
矢部が辞典項目で「デモクラシーの危機」を論じた10年後に、日本では終戦直後の衆議院議員選挙と日本国憲法の公布を通じて、リベラル・デモクラシーの体制が復活・強化されました。しかし、リベラル派や左派(マルクス主義派)の知識人の議論には、「間接」民主政というとらえかた、そしてそれを低く評価する視線が残り続けます。矢部の「政治学」講座を継承した堀豊彦による教科書『政治学原理』増補版(東京大学出版会、1959年)には、「間接民主政治または代議的民主政治」という名称と、先ほど挙げた「公共」教科書と同じような論法が、やはり見えます。
さらに、日本共産党系のマルクス主義法学者だった平野義太郎が『世界歴史辞典』第18巻(平凡社、1953年)に寄稿した項目「民主主義」になると、「間接民主制」に対する嫌悪が露骨に表れています。そこで平野は、同時代の自由主義諸国における「代議制」を「ブルジョア民主主義」として否定し、事実上の一党独裁である東欧諸国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の政治体制を「人民民主主義」として礼賛したのでした。
もちろんここまで露骨な代表制批判は、冷戦終了後にはほとんど見かけなくなりますが、戦後の教育界、言論界、人文系の学界における左派の影響力の強さのゆえに、こうした「間接」民主政に対する冷たい視線が、教育現場や知識人の思考の内に根強く残ってしまった。「公共」教科書の例は、それをよく示しているのではないでしょうか。
代表制への嫌悪をこえて
もちろん先にもふれたとおり、市民の直接参加への憧れそのものは、デモクラシーを活性化させるためには重要な役割を果たします。実際に戦後日本では、そうした憧れが1960年代以降の市民運動や自治体改革を支え、成果を残してきたことも確かでしょう。
しかし、現実に機能しているはずの代表民主制への不信が、素朴な常識として定着してしまっていることは、デモクラシーを支える市民の意識のあり方として健全とは言えません。それは時として、民意を代弁すると称する強権的なリーダーや政党に対する、思慮を欠いた支持にもつながってしまうでしょう。他面で、政治家を目指す若者が極端に少ないという現状にも、「間接」民主政をめぐる否定的な感情が働いていないでしょうか。
こうした状況をのりこえるためにはどうすればいいのか。国民投票などを通じて直接参加の範囲を拡大し、タックの説く「眠れる主権者」が目覚めることを期待する。代表制の活性化に努め、その意義を人々がしっかりと実感できるようにする。政治参加に人々が主体性を発揮し、国民全体の強い一体性の内に生きるといった可能性はあきらめ、グレイが説くような「ホッブズ的近代」を現実化する。そんな3つの選択肢が考えられると思います。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月02日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債




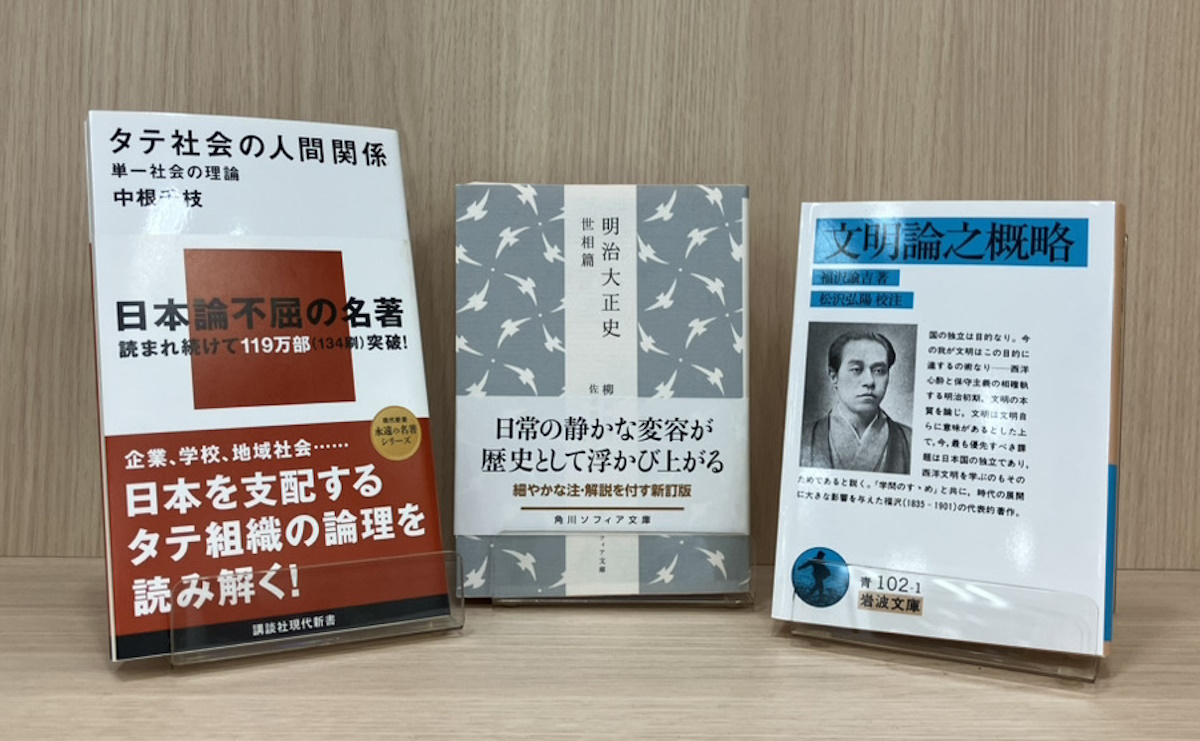

.jpg)
