【22世紀の人間像研究会・第3回】医療情報でつくられる「正しい」身体と社会
2025年10月24日 公開
2025年11月06日 更新

松下幸之助は終戦直後にPHP研究所を創設して以来、人間とは何かについて思索を重ね、その集大成ともいえる『人間を考える』(昭和47年〈1972年〉発刊)において、「人間には万物の王者たる優れた本質が与えられている」とする肯定的な人間観を提唱しました。
それから半世紀を経て、戦争や環境破壊、AIの進化など人類は新たな岐路に立っています。「22世紀の人間像研究会」では、多様な領域の専門家とともに「人間とは何か」を問い直し、次の時代を切り拓く人間像を模索していきます。(構成:中嶋 愛)
人間が数字になり、細分化されることへの違和感
私は医学人類学が専門ですが、もともとは運動生理学の出身です。高校時代には空手をやっていて、そこで怪我をする選手をたくさん見ていました。
大学に入った1990年代は、科学的トレーニングというものが出てきたころです。これを取り入れたら怪我も防げるしパフォーマンスも上がるだろうということで、早稲田大学の人間科学部のスポーツ科学科に入りました。科学的な実験をやっても、科学的にはわからないのが人間であると感じるようになりました。
実際、科学的な実験の現場に入っていくと、人間が数字になり、どんどん細分化されていくんです。たとえば、筋肉のパフォーマンスの話が筋繊維の話になって、次に筋膜の話になって、次にタンパク質の話になって、最終的にはアミノ酸まで行きつくんです。
そうするうちに、「あれ、人間どこにいたっけ?」という話になっていく。科学的な研究は細分化をするほうが成果につながりやすいのですが、それを突き詰めると人間の全体像が見えなくなってしまう。
それで大学3年ぐらいのときに悩み始めたのですが、私の運動生理学のゼミの先生が「磯野のその疑問はすごく大事だから、それを卒論に書け」と言ってくれたのです。これは非常にラッキーなことでした。
私は運動生理学のゼミにいながら人文的な卒論を書いて卒業しました。でもアスレチックトレーナーになりたかったので、そのままアメリカのオレゴン州立大学スポーツ科学部に入ったのですが、そこでもやはり自然科学の「数字にして細分化する」というところの違和感が取れずに、いろいろな授業に潜り出したところで出会ったのが文化人類学でした。
人間を人間のまま、まるごと捉えていくという文化人類学の手法に結構衝撃を受け、3日後に専攻を変えるという、結構過激なことをして、そのまま人類学者として幸いにも何とか生きてこれています。
コロナ禍を支配した「感染対策」至上主義の怖さ
私は文化人類学に身体というものからアプローチしました。いわゆる医療的な情報が人間の身体感覚、あるいは、生き方をどう変えてしまうのかというところに注目したんです。
最初にやったのは摂食障害の研究でした。拒食症とか過食症と呼ばれるものです。女性に多い疾患ですが、とにかくやせたいので、多くの当事者は、栄養学や生理学の知識を積極的に学び、自分の食べ方の見直しに使います。その情報に従って身体感覚が変わっていく。そこに注目をして1冊目の本(『なぜふつうに食べられないのか』)を書きました。
ところで、為末大さんのお話にゾーン体験が出てきたのですが、私も初作の摂食障害の研究で、過食症における過食は、自己が消える快感を伴うフロー体験に近しく、やめられない1つの理由が、過食を通じた快感ではないかという提言をしています。
話を元に戻すと、いわゆる医療情報が身体性をどう変えてしまうのか、という観点から近年いちばん衝撃を受けたのは、コロナ禍での体験です。最初のころは感染者がおらず、情報しか入ってこない状況でしたが、それでも人がここまで生き方を変えてしまうのかとショックを受けました。
また感染対策が進んでいくなかで、「感染対策より大事なことはない」という倫理観が前面に出てきました。私は医療人類学を通じて医療従事者とのおつきあいもあったのですが、「もしものときどんな医療やケアを受けたいか、人生会議で大切な人と話し合うことが大事だ」とか、「人間は関係性のなかで生きていて、関係性こそが大事だ」とか、「患者さん中心の医療が大事だ」と言っていた人たちが、感染者が少ない時の完全面会禁止を許容したり、何でもかんでも不要不急と名指して行なったりする状況を目の当たりにしました。この社会の急激な変化と、人びとが甘んじてその変化を引き受けているように見えることに衝撃を受けたことをきっかけに、国内の3カ所でフィールドワークを実施し、『コロナ禍と出会い直す』という本を書きました。
その流れをふまえて、今回私が「人間とは何か」について考える視点として、三つほどあります。
身体は機器を模倣する?
一つ目は「理想の身体というものどういうふうに変遷していくのか」ということです。
たとえば、昨今は脱毛や育毛というのがやたらと流行っていますが、これは一昔前にはなかったことです。これだけ短期間でも理想の身体のあり方が変わっていく背後には、テクノロジーの変遷があります。それを表すものとして、私はずっと「身体の比喩」に注目をしてきました。
私は授業で松下幸之助さんの話をすることがしばしばあるのですが、松下幸之助さんの著書のなかに、入院をする場面がでてきます。そこで「油を差してちょっと直してくる」と言っているんですね。当時、自転車を直したりとか、車を直したりするときになど、日常的に機会に油を差している状況があったからこういう表現になる。
いまだったら「油を差す」ではなく、「メンテナンスする」とか「チャージする」とか、そういう表現になると思います。身体の比喩がIT機器と絡んできているんです。
昭和の時代にはパワーがある人のことを車やバイクのエンジンになぞらえて「排気量がある」と言っていたのを、いまではIT機器を思わせる「スペックが高い」と言ったりします。そんなふうに、私たちが使ってる機器が人間の理想の身体に比喩として介入してくるというところに着目をしています。
暴力の「ゲーム化」によって何が起きるか
もう一つは、「暴力と身体」です。暴力にもいろいろあって、たとえばいま私が誰かを殴ったら、私も痛いし、殴られた人も痛い。でもSNS上の言葉の暴力で身体的な痛みに苦しむ人はいないわけですよね。
それからウクライナやアフガニスタンでもAIを使ってドローン攻撃が行なわれているわけですが、その仕事に従事する一部の人はアメリカにいながら8時-17時のシフトで働き、勤務時間内に標的に向けて爆弾を落としている。コーヒーを片手に戦闘に加わるといったことだって起こっているでしょう。つまり、人が死んでいるのだけれども、人の死体を見たりであるとか、自分も戦禍に巻き込まれて怪我をするといった身体性が圧倒的に欠けている。加害側に暴力の自覚がなく暴力ができるという状況が起こっています。
三つ目は、暴力がゲーム的になっているということです。さきほど定時で働き、国内でドローン攻撃に加わるという話をしましたが、,米国の歴史学者であるHeather Cox Richardsonは、イーロン・マスクとトランプ大統領(いまではすっかり仲が悪くなってしまったようですが)は、自分の敵について話すときに「NCP」という言葉を使うと指摘します。これは「ノン・キャラクター・プレーヤー」の略です。もともとはゲームの言葉で、ドラクエなどのロールプレイングゲームに出てくる、ただの街の人、そこにいるだけの人を指しているそうです。
RPGをやったことがある方はわかりますが、一定数の街の人びとは話しかけても同じことしか返さない。でも街のスペースを埋めてはいる。つまり自分たちを批判してくる人々を「NCP」を呼ぶことで、その人たちを非人間化するわけです。NCPであれば、何を言っても傷つくことはない。
このように、暴力をゲームの言葉におきかえると、身体性が希薄化し、暴力を向ける相手の肉体が意識されなくなります。人間が内集団と外集団、つまり敵と味方を分けていくときに、敵をどのように呼ぶのか、ということからも人間の身体の行く末が見えるのではないかと思います。
ここが気になる!
先崎彰容(思想史)
コロナ禍のときに情報だけで人間が生き方を変えてしまった。情報だけで身体の動き及び身体そのものの形が変わるというのは、身体そのもの知性をむしろ否定するようなことです。違和感のある情報に対しては身体的な知性がきちんと反応するというのが為末さん的な身体観になるはずですが、その逆になりますね。
一方で、リストカットという行為が示しているのは、情報に支配される身体でもそれをはねのける身体的知性でもない、「生の衰弱」です。リストカットして痛かったり、それを人から「どうしたの?」と言われたりすることを通じて自分のアイデンティティの存在を確認しなければいけないところまで言語が切り詰められている。生の充実感がもはや身体の痛覚のレベルにまで縮減されてしまっているということです。
同じ「言語を削っていく」という行為でも、座禅とリストカットではまったく違うことを意味している。こうやって見ると身体にも多面性がありますね。
*この連載は政策シンクタンクPHP総研が主宰する「22世紀の人間像研究会」での議論を記事化したものです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月19日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算


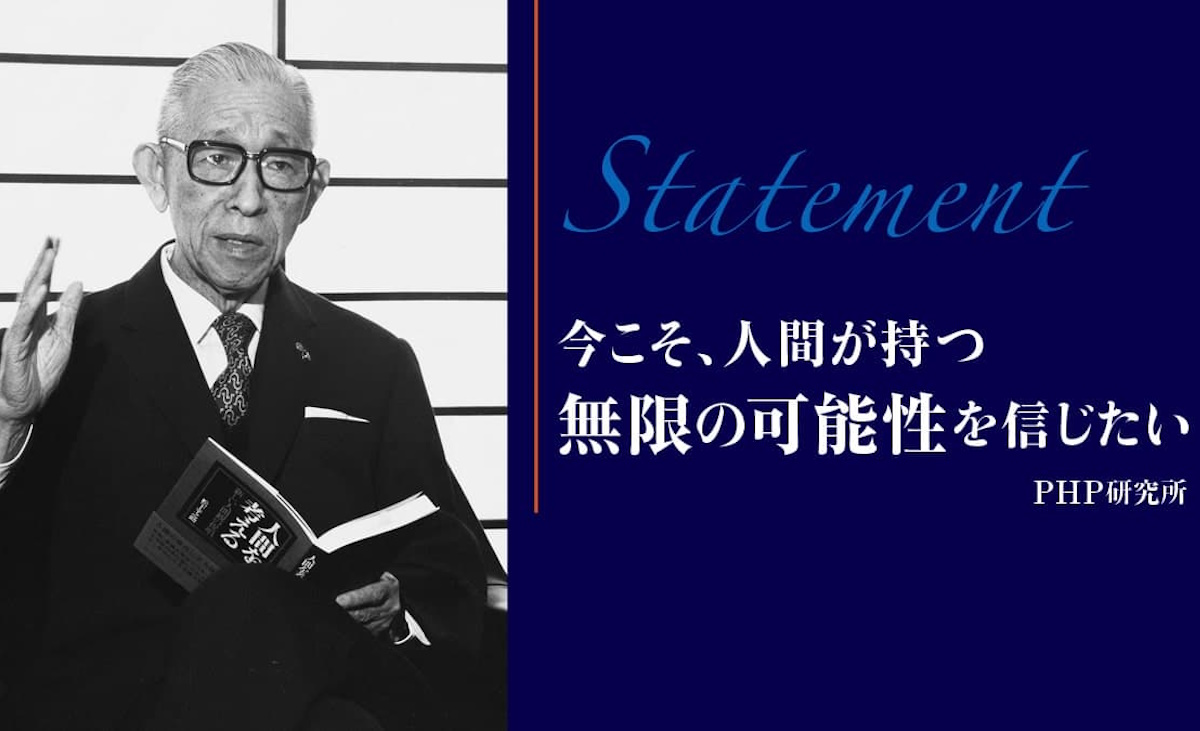




.jpg)
