【22世紀の人間像研究会・第1回】「終始一貫した私」から自由になってみる
2025年10月10日 公開
2025年11月06日 更新

松下幸之助は終戦直後にPHP研究所を創設して以来、人間とは何かについて思索を重ね、その集大成ともいえる『人間を考える』(昭和47年〈1972年〉発刊)において、「人間には万物の王者たる優れた本質が与えられている」とする肯定的な人間観を提唱しました。
それから半世紀を経て、戦争や環境破壊、AIの進化など人類は新たな岐路に立っています。「22世紀の人間像研究会」では、多様な領域の専門家とともに「人間とは何か」を問い直し、次の時代を切り拓く人間像を模索していきます。(構成:中嶋 愛)
「どうやったら人と社会が元気になるか」
私は男子400mハードルの陸上競技選手として、世界陸上で2度銅メダルを取りました。3回のオリンピックに出場し、2012年に現役を引退してからは、いろいろなことをやってきているのですが、基本的には「どうやったら人と社会が元気になるか」ということを、身体という切り口であれこれやっています。
「人間を考える」ということでは、ちょうど3年ぐらい前から「人間らしさの会」というのを個人的にやっています。きっかけはChatGPTが出てきたときに、動物的なものと、人工知能の間に挟まれた「人間」とはいったい何を指すのかを知りたいと思ったことでした。
その話を面白がってくれたPKSHA Technology(パークシャテクノロジー)というソフトウエア開発企業の上野山勝也さんと一緒に、いろんな人を呼んできて勉強会を開いています。といっても、大体は飲み会になるので、「結局、自堕落なところが人間らしさなのでは」といった話に落ち着きがちなのですが。
人間が外的環境と一体化する感覚
真面目に「人間とは何か」を考えるとあまりにも壮大な問いですよね。人によって切り口があるかなと思いますが、私は陸上競技をやってきた経験から、自分が身体を通して世界をどのように認識するかということに非常に興味がありました。
たとえば、「ゾーン体験」と呼ばれる現象があります。これは非常に強く集中した時に起きる状態です。ふつう、スポーツ選手は自分の体をコントロールすることで外的環境をコントロールするためにトレーニングをやっています。実際に練習を重ねることとで上達していくわけですが、ゾーンの状態までいくと、コントロールしているはずの自分がいなくなる感覚がある。
私自身も経験がありますが、外的環境と一体化してダンスしているような状態、というようなことを多くの選手が証言しています。この無我というか忘我のような境地に非常に興味をもっています。
AIにはない身体ベースの知性とは
それでいろいろな人に話を聞きにいった結果、フランシスコ・ヴァレラという人が、言っている「エナクティブ」という概念に行きつきました。
これは、外的環境と生物というものの間に壁のようなものがあるけれども、この壁は閉じていながら開いてもいて、両者は相互に影響し合っている状態にあるという考え方です。ヴァレラはこれを「構造的カップリング」と呼んでいます。この人は最終的には仏教に行きつくんですね。
私も人間というものは周りの環境と個の相互作用であり、周辺から切り離すことはできないのではないかと思っています。もし人間が脳からの指令で身体を動かしているというのであれば、AIの指令で身体を動かされるようになるのも時間の問題になってきますが、どうもそういう話ではないような気がしています。
AIには私たちのような身体がないので、排泄したりとか食事したりできない。そういう私たちがふだん意識しないような身体ベースの知性というものもあるような感じがしています。
3つの人間観の転換で生きやすい社会に
いまお話ししたような観点から、私は3つの軸で人間観の転換が起きたらいいな、と思っています。一つは、脳を中心とした人間観から、身体をベースとした人間観へ。もう一つは、「終始一貫した私」というものはなくて、人間は変わりゆくものだという人間観。
私はいまの社会では、個人としての一貫性に縛られ過ぎているのではないかと思っているんです。ヴァレラのいう構造的カップリングのように、人間は周辺の環境との相互作用のなかで、いかようにも変わり得るという考え方のほうが自然であるような気がします。
3つめの人間観の転換軸は、人間の非一貫性とも関連するのですが、やはり周辺と切り離されたIndividualな「個人」という人間観も変わっていくのではないかなと思います。
本質的に人間と環境は切り離せないのではないか、だとしたら自己と他者も本当は不可分なのではないか。「周辺との関係の中に生きている私」みたいな感覚です。
人間を考えることは「いい社会」とは何かを考えることにもつながると思うのですが、私は「いい社会」は人間同士の信頼の上に成り立つものだと思います。その信頼がいまいろいろなところで弱まったり失われたりしているような気がするので、それをもう一回社会の中に作り直していくような活動ができたらいいなと思っています。
「個人の元気は身体にあって、社会の元気は信頼にある」と私は思っています。
ここが気になる!
先崎彰容(思想史家)
為末さんのお話からものすごく触発されるところがあります。日本思想史の文脈ですと、湯浅泰雄という人が『身体論』という本を書いていて、身体から知性を考えるというお話とかぶるところがあると思って聞いていました。
人間は一貫したものではなく、変化していくものである、という人間像は、江戸時代の儒学者たちのなかにも、それまでの儒学の教義に出てくる硬直した人間像に反して、人間はもっと多面的な存在であると考えた人たちがいたんです。
高梨直紘(天文学者)
元バレーボール選手の中田久美さんにゾーン体験についてうかがったことがあります。彼女は現役時代に、1回だけ試合でゾーンに入ったことがあるそうです。しかもそれは彼女だけの体験ではなく、その場にいた他の仲間もみな、同じようにゾーンに入ったと認識していたそうなのです。
みな同時に……となると、それをロジカルに説明しようと思ったら、為末さんのいう「環境との関係の中でゾーンに入る」という考え方が説得力のある話だと思って興味深く拝聴しました。
*この連載は政策シンクタンクPHP総研が主宰する「22世紀の人間像研究会」での議論を記事化したものです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月19日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算


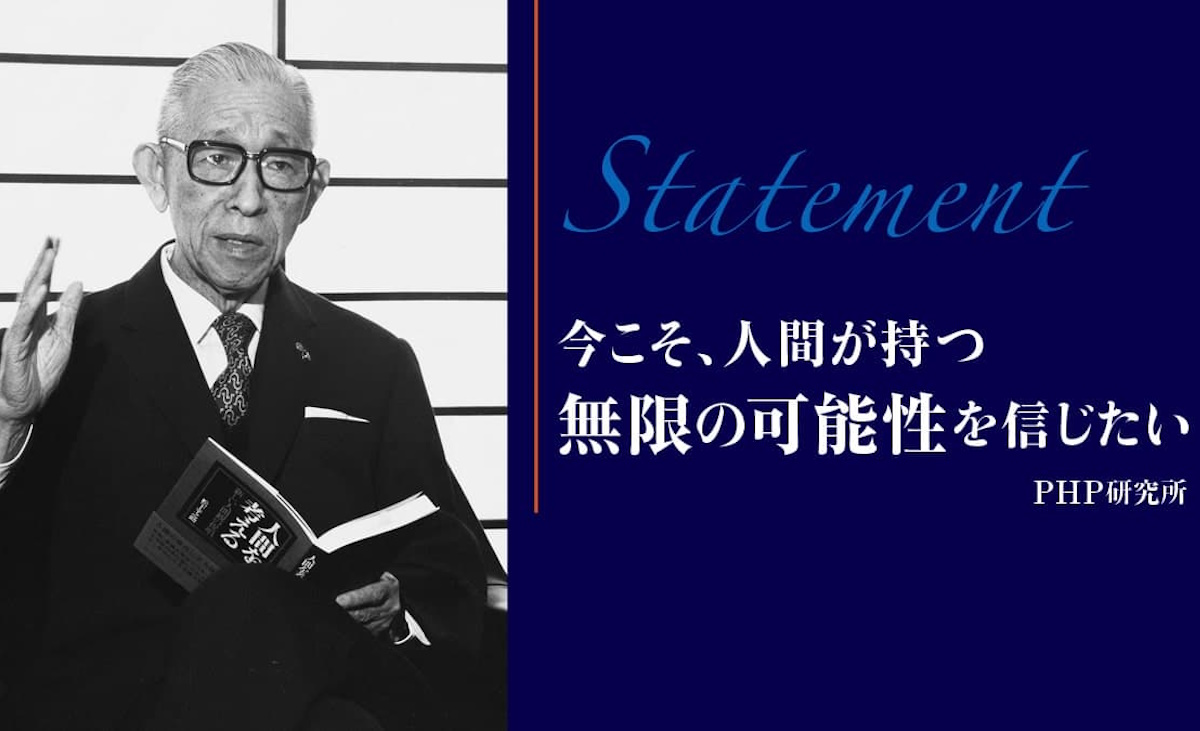




.jpg)
