【22世紀の人間像研究会・第2回】100年前の「人間学」ブームから考える
2025年10月17日 公開
2025年11月06日 更新

松下幸之助は終戦直後にPHP研究所を創設して以来、人間とは何かについて思索を重ね、その集大成ともいえる『人間を考える』(昭和47年〈1972年〉発刊)において、「人間には万物の王者たる優れた本質が与えられている」とする肯定的な人間観を提唱しました。
それから半世紀を経て、戦争や環境破壊、AIの進化など人類は新たな岐路に立っています。「22世紀の人間像研究会」では、多様な領域の専門家とともに「人間とは何か」を問い直し、次の時代を切り拓く人間像を模索していきます。(構成:中嶋 愛)
東日本大震災の避難生活で見た「人間の業」
僕個人が「人間とは何か」を考えるにあたってベースとなる実存的な体験として、東日本大震災があります。福島県のいわき市で被災し、5年間ぐらい避難生活を送りました。その時に「人間の業」をすべて見たように思います。人間が金によってどう動くかとか、人間ってそんな生やさしいものじゃないんだというすべてを見させていただきました。
その際、思想史家として、僕は何ができるのか。こう自問自答しました。
反原発デモや、被災者の生の声で批判罵倒しても仕方ない。この未曽有の危機、崩壊の経験をどう「生かすか」。そう考えた僕は、戦争を経験した文学者・思想家の言葉を、本気で読むことができると思った。臨場感をもって読むことができると確信したんです。
坂口安吾であれ、丸山眞男であれ、三島由紀夫の言葉が、にわかに生々しく僕の前に現れた。僕は自分が被災するまで、そうしたものをただの「勉強」として読んでいた。本当に目の前がぶっ壊れているなかで、秩序が徐々に再形成されていくときに思想形成をした人たちのリアリティをもってテキストを読んだことがそれまでほぼなかった。それが大きく変わったのです。
具体的には、福島第一原発に関する被災です。そこで「苦しかった」という現場の声は山ほどありました。しかし、思想家は、こういうときこそ言語で何ができるのかを問われている気がしました。それで避難生活の最中に、本を読むことをずっとやっていた。それが僕の思想の根本だと思っています。30代のときですね。それまではのらりくらりと生きていたともいえます。
そういった実存的な経験をしてみると、政治の見え方も全く変わってくる。たとえば現在のトランプ政権がああだとかこうだとか単なる説明に終始するのではなくて、人間とは何か、何を主張したくて大衆が蠢いているのか。こういう観点から説明したくなるのです。
1920年代は2020年代と酷似しているという説
僕は人間像を考えるときには、まず「同時代性」を意識します。僕の考えはよくも悪くも時代からの限定を受ける。だから、時代性と人間という一見抽象的なものを行ったり来たりしながら考えたい。たとえばいま、国際秩序の転換点だといわれています。資本主義、民主主義、自由、といったもので社会なり国際秩序が転換点にあると言われる。では、転換点において、人はどう振る舞うのだろうか。
行ったり来たり、というのは、短期的な視野と長期的視野で物事を見ることでもあります。この場合の短期は、それでも100年くらいの単位の話です。今年は「昭和100年」にあたりますが、昭和が始まったのは西暦だと1920年代後半です。その時代にいまの社会がとても似てきている、と国際政治学者の人たちが言っているのをよく聞きますが、実際僕もそう思います。
100年前の1925年といえば、第1次世界大戦と第2次世界大戦の間にあたります。歴史的には第1次世界大戦というほうが決定的でした。この戦争で、とんでもない大量の殺戮が行われた。その結果、人間に対する不信感、ある種の自暴自棄的な自己認識が生れ、人間学としてのアントロトポロジーが流行しました。
有名なところではハイデガーの『存在と時間』がありますが、それが存在論ではなくて人間学として読まれた。そのハイデガーを強く意識した日本の哲学者に和辻哲郎がいます。和辻は『人間の学としての倫理学』とか『倫理学』という本を書いています。『パスカルにおける人間の研究』という本を書いた三木清という人もいます、「人間とは何ぞや」ということがしきりに問われた時代でした。
芸術の領域においては、ダダやシュールリアリズムと言われる、人間の心の奥底をのぞいた芸術であるとか、人間性そのものにかなり懐疑的な芸術なども出てきたのがこの時代です。このあたりを参照したら22世紀の人間像を考えるうえで何か出てくると考えています。
兵士が戦場に携えたハイデガーの『存在と時間』
100年前に流行った「人間学」は、哲学の流行としてはもう終わった部分はありますが、時代状況が似ているというなかで、もう1回取り上げる意味はあると思います。実際に、三木清、和辻哲郎とハイデガーといった人たちを読み直し続ける時の解釈の軸は、時代の流行によって変わってきています。
たとえば、三木清はドイツで学びつつ、最後フランスへ行ったんですが、ドイツ語もフランス語もできたので、フランス滞在中、寝る前にパスカルの『パンセ』を読んだんですね。そうしたら、パスカルの著作こそハイデガーの哲学で解釈できるではないかと感動して泣いたと書いています。日本に帰国した直後に書いたのが『パスカルにおける人間の研究』という本です。
そこで三木は人間を一言で定義すると、「中間者」であると言っています。広大な宇宙に比したら、とても微細などうでもいい存在なのだけれども、どんどん細かく細胞にまで分割していったときに、この肉体が一個存在するというのは奇跡に近い壮大な完成体である。つまり、この極小のものと極大の間でたゆたっている中間的な存在こそが人間であるとするのですね。
ここで同時代性という話になるのですが、第1次世界大戦を戦った多くの若い兵士たちのリュックサックのなかには、ハイデガーの『存在と時間』が入っていたといわれます。人間が不安定な存在だととうい思想には、第1次世界大戦後の、人間に対する強烈な不信感があります。これが哲学者も時代背景を背負いっているという意味なのです。
マルクス主義における「実践する人間」像
第1次世界大戦のもっている意味は二つあって、一つは総力戦という戦争形態です。戦場にいる以外の人間が動員され、戦いに巻き込まれるようになりました。もう一つはそのためにも使われた情報の力です。戦争の現場にいない人たちが、ラジオなどのメディアによって、リアルな戦況を知ることができるようになりました。もっと時代を下ってベトナム戦争になると、テレビがでてきて、それこそ寝ころがりながら人が戦争で死んでいくのを見られるような時代になります。三木がフランスにいたのは、そんな時代のはじまりの頃なのです。
第1次世界大戦で起きたのは、合理的で進歩的で啓蒙的という人間像の全否定です。「人間が賢くなった結果、人を大量に殺せるようになった」というのはいったいどういうことなのかという懐疑です。
パスカルの人間研究における「中間者」としての人間像は、こうした時代背景から出てきたものです。三木はまた、「夕の闇は私を悲哀に引き入れ、夜の闇は私を不安に陥れる。普通には情緒もしくは感情と見做されているこれら凡てのもの」これこそが「人間の存在論的なる原本的規定である」とハイデガーを引用しながら言っています。ものの見方が非常に暗い。何でこんなに暗い話になるのかというと、これも時代背景です。
1929年には世界大恐慌がおきて、一方で社会改造が必要となり、1917年にはロシア革命でソ連ができ、共産主義の力が強くなっていく。そうすると、三木清は「マルクス主義における人間的形態」という論文を書いて、マルクス主義を使って、今度「人間とは何か」を定義しなおすのです。人間の定義が全く変わってきて、人間というのは簡単に言うと実践し、行動する存在なのだというのです。
このように、時代背景とか、当時はやっている思想の影響を受けながら、人間の定義が変わってくるところがあります。人間観だけではない、国際秩序観も大きな変化を受けており、その危機を同時代の外交官にして知識人のE・H・カーが『危機の二十年』『平和の条件』で書いています。今から100年前は、あらゆる分野で従来の価値観の崩壊と再創造が模索されていました。22世紀の人間像は、こうした時代を参照することで見えてくると思っています。
*この連載は政策シンクタンクPHP総研が主宰する「22世紀の人間像研究会」での議論を記事化したものです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月01日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債


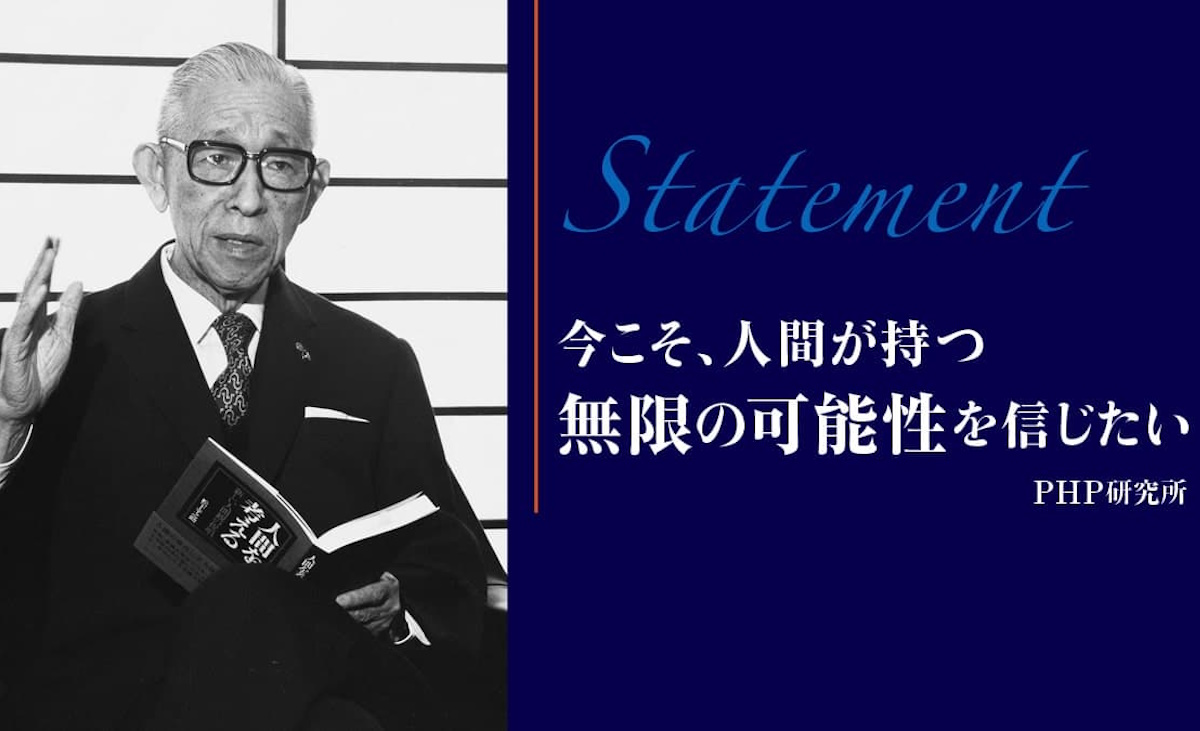




.jpg)
