対新型コロナ、リアリズムと「新しい地政学」の思考をもて
2020年04月15日 公開
2024年12月16日 更新
「救いの神」は見つからない
フランスの元外相ユベール・ヴェドリーヌは2007年に、その著書『「国家」の復権』(草思社、邦訳は2009年)のなかで、われわれがグローバル化に夢を見るあまり、国家を軽視するような傾向を、次のように戒めていた。
すなわち、「わたしたちは現代国家としてなすべき仕事を、国際社会や国連その他の『救いの神』に押しつけて逃げてはいけない」のだ。
というのも、「国家が主権を放棄しても、ヨーロッパや世界、あるいはなんらかの民主的な場がそれを引き継いでくれるわけではない」からだ。
同様に北岡伸一氏も、2001年の対テロ戦争が始まった年に、「国家の時代は終わったということが言われて久しい」が、しかしながら「依然として国際社会ではそのもっとも重要な主体であり、それぞれの国内では最終的な意思決定者でありつづけるだろう」と論じていた(北岡伸一「国家の弁証――21世紀日本の国家と政治」『アステイオン』55号)。
この2人とも、グローバル化がもたらした国際社会の変化に十分に留意しながらも、それによって国家の役割が減じたわけではないと論じている。
それはじつに的確な指摘であった。だが、そのころに人びとは、グローバル化が不可避的な世界的趨勢であり、同時にそれが多くの福音をもたらすことを信じていた。
ところが、世界はようやくそのような地政学的な国家間対立という現実に目を向けるようになったというべきであろう。
だとすれば、日本という国家、そして日本国政府がこれまで以上に賢明な政策判断を行なわなければならない。
「救いの神」を探しても、見つけることはできないであろう。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月07日 00:05
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

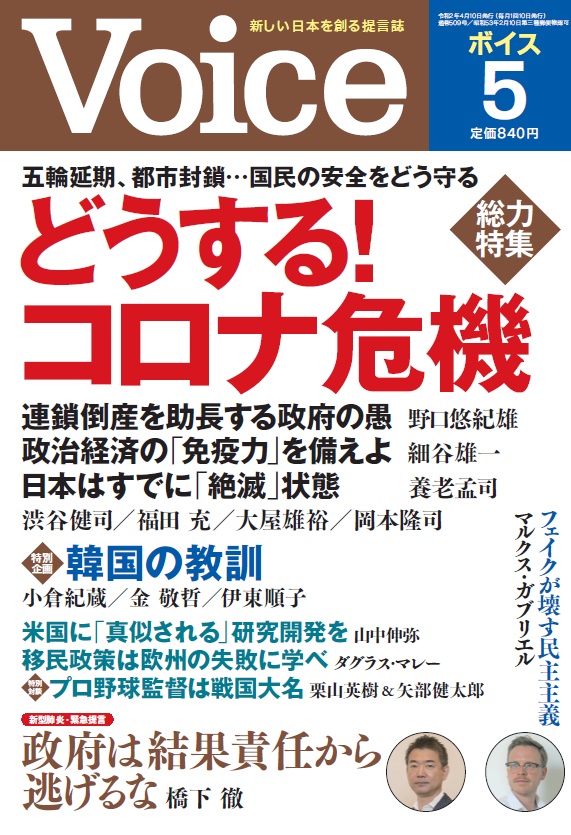





.jpg)
