赤字の公立病院をどう建て直すか? 現場を動かした「職業倫理に合致したKPI」

政策デザインの現場、さらにはあらゆる組織の経営において「KPI(重要業績評価目標)」が重要視されている。しかし、数字には大切なことを見失わせてしまう力もある。KPIの罠に陥らず経営改善を成し遂げた公立病院の例を挙げて考える。
※本稿は、亀井善太郎著『実務家のための政策デザイン入門』から、一部を抜粋・編集したものです。
収支目標の設定が腹落ちしない
政策デザイン、その実践としてのEBPMというと、KPI、数値目標の設定のことだという誤解が蔓延しています。
EBPMは政策立案(Policy Making)であって、立案にうまく使うことができるエビデンス(Evidence)を集め、政策をつくっていかなければならないのですが、なかなか、その理解が進みません。
背景には、うまく説明できる作文を作ろうとしている意識があるように思いますが、それも含めて、KPIという数字のワナを乗り越えた、政策デザインが求められるのです。
私が、ある公立病院の経営改革に携わったときのお話です。
この病院は地方のあるまちの、高度急性期の病院です。重症度が高く、24時間の看護が必要な患者さんを対象とする病院ですから、入院病棟もあって、400床ほどのベッドを有していました。
しかし同じ医療圏には、大学医学部附属病院があり、また、他にも高度急性期を担う病院が複数あって、激しい競争状況に置かれ、その結果として大きな赤字を出してしまい、地元自治体から財政支援を受けることになったのでした。そんなときに経営再建を手伝ってほしいと声をかけられたのです。
その自治体と病院を訪問してみると、経営再建のための方策がすでに検討されていました。公立病院によくある話なのですが、医師は数年先には大学に戻るかもしれないし、別の病院に行くことになるかもしれないから派遣元の大学医学部の方を見ている、看護師や薬剤師は日々の仕事で忙しく組織全体のことは考えられない、事務方は出向元の役所の方を見ている、といったわけで、当の病院のことは誰も考えていないという話が聞こえてきます。
そんな中、市の財政当局から提案があったのは、収支の責任を現場にも割り振ろう、具体的には、診療科ごとに収支の改善を割り振って、これにコミットしてもらおうというものでした。
たしかによくあるアイデアで、一人ひとりが経営者になるという発想です。うまくいくかもしれないし、まずは反応を聞いてみたいと思い、とりあえず、病院経営を担う病院事業管理者と、院長と、ある診療科長の打ち合わせに陪席することになりました。
事業管理者と院長から、診療科ごとの収支責任について説明を受けた診療科長の医師の反応は、自分はお金儲けをしたくて医師になったわけではない、病気やケガで苦しむ人を助けたいと思ったから医師になったわけで、収支責任といわれてもまったくピンとこないしやる気もでない、自分以外の医師や看護師も同じ思いだというものでした。
現場のやる気を引き出す目標設定に
なるほど、たしかにそのとおりです。このままではまずいなあと感じた私から申し上げ、診療科長とお話ししたのは以下のとおりです。
私:「先生のご専門は何でしたか。たしか、消化器外科ですよね。肝臓、すい臓、胆のうあたりの下部消化管をご専門にされていたと承知しています」
診療科長:「はい。そのとおりです」
私:「なるほど。ところで、お伺いしたいのですが、先生のご専門の領域の技術や知見を直接活かすことができる患者さんは、100人患者さんが外来にいらしたとしたら何人くらいいらっしゃるのでしょうか?」
診療科長:「10人くらいですかね。あまり多くはありません。残りの90人くらいの患者さんは、この病院というよりは、地域のかかりつけ医でも診ていただける患者さんかもしれません。公立病院ですから、受け入れないわけにもいきませんからね」
私:「いま進められている地域医療構想では、公立病院といえども、高度急性期として担うべき機能をしっかり発揮することが求められていますよね。例えば、これから進める改革というのが、先生の専門性をもっと発揮することができる、いまの10人を、20人、30人とさらに増やしていく方向性であるとすれば、それは賛同できますか?」
診療科長:「それなら大歓迎です。新しい技術を学び、積極的に取り入れ、患者さんの治癒に役立つものとして、自らの手技を磨いてきましたからね。それができるのならばチャレンジしたい」
私:「収支改善へのコミットメントではなく、先生の患者さん、先生の専門性が活かせる人を増やしていくことを目標にするのであれば、いかがでしょうか。これは同じ診療科の他の先生たちも同じです。それぞれの専門性が活かせる重症度の高い、高度な医療をもっとやれるようにしていくという方向性です」
院長と診療科長:「それはわかるけど、でも、自分たちは何をすればよいのか、よくわからない」
私:「この診療科の先生たちがコントロールできることとして、これから申し上げる2つのことをお願いするのはいかがでしょうか。①いまいる患者さんのうち、地元のかかりつけ医の先生にお願いしたほうがよい患者さんはお返しする、つまり、逆紹介を増やしていくこと、②先生の専門性について、かかりつけ医の先生たち、さらには、地域の市民の皆さんにお伝えする機会をもっとつくってください、どんどんお話しして、伝えていってくださいということです。いかがでしょうか?」
事業管理者、院長、診療科長:「それならやります。やりたいです。その2つであれば、自分たちがやるべきことですからね」
結果として、診療科長がコミットしたのは、①救急も含めて外来で来た患者さんをかかりつけ医に返す割合である逆紹介率、②地域でのカンファレンスの開催回数と市民向け講座の開催回数となりました。
これを進めていくうちに、病院に変化があらわれてきました。まず、外来患者が減りました。外来の待ち時間も減り、正午くらいに行くと、外来の精算窓口が空いてくるようになりました。
これによって医師たちは、入院患者のいる病棟に時間をかけられるようになりました。患者さんたちからの評価が高まったことはいうまでもありません。
かかりつけ医に患者さんを返したことによって、また、医師たちの専門性、技術の高さを共有したことによって、かかりつけ医からの紹介が増えるようになりました。
その結果、この病院の医師たちが担うべき重症度の高い患者が増えるようになりました。患者の回復が進めば、また、かかりつけ医に返します。併せて救命救急の強化にも取り組みました。
公立病院として、断らない救命救急を掲げれば、搬送数も増えることになります。救命救急の現場は毎日忙しいですが、自らの使命を果たしているので、現場のやりがいも高まっていきます。
結果として、担うべき質の高い医療を進めたことによって診療単価が改善し、病院経営を健全な水準に戻すことができました。
地域社会からの寄付も増えて、病院保有の救急車を持つようになるなど、地域に根差した高度急性期病院のあるべき姿に向けて、職員が一丸となって努力を重ねています。
この一連のプロセスでは、あるべき病院像を具体的な言葉で示すとともに、いろいろな数値目標も設定しました。しかし、収支目標を現場に課すことはまったくありませんでした。
大切なのは、組織が掲げる数値目標があるとすれば、それは、現場を動かす一人ひとりの専門性やその背景にある職業倫理に合致していることなのです。
最初の打ち合わせの一連のやりとりに見るとおり、納得がいかない数値目標は、そこで働く一人ひとりのやる気を削いでしまい、ひいては、組織の力を失わせてしまいます。
数字は、そこにいる人たちのやる気を引き出すことに使うこともできれば、それを失わせることもできるのです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

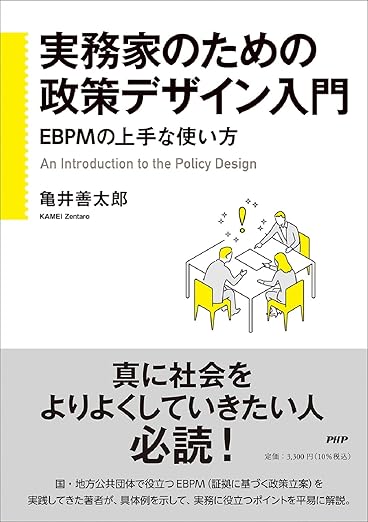





.jpg)
