「旬の美味しい食材」を守る新たな技術とは? 日本の食料自給率から考える

皆さんは"フードテック"という言葉をご存じだろうか?
食のシーンにデジタル技術(特にIoT)やバイオサイエンスなどが融合することで起こるイノベーションのトレンドの総称であり、特定の技術というわけではない、食に関わる無数の技術の集合知と言われる。
我々はフードテックを駆使することで、日本の食料自給率を向上させ、旬の美味しい食材を守ることはできるのか?フードテックの今に詳しい田中宏隆氏、岡田亜希子氏に解説して頂く。
※本記事は田中宏隆/岡田亜希子著『フードテックで変わる食の未来』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。
日本の食料自給率はなぜ下がったのか
かつて日本の食料自給率は高かった。
1960年にはカロリーベースで79%だったのだ。それが2023年には38%にまで落ち込んだ。これは農業労働従事者が高齢化したということもあるが、産業構造的な影響も大きい。一次産業は大変な労力の割には儲けが少ない産業になってしまったからだ。
食産業は、一次産業の産物を加工し、流通させる上で、さまざまな業者が入り込んでいる。農協、中間卸売、小売とバリューチェーンが長く、生活者に届くまでコストがかかる。
それでなくても、家族経営で小規模な農家が多く、大規模化したり技術を投入したりしている経営体も少ない。その上で、国民の健康を維持するために、ある程度の低価格を維持する「公共性」も求められる。
多くの企業が相当な工夫をして、今の食品価格を実現できるようにしているわけだが、薄利を多数の産業で分け合っている形だ。結局のところ一次産業に利益が配分される率は多くはない。
さらに、かつて日本は経済成長のために半導体や自動車など、高度な製造業の産物を輸出し、その代わり相手国から食料を輸入する政策をとってきた。安価な食料が輸入しやすくなり、ますます国内で生産することの優位性が失われていったのだ。
しかし昨今は、諸外国からの輸入に頼ることへの懸念が生じ始めている。2020年代から、世界は異常気象を繰り返すようになり、農作物はもちろんのこと、畜産や水産においても影響が出始めた。
パンデミック、戦争、米国政治の不安定さも相まって、世界の潮流は自国主義へと移っていった。国際平和を前提に自由貿易で食料やエネルギー源を海外から調達してきた日本も、自国での農林水産業の生産性向上が重要な国家課題となった。
農業従事者の平均年齢は年々上昇して70代となり、技術継承が難しく、加えて気候も変化している。農業分野はイノベーションが待ったなしの状態である。
あなたの食事の自給率は?
農林水産省が毎年調査している「食生活・ライフスタイル調査」の令和5年度の結果が実に興味深い。同調査では、30名の方に毎日の食事を撮影してもらい、いつ、何を食べ、食料自給率(カロリーベース)を予測してもらっている。ある27歳会社員の場合の1日はこのような感じだ。
朝食:韓国のり、白米、北海道プレーンヨーグルト
昼食:白米、ポトフ、煮浸し、赤辛もやし
夕食:炊き込みご飯、唐揚げ、納豆、トマト、味噌汁
本人が予測した食料自給率は、朝食90%、昼食90%、夕食75%だが、実際には、朝食79%、昼食20%、夕食53%となっている。本人としてはほぼ国産のものを食べているという認識だが、実際には相当輸入に頼っている。
他の方々を見ても、大半は本人が認識している食料自給率よりも、実際の食料自給率は低く、下表を見るとおおよそ10%以上差がある。
おそらく多くの人は、日本全体の食料自給率が40%を切っているとニュースで見たとしても、それを自分ごとと捉えていないのではないだろうか。自分自身は「国産」を選んで購入していて、輸入物はそれほど食べていないと思っている方も多いかもしれない。
しかし、ほとんどの日本人は、1日の食事の自給率を平均してならすと40%程度になると思って間違いなさそうだ。つまり、私たちが食べているものの50%以上は海外に頼っている。

日本の「食」で世界の課題を解決する─自給自足6.0
食料自給率を上げるべきだからといって、「日本は食料自給率100%を目指すべき」というのも、2024年の現実を見れば取るべき戦略とも言えない。食料課題はグローバルに存在する。自給自足100%を達成したとして、もし自給自足を脅かす社会課題が勃発すれば、たちまち私たちは命の危機に晒される。
国内の自給率を高めながら、世界の食料課題も同時に解決していくこと。世界のさまざまな社会課題に対して、日本の食という技で世界の食料課題解決に貢献していくことが、日本としての役割となろう。
そう考えると、2040年までに、私たちは単純に「これまでの自給自足」を目指すのではなく、新たな「自給自足」の姿を考え、そこにシフトしていく必要がある。
自給自足のイノベーションはすでに日本で起きている。完全閉鎖型植物工場の手法で精密農業を実現しているスタートアップのプランテックスは、AIを活用して精緻に環境を制御することで、植物の生産性や栄養価の向上、衛生状態の制御、そして効率的なエネルギー消費などをコントロール可能にしている。
つまり、土がないところでも植物を栽培することができるということだ。都市の高層ビルでも地下空間でも可能なほか、砂漠やツンドラ気候のような場所でも可能になる。現在はレタスなど葉物野菜が中心だが、米や穀類も栽培可能だという。
発電所を作るのと同じように工場群を作れば、日本の食料自給率は確実に上げられる上、この技術は海外でも活用できるので、中東やアフリカ、シンガポールなどの都市国家など、世界各地で食料自給率向上に貢献できる。
また、植物工場スタートアップのプランティオが推進する“アーバンファーミング”も、食料自給率向上に有効だ。ポイントは、都市に住む生活者が「農的活動」に楽しく参加することで、「食料自給率向上」を意識していようといまいと、結果的に食料自給率向上に貢献できることだ。
自分が食べたいための栽培で構わない。しかし、植物の栽培に触れれば触れるほど、スーパーで並ぶ野菜を見る目も変わるし、農家に対する見方も変わる。農業に対する関心が高まることは、日本の食料自給率を上げる上で重要な一歩だ。
自給自足6.0。これは、Industry5.0がデジタルやIoTを使って「人間中心で環境変化に対応した持続可能な産業」を目指したことの、さらに先の概念を打ち出したものだ。
自国の自給率だけでなく、世界中と技や情報をつなげながら、一人一人がそれぞれの場所から食料生産の営みに参加できる可能性を広げていく。これを自給自足6.0と称している。
日本人にとって大切な「旬のおいしい食材」という存在を後世に伝えるために、技術で何ができるか、文化として何ができるか、考えるべき時がすでに来ている。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月19日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算

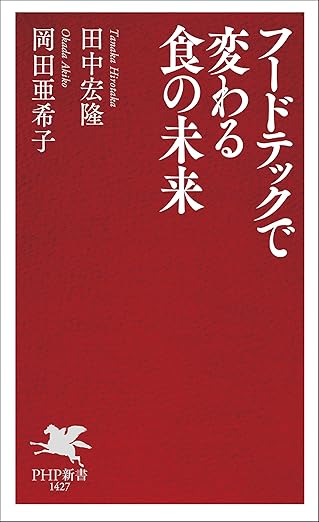





.jpg)
