ふえると困る「絶滅危惧種」 保全と経済発展のはざまで翻弄される野生動物
2025年10月30日 公開
2025年11月13日 更新

「守るべき存在」であった絶滅危惧種が、守って個体数が増えた結果、「厄介者」「排除すべき存在」になってしまうという現実は、自然保護という活動が抱える深いジレンマに他ならない――。
★本論稿は、意見集約プラットフォーム「Surfvote」と連動しています。
※本稿は、『Voice』2025年9月号より抜粋・編集した内容をお届けします。
社会的正義としての「生物保護」
「絶滅危惧種を守ることは大切ですか?」と聞かれたら、もちろん大切であると誰もが答えるでしょう。なぜ守ることが大切かと問われれば、それは人類の活動によって地球環境が破壊された結果、招いた事態であるからだと言わざるを得ません。絶滅危惧種は人類の活動の「犠牲者」であり、われわれ人類は「加害者」として、被害の軽減と損失の回復に努める義務があるということです。
「絶滅危惧種」と称される種は、国際自然保護連合(IUCN)が作成するレッドリストにおいて、2025年3月現在で、哺乳類だけで1363種、動物の合計は1万8109種、植物や菌類その他を含めると生物種全体で4万7000種以上がリストアップされています。これだけの数の絶滅危惧種を保護するには、一体どれくらいの資金が必要でしょうか。
少し古い論文ですが、たとえばScience誌に掲載されたMcCarthyら(2012)の試算によれば、鳥類の絶滅危機種の保全だけでも、年間で少なくとも8億7500万~12億3000万ドルが必要であり、哺乳類や両生類などほかの分類群も含めると、その額は年間34億~47億ドルに達すると言われています。
世界各地では官民問わず環境保全・保護政策が立ち上げられ、「ネイチャーポジティブ」「サステナブル」「カーボンニュートラル」などさまざまな標語のもと、自然を守る取り組みが推進され、多額の資金が投入されています。われわれ人類は、かつて環境を破壊し経済発展を遂げて得た利益をもって、まるで借金を返すかの如く、環境の保護や保全・回復に多額の費用を費やしています。
絶滅危惧種を守るためのこうした取り組みのなかには、成果に結びついたものもたくさんあります。一方で、同時にその「成功」が新たな問題を引き起こす、すなわち、保護された種の個体数が回復したことで、人間社会とのあいだに新たな軋轢が生まれてしまう事例もあります。
たとえば、農作物の被害、生活空間への侵入、インフラの破壊といった経済的・社会的な損失が、増えた絶滅危惧種によって引き起こされてしまうのです。
このように、かつて「守るべき存在」であったものが、守って個体数が増えた結果、「厄介者」「排除すべき存在」になってしまうという現実は、自然保護という活動が抱える深いジレンマにほかなりません。
絶滅危惧種・ベニガオザル
私が10年にわたり研究をおこなっているタイ中部に位置するカオタオモー保護区に生息するベニガオザルの事例は、まさにこのジレンマを象徴する典型例です。ベニガオザルはインド・中国・タイ・ベトナム・マレーシアなど、アジア地域に生息しているマカク属のサルの一種です。森林伐採や土地開拓によって生息域が消滅・分断化され、IUCNのレッドリストでは野生下での地域個体群の絶滅が危惧されるVulnerable(絶滅危惧Ⅱ類)に分類されています。
急峻な石灰岩質の岩山を好んで生息するためか、人間が追跡して観察・研究することが非常に難しく、野生下での研究はほとんどおこなわれていません。本種に関する長期的・継続的な研究を実施している場所は、世界でも私の調査地以外にはありません。
このカオタオモー保護区は、現在はタイ国立公園野生動植物保護局が管理する国立公園に準ずる「禁猟区」ですが、かつてはただの森でした。契機は1984年、ここで初めて野生のベニガオザルの群れの生息が確認・記録されたことでした。
当時の論文によると、確認されたのはわずか22頭という、非常に小さな群れだったようです。岩山であるがゆえに開発の手が及ばず、かろうじて残された麓の森の恵みを頼りに生き延びていたのでしょう。この野生群の発見を踏まえ、現地研究者がこの地域とベニガオザルの保全の重要性を当局に訴え、1999年に「禁猟区」に制定されることとなりました。この区域内でのベニガオザルを含むすべての野生動物の狩猟・捕獲が禁止され、タイ国立公園野生動植物保護局の職員が駐在する場所となりました。
禁猟区制定当時は森の奥まった場所にある広場でしかサルを見ることができなかったようです。そのため、入り口にはゲートが設けられ、サルを見にきた人から入園料を徴収していました。広場ではサルにエサをあげることもできたようです。サルたちは保護されるようになってから、地元の観光客を呼び込みお金を生む"観光資源"になったのです。
仏教国であるタイ王国では、地域住民や観光客による野生動物への餌付け行為が頻繁に見られます。お腹を空かせている(ように見える)野生動物に食べ物を与えることは道徳的行為であり、徳を積む行動("タンブン"と言います)であると考えられているためです。当然ながらこのカオタオモー保護区でも、地域の人が野菜や果物など余剰生産農作物を"タンブン"するために持ってきてはサルに与えるようになりました。
ヒトから食べ物をもらうことを覚えたサルたちは、次第に森の奥から山の麓の道沿いや近くのお寺にも出てくるようになりました。サルの出没範囲が広くなったのみならず、餌付けによる栄養状態の好転により、当然ながら個体数もどんどん増加していきます。
1984年には22頭しかいなかった、もはや絶滅寸前だったこの地域のベニガオザルは、2012年の段階で4群・計296頭、2018年には群れがひとつ増えて5群・計391頭、そして2025年現在では6群・460頭以上にまで増えました。非自然的であるとはいえ、個体数は見事に回復し、その保護に"成功"したと言えるわけです。
保護“成功”のあとに待ち受けるもの

日常的に行われる餌付け風景。2tトラックに満載した果物が与えられ、サルたちが全て食べきるのに1週間を要したこともある。恒常的に超過剰な食べ物が与えられるため、個体数は当然ながら急激に増加する。
これで話が終わっていれば、「日本では考えられないけれど、こういう動物保護のあり方もあり得るか」という学びのある事例と言えます。
しかし、そうは問屋が卸さないのが現実です。カオタオモー保護区では2020年以降、保護区周辺の農地にサルが出没し農作物を食い荒らす"猿害"被害が深刻化し、地域の農家との軋轢が激化しているのです。対応に苦慮したタイ国立公園野生動植物保護局の役人から相談を受けた私は、研究者の立場からこの問題の解決に関わることとなりました。
ここで10年もサルたちを見てきている私からすれば、農作物被害の発生はある意味で、"起きるべくして起きている当然の帰結"でした。地域の住民や農家は皆、口を揃えて「サルが増えすぎているのが原因だ!」と言います。それはある意味で正しいのですが、サルが増えすぎているそもそもの原因は、ヒトが無秩序に餌付けをおこなうからです。
仮に1984年にいた22頭がこの森にいたサルのすべてだとして、2025年現在の460頭に至る個体数の変遷状況は、とても自然な個体数増加とは言えません。
私が簡易に試算した限りにおいても、メスが性成熟後に毎年子どもを産み続け、乳児の死亡率は極めて低く、寿命ギリギリまで全頭が生き延びるという、相当な条件をクリアしないと整合性が合わないような経過を辿っているわけですから、自然要因以外に人為的な要因が甚大な影響を与えているのは間違いありません。サルは自然に増えたのではなく、まさにヒトが「増やした」のです。
もうひとつ、個体数増加以外の大きな要因があります。それは、保護区周辺の土地利用の変化です。われわれは衛星画像を用いて、過去10年間に保護区周辺の土地利用がどのように変化したかを解析したところ、禁猟区指定エリア以外の周辺の雑木林が、境界際々まで農地や太陽光発電所などに転換され、自然植生が破壊されていたことが可視化されました。
要するにサルたちは、個体数は毎年増えていくのに、森はどんどん破壊されて年々生息空間を奪われている状況でした。サルの遊動域が保護区からどんどん外に拡大していくのも、仕方がない状況です。
2020年以降で土地開発が急速に進んだ理由は、同年から施行された改正土地・建物税法による影響でした。この改正法下では、未使用の土地には税金が課せられる一方で、開発された農地であれば課税が免除されるのです。よって保護区周辺の土地所有者は、課税を逃れるために雑木林を次々と伐採して農地にしていったわけです。
さらに悪条件が重なります。雑木林を伐採して切り開いた農地で、サルたちが日常的に人間からもらって食べている果物を栽培作物として植えているのです。バナナやパイナップル、マンゴーやジャックフルーツといった果物は、自然の森には存在しない食べ物です。こうした果物が「食べられる美味しい食糧資源である」とサルたちに教えているのは、日常的に餌付けをしている人間です。
その人間が、サルの生息空間である森を伐採し、そこに農地を作り、普段サルたちに与えている果物を作っているのです。かつての遊動域を習慣的に訪れるサルたちがそれらの農作物を見つけたら、食べるのは当然です。サルにとっては、人間から"タンブン"で与えられるパイナップルと、農地に植わっているパイナップルの区別はありません。
ここまでくると、もはや人間側にはサルを非難する道理はまったくありません。個体数の増加、生息域の破壊と農地への転換、農作物への誘因......問題となっている事象のすべてが人間のせいで起きていることは、誰の目にも明らかです。
仏教国タイならではの苦悩

タイではカニクイザルの個体数増加も問題になっている。都市環境へも容易に進出するカニクイザルは人との軋轢を生みやすく、タイ各所で大規模な捕獲措置が取られている。撮影:プラチュアップキリカーン県フアヒン市内
タイ国内での増えすぎたサルによるこうした問題は、私の調査地に限った話ではありません。あちこちで餌付けが日常的に行なわれているわけですから、サルはどんどん増えていきます。タイではこうした増えすぎて問題を起こす動物に対する対策は、避妊手術か、捕獲後にケージへの収容ないしほかの場所での放獣が一般的です。しかしどれも科学的には正しい対策ではありません。
避妊手術は、その個体から「次世代を残す権利」を生涯にわたって不可逆的に剥奪する行為であり、動物福祉の観点から容認できる対策ではありません。
仮に避妊をするにしても、どれだけの個体数を避妊すれば効果的に個体数の増加を抑制できるのか、非常に複雑な個体群動態モデルを組んで検証をしなければなりません。無計画に必要以上の個体を避妊してしまうと、将来急激に少子化し、群れが消滅する恐れがあるためです。こうした取り組みは世界中で行なわれているものの、多くの場所で個体数増加の抑制に失敗しています。人間の考えた予定どおりにうまく進まないのが自然です。
捕獲後ケージへの収容は、まさに「投獄」と同じです。何の罪もない野生動物をある日突然、ケージに押し込めるのは非常に残酷です。かといって、別の場所に放獣するのは、人為的遺伝撹乱の原因となるため、これも悪手です。タイで一般的などの方策をとっても科学的には間違ったアプローチばかりですが、動物の殺処分をしない仏教国ならではのジレンマがここに垣間見えます。
生物保護のジレンマとどう向き合うか
正直に告白すると、私は長年、野生動物の保護保全との関わりを意図的に避けて、行動観察という純粋科学の"コンフォートゾーン"で研究をやってきました。「絶滅危惧種の保護」というのは、場合によっては複雑な利害関係に絡め取られて「科学的正しさ」が役に立たないことが多く、もはや学術研究の領域を超えて「政治化」「ビジネス化」する傾向があると思っていたからです。
しかし、自分の調査地で、自分の観察対象のサルたちが農作物を食べるせいで、地域住民によって殺されている可能性があるという事実を突きつけられたことにより、私はこの領域に足を踏み入れることになりました。
活動を始めて3年目になりますが、ベニガオザルによる農作物被害の話をしていると、いつも引っかかることがあります。「農作物被害問題」という表現のなかに、人間があたかも「被害者」であるかのような構図が内在していることに対する違和感です。
こういう表現を使わないと一般的理解が得られないので、本稿でもやむなく使用していますが、もとを辿れば自然環境を破壊し、野生生物の生息地を奪って動物を絶滅の危機に追いやってきたのはほかならぬ人間なのです。
そして人間の都合で、数が減ってしまった動物を保護するという選択をしたあとで、その"成果"が人間社会に「跳ね返って」くるとき、あたかも人間側が損害を受けているかのような立場をとる構図に、動物学者としてはうんざりとすることがあります。
もうひとつの引っかかりは、研究費の獲得の難しさです。自然保護の枠組みのなかで、多くの研究費や助成金は「絶滅回避」「個体数の増加」を最終目標として活発な資金投下が行なわれている一方で、保護成功後の動物と地域経済との共存や、適切な個体数の管理には関心を払われることなく、なかなか研究資金を獲得することができません。まるで「保護するために活動すること」そのものが目的化してしまっているような雰囲気さえあります。
「絶滅危惧種の保全」と「地域経済の発展」の持続可能な両立という難しい問題への対処は、もはや動物保護としての"魅力"が失われたものとして後回しにされ、別スキームの構築を求められるのです。
数が減っては困りますが、増えても困るわけです。つまり、絶滅危惧種は「絶滅の危惧が懸念される状態のまま」「保護活動が必要とされる状態のまま」存続してもらうほうが、人間にとっても、社会にとっても、都合がいいわけです。
まさに一部の人間のエゴとも言える"保護活動"に翻弄されている動物たちを見ながら、彼らを保護することが本当に彼らのためになるのか、研究者として自分がなすべきことは何なのか、自問自答を繰り返す日々です。
タイで初のモデルケース構築をめざして
ベニガオザルたちによる農作物被害にどんな生態学的な背景があろうが、地元の農家からしたらそんなことはどうでも良い話です。今日も、明日も、自分の農地にサルが来て、農作物を食べ荒らすわけで、その経済的な損失は日々大きくなっていくばかりです。そのサルが絶滅危惧種であろうとなかろうと、自分の生業を脅かす存在であることには変わりなく、"排除"を望む声が年々高まっています。
そこで私は、タイの二大学と共同で、この地域のベニガオザルの保護保全に関するプロジェクトを立ち上げることにしました。コンセプトは、「科学的根拠に立脚した保全計画の策定」です。
このプロジェクトは、二つの大きな柱で構成されています。柱の一本目は「自然淘汰による適正頭数への収束に向けた学術調査」で、もう一本は「農作物被害の即時的な軽減に向けた農地防護技術の普及」です。
自然淘汰による適正頭数への収束に向けた学術調査は、人為的・侵襲的な個体数管理の方策をとらず、自然淘汰によって、保護区の環境収容力に適した頭数まで自然に収束させることをめざすものです。
現在サルたちは、人間から超過剰な食糧供給を受けて個体数を増やしています。まずはこの餌付けを規制し、保護区内の植生内で入手可能な食糧資源のみで、自然に生きていけるようにしなければなりません。その過程で、森の環境収容力が現状の個体数を下回っていれば、サルたちは淘汰によって自然に個体数が適正サイズまで減っていくことになりますが、その環境で安定して持続的に生きていくことができるようになります。
実際に、保護区の森にどれくらいの環境収容力があるか(何頭くらいのサルたちが食べ物に困ることなく暮らしていけるか)を調べるには、植生調査や果実生産量の調査などをおこなう必要があります。
また、サルたちが自然植生内で何をどれくらい食べているのかという採食生態データも必要です。こうしたデータをもとに、適切に保護区内の森林を保全・管理できれば、サルたちは保護区内だけでその暮らしを完結できるようになるでしょう。
とはいっても、自然に適正な個体数に収束するまでには相当な時間を要します。その間もサルたちによる農作物被害は出続けます。そこで二本目の柱に、農作物被害の即時的な軽減に向けた農地防護技術の普及を掲げています。
農作物被害を軽減するには、サルを農地に侵入させない対策をとる以外に方法はありません。サルから農作物を守るシステムが構築されれば、軋轢を軽減することができ、サルたちが自然に適正な頭数に収束するまでの時間を稼ぐこともできます。
こうした科学的根拠に基づく保護動物の保全管理と地域経済との持続可能な共存をめざす取り組みは、これまでタイでは実施されてきませんでした。
今回、われわれがタイの大学と協力して推進するこの事例が成功すれば、タイで初のモデルケースとなります。この国の生物保護の新たなあり方を模索する一歩となるように、今後も取り組みを推進していきたいと思っています。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月21日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること





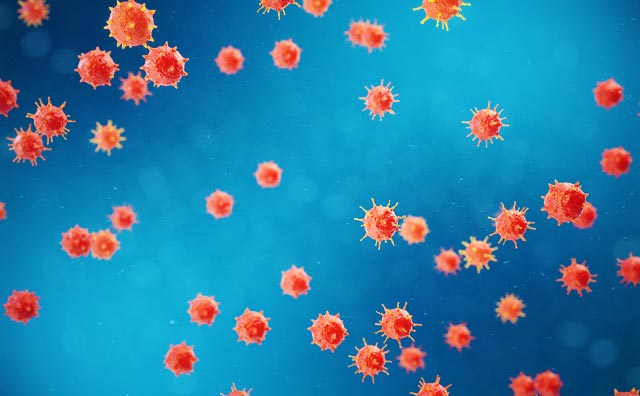

.jpg)
