戦後77年、「大東亜戦争」を経て日本が失ったものとは
2022年08月08日 公開
2024年12月16日 更新
ヨーロッパとアジアの連動
本書が最も力を入れて論じ、また独自性が強く出ていると考えるのが、ヨーロッパ情勢とアジア情勢を連動して捉えていることである。
たとえば、松浦正孝・立教大学教授は、「日本のアジア主義を練り上げたのは国際的な孤立感であった」と、満洲事変後の欧米からの批判で孤立した日本が、新たな秩序構想を抱き始めたそのつながりに注目する。
さらには、「当時の日本にとっては中華世界の解体と英国の駆逐こそが『国是』であった」と論じ、そのような「大和民族」の一大「事業」の帰結として、「東亜新秩序声明」が生まれていく。満洲事変を1つの大きな転機として、日本は後ろに下がれなくなってしまった。
日本が「満洲」という新しい空間で新たな開発を展開していったことが、グローバルな経済システムの再編と連動していたのである。だが、そのようなグローバルな動向を視野に入れて、そのことがアメリカの強い反発を喚起することについてあまりにも鈍感であったのだろう。そのことが、「大東亜戦争」勃発の伏線となる。
またドイツ軍事史家として高名な大木毅氏も、ヨーロッパとアジアの情勢が緊密に連動していた現実を活写する。日独伊三国同盟を学んできた我々は、あたかも日独協力が自明であったかのような認識をもつかもしれない。だが、大木氏によれば、伝統的に、「ドイツの極東政策は著しく親中路線に傾いていた」という。
だが、日本は陸軍を中心に、ドイツとの提携を求める「片思い」が見られた。そこに、ヒトラー政権が成立したことで、風向きが変わった。
1938年にヒトラーは、チェコスロバキアへの侵攻を計画していた。だが、英仏の介入の可能性は払拭できなかった。そこで「ヒトラーが眼をつけたのは日本であった」と論じる。
すなわち、ヒトラーから見れば、「日本と軍事同盟を結ぶことができれば、英仏ソは、極東の国土や植民地においても戦争に突入すると覚悟しないかぎり、チェコ支援を実行することはできない」。
いわば、「世界強国」をめざすヒトラーからすれば、チェコスロバキア侵攻という自らの領土的野心を実現するために、日本は都合の良い「駒」であったのだろう。ヨーロッパ情勢を冷静に分析することなく、日独二国間に奔走したことによる死角だったのかもしれない。
グローバルな大国として、ヨーロッパとアジアにまたがって戦略を形成していたのが、アメリカとソ連であった。世界戦略の一部として対日政策が位置づけられていたローズヴェルト政権の戦略を論じる村田晃嗣・同志社大学教授の章を読むことで、その全体像を俯瞰することができるだろう。
また、花田智之防衛研究所主任研究官は、「日本が太平洋戦線に集中し、ソ連が東部戦線(独ソ戦)に集中するため、互いに外交的・軍事的中立を必要とした」と論じ、「既存の国際秩序への挑戦国同士」である日ソ関係の特殊性を論じる。
それ以外の章でも、世界史的な視野から各国の動向を概観し、「大東亜戦争」の「複合性」がよりいっそう明らかになるであろう。
世界情勢をより深く理解するために
ウクライナでの戦争は、中国による台湾の武力統一への懸念を拡大し、また中国によるロシアへの実質的な支援がロシアの侵略的行動の継続を可能にし、停戦の可能性を不透明にしている。
こうしてヨーロッパ情勢とアジア情勢が連動することについては、それぞれの地域を切り離して各地域の専門家が論じる傾向が強いことから、これまでしばしば看過されてきた。
歴史研究でも、専門分化が進み、地域横断的で、巨視的な視座から歴史を語ることは以前よりも難しくなっているのかもしれない。
そのようなことからも、以前拙著『歴史認識とは何か』(新潮選書)のなかで、「空間的な束縛」、すなわち「日本を世界から切り離して、日本国内を閉じられた空間として論じる」問題に言及した。
そのような「束縛」から解放して、より自由で広がりのある視座から、「先の大戦」を捉え直さなければならない。日本が自らが開戦した「大東亜戦争」を、自らの営みとして主体的に総括し、それを世界史の中に埋め込むことが重要だ。
我々がこれまで知っていると思い込んできたこの戦争についても、『世界史としての「大東亜戦争」』を通じて多くの発見が得られるのではないかと期待している。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債


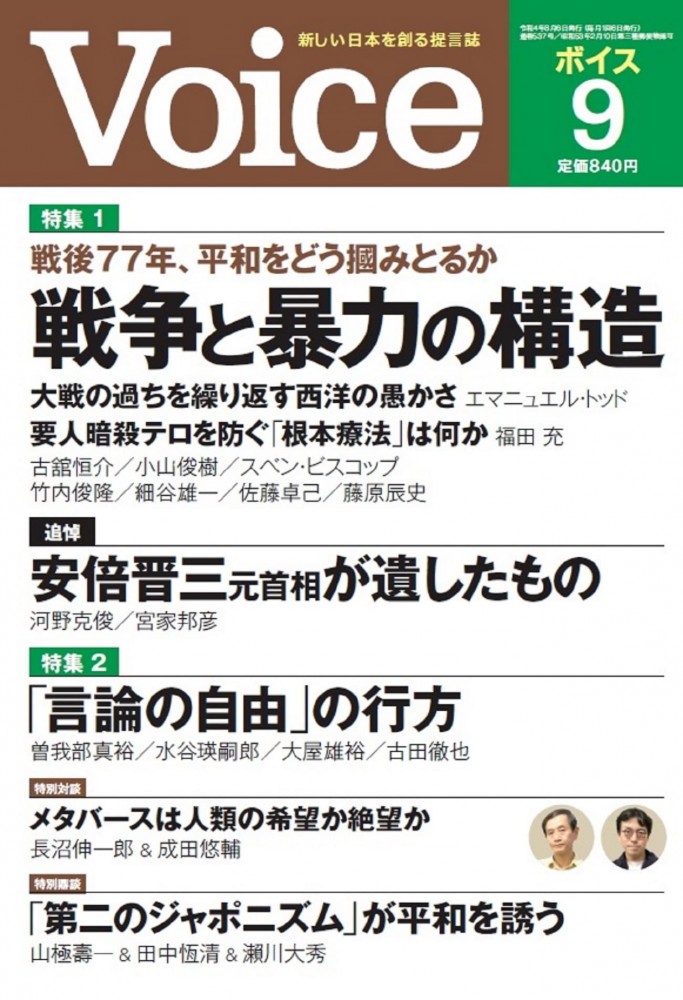




.jpg)
