「夜の街」の憲法論―飲食店は自粛要請に従うべきなのか
2021年06月14日 公開
2024年12月16日 更新

夜の街に賑わいが戻るのはいつになるのか…?(画像はイメージです)
度重なる緊急事態宣言による営業自粛や時短の要請で「夜の街」は壊滅的な打撃を受けている――そもそも従う必然性はどこにあるのだろうか。長年、スナックを研究している東京都立大学法学部教授・谷口功一氏は、かつて憲法学と法哲学の間で行なわれた「二重の基準」論争にヒントがあると語る。
※本稿は『Voice』2021年7⽉号より抜粋・編集したものです。
左派三紙の唖然とする憲法特集
5月3日の憲法記念日、もう20年以上、個人的な恒例行事になっている新聞全紙購入をしてきた。
2015年の「集団的自衛権祭り」の際には異様な盛り上がりを見せた憲法論議も、その後、憑き物が落ちたように低調化し、ここ数年は、各紙、おざなりな内容の企画が続くことも相まって、この恒例行事も苦痛になってきていたのだが……。
折しも3度目の緊急事態宣言が発令され、とうとう外で酒を呑むことさえできなくなった状況下での憲法記念日――韓国・軍事独裁政権の戒厳令下でさえ午前0時までは外で呑めた酒を禁じられた暗鬱たる日々のただ中で、各紙は何を重視し、どのような特集を組んでいるのか、私は紙面をめくってみた。
結果は予想外の驚きと失望だった。とくに朝日・毎日・東京新聞の左派三紙の内容には思わず目を剥いた。三紙ともに、この状況下で大書して特筆すべき憲法的イシューとして「ジェンダー問題」を掲げていたのだった。
『朝日新聞』は一面に「男女平等の理念 遠い日本」と大見出しを掲げ、二面では昇進差別・女性活躍・選択的夫婦別姓問題、五面には「世界のジェンダー平等の歩み」という巨大な年表を掲載していた。『毎日新聞』は、見開き全面を使っての夫婦別姓議論。
きわめつきは『東京新聞』で、一面に「憲法24条 軽視の1年」と大見出しを飾ったうえで、日本学術会議や民主主義科学者協会法律部会の関係者を中心とする学者・弁護士・活動家などの「有識者」らが昨年、政府に要望したコロナ禍でのジェンダー平等の対策強化(9項目)の政策反映度をチェックしていたのだった。
このようなかたちでの「チェック」に、記事としてのいかなる公共性(客観性)があるのかという問題はさておくとしても、2020年に最も軽視されたのが憲法24条であるという認識には唖然とせざるをえなかった。
この間、軽視され続けたのは、男女の別を問わず多くの人びとの生活を根底から脅かした「営業の自由」にまつわる問題、つまり憲法22条だったのではないか、というのが私自身の偽らざる思いだったからだ。
友人の学者は、以上のような各紙の紙面構成に対して「マジでトランプ5秒前」と言っていたが、まったくそのとおりであって、その意味するところについては本稿後半で「承認の政治」と「再分配の政治」を対比しながら詳述したい。
苦境に立つスナック
筆者は2015年からサントリー文化財団の研究助成の下、いわゆる「スナック研究会」というものを主催し、その成果として『日本の夜の公共圏 スナック研究序説』(白水社)という本を出したりもしている。
その関係で、このコロナ下でも全国のスナック経営者の方々からメールや電話、ときにはZoomなどを通じて、厳しい状況について話を伺い、また相談や愚痴を聞くことも多い。
昨年の夏頃には、あまりにも多くの苦境についての話を聴きすぎた結果、自分自身もスナック経営者の心情と同一化してしまい、深刻な気鬱になってしまったほどだった。いまでもスナックを含む飲食店の経営者たちが、どのような気持ちで毎日を過ごしているかと考えると、いたたまれなくなる日々だ。
昨年4月から独自に全国のスナックの軒数を経時的に記録し始めたが、この一年ちょっとの間に、最も少なく見積もっても8,000軒以上(全体の1割超)のスナックが全国で廃業しており、この勢いはさらに加速することが予想される。一つの産業セクターとしては壊滅的な事態である。
この間、仕事で訪れたある地方都市では、緊急事態宣言その他いかなる営業制限も出されていないにもかかわらず、その地域では最大の歓楽街の9割を超える店が灯りを消してドアを閉ざしていた。
所在なげに佇む客引きの男性と立ち話したところでは、とにかく夜になると人っこ一人歩かないので、予約があるとき、週末だけ店を開けるのだと言う。
地元の大手経営者の話では、シングルマザーで子どもを抱え路頭に迷いそうになっているホステスさんたちを助けるために、地元商工業界の名士たちが会社や工場で彼女たちを臨時で雇う分担の振り分けさえしているとのことだった。
「(緊急事態)宣言が出たりして休業させられたほうが、協力金などが出るので羨ましい」という話が重く心に残る。このような話は、全国いたるところで、現在進行形で存在している。
コロナ下の初期から「夜の街」として指弾・規制の対象とされた、このスナックという存在、じつのところ前回の東京オリンピック(1964年)と共に生まれたものなのだが、二度目のオリンピックを迎えるこのタイミングでの、この惨たらしいまでの状況は、もはや皮肉を通り越して、それを表現する言葉さえない。
首都圏に住むホワイトカラー層には、あまりピンとこないかもしれないが、近年でもとくに地方部ではスナックは夜の社交を通じた一種の「公共圏」として重要な機能を果たし続けてきた場所であり、また、人口縮減に苦しむ自治体では公的助成を受けた「夜の公民館」的なスナックや、あるいは超高齢化社会に対応した「介護スナック」などの画期的な取り組みも存在しているのである。
圧倒的なコロナ下の存在に覆い隠されてしまった人口減や高齢化などの問題が再び前景化される日まで、全国のスナックのどれほどが生き残ることができるだろうか……。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月13日 00:05
- 「私が長官を撃ちました」 國松長官狙撃事件の真犯人は誰か
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- なぜ日本だけが「目の敵」にされるのか 習近平政権が台湾問題で絶対に譲らない理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点
- イギリスでさえも二大政党制が融解 ヨーロッパに見る従来型政党政治の限界と模索
- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か


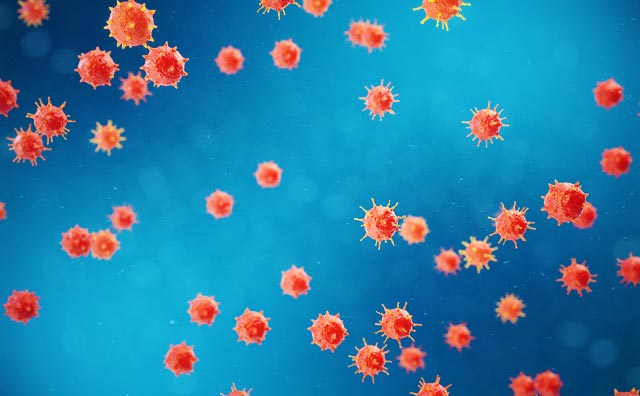

.jpg)
