「夜の街」の憲法論―飲食店は自粛要請に従うべきなのか
2021年06月14日 公開
2024年12月16日 更新
「経済的自由」は「精神的自由」より劣るのか
ところで、スナックをはじめとする飲食店に対して、この間、当たり前のように行なわれている「時短」や「休業」要請などの営業規制は、いったい何を根拠として行なわれているのだろうか。
そのことを考えるにあたって、かつて憲法学と法哲学の間で行なわれた「二重の基準」論争を振り返ってみたい。
憲法学においては、営業の自由を含む「経済的自由」の公権力による規制は、表現の自由などの「精神的自由」の規制よりも緩やかな司法審査に服すこととなっており、このように規制対象によって基準が二重になっていることを指して「二重の基準」と呼んできた。
噛み砕いて言うなら、「営業の自由」は「表現の自由」や「報道の自由」などに比べると、簡単に政府による規制の対象となってしまうのである。このようなかたちで経済的自由を精神的自由に対して劣位に置くのは、「知識人」特有の偏見なのではないかと法哲学者の井上達夫は論じた。
以下、有名な一節だが、井上は「例えば、中卒の学歴しかないために、社長と呼ばれるのを生き甲斐にして事業に精を出す人や、一国一城の主として独立するために個人タクシーをやりたいと、何度も運輸省に申請を繰り返すタクシー運転手にとっての営業の自由は、自己の研究を発表しようとする大学教授にとっての言論・出版の自由に比して、内在的価値において何ら劣るところはない」と言うのである。
これに対して憲法学者の長谷部恭男は、人びとが何に生き甲斐を見い出すかは「当人にとっての主観的価値にとどまる」ものであり、「その当人にとってしか意味の無い行為であるにもかかわらず、なぜ社会一般に共通する『公共の福祉』を理由とする制約に対抗できるのであろうか」と冷淡に反応する。
長谷部はさらに「個人の自律を尊ぶ以上は、個人が選んだ生き方についてはその個人が責任を負い、自らそのコストを負担すべきである」とも言うが、これははたして(長谷部も好んでその理論を引用する)ロナルド・ドゥオーキンの「選択の運(ギャンブルなど自らの意志で選択した結果)」と「自然の運(災害など自らの意志によらない不可避な結果)」の区別を踏まえても、また、このコロナ下でもなお、通用する理屈なのだろうか。
ちなみにこのことについては最近話題になっているマイケル・サンデルの『実力も運のうち 能力主義は正義か?』(早川書房)のなかでもわかりやすく説明されている。
営業の自由は、じつのところ憲法典のなかには明示的に記されていない言葉であり、それは憲法22条の「居住、移転・職業選択の自由」から導出される権利だ。これについては複雑な議論が存在し、憲法学者・石川健治などがきわめて精密で整序された議論を展開している。
しかし、今回、石川らの議論をあらためて読み返してみて思ったのは、全体として憲法学は大企業を念頭に置いた消費者保護・環境規制や競争政策のほうに関心をもっていかれがちで、普通のありふれた中小事業者の「生存」と「人格実現」がかかった「営業」に定位した議論が希薄なのである。
そもそも、なぜ「精神的自由>経済的自由」なのかというと、前者に含まれる言論・出版の自由は、民主的政治回路を健全に作動させるための必須条件であり、それがいったん損なわれると回復困難なダメージが政治社会にもたらされるからなのだと説明される。
しかし、この間の各種報道を見ている限りでは、はたして民主政の守護神(?)として手厚く擁護されている報道が、我々の政治社会を守るために、本当に正しく立ち働いているのかは甚だ疑問とせざるをえない。
みなまでは言いたくないが、昼間の低劣なワイドショーや感染者数だけを垂れ流して不安だけを煽る「報道の自由」を、ただ正直に商売をしたいだけの飲食店を含む中小事業者の「営業の自由」よりも厚く保障することに何の正義があるのだろうか。
もちろん精神的自由が、それ自体として重要なものであり、憲法的価値の中核の一つを構成していることは否定しない。しかし、このような破廉恥な状況が今後も続くようなら、「報道の自由」を含む憲法典全体、立憲主義的秩序そのものの正統性が根本から掘り崩されかねないことが強く懸念されるのである。
コミュニティの喪失が及ぼす影響
私の好きな言葉に「独裁者が恐れるのは、経済生活に疎いインテリなどでは毛頭なく、自分の足でしっかと立つ独立自営業者である」というものがあるが、日々、何の変哲もない営業を続ける自営業者たちこそがデモクラシーの担い手であり、先に示されたような理屈(二重の基準)で劣位に置かれるいわれはないのである。
デモクラシーとの関連では、最近、イギリスのパブについて興味深い論文が話題になっていたことが思い出される。
日本のスナックと同様、コミュニティの集いの場となっているイギリスのパブは、昨年5月段階で、秋までには全国4万7000店のうち4割が閉店する可能性があると報道されていた。
この時点では9月までに2万店近くが閉店に追い込まれ、パブで働く23万人の雇用が失われる可能性があるという試算も出されていたのだった(『毎日新聞』2020年5月9日)。
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのダイアン=ボレット氏は、最近「孤独な呑んべえ/地域の社会文化的荒廃と極右の伸張――廃業に追い込まれるイギリスのパブを事例に(Bolet, Drinking Alone)」という論文を比較政治学の国際ジャーナルに投稿し、評判を博した。
その内容は、地域におけるパブの閉店は、人びとの社会的孤立を引き起こし、イギリスの労働者階級の生活条件の悪化のシグナルになっているというものだ。
じつに興味深いことに、パブが地域から姿を消すことによってコミュニティのハブとなる場所が失われ、その帰結としてイギリス独立党(UKIP、右翼政党)への投票行動が促進されるというのである。
この論文は複雑な統計学を駆使した専門的な内容なのだが、結論は明瞭で、人びとの「夜の社交」を支える場所が失われることは、じつは政治的にも大きなインパクトをもつというきわめてシンプルな指摘を行なっているのである。
イギリスでは「コミュニティの中心が永遠に喪われることになり、結果として多くの人の幸福に計り知れない損失をもたらすことになる」ことが懸念されたが、日本におけるスナックの廃業は、どのような意味をもつことになるのだろうか――。
なお、憲法学のなかでも、このような「社交」の権利を重要なものとして捉え、コロナ下でのその意義を正面から論じるものとして、山羽祥貴「『密』への権利(上)」(『法律時報』2021年5月号)が注目に値する。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月21日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること


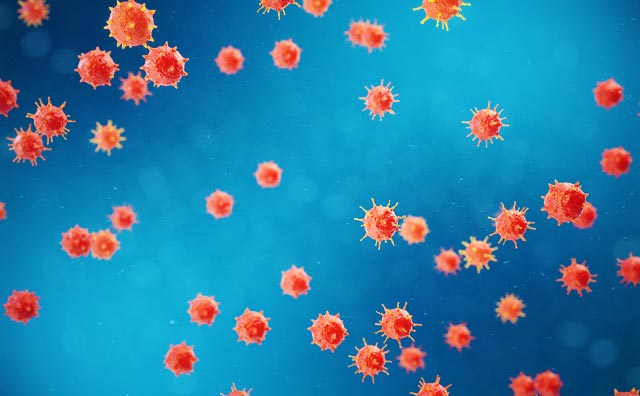

.jpg)
