「“復興五輪”の理念だけは忘れないで」 震災から10年、俳優・渡辺謙の願い
2021年03月11日 公開
2024年12月16日 更新

(写真:吉田和本)
東日本大震災から10年が経った。俳優の渡辺謙氏は、震災直後から被災者と交流し、2013年からは宮城県気仙沼市でカフェ「K-port(ケイポート)」を経営している。新型コロナ禍に直面するいま、我々が震災から得るべき教訓とは。(取材・構成:Voice編集部 中西史也)
※本稿は『Voice』2021年4⽉号より⼀部抜粋・編集したものです。
僕たちのほうが被災者に励まされた
エンタメ業界がコロナ禍で危機的な状況に陥るなか、頭を巡ったことがあります。それは、東日本大震災後に東北を回ったときに受けた、被災地の方々からの温かい声でした。
「あなたのあの作品が好きなの」「また良い作品を観せてね」。そうした言葉の一つひとつが僕の心に残り、逆にこちらがいまなお励まされているのです。
コロナ禍以降、僕は無観客で芝居をする機会がありました。自分たちがこれまで、いかにお客さんからエネルギーをもらってきたのか、あらためて痛感しました。
同じ空間で、同じ熱量を共有できることが、どれだけ幸せなことか。厳しい状況にあるからこそ、人びとはいままで以上にエンタメを求めている。そして演者である我々も、芝居ができる喜びを感じるのです。
とはいえ同時に、日本ではまだ社会における表現者のヒエラルキーが低い。一例を挙げれば、海外と比べて撮影の許可が下りにくい現実があります。これが文化芸術をサポートする意識が染みついている国だと、許可を得やすい。
日本でそうした機運が弱いのは、我々が「エンタメも日本文化の重要な担い手です」と訴える努力が平時から足りなかったともいえますね。これは大いに反省すべき点です。もともと存在していたヒエラルキーの格差が、コロナ禍でより浮き彫りになった気がします。
では、いったい自分に何ができるのか。僕自身も、コロナで多くの仕事がなくなりました。それでも、より深刻な打撃を受けているエンタメ事業者をなんとか支援できないものか、有志の何人かで話し合ったことがあります。
しかし、個人のレベルではどうにもならない損害額だったこともあり、最終的には国の補助金に頼るほかないという現実を思い知らされました。
日本の俳優界の大きな問題は、ユニオン(労働組合)が存在しないことです。こうした難局に立たされたときに、大きな束となってうねりを生む組織がないのです。
個人がいかに支援の気持ちを抱いても、悲しいかな、できることには限界がある。今後さらなる危機が訪れたとき、俳優界にユニオンがなければ、我々の要望はやはり社会に受け入れられないかもしれません。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月02日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債




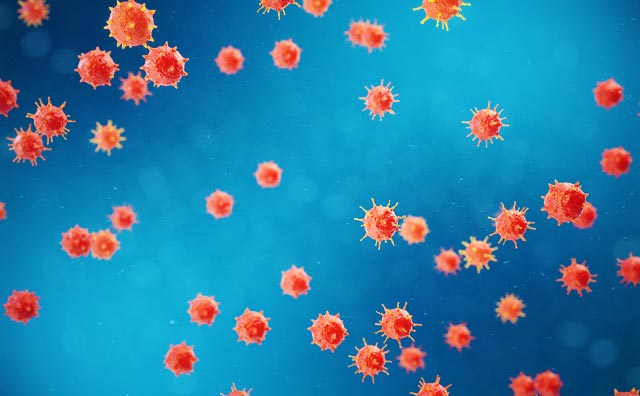

.jpg)
