門田隆将 井上嘉浩・炎天下のコンテナ監禁――4日間「断水断食」の地獄
2018年12月27日 公開
2024年12月16日 更新
“救いの雨”が降った
3日目、ポトリと滴しずくが顔に落ち、目が覚めた。ザーザーと音がする。雨だ。
懐中電灯で天井を照らしてみた。水滴が光り、溜まっている。雨の恵みで、中の湿気が増したのだ。助かるかもしれない。嘉浩は反射的にそう思った。
まさに“天の恵み”だった。トイレを台にして天井に手を伸ばしてみた。ティッシュで水滴を拭き取るのだ。ティッシュには、水分がついていた。嘉浩は、これを口に含んだ。ほんの少し、口が湿る程度である。だが、乾きが微かだが癒された。
日中、雨が降りつづき、暑さがやわらいだ。運がよかったというほかない。天が嘉浩を救ってくれたのだ。
午前0時、おばさんがまた声をかけてくれた。
「彼女は無事ですよ」
ホッとする情報だった。彼女は3日だ。生き延びたことを知った。ついに4日目、雨が上がり、猛烈な蒸し暑さが戻った。しかし、「あと1日だ」と、嘉浩は気力を振り絞った。
午前0時、おばさんが、またやって来た。
「普通のオウム食でごめんなさい」
そう言いながら、食事と水筒を差し入れてくれた。
「断水断食後はおかゆ、と思って用意していたら、特総大師に“そんなことはしなくていい”と言われてしまいました」
彼女は、申し訳なさそうにそう言った。断食後の食事は危険だ。だから、おばさんは気を遣ってくれたのだ。
「気にしなくていいですよ」
嘉浩はそう答えたものの、特総大師の話にはムッときた。特総大師とは、富士山総本部に常駐している20人ほどの大師たちのことだ。麻原の近くにいるため、その威光を笠に着ており、支部の人間にとって印象は決してよくない。彼らに、自分など「死ねばいい」と思われているような気がした。
地獄の4日間を生き延びた末の食事と水だった。嘉浩は、ゆっくりゆっくり、口にした。生き抜いたことは満足だが、嘉浩は、しばらく何もできず、蹲っていた。
横たわったまま、麻原への「信」、彼女への「思い」、断水断食時の「死への恐怖」、決して馴染(なじ)めない特総部の「管理体制」……さまざまなものが入り交じった思いが嘉浩の頭に浮かんでは消えた。しかし、何ひとつ頭の中で整理することはできなかった。
(修行らしい修行はさせてもらえなかった。今、やっとそれができているではないか)
そう考え直して、瞑想に没頭した。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

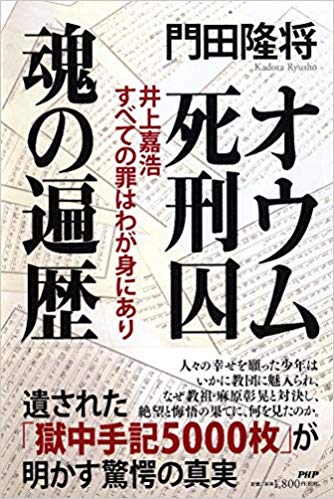
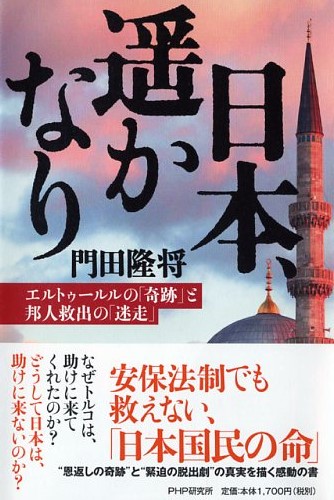


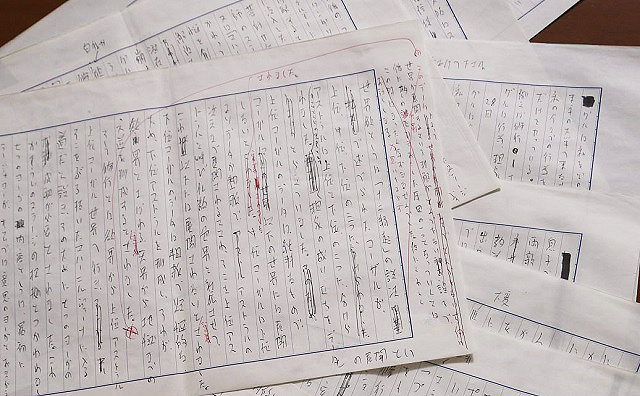



.jpg)
