『罪の声』作者が語る、昭和の未解決事件を“フィクション”として描いた理由
2017年08月09日 公開
2024年12月16日 更新
エンタメと社会派を両立させたかった
――その意味でも、グリ森事件は80年代を象徴する事件だったと塩田さんは捉えているわけですね。ちなみに、「子どもの声」として犯行声明に使われた3人には、もちろん会ったことはないですよね?
【塩田】 ないですね。でも会いたい。彼らが普通の人生を送っていればほっとするし、そうでないとしたら、それこそ世に出て訴えるべきだと思います。
自分の声が犯行に使われたことにいつ気付いたのか。そのときどう思ったのか、などを誰よりも先に僕が聞きたい。現に、そうした境遇の人たちが日本に3人いるわけですから。
――犯人にはどうですか、やはり会いたいですか。
【塩田】 そうですね、会ってみたいですね。
――この作品をきっかけとして、「子どもの声」の主が現れる可能性を読者としては期待してしまいます。
【塩田】 僕は小説という物語の力を借りて、そこに賭けたわけです。
――いまのところ、そのような動きというのは、何かありますか。
【塩田】 残念ながらまだありません。ただ、『罪の声』が世に出てからまだ1年しか経っておらず、そんなに早く「結果」が出るとは僕も考えていません。
本作はコミック化もされていますし、これからもメディアを変えてどんどん世に広まっていってほしい。
そしてこの作品に対して何らかのかたちで接触した何者かが、過去の記憶を辿っていくうちに、あのテープの声の主は自分だった、と気付くかもしれない。
その可能性は「ゼロ」ではないわけで、そう考えると、いまでも鳥肌が立ちますね。
――本作は重厚なテーマを扱いながらも、いい意味で軽妙さを失っていません。400ページを超える長編でありながら、時を忘れて一気に読んでしまいました。
【塩田】 自分は昔から何より人を笑わせる、楽しませることを意識して生きてきました。関西では運動ができるとか、勉強が得意だということ以上に、面白いことが大事という文化がありますから(笑)。
僕は中学生のときから漫才のネタ帳を付けていましたし、高校生になると実際にコンビを組んで舞台に立ち、ネタを披露していました。
――塩田さんの小説では本作に限らず、エンターテインメントの要素が巧みに盛り込まれています。
【塩田】 たとえシリアスな内容であっても、エンタメとの両立をつねに意識しています。そのなかでも、過去8作品は一人の人間を書き上げることに徹してきましたが、『罪の声』では「社会」を描きました。
やはり山崎豊子や松本清張など、「社会」を描ける作家になりたいという思いが強くあって、それを本作ではグリ森事件をテーマに出し切ったつもりです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月08日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 習近平の「暗殺未遂数」は歴代トップクラス
- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」
- 「台湾有事は日本有事」の意味とは? 地政学で読み解く危機の現実
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「教育先進国」シンガポールでの子育て 海外の公立校で教育を受ける意味とは
- 七三一部隊はいかにして生まれたか? 石井四郎がソ連の細菌兵器から得た口実

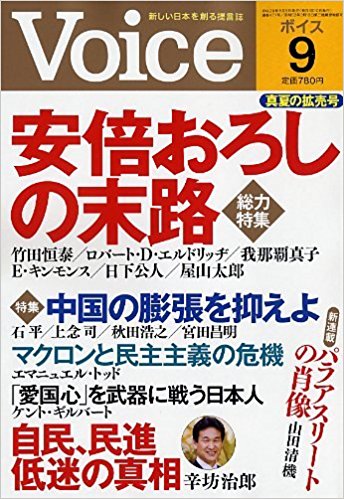
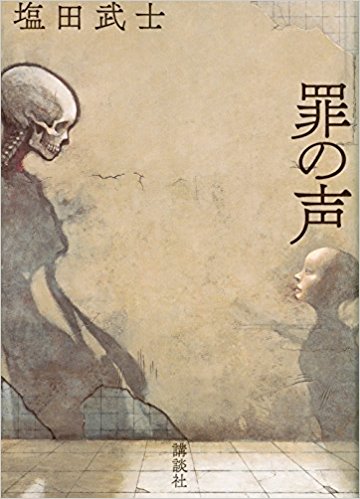





.jpg)
