100年前の「少数与党政権」が直面した困難とは? 多党化時代が到来した現代日本への教訓

135年にわたる日本の憲政史を振り返ると、第一次世界大戦後の「憲政常道」と呼ばれた時代には、多くが少数党のリーダーとして首相となっていたことがわかる。多党化時代が訪れた現代の日本政治は、近代史から何を学ぶべきか。
※本稿は、『Voice』2025年12月号より抜粋・編集した内容をお届けします。
歴史のなかの少数与党政権
本稿は歴史のなかから少数与党政権でのリーダーシップに注目する。
戦後政治では1955年の自民党結党以来、1993年まで38年間政権を維持し(途中短期間の新自由クラブとの連立あり)、第二党に社会党を配する55年体制と呼ばれた。その後日本政治が流動化した「改革の時代」のあと辿り着いた政治システムは、安倍晋三長期政権を経て「ネオ55年体制」とも呼ばれた(境家史郎『戦後日本政治史』中公新書)。その数年後の現状である。1986年に衆参同日選挙を強行した中曽根康弘首相が、与野党伯仲状況を吹き飛ばす圧勝に、「1986年体制」の始まりを説いたことを思い出す。顧みれば中休みでしかなかった。
戦後日本国憲法下で少数与党政権として発足したのは、1948年の第二次吉田茂内閣、1954年の鳩山一郎内閣、そして1994年の羽田孜内閣である。そのあいだに55年体制期がすっぽり入る。では、戦前はどうだったか。困難な時代には視野を広げ、思考を柔軟にすると良いだろう。
日本憲政135年のなかで、第一次世界大戦後には衆議院多数党が政権を担うことが賛同者、批判者の双方から常態化していると見られ、「憲政常道」と呼ばれた。現在との対比で重要なのは、その時期多くが少数党のリーダーとして首相になり、事後的に衆議院での多数を得たことである。現在に何を示唆するのかを考えてみたい(事実や先行研究は村井良太『「憲政常道」の近代日本』〈NHKブックス〉を参照)。
大政党の分裂と多党化
1890年施行の大日本帝国憲法では、首相は天皇の指名によって誕生し、議員である必要はなかった。衆議院は藩閥政府を批判する民党が多数を占めるとの予想から新たに華族をつくって貴族院を設け、帝国議会とは別に条約など重要国務を審議する枢密院を設置して政府の合理的統治への防壁とした。さらに政府は、一党一派に偏せず政党内閣を否定する「超然主義」を掲げた。
それでも訪欧憲法調査時のプロイセンでの助言に反発してつくった真っ当な憲法、すなわち議会を通さないと予算と法律ができないなか、政党は政府内での存在感を次第に高めていった。早くも1898年に初の政党内閣、第一次大隈重信内閣が誕生した。その後も1900年には憲法制定を主導した伊藤博文自身が立憲政友会を組織し、政党内閣を担った。いずれも短命内閣であったが、日露戦争後には政党が統治の一角を担うようになり、1912年には第一次憲政擁護運動が起こって多数党が政権を担うべきであるという「憲政常道」論が社会に浸透していった。天皇の指名といっても、君主無答責原則から実際の首相選定は天皇の助言者である元老などが行ない、その際の非人格的ルールを求める主張であった。
1914年からの第一次世界大戦は、この流れを加速させた。政治学者吉野作造を筆頭に二大政党による政党内閣制が主張され、大戦末期の1918年には衆議院で多数を占める政友会の原敬内閣が成立した。原は力強い施政運営で政党内閣の能力を示したが暗殺され、あとを継いだ高橋是清政友会内閣は短命に終わり、ふたたび官僚内閣が続いた。このころには納税資格を撤廃した男子普通選挙制の実現が喫緊の政治課題として意識されていた。
そして関東大震災が起きた翌年の1924年、清浦奎吾内閣の成立に、政党が政権を担う政党内閣制を求めて第二次憲政擁護運動が起こった。その過程で多数党政友会が大分裂を起こし、政友会、憲政会、革新倶楽部が「護憲三派」として連合し、政府支持の新党、政友本党と対峙した。衆議院解散後の総選挙では憲政会152、政友本党111、政友会102、革新倶楽部30議席となった。清浦首相がみずから退陣したため、元老西園寺公望はやむなく第一党憲政会の党首加藤高明を首相に奏選した。
加藤高明「護憲三派」内閣―多党化後の過大連立内閣
西園寺にとって加藤指名は不本意であった。加藤は第二次大隈内閣外相時に対華二十一カ条要求を行ない、近隣関係に加えて対欧米関係をも傷つけたからであったが、憲政会内の雑多さも不安材料であった。結党以来、一貫して日本政治の中心的存在であった政友会に敵した政党政派の離合集散の帰結が憲政会であった。改革でも政党内閣制を重視する官僚出身の幹部層と男子普通選挙制を重視する党人層で違いがあった。
社会でも「護憲三派」の協力が続くか懸念されていたが、大命降下を受けた加藤は、高橋と革新倶楽部代表の犬養毅を訪ねて連立を呼びかけた。注目されたのは伝統ある大政党の党首で首相経験者でもある高橋の動向であった。高橋は貴族院議員から衆議院に転じて原の故郷から選挙を勝ち抜いており、日本政治の未来のために欣然として犬養と入閣した。これで衆議院464議席中284議席を占める過大連立内閣となり、また貴族院は政党化の途上にあったが、第二次護憲運動で強く批判され、衆議院がまとまっている限り院として挑戦できる時代ではなくなっていた。
「護憲三派」内閣は次々と課題に対処していく。象徴は長く懸案であった男子普通選挙制の導入と貴族院改革であり、そのほかにも日ソ基本条約の締結、治安維持法の制定、宇垣陸軍軍縮も実現していく。そして男子普通選挙制の実現は久布白落実や市川房枝らによる婦人参政権獲得運動を活発化させた。しかし、政権課題の達成は連立を弛緩させる。高橋は政友会総裁を引退し、陸軍出身の田中義一に譲った。加藤首相の慰留も空しく、閣僚も辞任した。引き続き政友会は与党だったが、田中新総裁は入閣の求めには応じなかった。
革新倶楽部の犬養も内閣を去った。政友会への合同のためで、長い政治歴をもつ犬養は政界引退を希望していた。政友会は革新倶楽部の産業立国論を看板政策に取り込み、のちには犬養が総裁となる。総裁の入閣者は加藤一人となり、政友会と憲政会の二派は数でも拮抗した。そして1925年7月、憲政会の浜口雄幸蔵相が出した税制整理案に政友会出身閣僚が反対し、閣内不統一で内閣は総辞職した。
次の首相に誰を選ぶか。遺された元老は西園寺一人であり、宮中官僚の内大臣と話し合うようになっていた。政友会と政友本党は合同の意向を西園寺に伝えており、与野党間での政権交代であればそのまま政友本党に政権が渡るかもしれなかった。しかし、西園寺はふたたび加藤を選んだ。西園寺は困難な連立内閣を運営してきた加藤の立憲手腕を評価するようになっていた。こうして三党鼎立下で少数与党政権が誕生する。
憲政会少数与党政権の発足と模索――第二次加藤内閣と若槻礼次郎内閣
年末の通常議会召集時、憲政会165、政友会161、政友本党87議席であった。政友本党は政友会への合同をめざす者、憲政会との連携を模索する者で混乱し、数を減じていた。過半数を失った政府は多数工作を進める。ところが、まさに審議が始まる1926年1月、加藤首相は議場で体調を崩し、急死した。そして首相臨時代理に就いていた若槻礼次郎内相が次期首相に選ばれた。
若槻は多数工作も引き継ぎ、政友本党総裁床次竹二郎と連立交渉を行なって閣内協力を求めた。しかし、政友本党もまとまらず、憲政会内にも不満があるなかで連立は実らなかった。
それでも年末の通常議会は来る。連立内閣を組めず少数与党内閣だったので解散による初の男子普選総選挙が予想された。ところが大正天皇が崩御し、すでに摂政を務めていた昭和天皇が即位するなかで、若槻首相は党にも諮らずに田中、床次と話し合いをもち、諒闇中の政争中止に合意した。三党首妥協と言われる。憲政会の浜口は選挙をすれば勝てるのにと若槻の判断を惜しんだ。
政争中止の合意は頼りにならなかった。多数を必要とする憲政会は政友本党との繋がりを深めようとし、それを見た政友会は強く反発した。
そこで起こったのが蔵相の失言に端を発した金融恐慌であった。政友本党の協力で議会は乗り切れたが、対立は枢密院に波及し、台湾銀行救済案を否決されて総辞職した。
そもそも三党首妥協は曖昧ながらも若槻内閣の退陣を約束していたとも言われた。では若槻はなぜ妥協を選んだのか。解散して選挙に勝つ自信がなかったとのちに語ったが、当時の選挙予想では憲政会は22議席上乗せして188議席、政友会は15議席減じて147議席であった。過半数を得るには結局議会内で多数工作を重ねるか再解散に賭けるしかない。牧野伸顕内大臣は「憲政の常道」により政友会総裁の田中を次期首相に推す意見を西園寺に伝えた。西園寺は倒れた政権党以外での比較多数党を重視し、田中を選んだ。
政友会少数与党政権の発足と不安定な二大政党――田中義一内閣
政権交代後の田中義一内閣も少数与党であった。しかも金融危機下での政変である。ここで尽力したのが野党憲政会の若槻総裁であった。枢密院の求めで臨時議会を開いても政友会は多数を占めていない。他方で課題解決は待ったなしであった。若槻は憲政会をまとめ、高橋を蔵相に据えた田中内閣の危機対応に全面協力した。
そして憲政会と政友本党が合同して浜口を新総裁に立憲民政党が組織された。政友本党のなかで憲政会との合同を望まない人間は政友会に復帰していった。鳩山一郎もその一人であった。床次は新選挙法への対応と時論が小党分立に満足しないことを合同の理由に挙げた。
金融危機に目処をつけ、政友会は多数をめざして衆議院を解散した。初の男子普通選挙制に基づく総選挙である。三党首妥協で遅れたので浜松市会議員選挙など地方選挙で実施例があった。結果、政友会と民政党は217と216の1議席差となった。第一党だが過半数をもたない政友会は3議席の実業同志会と政策協定を結んだ。また野党は無産政党との連携を模索するとともに、政府からの議員引き抜きに缶詰と言われる合宿で対抗した。狂奔の様は新聞に揶揄された。田中は再解散も考えていたが、昭和天皇と宮中官僚は同一理由での再解散には消極的であった。
混乱下でしのいだ田中内閣だったが、第一党と第二党の拮抗は続かなかった。張作霖爆殺事件が起こるなか、床次が民政党を飛び出し、差が広がった。貴族院も枢密院も衆議院で多数をもつ内閣は倒せず、結局田中内閣は昭和天皇の「辞表を出してはどうか」という強い言葉を受けて退陣した。昭和天皇は中国政策への憂慮に止まらず、田中首相の立憲的でない行動に批判的であった。西園寺と牧野は野党総裁の浜口を首相に選んだ。
二大政党の少数与党政権発足――浜口雄幸内閣と犬養毅内閣
浜口内閣も少数与党で発足した。床次はついに政友会に合流する。このころにはジャーナリストの馬場恒吾が、少数党として政権に就き選挙で多数を獲得する「憲政常道」について、多数党が政権に就くよう今後の課題を説いた。また識者のなかには政権発足後すぐに国民に信を問うべきだと主張する者もあった。議会までにできることを行ない、議会で信任を問うのは古典的な英国モデルと言うべきであろう。浜口は金解禁後に総選挙を行ない、圧勝してからロンドン海軍軍縮会議での交渉を本格化させた。
浜口内閣は選挙で少数派に転落したから退陣したわけではなかった。世界大恐慌下で社会不安が昂じるなか、テロに襲われた。第一次世界大戦後の平和的な大国間協調を象徴する海軍軍縮条約を成立させた直後に浜口は撃たれ、結局その傷がもとで死去する。回復困難ななかで西園寺と牧野は次期首相にふたたび若槻を選んだ。若槻を選んだのは民政党でもあり、加藤死去後とは違い首相選定時には次期総裁に決定していた。
その若槻内閣も多数を失って倒れたわけではない。浜口内閣下で婦人の地方参政を認める政府法案が衆議院で可決され、貴族院で否決されていた。近い将来に国政参加の実現も見込まれていたが、出先陸軍軍人の陰謀による満州事変で吹き飛んだ。確信犯として戦線を広げる出先を政府・軍中央も抑えられないなかで、国民代表性をより高めようと二大政党の過大連立の動きが進んだが、与党内の混乱を招き、閣内不統一で総辞職した。
西園寺は野党政友会の犬養総裁を選び、犬養は単独内閣を組織した。しかし、犬養内閣が倒れたのも多数喪失が理由ではない。総選挙圧勝後の5.15事件、海軍青年将校を中心とするテロであった。政友会の次の総裁は首相就任を確実視していたが、政党と軍の対立の激化を恐れた西園寺は、国際派の海軍軍人斎藤実を選び、時勢沈静化後の政党内閣復帰をめざした。しかし2.26事件というふたたびの官製暴力によって敗戦後まで果たせなかった。
困難なリーダーシップから何を学ぶか
約100年前の少数与党政権下でのリーダーシップから私たちは何を学ぶか。第一に少数与党内閣は大変だということである。身内をまとめ多数獲得のために奔走しつつ、男子普通選挙制の導入や軍縮会議への参加など、時代を画する課題にも答えなければならない。しかも多数工作は政治への信頼を下げかねない。当時は社会主義が議会批判を行なっており、右翼にも利用された。困難な時期にこそ業績を上げる努力が求められ、しかも最善を尽くしても業績が上がるとは限らない。政治の信頼、国民との絆が大切であり、政治と金の問題は破壊的であった。
第二に既成政党批判である。既成政党とは社会主義政党に対して従来の自由主義政党を批判する言葉であったが、新しい政党は概して好ましく見える。しかしそうではない。政党づくりにも長い時間が必要で、新鮮さがなくなってからが政党の真価である。政友本党は政友会の本流と訴え、民政党は進歩党以来の伝統のうえに新時代性を主張した。政治家も当選回数は別として長い時間と経験のなかで育つ。
第三に政治と暴力の問題である。議会で多数を追求するのは立憲政治の常であるが、業績と信頼によっては暴力すら肯定されかねない。原暗殺後も政党政治は勢いを維持したが、世界大恐慌下の暴力は政党政治を壊した。しかも身内から組織暴力を起こした陸海軍関係者は逆に政党や議会を批判する始末であった。国民は混乱期にも暴力を肯定してはならない。目的は手段を正当化しないのである。
今回与党が衆参両院で多数を失い野党に受け皿もないことは、有権者の意思であると同時に大変困難な状況である。「マッドル・スルー(迷いながら進む)」と言うが、自由民主主義は泥のなかを掻き分けて進む。19世紀末の経済学者アルフレッド・マーシャルは「競争は建設的であることも破壊的であることもありうる」と説いたが、貧すれば鈍することなく、政党政治家の奮起と、未来を見すえた国民の忍耐と賢慮に期待したい。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月21日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること



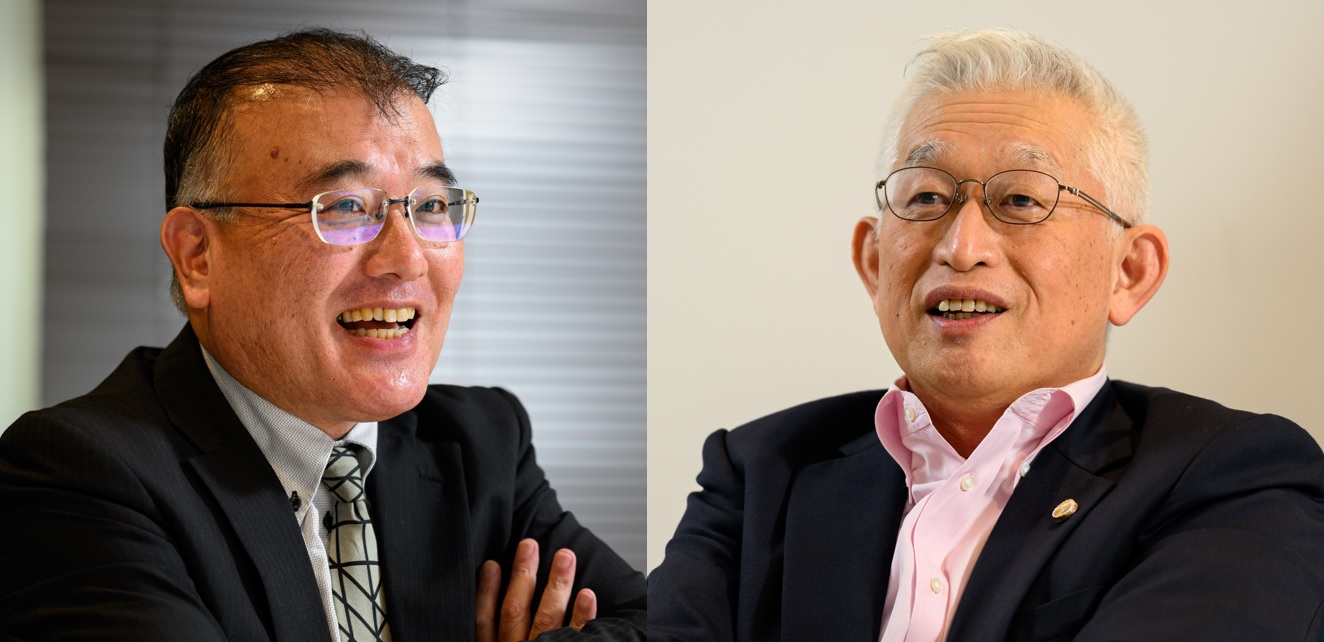



.jpg)
