参議院に存在意義はあるのか? 日本の議会制が抱える問題点

日本の議会制度では、第一院(衆議院)と第二院(参議院)はそれぞれどのような役割を果たしているのか。本稿では、第二院が存在する意義を示しながら、日本の議会制の現状や課題について、慶應義塾大学法学部の大屋雄裕教授が解説する。
★本論稿は、意見集約プラットフォーム「Surfvote」と連動しています。
※本稿は、『Voice』2025年8月号特集「選挙は「国」を救うか、壊すか」より抜粋・編集した内容をお届けします。
第二院の意義
「第二院に何の意味があるのか。第一院と同じでは無意味であり、違ったならば有害である」という、シェイエスのものとされる言葉から始めよう。
もちろんこの見解が表層的にすぎることは、現在でも多くの先進国が二院制を採用していることにも現われている。第一院――日本で言えば衆議院――がつねに民意を反映した正しい決定が行なえるという保証もないし、その構成もあくまで数年に一度行なわれる総選挙の時点において、かつ一定の選挙制度という制約のもとで、民意を議席数へと反映したものにすぎない。
その際、たとえば外交については政党A、経済政策については政党B、文化振興については政党Cの提示している政策がもっとも自分の選好に近いとしても、もっている一票を分割して投じることは(少なくとも現在の選挙制度において)認められていないし、さらに言えば、個々の候補者が政党全体とは異なる見解をもっていることや、支持する政党の候補者が自分の住む選挙区には立候補していないといった事態もあるだろう。
個々の有権者のもつ意見を集約したものであるはずの民意を政治へと反映する仕組みとして、選挙には何重にも制約や障害があるということになるはずだ。
あるいは民意自体も、たとえば科学的にとか学術的にといった観点で、つねに正しい判断を行なえるものではないということも指摘できるだろう。第一院が、民主的にであれ科学的にであれ誤った決断を行ないそうになったときに、それを阻止する役割が第二院に期待されると、ここまでは誰もが考えるはずだ。
だが、そのように第一院に対する阻止・是正機能を第二院に求めるのだとすれば、それは第一院とは異なる何かによって構成されていなければならないのではないだろうか。
アメリカを取り上げよう。政治学者の待鳥聡史は、アメリカにおいて2年任期の下院がごく短期で変動するそのときどきの民意を反映し、6年任期で2年ごとに3分の1ずつが改選される上院が長期的な民意の流れをくみ取り、その中間に4年任期の大統領選挙が入ることによって、長期から短期までのさまざまな民意を組み合わせて統治へと反映させる狙いがあることに注意を促している(待鳥聡史『代議制民主主義―「民意」と「政治家」を問い直す』中公新書、2015年)。
さらに外交は大統領、財政は下院、最高裁判事を典型とする主要官職の候補者に対する審査は上院というかたちで、それぞれの主要な役割が分割されている点も、待鳥の指摘するとおりである。
もちろん法学者の端くれである筆者としては、これに加え終身制――一旦任命されれば自分から引退するか死亡するまでは続けることができる、という連邦最高裁判事を、具体的な紛争の解決を通じてさらに長期のトレンドを示すという役割を担う存在としてここに重ね合わせたくなるのだが、このようなかたちで異なる民意を代表し異なる権限を担う機関のあいだで調整を行なわせることにより、暴走を防ぎ統治を安定させる効果が生じることが期待されていると考えることは許されるだろう(現在のアメリカでそれが十分に機能しているだろうかという疑問は出てくるとしても)。
また、下院の定数が基本的に人口に比例的に配分されるのに対し、上院はすべての州から二人ずつというかたちで、むしろ人口比例を否定するかたちになっていることも注意されるべきだろう。
同様にドイツでも、下院にあたる連邦議会においては基本的に人口に比例するかたちで選挙区が設定され、得票に応じて各政党のあいだで議席数が配分されるのに対し(小選挙区比例代表併用制――小選挙区で当選した候補者から優先して各党に配分された議席が割り当てられる)、上院にあたる連邦参議院の議席数は人口を加味したかたちで(比例的ではなく)各州に配分され、また選挙ではなく各州が代表者を派遣するというかたちで構成される。
この代表者は各州の首相や閣僚なのが一般的であり、また固定されたものでもなく、議案に応じて異なる閣僚が参加することも多い。ここでも、全国民に関する決定を主に連邦議会が担当するのに対し、各州の権限に関する問題について当事者たる州の同意を得るために連邦参議院を置くという両者の役割分担と、それに基づく構成原理の差異は歴然としている、と考えることができるだろう。
日本の議会制
では、日本はどうなのだろうか。もちろん衆議院(任期4年・解散あり)と参議院(任期6年・3年ごとに半数ずつ改選・解散なし)で制度的に異なる部分はある。内閣不信任決議を行なう権限は衆議院のみにあり、予算については衆議院から審議されることになっているなど、下院の優越性がある程度定められてはいる。しかし通常の法律については、基本的に両院の可決がなければ成立しないという意味で、両者の権限の主要部分は共通している。
また、会計検査院検査官や日本銀行総裁・副総裁など国会の事前同意を得て任命可能になる職(国会同意人事)についても、衆参両院の立場は同等であり、いずれか一者が否決すれば任命することができない。要するにわが国は、2つの院を国会内に置いているにもかかわらず、その権限においてはほぼ差を付けていないのである。
選挙制度についてはどうだろうか。衆参両院とも国民による直接選挙により選ばれていることは広く知られているだろう(憲法43条1項)。さらに、少しでも多くの投票を得た候補者1人が当選することにより実際の民意の差を拡大するかたちで議会勢力に反映するか(小選挙区制)、民意の分布に忠実なかたちで議席を配分するか(比例代表制)という軸に沿って考えるならば、衆参両院ともどちらかわからない中途半端な状態にあるということになるだろう。
衆議院は全国の小選挙区から289人、全国を11ブロックに分けて戦われる比例代表制から176人の議員を選出するという制度(小選挙区比例代表並立制)を採用しており、参議院は都道府県ごとに2から12(したがって選挙ごとの改選数は1から6、鳥取・島根、徳島・高知は2県で1選挙区)の定数で行なわれる選挙区部分と、全国から100人(改選数は50人)を選出する比例代表部分から構成されているからである。
選挙ごとの改選数が1となる部分は小選挙区であり、2から6になる部分は中~大選挙区、それに比例代表が加わることによって、全体的な選挙の性質は複雑ないし曖昧そのものになっていると言えるだろう。
いったいわが国の議会制は、上院に何を、下院に何を期待し、それを実現するためにどのような権限配分と選挙制度を用意していると考えるべきなのだろうか。その答は、わからないとしか言いようがない。性質の判然としない第一院に、性質の判然としない第二院を重ねて存在させているのが、日本の議会制度の現状なのである。
何が現状を生んだのか
しかし、なぜわが国の議会制度は、このような状況になっているのだろうか。その答は、大きく2つ与えることができる。
直接的には、衆参両院が相互に独立して選挙制度改革を行なってきたことである。参議院は当初から都道府県ごとの選挙区と全国区の組み合わせであったが、後者における選挙運動が苛酷なものとなり、事前の知名度を活かすことができるタレント候補や組織候補が蔓延する原因にもなっているという批判が強まった。そのため1982年に比例代表制がその代わりに導入され、概ね現在の選挙制度が確立したのである。
他方で、衆議院では長らく中選挙区制(選挙区ごとの定数が3~5人)という世界的にも稀な制度が採用されてきたが、1990年代の政治改革において、一方では政権交代を可能とする大幅な議席数変動を実現するために小選挙区制が基本的に採用され、他方で中小政党の消滅を避けるためにブロックごとの比例代表制が導入されることにより、そのどちらでもない中間的性格をもつ議会が構成されたと考えることができる。
結果的に、衆参両院ともその性質が判然としない曖昧な議会を2つ抱えることになったのが、わが国の議会制度だということになるだろう。
第二に、皮肉なことではあるが、戦後一貫して参議院の権限を強化し、衆参両院をほぼ対等な議院として構成してきたことである。前述した国会同意人事についても、日本国憲法制定からすぐの時点では衆議院の優越が認められている部分も多かったのだが(会計検査院検査官、人事院人事官など)、それが衆参両院の不平等を招いているという参議院側からの批判もあって順次撤廃され、現在の状態に至っている。
しかしその結果、国会同意人事にせよ法律の審議にせよ、衆参双方からの支持が得られなければ進まなくなったため、政権としてはその成立の基礎を衆議院に置いているにもかかわらず、参議院の同意を確実なものとする必要が生じたのである。
そのため、あるいはその意を迎え、あるいは事前調整や政治的取引を通じて参議院の賛成をあらかじめ確保するよう振る舞わざるを得なかったと言える(逆に言えば、衆参両院の多数派が食い違うことにより、立法・国会同意人事とも停滞せざるを得なかった「ねじれ国会」がその失敗例として理解されることになる)。
結果的に、衆議院と同等の権力をもつ参議院には衆議院のカーボンコピーたることが求められ、両院の差異が消失していった、ということになるだろう。そこに存在するのは、まさにシェイエスが無意味だと呼んだ意味における第二院にほかならないのだ。
1947年、戦後発足した参議院で初の選挙が行なわれた際には無所属議員が108名と最大勢力であり、彼らを中心として既存政党から距離をとるかたちで緑風会が結成されたことはよく知られているだろう。
政党政治を担う衆議院とは異なる「良識の府」、衆議院の過ちを是正・抑制することが期待される「再考の府」としてのあり方をめざした動きだったが、第二院としては強すぎる権限をもった参議院を政権が支配下に置く必要性のなかで次第に勢力を弱め、1955年の保守合同を経て1965年までに自然消滅するに至った。この緑風会の運命こそ、制度的な権限の強さゆえに独立性を保つことができなかった第二院の象徴だと言ってよい。
イギリス貴族院の教訓
問題は、衆参両院における選挙制度改革がそれぞれ独自に行なわれ、結果的に両院の性格付けに関するグランドデザインを欠いたことにあるだろう。「第二院に何の意味があるのか」というシェイエスの問いに答えるためには、両院の役割分担とそれを支える権限分配について考える必要がある。
だが、具体的にはどのようにすればいいのだろうか。その一つのアイディアは、イギリスの二院制にあるだろう。周知のとおりイギリスにおける第二院は、その構成員が民主的な選挙によって選ばれることのない貴族院である。伝統的に世襲貴族はその審議に積極的には参加してこなかったし、1999年の改革により世襲貴族の議席が92に削減されたため(2議席が世襲、それ以外は世襲貴族による互選)、現在では構成員の大半が一代貴族(約630名)となり、政治・行政・司法・軍といった政府機関、さらには実業界や学芸などにおける貢献と専門性が評価されて任命された人びとが主に構成する議院となっている。
「クロスベンチャー」と呼ばれる無所属議員が多い(200名弱)のも、その点を反映した特徴である(ほかにイギリス国教会の高位聖職者26名が議員となっている〈聖職議員〉。伝統的には貴族院が最高裁判所の機能を果たしていたため、法律家12名が一代貴族としてその任に当っていたが〈法服貴族〉、2009年の最高裁判所分離・発足により消滅した)。
他方、このように民主的正統性を欠く議院の存在が許容される理由として、その権限が弱いことも指摘できよう。財政法案(Finance Bill)については下院たる庶民院が先議権をもっているし、なかでも歳入歳出のみに関する金銭法案(Money Bill)について貴族院はその成立を1カ月遅らせることができるだけで、修正する権限すらもっていない。何が財政に関する法案かを決める権限も庶民院議長がもっているため、庶民院と異なる政治的立場からその行動を妨害するようなことはほぼ不可能になっている。
では、貴族院は何のためにあるのだろうか。第一に、庶民院が政党政治のなかで法案への賛否をめぐって議論するのに対し、貴族院には法案の内容やほかの法令との整合性といった専門的見地からの検討が期待されている。下院と異なり、法案に対して提出された修正案はそのすべてを時間制限なく討議するとされていることも、そのような機能を示すものと理解できるだろう。
第二に、たとえば生殖医療や同性婚の可否のように民意が政党制とは異なる原理で分裂しているような問題、あるいは生成AIによる学習のように先端技術に関する複雑な問題に対し、中立的・専門的見地から加えた検討の結果を報告書として公表し、一般社会から政府、下院までにおける議論の参考に供することも広く行なわれてきた。皮肉なことではあるが、実際の政治権限から遠ざかるからこそ良識や再考といった役割を担うことができている、ということになるのかもしれない。
新たなグランドデザインに向けて
だとすれば、わが国の参議院についても、一方で強すぎる権限を手放し、他方で――短い会期に縛られ日程闘争の舞台となる衆議院とは異なり――通年会期制を採用することで重大課題にじっくりと取り組むことができる議院たることを指向する、といった可能性が考えられるのではないだろうか。
何が違うのか――第二院としてのアイデンティティを問うことが、当の参議院のみにとってではなく、日本政治のグランドデザインという観点から重要なものとなっているのである。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月21日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること



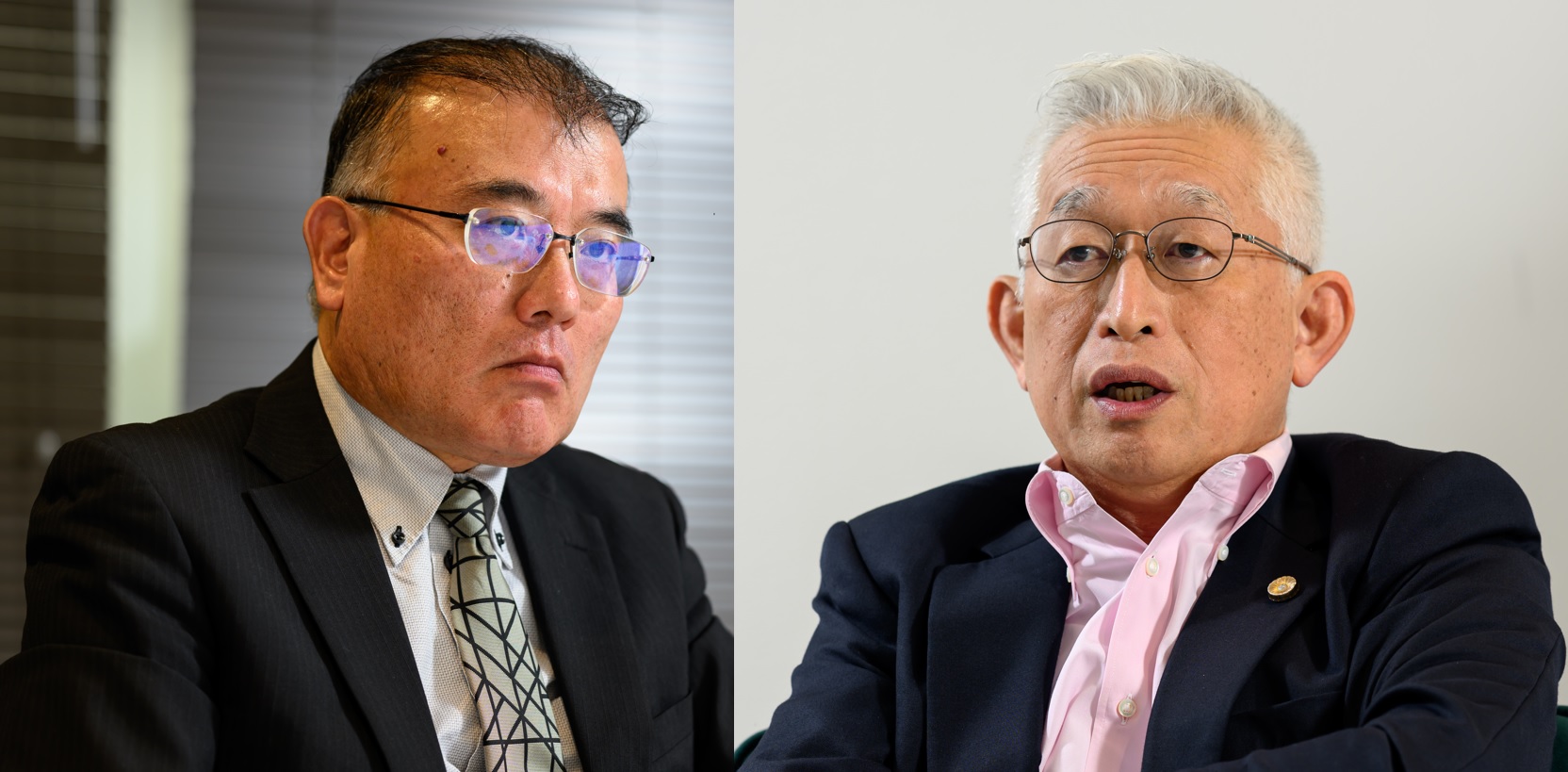



.jpg)
