本当に前世紀の遺物? 大阪・関西万博の真の「費用対効果」とは
2025年05月02日 公開

いよいよ開幕した大阪・関西万博。開幕前から賛否両論が寄せられており、万博開催の意義を問う論調も強い。
大阪・関西万博が単なる一過性イベントで終わらないために必要な視点とは何か。日本と世界のナラティブが交通する契機という側面から論じる。
日本にとっては「絶好の機会」
2025年4月13日、大阪・関西万博が開幕した。各パビリオンを中心とした会場内建築物など、主にハード面に注目が集まっているが、世界中からキーパーソンが集結し、メディアの関心を引く国際的なメガイベントは、日本のナラティブ(物語・語り)を世界に接続する絶好の機会でもある。日本のソフト・パワー、なかでも言説の力を発揮するまたとない半年間であることは、もっと強調されてよい。
さらに言えば、人類の課題を問い直し、より良い未来を展望するナラティブを世界とともに築いていく場とすることで、大阪・関西万博は真に有意義なものとなるはずだ。多額の国家予算をかけた国際的なメガイベント開催の真の「費用対効果」は、その点にこそあると筆者は考える。
筆者は2023年に『日本のナラティブ・パワー 2025とその先への戦略』と題した研究報告書を取りまとめ、大阪・関西万博を含めた日本の国際発信のあり方について提言した。以下、本記事では、本報告書の内容をもとに、日本と世界のナラティブが交通する契機としての万博の可能性を考えてみたい。「万博は前世紀の遺物」といった声も聞かれるが、今こそ万博のあるべき姿を再定義し、世界と日本のナラティブをつなぐ場としていかに再・創造/想像するかを考えることは、人類の良き未来にとっても意義のある作業になるのではないだろうか。
あるべき万博の姿──「20世紀の遺物」から「知的国際協同作業の場」へ
1970年に開催された大阪万博では、立ち上げ段階から民間の知的蓄積に基づく自由な発想の力が寄与している。70年の大阪万博の開催決定に先立ち、梅棹忠夫・加藤秀俊・小松左京らが1964年に自主的に立ち上げた勉強会「万国博を考える会」は、それまでの万博の歴史や問題点、ケーススタディなどを自発的に検討するものであった。その後、日本での大阪万博の開催が正式決定し、その過程で梅棹や小松は委員の選定やテーマの設定などに深く関わることになる。
当時、大阪万博の開催については芸術家たちによる反対運動が展開されるなど、決して歓迎ムードだけではなかった。しかし「人類の進歩と調和」をメインテーマに掲げ、当時の新進気鋭のアーティストや識者を結集して造られたパビリオンや展示は最終的に6400万人超の来訪者を集め、高度成長を象徴する存在ともなった。
このように大きな成功を収めた大阪万博であったが、当初、加藤・小松は大阪万博を、その発足の段階から国際的な叡智を集めた「知的国際協働作業」たらしめようとしていた。この「野望」は予算やスケジュールの問題などから残念ながらついえたが、この夢は「かなり長い間、私たちの中で生きつづけ、何かの場面で実現させられないか、と思いつづけた」と小松は回想記『やぶれかぶれ青春記 大阪万博奮闘記』でしるしている。
大阪・関西万博は、2020年から世界中で猛威を振るったパンデミックを経て、初めて「コロナ後」に開催される万博である。コロナ禍により、かえってリアルの場で集まり、言葉を交わすことの貴重さを実感した人も多いだろう。一方、世界ではウクライナ戦争の勃発後ますます分断が進み、世界的なインフレに加えて、トランプ新政権による世界経済の混乱、各国でのポピュリズム勢力の台頭など、問題は山積している。
今こそ、万博を「知的国際協働作業」の場たらしめようとした小松や梅棹らの問題意識があらためて求められているのではないだろうか。
日本を代表する「国際的言論人」は、万博を機に誕生
ここで参照されるべきは、鈴木大拙の事例である。1960年代にアメリカで起こった「ZEN」(禅)ブームは、コロンビア大学で教鞭をとっていた鈴木大拙の英語による一連の著作や、大拙の元に集ったビートニク世代の芸術家たちの影響を強く受けていると言われる。
実は大拙が世界に向けて禅を発信する最初の契機となったのが、1893年にシカゴ万国博覧会(世界コロンビア博覧会)の関連事業として行なわれたシカゴ万国宗教会議であった。大拙の師である釈宗演がシカゴ万国宗教会議で行なった近代仏教に関する演説原稿の英訳を、大拙が手がけたのである。
釈宗演はシカゴ万国宗教会議に出席したのち、1週間ほどアメリカの宗教者ポール・ケーラスの元に滞在した。ポール・ケーラスは釈の演説に感化され、近代仏教の可能性を追求すべく仏教啓蒙活動を開始、釈の弟子である大拙を助手としてアメリカに呼び寄せた。大拙はその後、ケーラスのオープン・コートという出版社で編集者・翻訳者としてのキャリアをスタートさせた。この経験が、大拙の後の主著『Zen and Japanese Culture』(邦題:禅と日本文化)に結実することとなる。
シカゴ万国博覧会の関連事業として開催されたシカゴ万国宗教会議に釈宗演が出席することがなければ、鈴木大拙という偉大な「グローバル言論人」は誕生していなかったかもしれない。当時、個人の海外渡航や海外の識者との交流には物理的に大きな障壁があり、万博などの国家イベントが果たす役割は現代よりも大きかったと考えられる。しかし、それらを差し引いても、万博が持つ「知と知の出会いの場」としての機能は改めて注目されるべきであり、2025年の大阪・関西万博においてもこうした視座は欠かせない。
万博が単なる大型展示会、国威発揚の一過性イベントで終わることがないよう、「万博を契機に、万博を超える」ことが求められている。
気候変動、国際政治などをめぐってナラティブは対立しがちであり、現実政治に照らしてやむを得ない面もあるが、世界のナラティブ空間が対立のための対立に終始することは望ましくない。2025年の大阪・関西万博の機会を活かして日本を含む多様なナラティブを開花させ、人類の視点に立つ開放的なナラティブの場を創造し、発展させることを目指すべきだろう。
大阪・関西万博と日本のナラティブ
今回の大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)」である。「いのち」が表すものは、人間の命や自然界に存在する命など字義通りの「生命」はもちろんのこと、狭義の意味での生命に留まらず、「生そのもの」「人間という存在」を問うキーワードであると言えるだろう。
また、日本館のテーマ「いのちと、いのちの、あいだに」は、環境問題などのグローバル・アジェンダに日本人の自然観・死生観を反映させたものであり、日本から世界へ投げかけるメッセージとして相応しいものだ。しかし、日本のナラティブを世界に届ける、あるいは日本のナラティブと海外のナラティブを相互交流させる観点からの取り組みは今のところ目立たない。
今後、開催期間中には会場内外で多くのイベントが予定されており、パビリオンのみならず、こうした機会を通じて大阪・関西万博を、いのちや人間存在の本質、未来について、人類がより良いナラティブを創造する契機としていくべきだろう。2025年をマイルストーンとして、日本の識者が普遍的・グローバルな課題に鋭く切り込み、世界に問題提起するパワフルな論考を英語などの他言語で次々と発表し、日本の識者と海外識者との対話が集中的、重層的に行なわれることが理想的だ。日本館やシグネチャーパビリオン、日本企業の企業館の問題設定をナラティブとしてさらに磨き上げていくことも意識すべきだ。
万博の強みはなんと言っても強烈な身体体験を提供できる点にある。ナラティブとの相乗効果により、体験のインパクトがより深められ、持続することになるだろうし、ナラティブの説得力、訴求力が増すことも期待できる。8人のテーマ事業プロデューサーはすでにグローバルに活躍しており、彼ら彼女らを軸として新たな「グローバル言論人」が登場する素地は十分ある。
大阪・関西という地域性も活かしたい。すでに大阪大学を中心に複数のプロジェクトが動いているが、関西に拠点を置く大学が知的国際協働作業の推進役となり、万博と並行して世界に対して問題提起する仕掛けをいっそう推進していくべきだろう。9月には京都大学とNTTを中心に設立された「京都哲学研究所」主催の国際会議「京都会議」が予定されており、同様の取り組みが同時多発的に創発されることが望ましい。
関西でユニークな実績を積んでいる企業の経営者や自治体の首長もナラティブの担い手として有望である。大阪船場の商哲学や京都の伝統工芸・民藝など、関西で培われてきた文化的資産を、サステナビリティが求められる世界に相応しい経営やライフスタイルの提案として、グローバルな文脈に位置づけていくことも必要だ。
転形期にある人類の課題を問い直し、未来をともに築くナラティブを世界へ開いていく場とすることで、大阪・関西万博は真に有意義なものとなるだろう。繰り返しになるが、そうした点にこそ、多額の国家予算を費やす国際的なメガイベントを開催する意義がある。万博開催期間だけに留まらず、人類が直面する大きなテーマについて衆知を結集し、新しい人間観について継続して語り合う場を万博以降もレガシーとして残すことを期待したい。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月18日 00:05
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

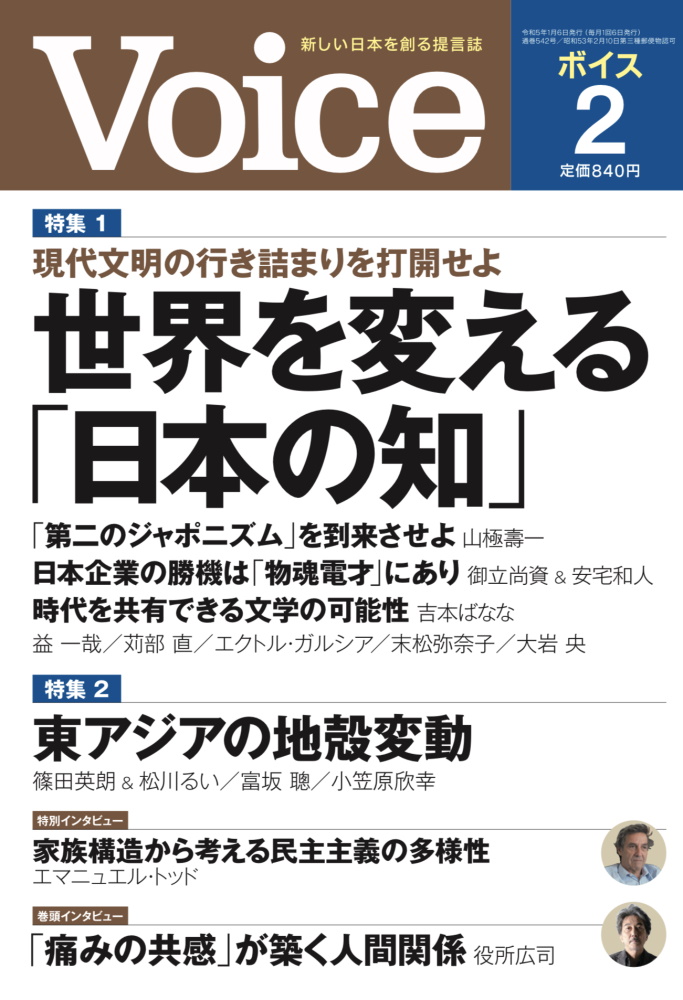






.jpg)
