世界も熱視線を送る「日本の食文化」...食で新規産業を創出する8つのポイント

皆さんは"フードテック"という言葉をご存じだろうか?
食のシーンにデジタル技術(特にIoT)やバイオサイエンスなどが融合することで起こるイノベーションのトレンドの総称であり、特定の技術というわけではない、食に関わる無数の術の集合知と言われる。
日本の食には世界が注目する強みがあり、様々な技術もあるが、それらを統合したライフソリューションを提案するには至っていない。では、どうしたら良いのか?フードテックの今に詳しい田中宏隆氏、岡田亜希子氏に解説して頂く。
※本記事は田中宏隆/岡田亜希子著『フードテックで変わる食の未来』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。
日本の食の強みは空前絶後の注目度!
筆者たちは、さまざまなところで食の領域において日本の強みはあるのか、日本に可能性はあるのかということをよく聞かれる。答えはもちろんイエスである。例えば
・高齢化・孤独・自然災害を抱える課題先進国としてのポジショニング
・企業・研究機関が有するおいしさ設計技術・素材開発力・食品加工技術
・日本に存在する食文化や技(大豆食文化、海藻食文化、発酵技術、保存技術など)
・奇跡の国土が育んできた自然と共存する食の多様性
・和食の伝統や様式にリジェネラティブ(regenerative)さが織り込まれていること
・日本の地域の力:地方に眠るさまざまなアセット・地域における食文化
・料理人や調理人が有するエンジニアリング力・再現力・魔改造力
・世界的に見て圧倒的に効率的な物流オペレーション
・日本が持っているおもてなし・ホスピタリティ
・本当においしい飲食店・多様な選択肢 等々
おそらく、多様な視点から考えると、日本の食に関する強みは、かなりの数が出てくると考えているし、読者の方々もさほど違和感なく、強みの広がりは納得されるのではないか。
筆者らも世界中のイノベーターやエコシステムビルダーと対話をするなかで、この数年「日本と一緒に食の領域で何かをやりたい」というラブコールを数多く受けている。
日本に眠っている食の強みは、世界から注目の的となっており、その気になれば空前絶後のチャンスを獲得できる状況なのである。
強みを駆動せよ
では、食の領域に数多くの強みがあるからといって、それがそのまま日本の強みとして世界に打ち出すことができるのだろうか、この国を支える新産業に昇華させることができるのだろうか? 現在の強みは今後も日本の強みであり続けることができるのであろうか?
"日本の食には実は強みがある""実はすごい"、と言いつつも、本当にそれが実装・浸透し社会インパクトを出せているのか?経済インパクトは出せているのか?食品メーカーの世界トップランクに、日本企業はどれだけ食い込めているのだろうか?
調理家電を担う日本の家電メーカーは、家電のイノベーションを起こしうるのだろうか?(世界最大級のテクノロジー見本市CES2025を見る限り中韓との差が生まれている)。
スペイン、イタリア、オランダ、カナダ、韓国、シンガポールなどの国が、食を国家戦略として押し出しているが、日本は食を国家戦略として、新産業創造の起爆剤として取り上げられるのだろうか?
これまでワクワクした未来を提示してきた私たちだが、日本の強みは現時点では相応にあると感じつつも、その鮮度は実は短いのではと考えている。
デジタル化、AIやセンシング技術の浸透によって、これまでの職人技や特殊スキル技術がデータ化、可視化、自動化され、継承・共有しやすくなる。
日本の食文化・食体験に感動し、海外で模倣するプレイヤーも出てくるかもしれない(これ自体は喜ばしいことなのだが、ともすれば技術やアイデアだけ盗まれるというリスクがある=日本にお金が落ちない)。
さらには、昨今日本が有する食品開発・製造技術などに世界がアプローチしてきているが、日本企業の対応スピードが合わない場合や日本企業が積極的に外部と連携しない場合は、動かない日本を素通りして、日本以外でコトが進んでいく可能性も高い。
すなわちジャパン・パッシングだ(実際に海外プレイヤーからは、「日本は技術的にも市場的にも魅力だが、日本企業のスピードの遅さが深刻な課題だ」と言われることが本当に多い)。
ひょっとしたらパッシングはまだマシかもしれない。もし、企業が動かない場合は、技術者だけ引き抜いていく、技術を盗んでいくことも十分あり得るだろう(これもジャパン・パッシングと合わせて、ハイテクの世界が辿ってきた道である)。先手を打つべきである。
さらに地方に目を向けると、素晴らしい技術や技を持っている中小企業や個店が、後継者がいないなどの問題により、人知れず事業を閉じているということ、あるいは、外資資本がそういう企業を獲得している状況がある。
今のままでは、いつの間にか日本の強みが消えていく、どこかにいってしまうということが刻々と起きている。認識すべき危機である。
日本の食領域には世界に誇れる強みはあるものの、今この強みを駆動(Activate)しなければ、それが日本から消えてしまう可能性が高い。これは実際に、ハイテク分野で起きたことである。
日本のハイテク業界は、モノづくりは世界一、技術力は世界一、いいものを作れば売れるはず、と、誇りを持ち取り組むことは素晴らしかったが、世界の変化、生活者のニーズを捉えきれなかったことにより、「いいもの」が何かわからなくなった。
一方で、社会と生活者の求める価値を多元的に理解し、そこに技術を活用することを徹底したグローバルプレイヤーと大きな差が開いてしまった。結果として世界における日系電機メーカーのプレゼンスは劇的に下がってしまった。
ハイテク分野の轍は食の世界では踏むべきではない。日本の強みはある。ただ、それを再編集して、再定義して、新しい形で駆動させなければいけない。
iPhone前夜を超えて〜未来を共創するためのカギを握る要素
『フードテック革命』(日経BP)の中では、2020年は"iPhone前夜"であるという言い方をしていたが、今(2025年1月)は、食のiPhoneが生まれる環境が整ってきている。
iPhoneが生まれる環境とはどういうことか。
iPhoneが世に発表された時、それは非常にイノベーティブな製品に見えたが、部品単位で見てみると、目新しいものはなかった。
半導体チップやセンサー、ディスプレー、いずれもすでに世にあるものを組み合わせたものだった。それでも、人々にとっては単なる「電話」ではなく、「コンピュータ」を常に片手に持つという全く新しいライフスタイルが提示されたのだ。
今、食の領域では、生成AIを使った食品開発サービス、次世代型植物工場、未来型レシピサービス、分散型レストラン&フードロボ、3Dフードプリンター、医療レベルの生体情報が取得できるパーソナライズドサービスなど、食のイノベーションのパーツが生まれてきている。
これらを統合したライフスタイルソリューションがいつ出てきてもおかしくはない。
日本には、こうした先端領域向けのコア技術を有するだけでなく、食のiPhoneのOSを押さえること、そして体験を創ることができる技術や人財も存在する。
しかし、日本の食のイノベーターは大手企業をはじめ企業にロックイン(閉じ込められて)されており、外に出て、新規事業を自由に試したり、協業をドライブしたりすることがなかなかできない。
iPhoneが生まれる前も、大手企業にはiPhoneのコンセプトを理解する個人は確かに存在していた。ただし、企業から飛び出せる状況ではなく、結果として日本からiPhoneは生まれず、今のような低迷する状況に陥ってしまった。
日本の強みを駆動させていくべき今このタイミングで、食を新たな産業として昇華していくために必要なポイントは何か。
私たちは次の8つであると考えている。
⒈ 日本の食に関する強みを深く理解し可視化すること
⒉ 日本の強みをunlockし価値創造につなげる仕組みの構築
⒊ 共創が当たり前となるしくみと環境づくり
⒋ パッションを持ち、やり切れる人財の既存組織からの解放
⒌ パッションを持ち、やり切れる人財を生み出し、進化させること
⒍ 食が持つ多元的価値の定義とそれを評価する指標の策定
⒎ 人間理解を3段階ほど高めること(企業サイドも個人も)
⒏ 群としての羅針盤(ビジョン)をつくる
日本の食に関する強みを深く理解し可視化すること
先述した日本の強みであるが、日本企業自身が認識していないことも多い。日本では当たり前すぎて、それが強みであると実感することができないのだ。こうした強みは、世界の動きに触れ続けることで初めて見えてくる。
日本のプレイヤーには、展示会でもいいし、海外のウェビナーを聞くのでもいいし、とにかく世界に足を運んでアンテナを張ってほしい。
そして何が起きているのかを自ら体感してほしい、世界の取り組みを見てほしい。学んだこと気づいたことを社内や業界にシェアしていく、そうするとムーブメントを後追いするのではなく、先行してムーブメントを起こせるかもしれない。
米国ではホールフーズ・マーケットやウォール・ストリート・ジャーナルといった民間企業やメディアが世界に向けて食のトレンドを発信しているが、日本企業からもそうした発信を英語でしていくべきである。
私たちは世界中を駆け巡り、さまざまなプレーヤーと直接話すことで、日本が持つ強みを客観的に理解・体感している。私たち自身も、さまざまなステークホルダーと共にもっと日本の食の強みの発信・可視化をする活動を増やしていきたい。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

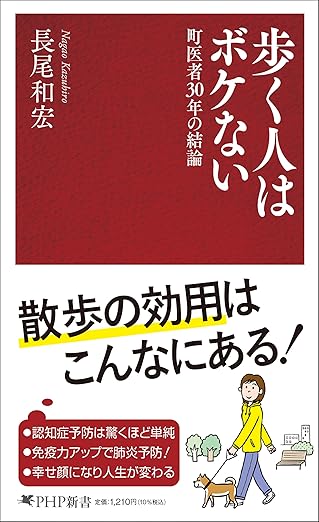





.jpg)
