ひろゆき氏の持論「高い学歴を持っておいた方がいい」は本質的? 学歴論争の現在地

学歴不要論が盛んに議論される一方で、学歴社会が根強く残るのはなぜでしょうか。盛田昭夫氏や堀江貴文氏の「学歴不要論」、お笑いコンビ「ロザン」やひろゆき氏の「学歴有用論」を引用しながら、学歴論争の現在地を書籍『学歴社会は誰のため』より解説します。
※本稿は、勅使川原真衣著『学歴社会は誰のため』(PHP新書)から一部を抜粋・編集したものです。
学歴がすべてではない説(不要論)
「学歴は究極のオワコン」「賢い奴は今どき大学なんか行かない」
学校で何を学んだか、どんな優秀な学校に通ったか、ましてや学校でいい子だと評価されたかどうかなんて、社会に出て仕事をするのにはちゃんちゃら関係ないとの主張。学歴オワコン発言は、ホリエモンこと堀江貴文氏のインタビュー記事中にあった学歴描写です(新R25・2020年10月9日、JCASTニュース・2022年5月2日)。
皆さんはどんなご意見、ご感想をおもちでしょうか。言うてもホリエモンは東京大学出身(中退)ですから、余裕を感じさせる発言にも思えます。ちなみに「ブランドとしての価値」という表現は経済学で言う、大学=個人の生産性を企業に伝達する手段、と考えるシグナリング理論をなぞっているように取れます。
続いて。1960年代、高度経済成長期のど真ん中に遡れば、こんな語りも忘れてはならないでしょう。
「会社は、激しい過当競争のさなかにあって、実力で勝負しなければならないというのに、そこで働いている人は、入社前に教育を受けた『場所』で評価されるというのは、どう考えても納得がいかない。教育の『質』が問われるのならばまだ解る。『場所』というのは、正常ではない。わずか数年間の学校教育が、以後何十年にもわたって、その人の看板として通用するというのは、奇妙というほかはない。
(中略)何々大学を出たからというだけで、その人の価値が高いと決めることにはなんら意味がないし、教育の程度と学校の名前だけで、その人が役立つ度合とするならば、大変な間違いであろう」
これはかの有名なソニー創業者盛田昭夫氏の『学歴無用論』の一節です。いまから半世紀以上前の指摘とはとても思えないのは、私だけでしょうか。名経営者という意味でのインフルエンサーが声高に叫ぶ、学歴無用論の走りです。
ちなみに盛田氏はこの一節のあと、安直な学歴による人の采配に頼るのは、職務要件定義とその評価の手間を惜しむからだ! といったことを説くのですが、それはそれは痺れます。これも学歴が個人の生産性のシグナル足りうるのか? という観点で効用を語っていると言えましょう。
さらには、(高)学歴を単純に「勉強ができる」に置き換えたとき、次のような言説もあるあるの1つではないでしょうか。
「勉強はできても、仕事はできない」
の類です。私もそうなのですが、一瞬「自分のことを言われてる!?」とつい記事をクリックしそうになるものです。じつに引きの強い言葉としての学歴不要・無用論。仕事との対比・接続で語られるといっそう、ドキッとさせられます。
これもやはり学歴と生産性との関連を疑う言説なため、学歴のシグナリング機能についての反論と言えそうです。
「学生時代は優秀だったのに......『勉強』はできても『仕事』ができない人の共通点」
「なぜ、『勉強ができる人』は『仕事ができない人』になってしまうのか」
さもありなんという実際の記事の見出しです。これでイラっとする人もいれば、ほっと胸をなでおろす人もいるのでしょう。
もっと人生とは壮大な話なんだよ派
他方で、学歴なんて......論の延長線上には、次のような発言もよく知られたところかと思います。
「人間にとって大事なことは、学歴とかそんなものではない。他人から愛され、協力してもらえるような徳を積むことではないだろうか。そして、そういう人間を育てようとする精神なのではないだろうか」
これはホンダ創業者・本田宗一郎氏の言葉とされていますが、学歴ではなく、愛、協力、徳ときました。本田氏に言われてはぐうの音も出ないかもしれませんね。
いわゆる「人間性」が人生のかぎを握る、といったことを指し示していると思われます。人間性と言い出すと私からすると、「頭の良さ」の評価より難易度が高そうな気もしたりしなかったり。道徳論、人生訓としての学歴言及といった様相です。
いささか類似したもので、もう1つ。経営の神様こと松下幸之助氏はこのようなことにも言及しています。
「病気がちで、家が貧しく、学歴もなかったから成功できた」
これまたわーお! という主張です。学歴がないのなら周りに知恵を借りればいいだけである、とも発言している松下氏(『人事万華鏡 私の人の見方・育て方』)。成功したから結果的に言える言葉のようにも思えなくもないですが、学歴が成功の秘訣では決してない、逆境や、周囲の協力を得られるような人物であることのほうが奥義ではないか? といった訓示と言えましょう。
経済学の話で言うと、学歴が生産性のリトマス試験紙になるかどうかという先のシグナリング理論的な見解というより、賃金上昇を達成・成果と捉えた場合に、学歴の獲得の投資効率を念頭に置いたような発言、すなわち人的資本論に近しい印象を受けます。
学歴はあって損はない説(有用論)
「学歴は浮輪のようなもの」
なかなかうまいたとえだな......が私の第一声でした。これは、いわゆる「下駄を履かせる」の意味を、浮輪や自転車の補助輪といったレトリックで説明したもの。最初から大海原でも泳げる猛者はそうしたらいいのですが、たいがいのひよっこには、せめて初心者のうちは浮輪があったほうが安心できる。
まぁいつかは外して泳がないと、バタバタ泳ぎしかできないのでは速度が圧倒的に遅く、ダメだろうが、それでも学校から就職という社会システムの流れに鑑みるに、高い学歴はその後大海原で悠々と泳ぐ最初の安全な一歩にはなるだろう――そんな意味のコメントをお笑いコンビ「ロザン」の宇治原史規さんと菅広文さんが『産経新聞』(2018年1月6日)で語っています。
さて、こうなってくるとまったく、いったい何が「正解」なんだか......とため息が出てきます。おそらく正解探しをするとどつぼにはまるのでしょう。なぜなら巷では、置かれた環境=スタートラインが違うのに、自分はやってこられたから学歴は要らないよ、とか、逆にやっぱりあるに越したことはないよ、などと言い合っている状態だからです。
また同時に、経済学の理論体系に照らし合わせても、シグナリング理論と人的資本論は、賃金上昇が見合うだけの資格かどうか? そのために時間とお金をかけることの費用対効果はいかほどか? といった議論です。ゆえに、生産性の示すものがそもそも曖昧模糊としているのに、唯一解があるかの前提で是非を問うため、神学論争化しがちなことも付言しましょう。
*
となると、学歴論争はどう扱っていくのがよいのでしょうか。ここで私が目を向けたいのは、あるインフルエンサーの言葉です。大卒と非大卒の生涯賃金格差についてデータを引き合いに出しつつ、次のように述べます。
「日本の大学で教えていることは、一部の専門的な分野を除いて、社会に出てからあまり役に立ちません。大学で学んだことが企業で生かされていないとすると、高卒の人と大卒の人で仕事内容はそれほど大きく変わらないはずです。にもかかわらず、生涯賃金に6000万円もの開きがある。これは、日本企業が「大学で何を学んだか」ではなく、「大卒である」ことに価値を見いだしていることの表れでしょう。
もちろん、ビル・ゲイツ氏やマーク・ザッカーバーグ氏、日本では堀江貴文さんのように大学を中退して成功している人はいます。でも、それはごく一握りの超優秀な人たちです。一般的には、大卒という肩書きは持っておいて損はないのです。もっと言えば、高い学歴を持っておくのに越したことはありません。(中略)『その人となりを見る』ことは困難。どうしても、学歴のようなわかりやすい基準に頼ることが多くなります」(ライブドアニュース、2020年12月11日)
これは誰の発言かと思えば、論破王として名高きひろゆき氏ではないですか。学歴有用・不要論のはざまで、ああでもない、こうでもないと持論を展開する著名人(インフルエンサー、いわゆる成功者)たち、メディアが散見されますが、このひろゆき氏の発言はどうも毛色が違うようです。
というのも、教育社会学を修めた組織開発者として言説を眺めるに、この論調は既視感たっぷり。それもそのはず、私の古巣でもある教育社会学が、学歴論争について解きほぐす際の論点が一挙に示されているのです。どうしたひろゆき氏。
換言すると、個人的な経験談や志向性を超えて、社会システムとしての学歴を考えた場合の論点はまさに、次の3点に集約できると言えます。
(1)学歴格差と不平等問題
(2)教育内容×労働(仕事内容)の関連性の問題
(3)学歴ではない「成功」のカギ
言説人が学歴について議論をする際に、「要らない」「いや、あったほうがいいでしょ」と自身の経験談ベースのポジショントーク(自分の立場や立ち位置を絶対として周囲を相対化すること)を展開することがままあります。
しかし、「何を選ぶのが最も得か?」とか「最強」「コスパ」がいいか? といった意味での「正解」探しに奔走すると、学歴論争は不毛に陥りやすい。
なぜなら、各人の状況の違いを棚上げしたままでは、一元的な「正解」なんて出せっこないのですから。生まれや置かれている環境は皆多様です。さまざまな初期値(インプット)に対して、アウトプットはと言うと、「生涯賃金」の高さといった一元的な「正解」でジャッジしようとしている――これが学歴論争の現在地なのです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

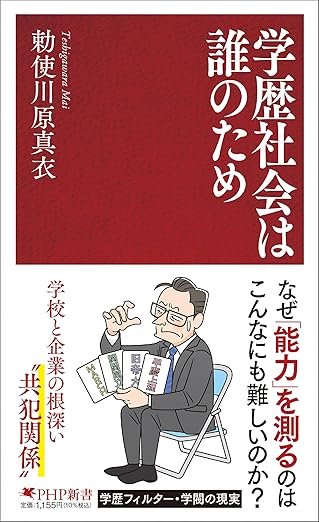

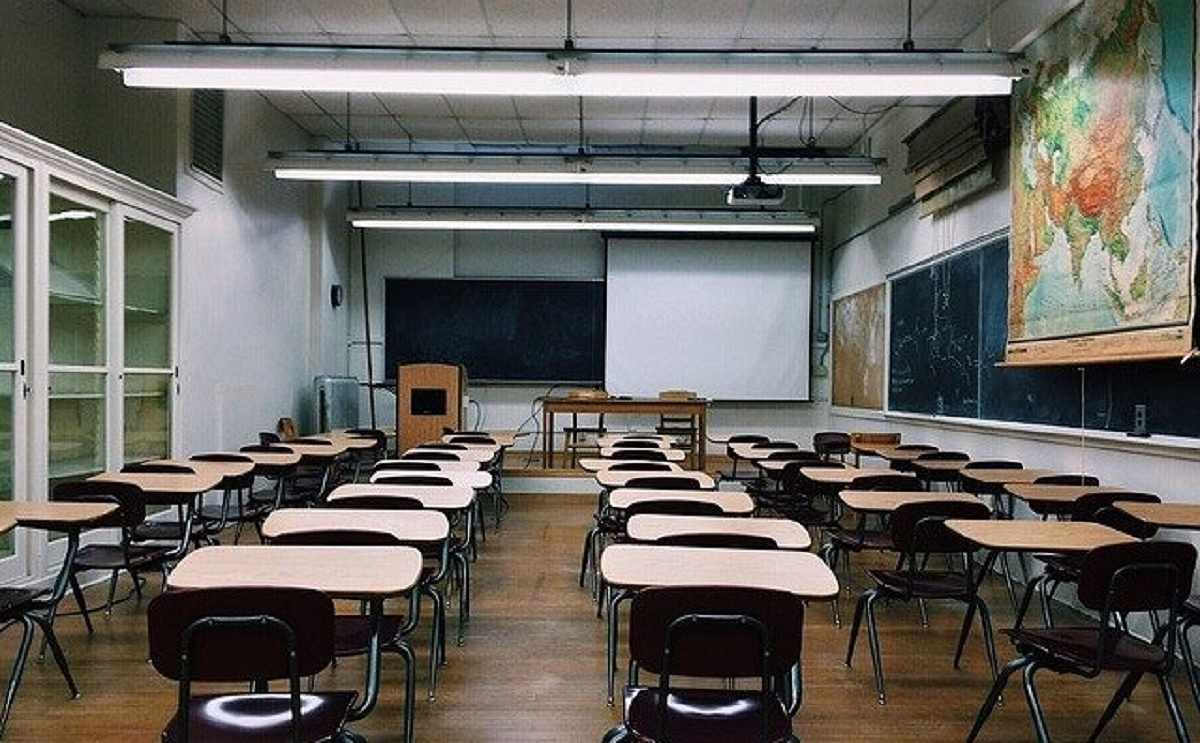



.jpg)
