アヘン戦争によって、中国人が今も抱え続ける「西洋に騙された」というトラウマ

中国人にとって近代は「暗い時代」として記憶されている。19世紀の半ば以降の清朝は、アヘン戦争・アロー戦争・清仏戦争・日清戦争と、列強諸国の侵略に繰り返し打ちのめされ、国家としての尊厳を大きく損なうことになった。特にアヘン戦争は、悲惨な「近代」をもたらした忌むべき端緒として認識され、現代でも中国人の行動原理に大きな影響を与えている。書籍『中国ぎらいのための中国史』(PHP新書)より解説する。
※本稿は、安田峰俊著『中国ぎらいのための中国史』(PHP新書)から一部を抜粋・編集したものです。
現代まで続く中国の愛国主義の歴史
満洲族の征服王朝だった清朝は、18世紀後半に極盛期を迎え、旺盛な拡大活動によって台湾や新疆を含むユーラシア東部の広大な範囲を支配した。外モンゴルを除いた清の最大版図は、現在の中華人民共和国の国土の領域とほぼ一致する。
彼らの統治は、長寿の皇帝だった乾隆帝の末期から徐々に緩んだ。ただ、19世紀初頭の清のGDP(国内総生産)は世界経済の3割以上を占めていたとみられ、最強の帝国としての存在感は健在だった。地大物博を誇る中国は、ヨーロッパ船の来航を南方の広州一港に限定して許可する管理貿易体制を敷いていた。
そんな中国から、茶や絹織物を購入していたのがイギリスである。対してイギリスが中国に売っていた人気商品の一つが、英領インド産のアヘンだった。
結果、中学校の社会科でもお馴染みの、英・清・印の「三角貿易」が成立する(実態は教科書の図式とはやや違うようだが、ここではひとまず一般に理解されやすい説明をしておく)。
当時の外国人商人の間では、広州の正規の港湾を通じた貿易は各種の税負担が重いため、非正規港を利用して納税をスルーする小規模貿易が常態化していた。ゆえに、少量でも利幅が大きいアヘンはこの手の密貿易に向いた商品でもあった。アヘン戦争前夜の1838年には、年間で約4万箱(約40万人分)ものアヘンが中国に流入していたという。
一方、1830年代の清国内では銀高による不況が起き、清朝はアヘンの密貿易による銀流出がその原因であると判断する。そのため朝廷は、欽差大臣(特命全権大臣)の林則徐を広東に派遣し、アヘンの摘発強化と没収アヘンの大量焼却といった措置を取らせた。
ただ、ここで対外トラブルが起きる。林則徐は一連の政策のなかで、広州のイギリス人商人にアヘンの持ち込み禁止の誓約を求めたのだが、商人側はこれに強く反発。イギリスの対中国貿易は停止状態に陥ってしまった。激怒したイギリスは、事態を打破するために砲艦外交に訴えることを決め、1840年に戦端が開かれた――。
これがアヘン戦争である。やがて、清朝の政策方針の一貫性のなさと火力の差、従来の長い太平からくる軍事戦略の稚拙さや対外戦争の経験の薄さ、満洲族支配への反発や密貿易の利益のために英軍に協力した漢民族の続出といった数多の要因が重なり、清は惨敗する。
1842年、清は南京条約を結ばされ、香港を植民地として割譲させられたほか、広州・福州・厦門・寧波・上海の五港を開港。従来の管理貿易体制を解体された。後年、現代中国を代表する都市に成長する香港や上海の歴史も、事実上このときからはじまる。
やがて、アメリカやフランスも同様の条約を清に押し付けた。中国は治外法権の容認と関税自主権の喪失という、19世紀の西洋列強諸国がアジアの各国に仕掛けたお馴染みのパターンに絡め取られることになった。14年後に勃発したアロー戦争でも清が敗北したことで、この構図は固定化する。
ちなみに、敗戦当時の清朝は、事態の深刻性をさほど認識していなかったといわれる。西洋諸国と結んだ不平等条約も、かつての匈奴やモンゴルが中華王朝の北辺に侵攻したときと同様、皇帝の徳にまつろわぬ化外の民への「恩典」のように考えていた節があった。
アヘン戦争は、そんな清朝にとって「気の毒」な事件だった。イギリス側の開戦理由は、議会でも根強い反対論が出るなど道義的な正当性に疑いがあった。清朝がオウンゴールを重ねた結果とはいえ、砲艦外交に屈した結果、国際ルールを十分に理解しない状態で不利な要求を呑まされた構図もあった。
その後、列強諸国は徐々に、清朝を与しやすい相手だとみなし、要求を積み重ねていく。彼らは「近代」を通じて、手練手管を用いて中国を騙し、国土を蚕食し続けた――。加害者の主役は、19世紀のうちは英仏米露、20世紀前半には日本である。
一方、中国側でも知識人を中心に危機を自覚する人が増えた。彼らは強い被害者意識を抱くと同時に、自国の「弱さ」が侮りを招いたのだと考えるようになった。現代まで続く中国の愛国主義の歴史はこうして始まる。
それが中国にとっての近代だった。
西側は中国を陥れようとしている
時代がずっと下って1989年、六四天安門事件が起きた。中国共産党が人民解放軍の武力を使い、体制改革を求める民衆のデモを鎮圧した事件だ。
事件後、党が盛んに主張したのが「和平演変」という概念だった。これはアメリカをはじめとした西側諸国が、基本的人権や議会制民主主義、自由主義といった美辞麗句を隠れ蓑に、武力を用いない方法で党体制の転覆を目論でいるとする国際認識である。天安門の学生デモは、アメリカなどの外国勢力に扇動された反革命暴乱だったとする説明がなされ、事件直後にはそうしたプロパガンダが繰り返された。
事実、天安門事件前夜の中国国内では、西側各国のマスコミや情報機関が活発に活動し、一部はデモ隊を助ける行動を取っていた。学生グループには当時イギリス領だった香港から膨大な寄付金が流れ込み、運動の中心人物の亡命にも、アメリカや英領香港・フランスが大きく関与した。加えて当時は、東欧の社会主義体制が雪崩を打って崩壊しはじめた時期だ。和平演変の懸念は一定の根拠があった。
だが、中国の警戒心には別の理由もあった。天安門の民主化デモを応援した「西側先進国」は、かつて国土を蚕食した帝国主義の列強諸国とほぼイコールだったからだ。
各国が「近代」に立ち戻り、結託して再び中国を陥れているという認識は、単なる妄想では片付けられない説得力があった。デモは外国勢力の扇動だったとするプロパガンダを、庶民のみならず元参加者の学生の一部ですら信じ込んだのは、そうした事情ゆえだった。
ただし、当時のこの考えはほどなく薄れた。武力鎮圧の当事者である鄧小平が、経済開放の継続を主張し、後継者の江沢民や胡錦濤も中国社会の自由化や国際化を進めたからだ。経済発展一辺倒のムードのなかで、西側企業の対中投資は歓迎され、WTO(世界貿易機関)の加盟や北京オリンピックの開催誘致を背景に国際協調が唱えられた。
江沢民時代の2002年の党大会では、のちの習近平政権のスローガンになる「中華民族の偉大なる復興」がはじめて唱えられた。だが、この時点では世界に伍して中国を豊かにしていこうという、明るい掛け声としての意味合いが強かった。
次の胡錦濤時代になると、西側的な「自由・民主・人権」の概念を人類の普遍的な価値観(普世価値)として認めて、中国もそれを受け入れようという「攻めた」意見まで力を持った。一時は政権もこれを容認しかけたほどだ。
結果的に「普世価値」の受け入れは保守派の反対で却下されている。また、チベット問題などで国際的な批判を受けるたび、中国が西側諸国に強く反発するのは相変わらずだった。
ただ、社会の民主化や自由化を外国の陰謀だと考える和平演変論が、存在感を弱めていたのは確かである。少なくとも、中国のまともな知識人は積極的に論じなくなっていた――。
コロナ対策に「失敗」した欧米を見下して得た自信
しかし、2012年秋以降、こうしたユルい雰囲気は一変する。
習近平の総書記就任が決まった第18回党大会から、「普世価値」に代わって「社会主義核心価値観」という中国(党体制下の中国)の独自の道徳が提唱され、街にプロパガンダ看板があふれるようになったのだ。
先進的な部分は西側諸国の方法も受け入れつつ、自国を立派にするという往年の姿勢も、中国自身のやり方を変えずに西側を追い抜く姿勢にスイッチする。中国が国際社会に合わせるよりも、強い中国に国際社会の側が合わせるべきだと開き直る風潮も強まった。
言論の自由の範囲が縮小し、メディアが党の礼賛一色になったことで、自国の正しさを確信してしまう国民も増えた。とりわけ中国人に自信を持たせたのが、2008年(胡錦濤時代)の世界金融危機と、2020年のコロナ禍の際の欧米諸国の混乱だ。
かつて仰ぎ見ていた諸国のぶざまな振る舞いを見た中国人には、当時の中国政府の対策のほうがよほど優れているように感じられたのである(もっとも、ゼロコロナ対策は2022年に破綻してしまうのだが)。
一方、自信とともに頭をもたげたのが不安である。
強くなった中国を邪魔するため、西側諸国が陰謀を企てているという被害妄想が生じたのだ。二〇一八年ごろから、アメリカが中国の台頭を警戒して米中対立が強まったことで、この不安はいっそう強まった。
習近平政権は西側諸国について、ゼロ年代に東欧諸国で起きた再民主化運動「カラー革命」(顔色革命)の扇動を、中国でも企図していると宣伝している。和平演変の現代版である。「2019年の香港デモはアメリカの扇動で起きた」「新型コロナウイルスはアメリカから流入した」など、被害意識を煽る陰謀論的なプロパガンダも盛んに流された。
結果、その影響を強力に受けているのが近年の中国人だ。
中国の庶民の大部分は、コロナのアメリカ起源説を現在でも信じている。
日本の福島原発の処理水排出についても、客観的データから安全性を確認できるにもかかわらず、中国当局は対日不信感を煽る情報発信を続けた。そのため、庶民が福島県内の民間の商店に嫌がらせの国際電話を掛けるような「意味不明」な行動に出るようになった。「中国版のポリコレ(政治的正しさ)」に反しているとして、中国の世論が「辱華」(中国への侮辱)を外資系企業の広告などを理由に吊し上げる現象も、根はこれと同じだ。
2019年の香港デモの時期、ティファニーの中国法人が、モデルが右目を隠したポーズの写真広告を使った(当時、香港の反体制派の間でたまたま似たポーズが流行していた)ことで批判されるなど、第三者の目には理解しがたい現象が多発している。
強国アピールと被害者意識を過度に強調するプロパガンダを通じて、人々が「自家中毒」を起こした結果だろう。自国が強くなったことで、かつての暗黒の近代の復讐を果たしたいという党の思考が、巡り巡って庶民を暴走に駆り立てている。
こうした中国社会の気質を風刺した「大嬰児」(大きな赤ん坊)という言葉がある。中国はすでに巨大な強者なのに、主観的意識としては近代のいじめられっ子のままで、都合のいいときだけ弱者ぶって世界に向き合うようになったというわけだ。
禍福は糾える縄の如し。
イギリス商人の密貿易からはじまったアヘン戦争は、約180年後にワガママ放題の大きな赤ん坊国家を生むという、誰も予測できなかった結果をもたらしている。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債


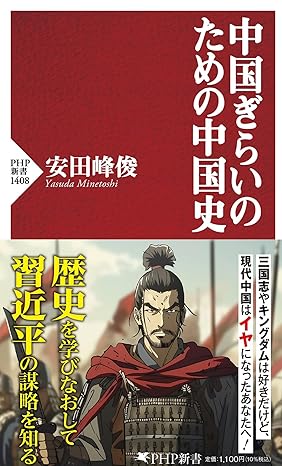





.jpg)
