「諦めがあるからこそ希望がある」小説すばる新人賞最年少受賞作家が語る
2020年09月12日 公開
2024年12月16日 更新
「人間ってこんなもんだよな」という諦観
――作品の中身に話を戻すと、十太の元同級生だった大宮夏佳は水泳選手として活躍しつつ、心の奥ではいつも十太の存在を意識していた。フリーライターの相葉光莉は、十太のバンドの演奏を偶然聴いたことで夏佳との関係を深めていく。立場や環境が違っても、皆が十太に巻き込まれていく様が印象的でした。
【青羽】 そう感じてもらえたなら良かったです。もしも自分が作家として秀でている部分があるとしたら、それは物語を構成する力だと思っています。もしくは構造と言い換えてもいい。
作家のなかには、書き進めていくなかで物語を膨らませていく方もいます。しかし僕は、最初から明確なメッセージや構造を決めています。
夏佳と光莉が、十太の生き方の「真相」に迫って行動を共にした最後のシーンは、描写から台詞まで最初から頭の中にありました。
――音楽の才能で周りを惹き付ける十太の姿は、若くして読者を魅了する青羽さんと重なって見えました。十太をどういう人物として描こうと思ったのでしょう。
【青羽】 十太は僕にとって理想とする人物だといえます。彼はいつも遠くを見ていて、現実に合わせた中途半端な妥協は許さない。
僕が小説を書くうえでも、たとえば自分の身近にある題材だからといって昨今の大学生の姿を描くだけでは、やはり深みがないでしょう。その先にある何か大きなテーマを捉えたい。いつもそう考えています。
一方で、十太はたしかに才能にあふれる人物ですが、安易なカリスマとしては描きたくなかった。彼の人物像は、周りの人間がつくり上げた側面もあります。
もしも十太を取り巻く環境が違っていたら、彼はたんなるギター好きなおじさんになっていたかもしれない。
人間とは誰もが大なり小なり多面性をもっているもので、十太のそうした部分も意識しながら描きました。
――「天才」といわれる人たちも当然、固有の悩みや葛藤を抱えている。青羽さん自身もそうですか。
【青羽】 僕の才能を認めてくれる人がいるのは有り難いことです。でも仮に自分が本当に「天才」だとしたら、小説の筆が進まなくて一日ブルーな気分で過ごすなんてことはないはずです(笑)。
本作の登場人物のなかでも、十太は決して特別な存在ではありません。世の中の全員は同じ場所に立っているのだと思います。
悩んだり輝いたりする瞬間がそれぞれにある。そういう意味で、僕は「人間ってこんなもんだよな」という諦観をつねにもっていますね。
一作目の『星に願いを、そして手を。』も、自分のなかでは諦めの物語でした。主人公の祐人は宇宙に憧れながらも挫折し、町役場に勤めています。
一方で元恋人の理奈は大学院に進学し、宇宙に携わる道へ邁進している。二人の対比は象徴的ですが、そこに明暗はないんです。「比べても仕方がない」という諦観があるからこそ、人は前に進んでいける気がします。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月08日 00:05
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

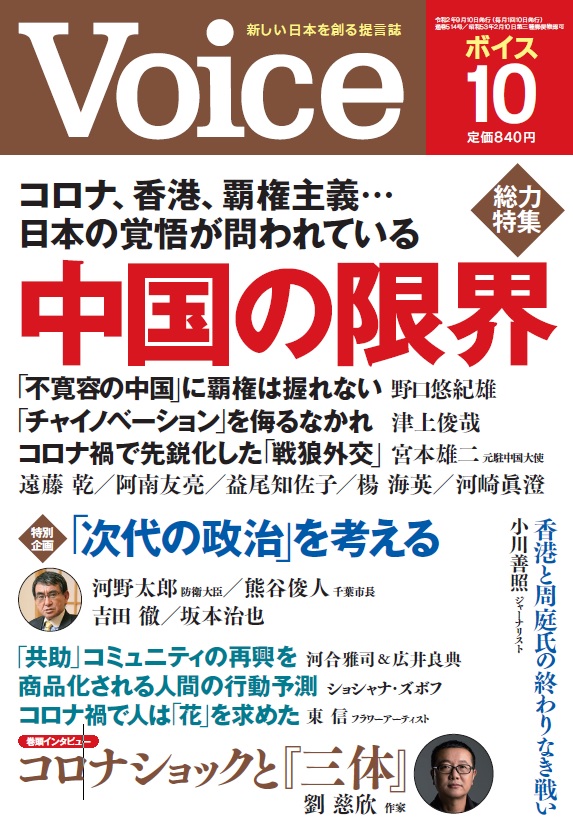


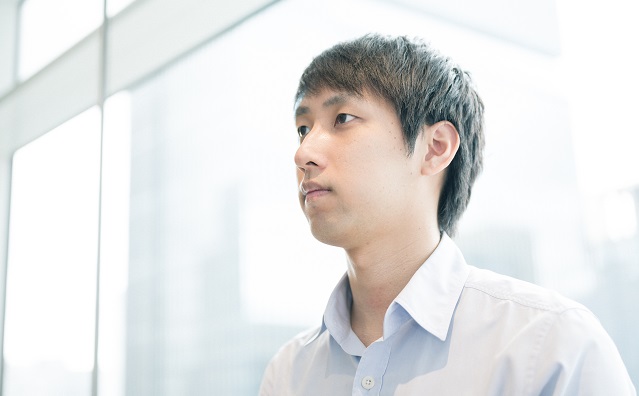
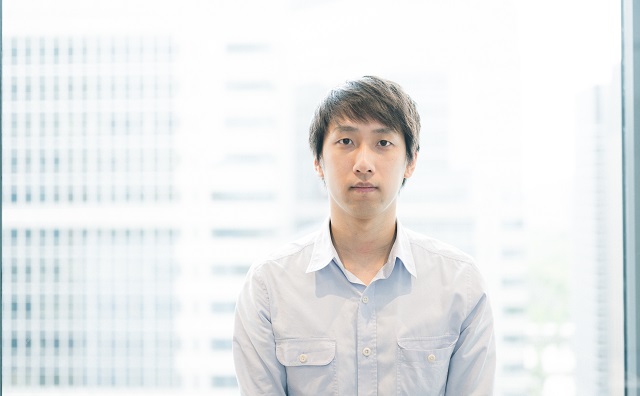


.jpg)
