天安門事件、新型コロナ、香港デモ…騒動の裏で進む「中国共産党のメディア支配」
2020年06月04日 公開
2024年12月16日 更新
不自然だらけの男の挙動は自作自演か?
当時、北京飯店の一室の最前線拠点で取材をしていた筆者も、その事件を直接目撃することができた。私やその一部始終を撮影したカメラマンは、しばしあっけにとられ、一体何が起きたのかもわからなかった。そして、考えれば考えるほど理解に苦しむことが次々と浮かび上がってきた。
まず、厳重な警備が敷かれていた天安門広場の近くになぜあの戦車男が易々と入り込めたのかということ。もし仲間がいれば数人で一斉に車道に飛び出したと思われる。前日の天安門事件の戦車男はたった一人で無謀にも戦車の前に立ちふさがったのだ。完全な単独行動だった。
しかも男が戦車を止めた場所は公安省の目の前の路上で、当時その近辺には、非常に多くの私服警察官が見張っていたはずだった。もし不審な男がいれば、道路に飛び出した瞬間につかまってしまうような緊迫した状況だった。
なぜ私服警官たちは、あの戦車男が戦車の前に飛び出してもすぐに取り押さえず、しばらく戦車の行く手を妨害し続けることを黙認したのだろうか。男が着ていた服装もおかしかった。真っ白なワイシャツを着ていたのだ。
当時、天安門広場で抗議運動をしていた学生や市民の多くは、その場に何日も寝泊りしていたため、顔はすすけ、着ているものはだいぶ汚れていた。汚れが目立たないよう色物のシャツを着ている人が多かった。
天安門広場の周辺で見かけた「きれいな白いシャツ」の人たちは、その多くが二人ずつペアで行動する私服警官など当局側の人間が多かった。われわれが天安門広場などで取材する時も、常に「白シャツ」の姿や視線を確認しながら行動していた。
当日、戦車男を取り押さえた私服警官と見られる人たちも、その多くが白シャツだった。そして何より、秘かに人民大会堂に進駐した兵士たちも白シャツ姿だった。
自作自演を示唆する証言
数日後、接触ができた党宣伝部門の関係者はさりげなくこう耳打ちしてくれた。
「あれは一人の勇敢な男が戦車に立ち向かったということよりも、戦車が人をひかなかったことこそ重要なのです。そこに注目してほしい」
それは「あの勇ましい男と戦車の光景」は、「戦車は人をひかない」ということをわれわれ外国メディアにアピールするために当局側が仕組んだ「自作自演」である可能性を示唆する言葉だった。もしその通りだとすれば合点がいくことが非常に多い。
舞台はまさに外国メディアがカメラを向けているその目の前で起きた。ほとんどの海外メディアが活動拠点としていた、北京飯店のバルコニーからよく見える場所で、一連の出来事が繰り広げられたのだ。そのため世界中のメディアが、あの光景をしっかりと撮影できていたのだ。
多くの社が取材をしていながら、事件から30年を経ていまだにあの戦車男は名前すらはっきりしていない。やはり当局側の人物、もしかしたら戦車部隊の現場指揮官だった可能性も十分ある。
いずれにせよ、そこまでつじつまが合うのであれば、やはり戦車男が引き起こした行動は、「戦車は人をひかない」ということを外国メディアにアピールすることが最大目的であったと結論づけるのが自然だろう。
厳しさを増す言論統制は天安門事件の呪縛か
天安門事件のさなか、国内外に対して様々な情報を流しながら、国民感情や海外メディアを巧みに政治に利用してきた中国共産党。これらはそのほんの一部に過ぎない。
毎年事件が起きた6月4日の前後には、広場周辺はものものしい警備体制が敷かれる。事件への抗議活動や、追悼活動、さらには名誉回復を求める動きなどが起きることに当局が極めて神経質になっていることが透けて見える。
何より中国国内の言論統制はその後も厳しさを増している。2008年の北京オリンピック・パラリンピック開催の前後と、2010年の上海万博開催の前後は、一時期報道規制が緩和された印象も若干あるが、2012年秋の党大会で習近平指導部が生まれると、言論統制は一層厳しくなった。
事件の後、急速に普及したインターネットの世界では、天安門事件に関わる言葉を打ち込むとただちに削除される仕組みになっている。徹底した監視体制の下、14億の民は、今そのハイテク技術の進歩によって、一挙手一投足まで当局に把握されるようになりつつあるようだ。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月07日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点
- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

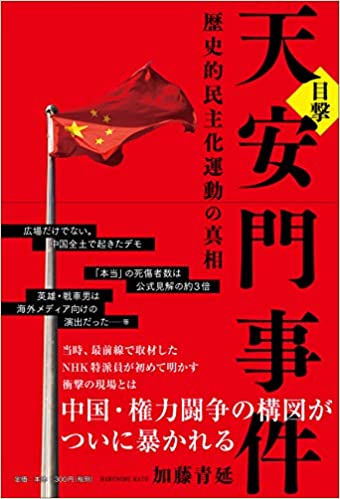




.jpg)
