ノーベル賞経済学者が猛批判した「日本のバブル崩壊の真犯人」
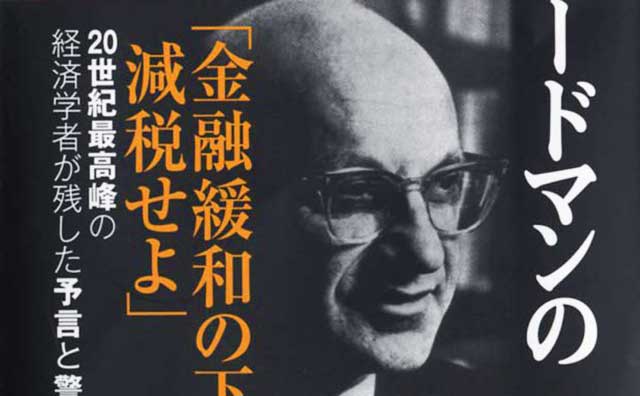
ノーベル経済学賞を受賞し、20世紀後半から21世紀初めにかけて世界に燦然たる輝きを放ったアメリカの経済学者ミルトン・フリードマン(1912-2006)。
この「巨匠」がじつは繰り返し日本に関する分析と発言を行なってきたことをご存知だろうか? 日本のバブル崩壊とデフレ不況を予見し、金融政策の誤りや貿易摩擦、構造問題を鋭く語ったフリードマンへの再評価が進んでいる。
日本のエコノミストから「市場原理主義者」のレッテルを貼られ誤解されがちなフリードマンの対日分析を行った書『ミルトン・フリードマンの日本経済論』。同書より、日本のバブル崩壊を予見し的中させたフリードマンが、その原因を日銀と指摘していたことを解説する一節を紹介する。
※本稿は柿埜真吾著『フリードマンの日本経済論』(PHP新書)より一部抜粋・編集したものです
バブル経済批判──「東京の株式市場は健全とは思えない」
1990年2月7日、フリードマンは、イタリアの経済紙に対して「東京の株式市場の時価総額はすでに500兆円を超えているが、この数字は世界の株式の40%近くに当たり、決して健全なものとは思えない」と指摘、将来の暴落を予測した。
当時、日経平均株価は1989年12月の最高値からは下落していたものの、1月半ば以降3万7000円前後で安定、恒久的な高原状態を続けるかに見えていた。
だが、不吉な予言は、やがて現実のものとなった。資産バブルを懸念した日本銀行は1989年から金融引き締めを続けていたが、1990年3月に入ると株価は暴落、3万円を割り、年末には2万円台前半まで下落、翌年には2万円も割り込むに至った。
金融市場の逼迫、貨幣量(M2+CD)成長率の急低下にもかかわらず、日銀は資産バブル潰しに固執し、ハイパワード・マネーを減少させ、金融引き締めを1992年半ばまで継続した。
日銀が公定歩合引き下げに乗り出した頃にはM2+CD成長率はマイナスに転落していた。日本経済の運命は暗転し、失われた20年の停滞に沈むこととなったのである。
株価急落後の特集で『日本経済新聞』は「年初からの急落を「予知」した」一人としてフリードマンに言及している(「ドキュメント株価急落 第1部 衝撃編〈8〉」『日本経済新聞』朝刊、1990年3月28日)。
株価の下落はすでに始まりつつあったものの、楽観的な空気が支配的だったなかで、フリードマンの発言はきわめて早いものの一つだった。
「なぜこんなことになったのか。私の解説は至極単純なものです。全ては1987年のルーブル合意に起因する。日本とドイツ、特に日本は、この合意に縛られ、自らの犠牲においてドルを買い支えた」
この結果、日本の貨幣量は10%以上のスピードで増加、これが景気過熱と地価、株価のバブルを煽ることになった。慌てた日銀は引き締めに転じたが、「やり過ぎたのですよ。通貨供給量の増大に対して、ブレーキを強く踏み過ぎたわけです」
「プラザ合意やルーブル合意がなくても、ドル相場は今日ある水準になっていた……。……これらの合意による政府の協調介入が、逆に市場の調整を遅らせ、バブル経済とその反動不況という深刻な試練を、日本やドイツ、……米国にも課す結果となったのです」。
当初、フリードマンは、1980年代半ばまでマネタリズムを理解しているかに見えた「世界一優秀な通貨当局」日銀の能力を高く評価し、バブル経済の発生は、日銀の政策の結果というよりも日銀の金融政策に対する日米の政治家の干渉の結果だと見なしていた。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

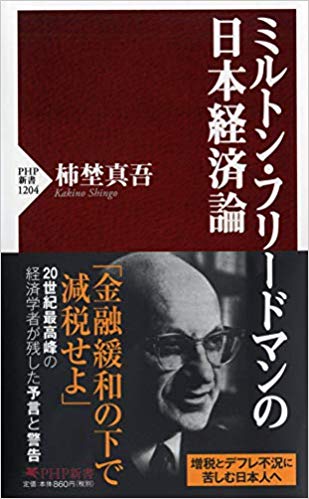



.jpg)
