門田隆将 すべての罪はわが身にあり――その言葉を嘉浩は何度もくり返した
2018年12月27日 公開
2024年12月16日 更新
人間の「業」とは何なのか
私と嘉浩との最後の面会になったのは、2010年1月8日、ちょうど松の内が明けて、学校も新学期がスタートし、本格的にその1年が活動を始める日だった。
前年11月から始まった嘉浩との面会は、すでに四度目となっていた。いつもの6階の同じ3番面会室に私は通された。
狭くはあるが、さまざまなことを話し合った空間が、新しい年にも私を迎え入れてくれた。
しかし、私には、これが嘉浩との最後の面会になることがわかっていた。最高裁判決への不服申し立てが却下されれば、自動的に死刑判決が確定してしまうからだ。
これを過ぎれば、確定死刑囚の外部交通権は、既述のように大きく制限されるのである。私のようなジャーナリストが面会できるのは、これが最後だった。
そのことが嘉浩にもわかっていたのだろう。午後1時20分から始まった面会は、新年の挨拶もそこそこに、嘉浩のこんな話から始まった。
「すべての罪はわが身にあり、と私は思っています」
狭い面会室のアクリル板の向こうから、嘉浩は、いきなりそう語りかけてきた。柔和な笑顔と、死刑囚という厳然たる事実。私には、目の前の光景が「現実のものではない」ような不思議な思いがした。
「私には、(オウムの)マインドコントロールが外れて、初めて反省が生まれました。オウムと出会ってしまったことは、“業”だったと思います。私の宿業です。業は人によって違います。武士は人を殺さなければならない時があります。また、貧しい人はつらい生活をしなければいけません。人間にとって、それぞれの宿業があるのです。
自分を見失っていたこと、そこに私の後悔があります。先生がいたとしても、先生から学んで、先生から自立してこそ、本当の弟子のはずです。しかし、私は自立しようとしなかった。
そして、麻原も私を自立させようとはしなかったのです。私は、師の誤りを正すことができませんでした。その意味で、すべての罪はわが身にあり、と思っています」
越えてはならないものを越えてしまったオウムの信者たち。自分勝手な教義で、殺人さえ正当化して突き進み、あれほどの犯罪を引き起こしたのである。
嘉浩はその幹部として、数々の犯罪に関わったのだ。そして、その陰で無念の思いを吞んで死んでいった犠牲者や、二度と幸せを摑むことができなくなった遺族たちがいる。
事件から15年という歳月によって、やっと嘉浩は法廷での自分の役割を終え、自身の判決も確定したのである。
嘉浩は、私にというより、自分に言い聞かせるように、こう語った。
「本当に自分が解脱を求めていたなら、そして、おかしい、と思ったら麻原のもとを離れなければなりませんでした。そうあるべき自分が、“そうではない、これについて行かないといけない”と思い、若さで妥協してしまいました。しかし、若いからこそ、私は離れなければいけませんでした」
そして、こうつけ加えた。
「私は、お釈迦様の伝記も読んでいました。お釈迦様は、自分の師から離れ、自立していきます。その部分も私は読んだことがあります。師から学び、そこから自立してこそ、本当の弟子のはずです。しかし、私はオウムの中でただ“盲信”してしまい、おかしいと思っても、ただ黙っていました。そこに私の弱さがあったんです。その意味で、私は、すべての罪はわが身にあり、と思っています」
すべての罪は、わが身にあり――その言葉を嘉浩は短い間に何度もくり返した。懸命に、私にその意味を伝えようとしていた。三度の面会でも伝えられなかったものが、嘉浩には残っていたに違いない。
「坂本弁護士事件も、私は、薄々気づいていました。これはおかしい、と心の中で思っていました。でも、その疑問を口に出さず、黙っていたんです。
完全にわかったのは、もちろん逮捕されてからですが、くさいなあと思っていました。なぜ、それでも(オウムから)離れられなかったのか、それが私の罪なんです」
坂本事件にも触れながら、嘉浩はこうつづけた。
「私が16歳でオウムに出会ったこと、これも自己弁解にすぎません。私には、(師を)止められるはずだったと思います」
自らに言い聞かせるように、嘉浩はそう呟いた。
16歳ということを聞いて、私は、ふと、40歳の大台に乗った感想を聞きたくなった。
「嘉浩君、いよいよ40代になったけど、これはもう、中年になったということだなあ」
深刻な話がつづいていたのに、私は急にそんなことを言ってしまった。
その瞬間、嘉浩の話が止まった。
さまざまなことを話していた真剣な表情が急に緩んで、嘉浩はにっこりと笑った。人なつっこい、あの独特の笑顔だった。
「まだまだこれからですよ。“命あるかぎり”生きていきますよ」
中年という言葉が、いささかのユーモアを含んでいたのかもしれない。彼自身も、まだ自分は若い、と思っていただろう。しかし、まさにその中年である私が、そんな言葉を発したので、おかしくなったのかもしれない。
深刻なことであるはずなのに、嘉浩は、「“命あるかぎり”生きていきますよ」と言ってのけた。面会室が柔らかい笑いに包まれた。
ちょうど刑務官が、「そろそろ……」と、遠慮がちに時間が来たことを告げた。
刑務官は、お互いを笑顔のまま別れさせようとしてくれたのかもしれない。笑みをたたえたまま、嘉浩はすっと立ち上がり、私に向かって深々と礼をした。それは、法廷で見つづけたあの嘉浩の“九十度の礼”だった。
私が礼を返しても、嘉浩は深々と頭を下げたままだった。
「生を与える」という一審判決、「死を命じた」二審と三審。そこには、生と死の狭間で揺れた司法判断とは、まったく別の次元の男がいた。
すべての罪はわが身にあり、という嘉浩の言葉を反芻しながら、私は、嘉浩との最後の面会を終えた。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史

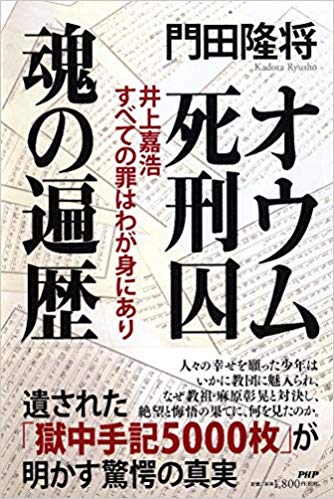

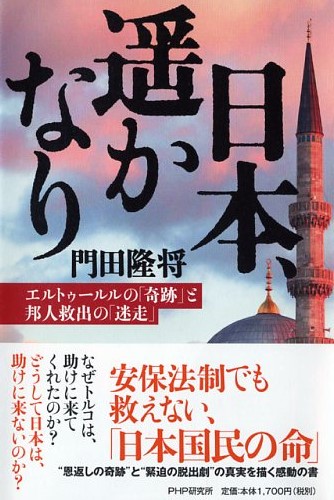

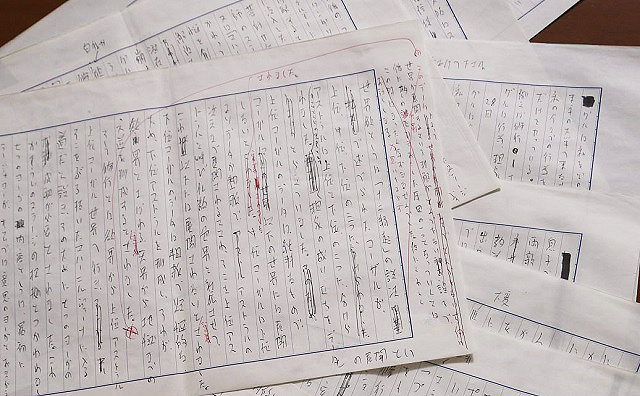



.jpg)
