投票を棄権するのは悪いことなのか? 有権者が負うべき道徳的責任
2025年08月26日 公開
2025年11月13日 更新
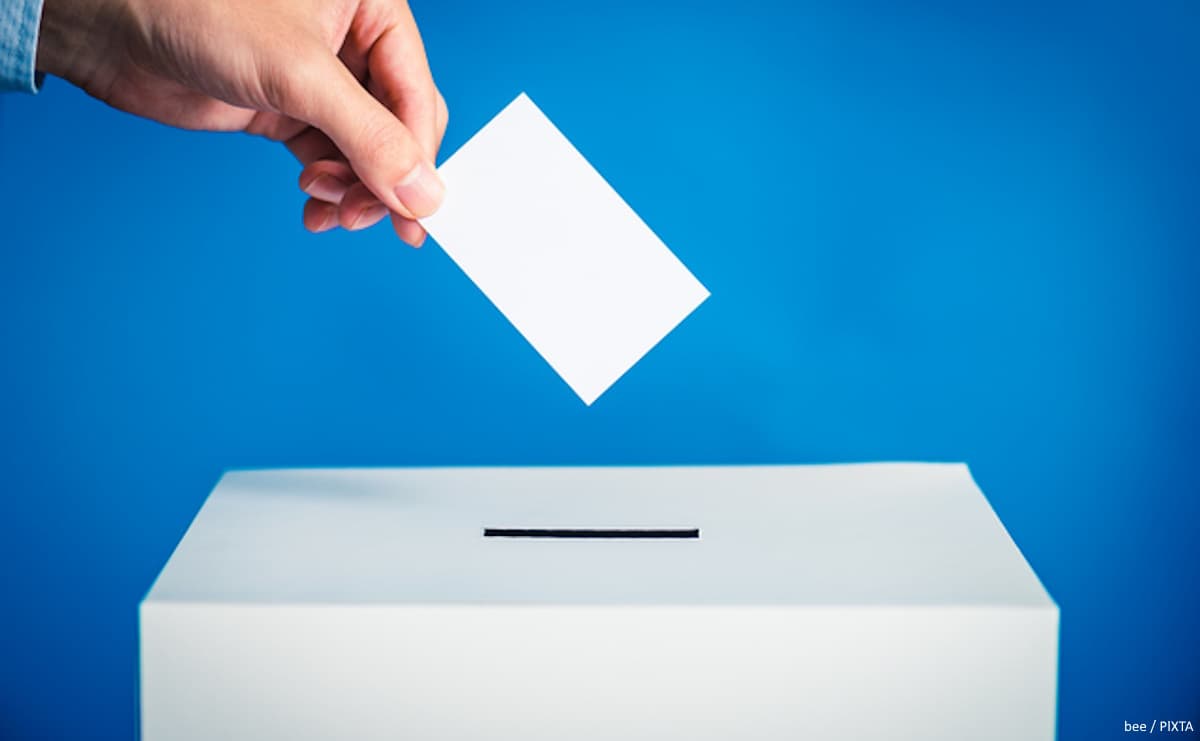
投票率が上がれば社会は本当に良くなるのか――。学習院大学の玉手慎太郎教授が、アメリカの政治哲学者、ジェイソン・ブレナンの主張を手がかりに解説する。
★本論稿は、意見集約プラットフォーム「Surfvote」と連動しています。
構成:編集部(阿部惇平)
※本稿は、『Voice』2025年8月号特集「選挙は「国」を救うか、壊すか」より抜粋・編集した内容をお届けします。
高い投票率は必ずしも「良い統治」をもたらさない
アメリカの政治哲学者ジェイソン・ブレナンは、2011年の著書『投票の倫理学』(原著:The Ethics of Voting, Princeton University Press, 2011:邦訳2025年1月、勁草書房、上下巻)の冒頭で、次のように述べた。
「うまく投票するための動機、知識、合理性、あるいは能力を欠いた市民は、投票を棄権すべきである」(上巻7~8頁、傍点は筆者追記)
私たちの多くは、選挙で投票するのは「投票しない」よりも良いことである、と考えている。メディアでも同様に、投票率の低下が問題視され、投票に行くよう広く呼びかけられている。
だが、投票率が上がれば、私たちの社会は本当に良くなるのだろうか。ブレナンは同書でこうも記している。
「明らかに、たくさんの人が投票すればするほど、社会はより民主的になる。だから何なのか?」(上巻、51頁)
たしかに、投票率の上昇によって、より多くの民意を選挙結果に反映させられるのかもしれない。しかし、高い投票率が必ずしも「良い統治」をもたらすわけではない。歴史を振り返れば、投票率が上がったにもかかわらず、状況が悪化した例は数多く存在する。
卑近な例を挙げれば、昨年(2024年)11月に実施された兵庫県知事選挙である。投票率は55.65%と、前回から約15ポイントも上昇した。しかしながら、再選を果たした齋藤元彦知事の現在の不支持率は55.9%(2025年4月23日時点)に達しており、兵庫県政は依然として混迷を極めている。
もちろん、投票率の上昇と統治の失敗の因果関係を断定するには、落選した候補者の施策のほうが齋藤県政より優れていたことを客観的に証明する必要がある。比較と判断には慎重を期すべきだが、少なくとも「投票率の上昇が兵庫県政に良い結果をもたらした」と実感している有権者は少ない、と言うことができる。
小泉純一郎内閣時の「郵政解散」による衆議院総選挙(2005年8月)も同様である。「郵政民営化の是非」に論点を収斂させた同選挙の投票率は、67.51%を記録した。
では、高い投票率を伴った選挙の結果として実現した郵政民営化によって、私たち市民の暮らしは良くなっただろうか。あるいは低い投票率の選挙と比べて、より「良い選択」ができたと、確信を持って言えるだろうか。
ブレナンによれば、私たちは悪い投票をすることがありうる。悪い投票とは、人びとに危害や損失を及ぼすような政策、あるいはそのような政策を制定しそうな候補者に対する投票のことである。そういった投票がありうるからこそブレナンは、投票率の低下を単純に問題視する見方に対して、むしろ棄権を推奨するのである。ブレナンの示す次のアナロジーは、悪い投票のイメージをうまく捉えている。
「私見では、投票者らは投票の義務を負わない。だが、もし投票するなら、投票者らは、きちんと合理的で・偏見なく・公平で・自身の政治的信念について精通しているという責任を、他者と自分自身に負う。似た話として、我々のほとんどが、親になる義務はないと考える。だが、親になるなら、責任ある良い親であるべきである」(上巻、144頁)
じつは、投票はその内容と関係なく望ましい、という立場に対する批判は、けっして目新しいものではない。たとえば地元の利権を守るための政治家への投票や、信仰する宗教団体が支援する候補への投票、あるいは知名度先行の元アイドル・タレントへの投票は、以前から日本社会で好ましくない行動として認識されてきた。そういった投票をするべきではない、ということはある種の常識であったと言ってよいだろう。
さらに、ブレナンは不適切な投票を嫌う社会通念から一歩進んで「場合によっては、棄権も必要である」と主張する。彼は、前掲書で「棄権票」を肯定する理由をレストラン選びに喩えている。すなわち棄権票とは実質的には委任というかたちの間接投票であり、投票の放棄ではないということだ。
「『私は最高のレストランに投票する。しかし、私はどのレストランがそうなのかを知らない。私以外の皆さんは、私よりもよく知っているので、皆さんの集団的な知恵を反映する形で、投票することにする。』このとき私は棄権している。しかし、実質的には、間接的な投票を行っているのである」(下巻、4頁)
たとえば、知らない土地に引っ越した友人を訪ねた際、夕食のレストラン選びを友人に任せるのは、しごく合理的な判断と言えるだろう。このとき、たしかに友人にお店の選択を委ねることは、自らの判断を保留して「棄権」する行為である。かといって、未知の対象を選ぶ際に「判断しない」という選択を非難する人はまずいない。
投票の棄権も同じことだ、とブレナンは考える。自身の判断に確信が持てない場合、「より良い判断」ができる人に投票を委ねることはむしろ正しい、と彼は主張するのである。
民主主義そのものを放棄すべき?
一方で、ブレナンの主張には危うさも含まれている。
第一に、「悪い投票をするくらいなら棄権すべき」という主張が人びとのあいだで誤って解釈され、本来の文脈から離れて独り歩きしてしまう危険性がある。
『投票の倫理学』でブレナンが意図したのは、「自分は良い投票ができているか」「良い投票をするための努力ができるか」と有権者に自省を促すことである。
ところが、ブレナンの「自分が不適格だと思うなら棄権すべき」というメッセージが誤読されると、「あなたは不適格なので棄権せよ」と訴える他者批判へと歪められかねない。「汝自身を知れ」という自省を求める書物が、「○○政党の支持者は愚かだから投票するな」という他者攻撃の道具として悪用される可能性を否定できないのである。
第二に、ブレナンの棄権推奨論は、「良い投票」をする人が一定数以上存在することを前提としている。つまり、たんに棄権票が増えるだけでは不十分であり、「良い投票」をする人が増加しなければ、社会にとって望ましい結果は得られない。
ブレナン自身も脆弱性を認識していたようで、『投票の倫理学』下巻の巻末には「上手な投票の仕方」という章が設けられている。そこでは個々人が合理的な投票をするための具体的な指針が示されており、「良い投票者」を増やすための彼なりの努力が垣間見える。ブレナンは、具体的な指針を示せば人びとは「良い投票」への努力をするだろうと期待する点で、いささか楽観的な性善説に立っていたと言えるかもしれない。
ところが『投票の倫理学』の約5年後にあたる2016年、ブレナンは『アゲインスト・デモクラシー』(原著:Against Democracy, Princeton University Press, 2016:邦訳2022年8月、勁草書房、上下巻)で、「良い投票」への個々人の努力には限界があるとして、「民主主義そのものを放棄すべき」という結論に至る。
ブレナンの立場の転換には、『投票の倫理学』が第一次オバマ政権時(2011年)に、『アゲインスト・デモクラシー』が第一次トランプ政権誕生の直前(2016年)に発刊されたという時代背景が影響しているのかもしれない。『アゲインスト・デモクラシー』では、大多数の人びとは政治に無知であり、たとえ学習を重ねてもバイアス(固定観念)から解放されず、自己に都合の良い判断をしてしまう。したがって「良い投票」を期待することは非現実的だ、という指摘がなされている。
エピストクラシーか、民主主義か
民主主義を断念したブレナンが『アゲインスト・デモクラシー』において提唱した政治制度が、「エピストクラシー」と呼ばれるものである。これは知識や能力をもつ者による統治・支配を意味する言葉であり、実態としては、一定の基準を満たした優れた者に対して大きな政治的影響力を認める政治制度を指す。
具体的には、以下のようなものがエピストクラティックな制度の例である。いずれも、知識と熟慮を欠いた投票に基づくポピュリズムを抑制すると期待できる。
複数投票制:政治学の博士号を持っているとプラス一票が加算されるなど、高い知識を持つ人に追加の票を与える制度。
知者の拒否権の導入:現状の議会に追加して、有識者によって構成される議院を創設し、法案の拒否権のみを与える制度。
参政権くじ引き制:無作為抽出(くじ引き)によって選ばれた一部の人にのみ投票権を与える制度。選ばれた人びとは一定期間、知的訓練を受けたうえで投票することが求められる。
しかしエピストクラシーにも、無視できない問題が含まれている。特定の社会層(高学歴層や富裕層など)への政治的権力の集中を招き、政治の暴走や特定層への利益誘導につながる危険性である。
たしかに民主主義は完璧な制度ではない。ただ、ウィンストン・チャーチルが「民主主義は最悪の政治制度だ。だが、これまでに試みられてきた他のあらゆる制度よりはましだ」と述べたように、民主主義は歴史上、大規模な殺戮や人類の権利に対する極端な制約を防ぐ抑止力として機能してきた。エピストクラシーに基づく権力の寡占を民主主義に代わる現実的な選択肢とするブレナンの主張に、安易に同意することはできないだろう。
根拠のない投票は不道徳
令和の時代を生きる私たちは、さまざまなジレンマを抱えている。一方では、東日本大震災を契機とした原子力エネルギーの問題や経済的・社会的な格差の拡大など深刻な問題に直面し、かつてのような楽観的な(ある意味では幸福な)政治的無関心を許されない状況にある。しかし他方では、民主党への政権交代の失敗などから政治への直接参加にも躊躇を覚え、虚無感や焦燥感に苛まれてもいる。
このような板挟みの状況において危険な誘惑となるのが、テーブルをひっくり返すような劇的な解決策である。しかし政治的な「劇薬」は、往々にしてまともではない方向へと向かう。近年における、品性や道徳性を疑わせる政治家の台頭や、その熱狂的支持者による過激な言動は、典型的な例と言えるだろう。
では、私たちが粗暴な手法を避けながら、板挟みの状況を打開するために何が必要なのか――。とりうる手法の一つが、物事を根本から考え直すことである。
ブレナンの『投票の倫理学』は、まさしく「投票とは何か」「民主主義とは何か」という問いを投げかけ、再考を迫る政治哲学であり、それゆえに注目を集めているのだと考えられる。
実際、『投票の倫理学』における「良い投票をするための努力ができるか」というブレナンの主張は、現代の私たちに訴えるところが大きい。
たとえばアメリカでは今年1月、トランプ大統領の再選によって移民やLGBTQの人びとの権利が制約されることになった。つまり投票は現実として、意図せず他者の福利を大きく損なう可能性がある。
ブレナンが主張するように、候補者に対する十分な知識や理解がないまま投票することは、不道徳な行為にほかならない。子どもを産むことを決めた親が子育てについて真剣に考えず、育児を放棄することが許されないように、私たちも選挙に行く以上、投票について真剣に考える道徳的責任が課せられているのだ。
ブレナンは徹底して「投票者の倫理」を問う。だが読者のなかには、むしろ選挙に出馬する「候補者の倫理」を問うべきではないか、と考える人もいるだろう。たとえば、2024年の東京都知事選挙では泡沫候補が乱立し、立候補の条件に疑問符がつく出来事が見られた。
しかし民主主義の理念に照らせば、誰もが立候補できる自由はやはり保障されるべきである。いくら思想的な偏りがあろうと、政治に必要な知識・見識・能力が不足していようと、被選挙権の制約には慎重であるべきだ。
現状の日本社会では、行政や司法の職に就く者には膨大な知識、能力を証明する試験など厳しいハードルが課される。だからこそ、立法を担う議員には「誰もがなれる」という寛容さが不可欠である。
民主主義社会において重要なのは、立候補者に厳しい制限を課すことではない。むしろ、有権者が立候補者のなかから「愚か者」を見極め、粛々と落選させることである。熟慮のうえでの投票が大事だという意味で、ブレナンの思想とも相通じる点ではないだろうか。
リベラリズムと自由の擁護
ブレナンの思想は、有権者に高い倫理を求める点で、「選民思想」「上から目線」に映るかもしれない。しかし彼の主張の根底にあるのは、「どのような人びとでも自由に生きられる社会が最も望ましい」というリベラリズム的な理想主義である。事実、ブレナンは『投票の倫理学』においてリベラリズムを強く擁護し、個々人の自由な生き方を肯定している。
社会には、政治や学問を得意としない人もおり、それらとは異なる分野に価値を見出す人もいる。ブレナンは、そうした人びとの生き方を否定せず、むしろ別の分野でより大きな貢献ができるのであれば、あえて投票という負担を課す必要はない、と論じている。
なぜなら、市民は投票や政治活動以外にもさまざまな方法で社会に貢献できるからだ。たとえば、政治について考えるのが苦手な人が、ボランティアを通じて多くの人の役に立てるのであれば、その時間をなげうってまで投票に行く必要はないと言えるかもしれない。
ただし、多様な人びとが安心して穏やかに生きられる社会の実現には、やはり選挙を通じた確固とした社会の仕組みが必要である。ブレナンが『投票の倫理学』で、社会に害をもたらす者や最低ラインを下回る有権者は「足切り」する必要があるとまで主張するのは、何よりも社会の安定性を意識してのことである。
他方、前述したように『投票の倫理学』時点のブレナンの限界は、彼が想定する個人が、投票の資格がないと自覚して自ら棄権し、社会のために適切な投票行動をとろうとする善良な人びとだという楽観にある。
現代のSNS空間を見渡せば、ルサンチマン(恨み・嫉妬)やシャーデンフロイデ(他人の不幸は蜜の味)の感情を露わにし、気に入らない候補者の欠点を探して追い落とそうとする人びとや、売名や金儲けの私的な動機から過激な言動で注目を集める候補者を支持する人びとが少なくない。
「劇薬」を求める有権者に社会の安定性を説いても、「良い投票」や「投票の棄権」は期待できない。この悲観こそ、ブレナンが『アゲインスト・デモクラシー』で民主主義の否定へと転向してしまった理由であり、私たちが向き合うべき課題でもある。
SNSが選挙結果を左右するほどの影響力を持つ今日、ブレナンが提起した「道徳的な有権者」としての責任を、私たちはあらためて考える必要がある。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月21日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること




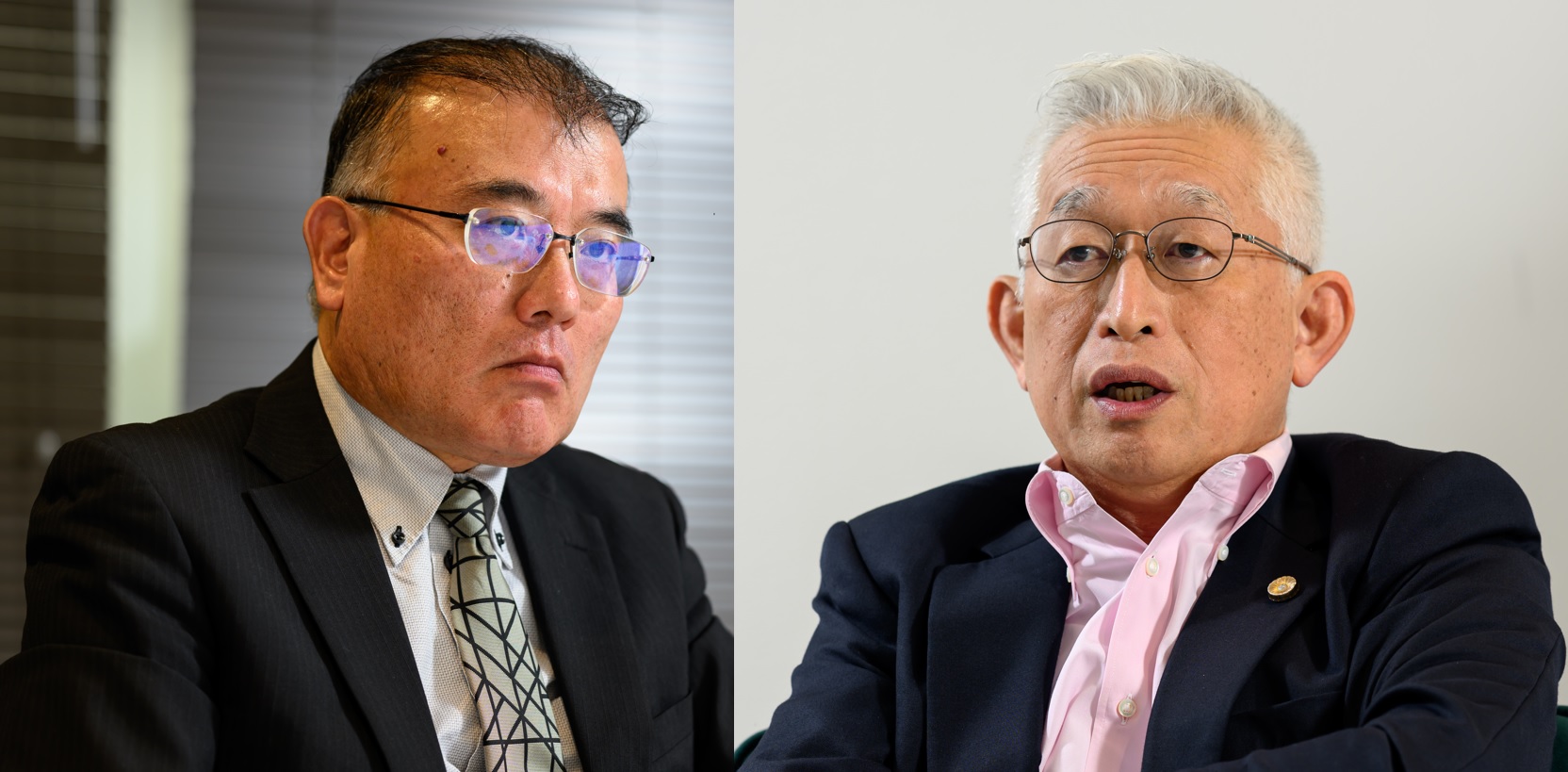


.jpg)
