「仕事は喜び」というデンマークの労働観 我慢して働く日本人と何が違うのか?

5年連続でビジネス効率性世界一を誇るデンマーク。その背景には、「仕事は喜びであり、楽しむもの」という独自の価値観が存在する。一方、仕事の裁量権が限られ、我慢が常態化しやすい日本の職場環境との間には、大きな隔たりが見られる。この対照的な仕事観は、一体どのような要因によって生み出されたのだろうか。
組織開発専門家の勅使川原真衣氏と、デンマーク文化研究家の針貝有佳氏による対談から、デンマークに学ぶべき労働観について探っていく。
※本稿は、『Voice』2025年6月号より抜粋・編集した内容をお届けします。
「仕事は喜び」というデンマークの労働観とその背景
【勅使川原】針貝さんの新著『デンマーク人はなぜ会議より3分の雑談を大切にするのか』、一気に読んでしまいました。私はかねてより「一人ひとりが発揮しやすい能力をもち寄って仕事をするべき」と主張してきましたが、その一つの突破口になりうるのが「雑談」なのだと感じました。同年代で同じ問題意識をおもちの方がいることは、とても心強いです。
【針貝】「心強い」のは私も同じで、勝手ながら勅使川原さんには仲間のような感覚を抱いてきたんです(笑)。
【勅使川原】本書を読むと、お互いの能力をもち寄るためにコミュニケーションするとは具体的にどういうことなのかが、明確に理解できます。ただ、雑談ってやろうと心がけても、すぐにできるものではないと思うんです。
本書では「ラク」という言葉が随所で出てきますよね。それはおそらく、私が講演でよく使う「自然体」という言葉と同じ意味だと解釈しました。お互いに強みを発揮し合えば、「ラク」「自然体」でいられて、組織としてもパフォーマンスが上がる。ただ日本では、とくに能力主義の考え方によって「ラク」するのはネガティブに受け止められます。
【針貝】つねに頑張っていなきゃいけない、という空気がありますよね。
【勅使川原】労働観や人間観のベースに「歯を食いしばる」という考え方があるのではないでしょうか。一方でデンマーク人は、「存在をそのまま承認する」という前提から仕事観がかたちづくられている。もちろん善し悪しはあるにせよ、この出発点の差が日本人とデンマーク人の仕事観の違いに繋がっていると感じています。
【針貝】私も勅使川原さんの新著『学歴社会は誰のため』を読ませていただきましたが、「そうだよね」と頷かされるばかりでした。私と勅使川原さんは、根本の問題意識がとても近いですよね。仕事とは絶対的な個人の能力によって進められるものではなく、タスクや人との組み合わせによって成り立つという考え方です。
勅使川原さんが昨年に発表された『働くということ――「能力主義」を超えて』で印象的だったのは、「レゴブロック」の喩えでした。仕事とは「組み合わせ」でつくるものであって、一人ひとりに完璧なレゴブロックになれと言っても、それは無理なんですよね。
【勅使川原】針貝さんは、日本人とデンマーク人の労働観の違いをどう解釈されているのでしょうか。
【針貝】デンマークでは基本的に、「仕事は喜びであり、楽しむもの」と考えられています。もちろんさまざまな理由で本来は望んでいない職業に就いている方もいますが、それでも仕事を通じて社会に貢献することが喜びだ、という共通の認識がある。社会の構成員である限り、何らかのかたちでパブリックに貢献するのが望ましいという考え方ですね。
【勅使川原】エミール・デュルケームが提唱した「社会分業論」を地で行くようなイメージでしょうか。
【針貝】そうですね。もちろん職種によって給料の多寡はありますが、ステータス的な上下関係はありません。ゴミの清掃も尊くて社会に必要な仕事の一つとして理解されている。「やってくれる人がいてありがたい」という認識のもと、それぞれの仕事がリスペクトされています。
【勅使川原】職業に貴賤なし、ですね。翻って日本では、北欧諸国と比べると社会保障が手厚くないせいか、なるべく稼がないと満足に生きられないという考えが主流ですから、余裕をもちにくい。社会制度の違いも日本とデンマークそれぞれの労働観に影響している気がします。
【針貝】誰だって予想外の事態に見舞われることはあり得ます。そのとき、デンマークでは医療費の原則無料や手厚い失業保険制度が用意されている安心感があります。日本よりも解雇規制が緩いですが、それは転職しやすい社会という裏返しなので、国民の不安感に繋がっている印象はありませんね。
【勅使川原】ご説明いただいた社会保障の心理的安全性に加えて、ジョブディスクリプション(職務内容やスキルなどを記述した職務記述書)が明確で成果もしっかり定義されているからこそ、ワークシェアリング(雇用を分け合うこと)や分業が成り立つのでしょう。
デンマークでも学歴が重視される?
【針貝】勅使川原さんは著書『学歴社会は誰のため』で「日本は仕事上の評価基準が曖昧」と指摘されています。日本では仕事をするうえで「絶対的な能力」があると思われていて、しかもその優秀さの基準は「頑張れること」「困難を乗り越えられること」など非常に曖昧です。
【勅使川原】あとは「うまくやれる」とか(苦笑)。
【針貝】私にとってはじつに印象的な問題提起でした。デンマークでは基本的に「その人は何に関心があるのか」「何をめざしているのか」が問われます。雇用される側の意識も日本とは異なり、どの会社に就職するかよりも「自分のプロフェッショナルはこれだから」という意識で会社を選ぶ。
【勅使川原】まさに「職に就く」意識ですね。ちなみに、デンマークでも職務経歴書に学歴は書くのでしょうか。
【針貝】意外に思われるかもしれませんが、デンマークでも学歴は評価の一つとして見られています。大手企業の採用では学歴による足切りが存在する。企業側が公表しているわけではありませんが、応募が大量であれば、一つひとつの職務経歴書を丁寧に見るのはどうしても物理的に難しいですから。
ただし、大学の知名度と同じくらい、その人が何を学んだのかという「専攻」が希望職種に合っているのかが重視されますね。
また学歴に関係なく、横の繋がりで次の仕事が決まることも少なくありません。たとえば、ある会社に勤めていた人が「将来的にこういう仕事がしたい」と考えていたら、周囲が「それならあの会社の人を紹介するよ」と口添えしてくれて、学歴に関係なく大企業に就職できるケースもあります。ただ、日本でもキャリアの半ばになると学歴はそれほど関係なくなるので、デンマークとの違いはあまりないかもしれませんね。
ケアする組織、我慢する組織
【針貝】デンマークでは関心分野が職務に結び付いているので、本人が希望しない仕事をさせられることは基本的にありません。その代わり、人気で志望者があふれる職種で、その人が会社にフィットしていなければ解雇されることも珍しくない。ある意味ではドライで厳しい社会だと言えます。
一方、解雇まではさせられない日本では被雇用者が守られています。それでも、日本ではビジネスパーソンが仕事を自分で決められる裁量が少なく、多くの方が「我慢」させられているように思えて、その点はとても気がかりです。
【勅使川原】笑顔で「ラク」に仕事をしていたら、「もっと仕事できそうだね」と次のハードルを用意されてしまうことも......。つまり、余白があってもそれを外に見せないほうが都合がよい社会だと言えます。でも、それでいいのか? という話です。
【針貝】デンマーク社会は「私も楽しむからあなたも楽しんで」という考え方ですが、私が日本にいたときに感じたのは「私も頑張るから、あなたも多少無理して頑張ってよ」という空気でした。
【勅使川原】そうなんです! そしてその源流の一つが学校教育だというのが私の考えです。学校教育の時点で「頑張り」という「態度・姿勢」が教師から評価されるから、燃え尽きる寸前くらいまで働かないといけないという発想になる。
【針貝】もちろんデンマークでも、長い時間頑張って働く人はいます。でもそれは、自分が心から望んでやっている人たちだけ。そんな人たちと、仕事はあくまでも人生の一部にすぎないと考えて「4時に帰る」人たちが共存し、お互いに尊重し合っている社会です。
【勅使川原】ちなみに、デンマークにもいわゆる「自己責任論」を掲げるタイプの人はいるんですか。
【針貝】いますよ。給料の高い仕事でガンガン働いている人に多い印象ですね。デンマークでも、そもそも仕事を通じて社会に貢献する意識をもちにくい人がいます。彼ら彼女らに対して、「自分たちが稼いだお金が、やる気が乏しい人たちに渡るのは納得できない」という意見は公にもある。移民の問題も絡むなど複雑で、デンマークでも社会の分断が存在するのは事実です。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月21日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること



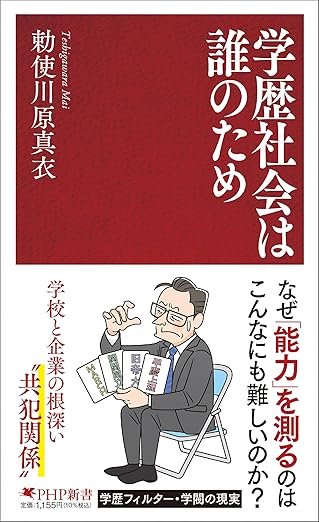
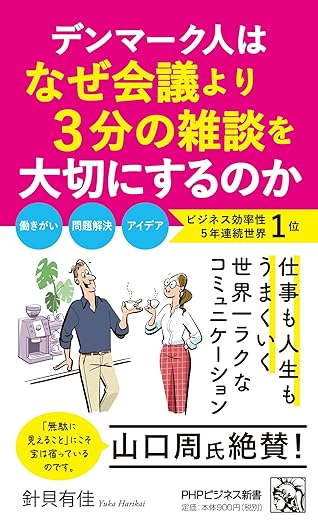
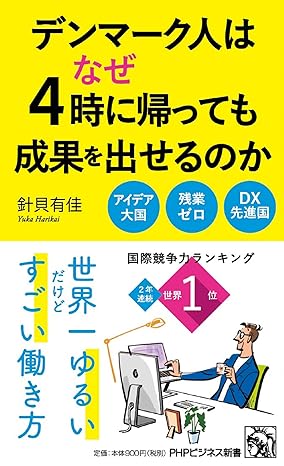






.jpg)
