もし不老不死が実現したら? 禅僧と神父が憂慮する「認知症の苦しみ」

人は死んだらどうなるか。不老不死が実現したらどうなるのか。延命治療や安楽死の是非が語られる現在、生老病死に加えて新たな「第五の苦しみ」が生まれている、という。人間の生きる苦悩と解放をめぐり、禅僧と神父が語り合った。
煉獄と四十九日
【片柳】キリスト教の死後についての説明で理解しにくいのは、世界の終わりに行われる「最後の審判」と、個人の死の直後に行われる「私審判」(ししんぱん)の関係です。死の直後に、魂の行き先が天国か地獄、ないし煉獄かを決める「私審判」があり、世界の終わりにもう一度、すべての魂についての「最後の審判」があります。
ただ、2回も審判があるというのはおかしいので、1回と考えたらいいと教わりました。なぜなら、死後の世界は時間から解放された世界で、前後の関係がないからです。
天国のことを「神の国」と呼ぶこともありますが、この「神の国」が愛の国であること。神は、正しい人より、罪びとを招く方であることを知らせるためにやってきたのがイエス・キリストということになります。罪びとというのは、罪の自覚があり、罪の苦しみからの救いを願っている人ということです。
【横田】なるほど。
【片柳】弟子たちが自分を裏切っても、イエスは決して彼らを見捨てない。神は罪びとを見捨てないということを、弟子たちはイエスの生き方から学ぶことになりました。
【横田】「人が死んだらどうなるか」に関して、円覚寺の朝比奈宗源老師はよく「海」と「泡」にたとえておられました。「仏の命とは、大きな海のようなものだ。私たち個別の存在は、その海に浮かんだ小さな泡のようなものである」と。
泡はやがて消えるけれども、泡を生み出す元の海は決してなくならない。一度は消えた泡も、どこかで再び新しい泡として浮かび上がる。すべては移り変わるものであり、海という存在自体は不生不滅という考え方です。
自分は独立した存在ではなく、現象にすぎず、根っこを探せば宇宙の大きな命と一つにつながっている。この真理を坐禅によって体で感得するのが、禅の修行といえるでしょう。
【片柳】聖書では、死後の世界は天国か地獄かの二者択一です。しかし、カトリックには両者のあいだにもう一つ、「煉獄」があります。「すぐには天国には入れないが、地獄に落ちるほどではない」という中間段階の場です。罪の清めの場という位置づけですが、私たちはその人が早く清められて天国に行けるよう犠牲や祈りを捧げる。
【横田】煉獄に、一定の期間はあるのでしょうか。
【片柳】死後の存在は時間から解放されているので、期間という考え方はありません。
【横田】ご承知のように、仏教には四十九日の儀式があります。人が亡くなったのちの四十九日、どこにいくのか定まらない状態で、もし生前の功徳が足りなかったならお坊さんがお経を読んでご供養する、という期間です。
【片柳】煉獄の存在をめぐっては、キリスト教のなかでも論争があり、プロテスタントでは煉獄の存在を認めません。
カトリックのなかでも、ベネディクト16世が教皇になる前、煉獄の必要性について問われたことがあります。ベネディクト16世の答えは、亡くなった人のために祈りたいという人々の気持ちを受け止めるために煉獄は必要、というもので、「なるほど」と思いましたね。大切なのは、残された人たちの気持ちなのです。
たしかにプロテスタント側からすればいい加減な話で、かつてルターが批判した贖宥状(免罪符)も、お金を払って購入すれば煉獄の魂が救われる、というものでした。お寺や教会を建てるためにお金を払うのは善で、その善行が死後の世界に反映されるという考え方は、仏教でもカトリックでも変わらないのでしょう。
生老病死+第五の苦しみ
【横田】仮に将来、生命医学の進歩で不老不死のようなことが実現した場合、世の中はどうなるのでしょう。iPS細胞(人工的に培養・作成された多能性幹細胞)のような技術の進歩によって、不治の病に苦しむ人が救われるのは素晴らしいと思う半面、永遠に死ねなくなったらそれはそれで恐ろしいことではないか、という危惧もあります。
【片柳】おっしゃるように、これからの時代は死の苦しみとともに、「死ねないことの苦しみ」が生じるかもしれません。
ちなみに、キリスト教でいう「永遠の命」とは、とても長い時間という意味ではありません。天国で何億年も暮らしたとして毎日、何をするのか。暇じゃないですか(笑)。キリスト教の考え方では、永遠はむしろ不変の状態というか、何があっても決して変わらない愛で神と結ばれている状態を永遠と呼ぶわけです。
【横田】お釈迦様は人間がもつ4つの苦しみとして、生まれて、老いて、病を得て、死ぬことを挙げられました。しかしこの生老病死に加え、現代ではもう一つ「認知症」という第五の苦しみがあります。健康長寿に伴う悩みは、お釈迦様の時代にはなかったものでしょう。
【片柳】皆、いつまでも自分は健康で長生きできると思っていますが、たとえ体は丈夫でも、認知症に罹る確率は決して低くない。
なるほどと思ったのは、介護つきの修道院で働く友人の神父が、老後をマラソンの最後にたとえた話です。マラソンでは走る距離が長くなるほど、最後の苦しい区間も長い。高齢化に伴う苦しみも似たようなもので、人生が長くなるにつれて、最後の苦しみも期間も1kmが3km、5kmと伸びるというのです。
【横田】自ら死を選ぶ安楽死や、延命治療を拒む尊厳死の話題がしばしば語られるのも、無理のないことだと思いますね。映画『PLAN75』のように、政府が75歳以上に死を選択させる社会が夢物語に映らない恐ろしさがあります。カトリックでは、延命治療を拒否できるのでしょうか。
【片柳】延命治療を本人が望むかどうか、あらかじめ確認することは行われています。
【横田】しかし、安楽死は違いますね。
【片柳】はい。神から賜わった命は最後まで全うする、ということなので、安楽死は認めていません。ただし、どこまでが延命治療の拒否で、どこからが安楽死かの線引きはたいへん難しい。
笑い話で以前、治療中の神父が医師に「延命治療は要りません」と申し出たところ、「いまあなたが受けているのが延命治療です。やめてもいいですか?」といわれ、驚いて「続けてください」と(笑)。
【横田】たしかに、点滴すら延命治療といえなくもありませんからね。
「生きていたい」と思うのは、人間の基本的な欲求であります。これを否定することはできません。しかし、死ねなくなるのも苦痛であると思います。あらかじめ死生観をもっておくことは今後ますます必要になるでしょう。
光と花
【片柳】他方で前回、お話にあった鈴木秀子シスターのように、90歳を超えてもなお聡明極まる方がいます。興味深いのは、あの方が語られるご自分の臨死体験です。
【横田】人は死に際して「光に包まれる」という。
【片柳】先日、お会いしたときは「光に包まれたとき、体もすっかり元気になった気がする」とおっしゃっていました。鈴木さんのお話は、カトリックの、体も新しくなるという「復活」の教えと整合性があり、納得のいくところがあります。
トルストイの小説『イワン・イリッチの死』の描写でも、自分が想像していたのは闇に落ちて消えていくような最期だったが、そのような死は存在せず、待っていたのは「光」だったという。
【横田】鈴木さんはまた、どこからか声が聞こえてきて「あなたがこの世でなすべきは『愛すること』と『知ること』だ」と。まさに仏教の「慈悲」と「智恵」と相似するもので、私はこのお話がとても好きなんです。
【片柳】希望を与える死生観ですよね。
【横田】希望と伺って思い出したのは、柳宗悦(宗教哲学者、思想家)の次の句です。
「吉野山 ころびても又 花の中」
私たちがどれほど悲しみ、苦痛にもだえようと、それは「花の中」すなわち御仏の御手の只中にある。絶対的な安心感のもとで、やがて光の中で解放されるという希望があれば、たとえ不安に苛まれたとしてもそれらを受け止め、生きていけるような気がするのです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月23日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)





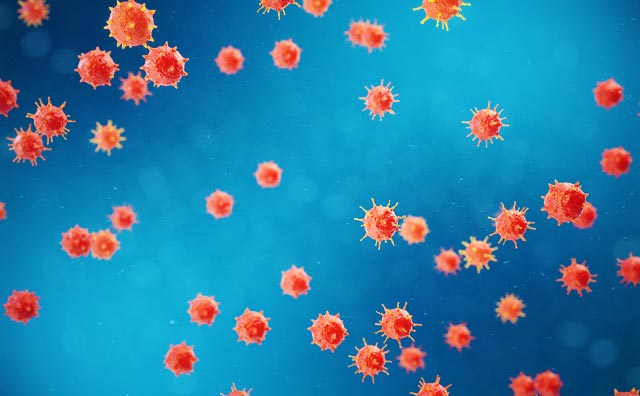

.jpg)
