「宗教は自分を納得させるための物語」 カミュの『ペスト』に見る、宗教と疫病の意外な関係
2020年07月15日 公開
2024年12月16日 更新
 写真:遠藤宏
写真:遠藤宏
人類は危機に直面するたび、宗教に精神的拠り所を求めてきた。このたびの新型コロナ禍は宗教にどのような影響を及ぼすのか。国際基督教大学教授で『反知性主義』などの著書がある森本あんり氏が、アルベール・カミュの小説『ペスト』を基に、パンデミックと宗教の関係を読み解く。
※本稿は月刊誌『Voice』2020年8月号、森本あんり氏の「民主社会の正統性が問われている」より一部抜粋・編集したものです。
聞き手:Voice編集部(中西史也)
信徒の多くは信仰で感染を防げるとは考えない
――新型コロナウイルス蔓延の影響で世界では礼拝や巡礼が見送られる一方、韓国のキリスト教系団体でクラスター(集団感染)が発生するなど、感染拡大の温床となるケースもありました。今回のコロナ禍と宗教との関係性をどう見ますか。
【森本】まず宗教を生活感覚から説明すると、二つの側面があるように思います。
一つは、思想的な世界観の形成です。いわば、宗教が身の回りの世界を説明する原理になること。もう一つは身体的な表現行動で、これは信者の日常生活の習慣を形成します。
具体的には礼拝などに集まることですが、素朴な体感としては宗教的な意味よりも「信仰を同じくする人びとに会いに行く」という社会的な機能のほうが強い。
要するに、クラブ活動のようなものでしょうか。仲間と一緒に話したり、歌ったり、祈ったりしたい。そこに今回のコロナ禍が起きたわけで、そうした活動ができなくなったことが信徒にとっていちばん辛いところでしょう。
一部のイスラム地域や韓国では、信じていれば神が護ってくれるから感染しない、と主張する指導者もいました。しかしそれは、ごく限定的な逸脱です。
大多数の信徒は、信仰で感染を防げるとは考えないし、感染拡大阻止のために実際的な行動指針を出した医者の信徒グループもいます。WHO(世界保健機関)も宗教集団の存在の大きさを理解しているので、専門家チームに宗教指導者を入れて諸宗教へのガイドラインを提示しました。
――有史以来、人類は感染症のパンデミック(世界的大流行)に向き合ってきましたね。
【森本】アルベール・カミュの小説『ペスト』には、ペストの蔓延に直面する人びとの姿が描かれています。カミュはペストの流行そのものを経験して書いたわけではありませんが、その描写があまりにいまの状況とそっくりで、私も今回あらためて読んで驚きました。
ロックダウン(都市封鎖)で人びとの暮らしがどう変わるか、商取引や旅行の計画など、日常生活のすべてがなぎ倒される様子がリアリティを帯びて描かれている。
『ペスト』が与えてくれる示唆はそれだけではありません。疫病は、一方で地位や階級にかかわらず人びとを襲う平等さをもつものの、他方で貧しい家庭は食べるのにも窮し、裕福な者は何一つ不自由しない、という平時の不平等を顕在化させてしまう。
現在われわれは「オンライン」化の味気なさを嘆きますが、当時はそれが「電報」化だったし、新型コロナで自宅に缶詰になることを日本では「巣ごもり」と言いますが、カミュは「自宅への流刑」と表現している。
他にも、混乱に乗じて金儲けをたくらむ男が現れたり、やがてゆっくりと感染症が収束に向かったりする様などは、現下の状況と酷似していて震撼させられます。
『ペスト』が示す、「手当をする」意義
――『ペスト』ではイエズス会の高名な神父が登場するなど、宗教との関わりも描かれています。
【森本】はい、小説の行間に滲み出ている最大の問いは宗教でしょう。カミュ自身、この小説は自身の作品のなかで「最も反キリスト教的」だと語っていたようですが、私にはもう少し違う問いかけがあるように思えます。
――どういうことでしょうか。
【森本】一つは、アルジェリア出身のレジスタンスだったカミュらしい反知性主義の精神です。彼が反発しているのは、フランスのカトリック教会という巨大な権力システムで、宗教や信仰そのものではありません。
『ペスト』に登場する神父を、主人公のリウーはこう評しています。「彼は書斎の人間だから、人の死ぬところを十分見たことがない。だから真理の名において語ったりする。
でも、どんなつまらない田舎の司祭でも、ちゃんと教区の人びとに接して、臨終の人間の息の音を聞いたことのあるものなら、悲惨のすぐれた効能とか語らないで、まず手当をする」。
つまり、インテリの権威ある神父が垂れるもっともなご高説などには何の興味もないが、田舎の司祭が人びとの暮らしのなかで日々果たしている地道な役割には、一種の共感をもっているのです。
もう一つ挙げるならば、リウーの台詞の「手当をする」という言葉にも表れていますが、一種のアクティヴィズムです。われわれは危機に陥ると、つい大仰で神学的な問いを発してしまいます。「神はどこにいるのだ」「宗教の意義は何か」という具合に。
でも、そんな高尚な議論はどうでもいいのだ、とリウーは語りかけているのではないか。私はそう捉えました。
「僕が憎んでいるのは死と不幸です」と彼は言う。信仰を抱いているか否かなど、実際のところどうでもいい。目の前で苦しむ人のために何かをしたい。
カミュ自身がそう思索していたからこそ、「神は信じないが、聖者になりたい」という献身的な奉仕者を描いたのです。
こういうアクティヴィズムは、キリスト教の歴史のなかで幾度となく生まれてきました。
ヒットラー暗殺を計画して逮捕・処刑されたドイツの神学者ディートリヒ・ボンヘッファーもそうですし、そもそも新約聖書のイエス自身がそうでした。
生まれつき盲目だった乞食を見て、弟子たちが「あの人が盲目なのは誰のせいなのか」と尋ねると、イエスは問いに答えずに、その人を癒やします。
弟子たちはそこにいて苦しんでいる人を、まるで神学の教材のように使っている。まったく無関心な傍観者なのです。
イエスはそういう知的問答を拒否して、その人を「手当した」わけです。カミュの言う田舎司祭と同じです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月23日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)



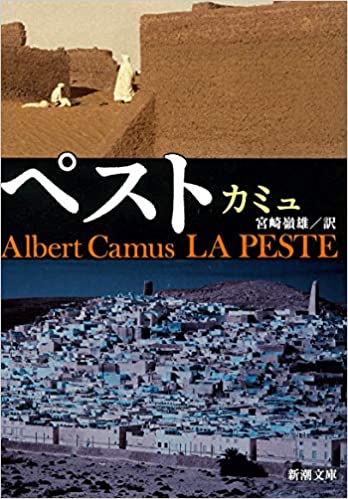





.jpg)
