「稲作が普及するのに800年?」東の縄文人が弥生文化を嫌った理由

考古学的に弥生時代のはじまりが数百年遡ったことで、北部九州から始まる稲作の伝播も、想像以上に長い時間がかかっていたことがわかってきた。東の縄文人はなぜ稲作を受け入れることに躊躇したのか?縄文人のメンタリティーから考えれば、その答えが見えてくる。
※本稿は、関裕二著『「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける』(PHP文庫)を一部抜粋・編集したものです。
弥生文化の普及は「バケツリレー」
炭素14年代法によって、弥生時代の始まりが数百年古くなった。この結果、稲作の急速な普及という前提は、崩れ去った。征服者が押し寄せてきたのではなく、「バケツリレー」という言葉が使われるようになった。
そして逆になぜ稲作は、一度東への進出を停滞させたのかという謎が湧きあがってきたのである。日本の「農耕社会化」は「弥生化」と呼ぶ。小林青樹は、弥生化に時間がかかった理由を目に見えない「縄文の壁」があって、文化的攻防が勃発していたからだと指摘している(『歴博フォーラム弥生時代はどう変わるか』学生社)
どういうことか、説明しておこう――小林青樹は、縄文人が壁を取り払い、弥生人になるためには大きな決断が必要であり、また水田稲作を始めるには共同作業をするのだから、集団の同意がなければならなかったと指摘する。
また新しい社会の枠組みを構築する必要もあったと、まず前置きをする。その上で、「縄文の壁」は、六つの地域に存在したという。1.南島の壁、2.九州の壁、3.中国地方と四国の壁、4.中部の壁、5.東日本の壁、6.北海道の壁だ。このうち、南島と北海道は弥生時代には突破できなかった。
北部九州でも水田、環濠集落、金属器、弥生土器すべてがそろうまで約200年を要している。弥生時代前期の関門海峡の東側では、日常生活でいまだに縄文系の道具類を使用していた。
また板付遺跡を起点にして、関東に弥生文化が到達するまで、400〜500年、最初の水田が北部九州にできてからだと、約700〜800年かかっている。
したがって「弥生時代」と一つに括ってしまっているが、その弥生時代の2/3の時間は、縄文的な暮らしを守ろうとする人たちと、新しい生活を始めた人たちが共存していた時期だったことになる。
この間、兵庫県神戸市付近(新方遺跡、明石駅の北側)では弥生前期に、無理やり近畿側に越えようとした「弥生人」と在地民の間に小競り合いがあったようだ。縄文系の人骨が出土していて、六体の人骨のうち、五体に石鏃が伴っていたのだ。十数本の矢を受けていた。
近畿地方が弥生化を始めたのは紀元前600年ごろだが、100年ほど縄文と弥生の棲み分けが起こり、なかなか純粋な弥生化には至らなかった。石棒などの縄文系祭祀具が守られ、信仰や世界観を変えることができなかったようだ。春と秋に展開される弥生の祭りに縄文人はなじめなかったのだろうか。
そしてこのとき、近畿の人びとが始めたのは、銅鐸の祭祀で、石棒の分布域と初期の銅鐸の分布域がぴたりと重なるという(中村豊『季刊考古学第86号』雄山閣)。新来の大陸系の祭祀に縄文的な信仰が融合したわけである。
弥生の祭殿も縄文的?
さらに小林青樹は弥生時代の祭殿の一つ、独立棟持柱付建物(棟持柱は建物の側面にやや離れ、棟を支える柱)は、東北や北陸の縄文時代後半の建物が起源ではないかと推理する。
筋違遺跡(三重県松阪市)で弥生時代前期の最古級の独立棟持柱付建物が見つかっているが、ここは東日本との接点であり、古い銅鐸と弥生祭殿の出発点が東日本の西の接点だったところに注目している。この後、中部の壁を越えて、関東南部に弥生文化が押し寄せるのは紀元前300〜同200年のころだ。
神奈川県小田原市の中里遺跡に、関東で最初の灌漑水田が出現したのだ。それまでは中部関東の台地上で、移動性の高い陸稲を栽培していた。だから食料貯蔵のための貯蔵穴の数は少なく、あったとしても規模も小さい。
関東が容易に弥生文化を受け入れようとしなかった理由を、小林青樹は「再葬墓」というキーワードで説明する。再葬墓造営集団は、同じ祖をいただく小規模の集団で死者の遺体を腐らせ、数回にわたって処理し、白骨化させて埋葬し、先祖の仲間入りを果たす。
このとき歯や指骨をとりだし、穴をあけて身に着けた。祖先から続く絆と、集団の再葬墓を聖地と見なし、集って暮らしていたのだ。再葬墓の分布は東日本一帯で、西側の端は「中部の壁」とほぼ一致する。
これに対し、稲作民は地縁でつながり集住した。再葬墓造営集団の集合原理とは異なっている。だからこそ、東の再葬墓を造る人びとは弥生社会への変換は難しかったのだろうと推理したのだ。
逆にいえば、再葬墓造営と先祖祭祀を脱却することで、水田稲作社会への転換は可能だったのだ。しかも弥生時代の東日本の再葬墓は、西方の弥生文化が神聖視していた壺棺を用いるようになっていた。少しずつ、新しい文化に適応する準備は進められていたのだ。
それだけではない。関東最初の灌漑水田が見つかった中里遺跡には、瀬戸内系の土器が約5パーセント含まれていた。しかもその土器は特殊なものばかりで、神話を想起させるような絵画が描かれていた。これは祖神や農耕神に供えられていたと思われる。
さらに、中里遺跡には、独立棟持柱付建物が集落の中央に建てられ、いくつかの集団をまとめ上げるシンボルとなっていた。これもすでに述べたように、独立棟持柱付建物はもともと縄文時代のもので、西側から東に逆輸入された形になった。
そして、このあと関東に水田がもたらされるのだが、それは旧利根川から西側だった。ここに、次の縄文の壁が誕生したのである。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月07日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点
- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由

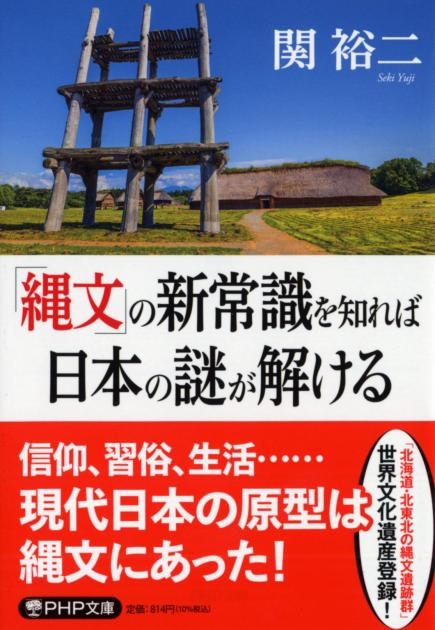


.jpg)
