生物学から男女の「性差」を考える 福岡伸一ハカセによる令和のジェンダー論
2020年07月23日 公開
2024年12月16日 更新
メスから強制的に子を託されるコオイムシのオス

コオイムシという小さな昆虫がいる。黒いカメムシみたいな虫で、沼や湖など、水辺に棲息する。鎌型の前脚を使って、他の虫や小さな貝、あるいはメダカみたいな小魚をつかまえて食べてしまう肉食性の昆虫である。
ところがその生活の様子を見ると、とても興味深いことがわかる。お父さんが、逃れられない義務として、必死に子どもを守っている。
人間の家庭なら、イクメンが増えたとはいえ、未だに赤ちゃんのお世話はもっぱらお母さんがしているけれど。コオイムシはそれがお父さんの仕事と決まっているのだ。強制的に。
人間のお父さんなら、ほうっておくと、すぐにちょっとものを買いに行くだとか、友だちと飲み会があるとか、仕事が忙しいとかいって、子育てから逃げてしまいがちである。たぶんコオイムシのお父さんも「できれば子守りなんて面倒なことはしたくないなあ」と思っているはずなのだ。
そこで、コオイムシのお母さんは一計を案じた。お父さんが子育てから絶対に逃げられないようにしてしまったのである。それはこういう方法だった。コオイムシのメスはオスと交尾したあと、卵をたくさん生む。
白い米粒のような卵である。卵を生むときメスはまずオスをつかまえる。そしてオスを押さえつけて、オスの背中に卵を生み付けてしまう。卵をオスの背中に貼り付けてしまうのだ。
このときの接着剤がすごいのである。接着剤は、メスが卵を生むときに、お尻から出す粘液性のタンパク質なのだが、これはおそらく史上最強の瞬間接着剤だ。
この接着剤を卵の一端に塗って、卵を順にオスの背中にしっかり貼り付けていく。ざっと50個くらいもある。オスにしてみたら、たぶん重いし、うっとうしいと思う。でも、いったん貼り付いたら、この接着剤は絶対とれない。背中を振ろうが、石に擦り付けようがびくともしない。
しかたがないので、オスのコオイムシは卵を背負ったまま、つまり、子どもたちを外敵から守りながらそのまま子守り生活をする。もし卵が、そのあたりの水草に生み付けられていたら、ザリガニとか魚がやってきてすぐに食べられてしまうかもしれないが、お父さんの背中に乗っかっていれば安全だ。
敵が来てもほいほい逃げてくれる。こうして数週間ほど卵を守ると、そのうち卵から子どものコオイムシがつぎつぎと生まれてくる。子どものコオイムシは小さいながらもう鎌型の前脚をもっているので、ここから先は、自分で小型のエサをつかまえてすぐに自活するようになる。
そうするとようやくお父さんの役割も終わり。「肩の荷を下ろす」とはまさにこういうこと。すると不思議なことに、このころになると、卵の抜け殻も自然とお父さんの背中から外れるようになる。そしてまた季節が来るとオスはメスに卵を背負わされてしまうのだ。
なので、郊外の田んぼや小川のほとりを注意深く観察すると、卵をたくさん背負ったコオイムシのオスがちょろちょろしているのを見つけることができる。
その姿はユーモラスですらある。背中に白い小荷物をいっぱい背負って、あせあせしている感じである。これが「コオイムシ(子負い虫)」の名の由来だ。地方によっては、子を背負う姿をカエルに見立てて、ケロ、と愛称をつけられているところもある。
さらに驚くことに、メスがオスの背中に産み付けた卵は、かならずしも交尾をしたパートナーのものではない場合があるのだ。
メスは、あたりをうろついている手近なオスをつかまえて卵を貼り付けてしまう。だから、オスは自分の子どもではない子ども(卵)を背負ってあくせくしている場合も多いはず。もちろんオスの側にそれを確かめるすべはなく、拒否する余地もない。
コオイムシのメスにとってオスは子守役でしかない。しかも一方的な強制力をもって有無をいわせない。オスはメスにとって徹底的にツールなのである。
ただし、オスは、もうひとつだけ役割がある。交尾のパートナーとしての役割だ。
つまり、オスには、遺伝子の使い走りとしての役割が残されている。しかし、いつその役割が振られるか、これまたメスの胸先三寸で決まるのである。
単為生殖のアリマキ的人生
アリマキ(アブラムシ)という小さな生物がいる。紡錘形のゴマ粒ほどの大きさで、透き通るような緑色をしている。虫メガネで見ると糸のような細い脚が6本ある。つまり、アリマキは昆虫の一種だ。
アリマキは季節のよい期間は、単為生殖で増殖する。単為生殖とは、メスの個体が、オスの力をまったく借りることなく、どんどん子どもを生むこと。生まれてくる子どももすべてメス。自分のコピーを自分の体内でつくりだす。つまり、クローンがつぎつぎと生まれてくるのだ。
母の身体の中にいる娘の身体の中に、すでに次世代の娘(母から見ると孫)が育っている。まるでマトリョーシカ人形である。こうしてアリマキは爆発的に増殖する。
植物の茎を見ると、無数のアリマキが貼り付いてじっと汁を吸って生きている。この群れはだいたいにおいてクローン集団といってよい。どれも同じ形態だが、大小さまざまな個体がいる。これは世代の違いである。
メスがメスを生み出すクローン生産のシステムは非常に効率がよい。オスなんて必要ない。どんどん増殖することが可能だ。しかし、ひとつだけ欠点がある。遺伝子の構成が、どの個体も同じなので、変化を生み出せないことである。
つまり、多様性をつくりだすことができない。縦糸だけの布は弱い。環境はどのように移り変わるかわからないので、生物にとっては増えることだけでなく(縦糸をつなぐだけでなく)、縦糸と縦糸の情報を交換できるようなしくみ、つまり「横糸」が必要となる。
アリマキはそのための知恵をちゃんと備えている。ここが生物のすごいところだ。夏が終わり、秋風が吹き、朝晩の気温が急に下がるころ、すなわち冬の予感を覚えると、メスは娘でなく、息子をつくり出すのだ。
つまりオスを生む。生殖細胞の内部で遺伝子の配分を変化させ、クローンとしてのメスではなく、自分の遺伝子を半分しかもたない、オスの個体を生産する。
この個体にはメスにはない特徴がある。見るからにしょぼいのだ。メスほどまるまる太っていない。むしろ、やせ細っている。そして翅がある。軽い身体で遠くに飛んでいくためだ。
オスの役割はただひとつ、遺伝子の使い走りである。お母さんの遺伝子を別のメスのところに運ぶ。そこで遺伝子は混ぜ合わされ、シャフリングされる。
これによって新しい変化、新しい可能性が生み出される。これこそが、すべてのオスの本質的な役割といってよい。オスは遺伝子の運び屋として、メスがわざわざつくり出したものである。
それ以上のものでも、それ以下のものでもない。もう一度いおう。生物の基本形はあくまでメスであり、オスはツールにすぎない。アダムがイヴをつくったのではなく、イヴがアダムをつくったのだ。
遺伝子を運び終わると、この時点でアリマキのオスの役割は終わる。細い身体のまま冬を前に野たれ死ぬ。一方、遺伝子を受け取ったメスのほうは冬越しをして、来春、また新しい子どもたちを生む。
そして、ここがまた生物の巧みなところなのだが、こうして次の春、生まれてくる新しいアリマキの個体はまたすべてメスとなる。
メスからメスへの系譜は、太くて強い「縦糸」、生命の基本線をつくる。オスはこの太くて強い縦糸のあいだをときどき橋渡しする、細い「横糸」の役割を果たしているにすぎない。
本来、すべての生物はまずメスとして発生する。なにごともなければメスはメスの王道をまっすぐに進み、立派なメスとなる。このプロセスの中にあって、使い走りのくじを引いたものが、王道を逸れて困難な隘路へと導かれる。それがオスなのである。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月08日 00:05
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)

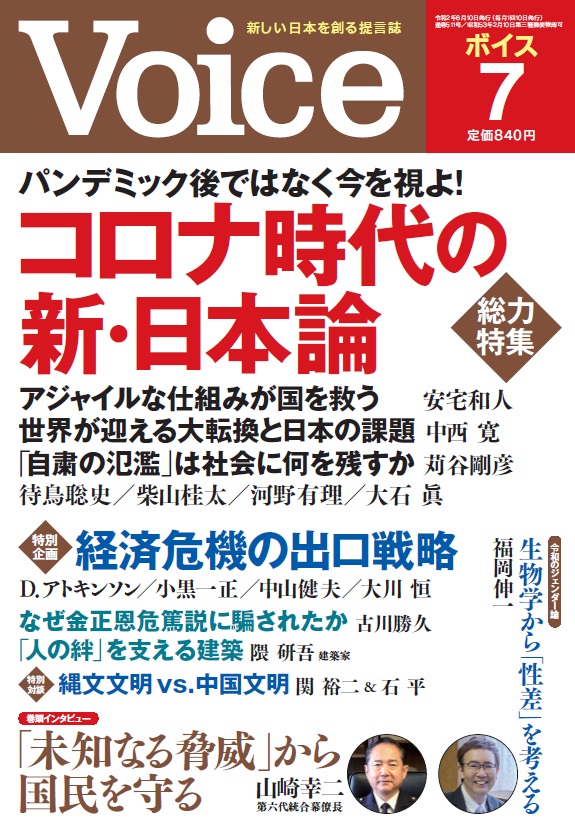


.jpg)
