第二次世界大戦から崩れ始める「戦争の姿」徐々に減少した主権国家間の紛争

第二次世界大戦以降、"戦争=主権国家同士の争い"の原則は崩れ、徐々に戦争の姿は変化し始めたという。東進ハイスクール講師の荒巻豊志氏による書籍『紛争から読む世界史』より解説する。
※本稿は、荒巻豊志著『紛争から読む世界史』(大和書房)から一部を抜粋・編集したものです。
複合戦争としての第二次世界大戦
第一次世界大戦終了からわずか20年で再び世界大戦が起きます。第一次世界大戦と異なり、日本が重要な関与国となったことでアジアにも大きな被害が生じます。
第二次世界大戦は第一次世界大戦で生じた流れに棹さす結果となりました。夜警国家から福祉国家へ、さらにイギリス、フランス、日本といった帝国主義国家の勢力が大きく減衰することで民族自決理念の普遍化は決定的となります。この第二次世界大戦は様々な性格が複合した戦争と評価されています。それをまとめてみましょう。
まず1つ目が民族絶滅戦争という性格です。ナチス=ドイツがこの戦争中に600万人にも及ぶユダヤ人虐殺(ホロコースト)を行なったことを知らない人はいないでしょう。このホロコーストを「戦争」と表現していいものか。
当事者の一方はナチス=ドイツという国家なのに対して、ユダヤ人は「国家」ではありません。ここが大事なところなのですが、戦争とは主権国家同士の争いであるという自明の理が崩れてきていると捉えてほしいのです。すぐ後で話しますが、こういった戦争のあり方を非対称戦争と表現します。
2つ目は帝国主義間戦争という性格です。イギリスやフランスが持っていた東南アジアの植民地を日本が奪おうとしていたことや、大戦末期にイギリスとソ連がバルカン半島分割の密約を結んでいたことがこれをあらわしています。
3つ目はイデオロギー戦争という性格です。当時、議会制民主主義、社会主義、ファシズムという3つの政治体制をめぐる対立があったわけですが、ファシズムを倒すために前二者が手を組んだという捉え方です。
難点はファシズムとは何かということが定式化されていないことです。社会主義もファシズムなのではないかといったような主張にも妥当性があるし、ファシズムといっても日本、ドイツ、イタリアで大きく異なっています。したがって、このイデオロギー戦争という物言いは戦勝国を正当化する考えだと思っています。
4つ目が民族解放戦争という性格です。2つ目の性格である帝国主義間戦争と対になっています。帝国主義間戦争が正しい戦争ではないとすると、この民族解放戦争は正しい戦争と捉えることができます。
だから、この性格を強調することは第二次世界大戦は正しい戦争だったという主張になります。日本が大東亜共栄圏を掲げてアジアの解放のために戦ったという主張は、日本にとって正義の戦争だったということです。
確かに、インドにおけるチャンドラ・ボースの運動や親ナチス=ドイツの立場を採ったアラブ人グループもあったけれど、東南アジア各地域で抗日運動が起きていた実態を考えると、これは支配下に置かれていた人々が評価すべきことでしょう。
ちなみに東南アジア各国の教科書で、日本が「アジア解放」のために戦ったと書かれているものは一冊もありません。
変わる戦争の姿
先に、第二次世界大戦と民族絶滅戦争の話をしました。このような戦争が非対称戦争ということですが、ユダヤ人に対するホロコーストを非対称戦争と表現するのはあまりにも極端な例かもしれません。なぜならユダヤ人は一切抵抗することなく虐殺されたのですから。
一般に非対称戦争といえばゲリラ戦のような正規軍と非正規軍との戦争を指します。たとえばベトナム戦争(1960年代から70年代)です。一方の当事者はアメリカ合衆国という国家なのに対して、もう一方は南ベトナム解放民族戦線というゲリラ軍でした。
1979年から始まるソ連のアフガニスタン出兵も、ソ連軍はアフガニスタンのゲリラ軍と戦っていました。類似語に低強度紛争という表現もあります。
2001年、アメリカの同時多発テロの後、ブッシュ大統領の下で始められたアフガニスタン紛争や、2003年のイラク戦争といった対テロ戦争(正式には「テロとのグローバル戦争」)も、国家対イスラーム組織アルカイダという非対称戦争の典型です。
20世紀後半から内戦も増えてきています。内戦の原因はやはり先に述べた国民国家の理念と現実との乖離です。非対称戦争や内戦は伝統的な国際法による枠組みでの処理が困難になります。従来、紛争に関する枠組みは戦時/平時、国際/国内に分けて考えられました。しかし、テロとの戦いは戦時なのか平時なのかわかりません。
また、内戦の主体は国家ではないため戦時国際法が適用できず、目もあてられないほどの惨劇が繰り広げられます。ロシアとウクライナの戦争の報道で、ロシアにワグネルと呼ばれる民間軍事会社があることを知った人がいるかと思います。この民間軍事会社も国軍ではないので残虐な行為を平気でやるといわれています。
まさに紛争といえば国家間戦争だった20世紀前半までと大きく異なり、国際法で対処しにくい事態が増加していることを「世界大戦から世界内戦へ」と表現したのが笠井潔です。『新・戦争論―「世界内戦」の時代』(言視舎)の中で、ドイツの思想家カール・シュミットの言葉を借りて、19世紀から21世紀に至る戦争のあり方を語っています。
2022年に始まり現在も続くロシアとウクライナの戦争ですが、この戦争が始まった当初、「21世紀になってまさか主権国家同士の戦争が、しかもヨーロッパで起こるとは」という声があがりました。これは、戦争のあり方が非対称戦争になっていく流れに逆行して帝国主義の時代に逆戻りしたように見えたのです。
価値の分配をめぐる政治
2020年のアメリカ合衆国の大統領選挙、バイデンvs.トランプの戦いで、「アメリカは内戦状態になるのではないか」という見立てを述べる論者がいました。さすがに内戦にはならなかったものの、両者の主張は違っても選挙が終わればノーサイドということにならなかったのは、2021年1月6日にトランプを支持する市民が起こした合衆国議会議事堂襲撃事件を見れば明らかでしょう。
何がそこまで国内を分断しているのかですが、これはアメリカだけでなく多くの国で同じような分断が生まれています。
アメリカでいえば妊娠中絶の是非はまさに国論を二分する議論になっています。世界各国を見ても、同性婚やLGBTQをめぐってさかんに議論されていることは共通しています。こうした議論を「価値の分配」といいます。
従来の政治は「富の分配」をめぐるものでしたが、これは妥協がつけやすいのに対して「価値の分配」は1か0かで妥協がしにくいものになっているため分断が起きやすいのです。
20世紀後半は世界規模で経済成長が続き、ある程度の豊かな社会が世界すべてではありませんが、いわゆる先進国で生じました。アメリカの政治学者ロナルド・イングルハートは「『脱物質主義的価値観』が政治の次元で重みを増す」と、すでに1977年の時点で主張していました。
『歴史の終わり』(三笠書房)で有名なアメリカの政治学者フランシス・フクヤマも『IDENTITY―尊厳の欲求と憤りの政治』(朝日新聞出版)の中で、トランプ現象やイギリスのブレグジット(EUからの離脱)の背景にあるものを分析して、経済合理性よりも敵と味方の単純な二文法で「敵だから倒す」といった感情が政治に持ちこまれることを示唆しています。
歴史認識をめぐる紛争も「価値の分配」の文脈で理解できます。現在を、そして未来をめぐって争うのではなく、過ぎ去ってしまった過去をめぐって争う、一見不毛な議論がどこの国でも展開されています。
それは21世紀における国民創造のために不可欠な物語をどうやって再構築すればいいのかということだけではなく、国民創造のために歴史が動員されることを拒否することも含めて妥協が困難な価値をめぐる争いになっているのです。
奴隷制度は19世紀に廃止されました。20世紀前半には女性参政権も実現しました。ところがこれらは人間を奴隷とそれ以外に分けること、男と女に分けることといった、人種主義的な発想に対する反省から起きたものではなく、単に経済的な利益や戦争遂行能力を高めるための要求から行なわれただけであり、「ブラック・ライヴズ・マター運動」の高揚やフェミニズムの運動が続いていることは、19世紀以来の国民国家建設の課題がまだ残されていることをあらわしています。
当然ながら「富の分配」をめぐる問題が解決したわけではありませんが、「価値の分配」が政治の大きな焦点になる中で国民国家としての同質性を保つことが難しくなっているのが現在といえるでしょう。
「富の分配」から「価値の分配」へ向かう大きな歴史の流れを確認するのに『リベラルとは何か―17世紀の自由主義から現代日本まで』(田中拓道/中公新書)、『アフター・リベラル―怒りと憎悪の政治』(吉田徹/講談社現代新書)はとても良い本です。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債




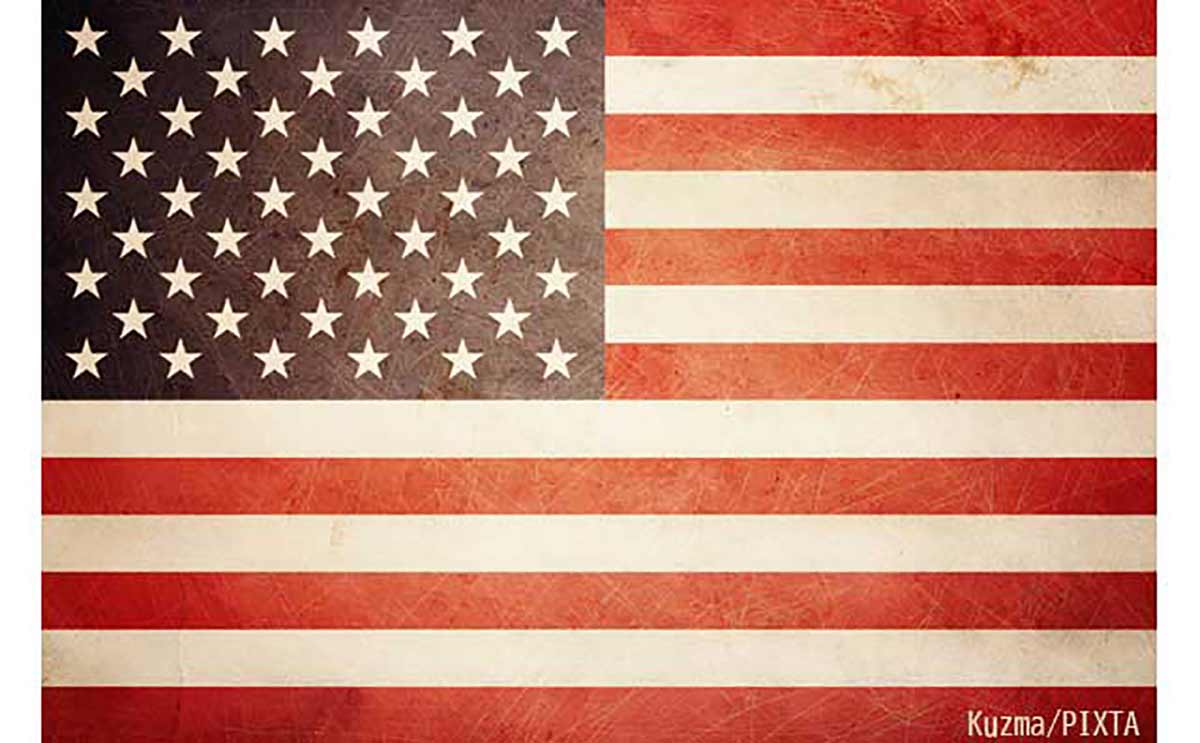


.jpg)
