「リベラルな価値」も一種の権力にすぎない...批判主義にみる決定的な矛盾
2024年07月04日 公開
2024年12月16日 更新

社会の自由と平等を求め続けるリベラルは、権力者やあらゆる差別などの「敵」を徹底的に批判する。しかし、フーコーの権力論を当てはめれば、「リベラルな価値」も一種の権力作用にほかならない。
※本稿は、佐伯啓思著『神なき時代の「終末論」』(PHP研究所)から一部を抜粋・編集したものです。
フクヤマのリベラリズムへの絶望
『歴史の終わり』の著者であるアメリカの政治経済学者フランシス・フクヤマは、2023年になって『リベラリズムへの不満』という書物を出版した。この書物のなかで、フクヤマは、自ら唱えてきた「自由・民主主義、人間の権利、法の支配」という「リベラルな価値」の現状を再考している。これはなかなか面白い書物である。
というのも、この書物のなかで、フクヤマは、自らを相変わらず「リベラリズム」の信奉者だと述べ、基本的態度は崩さないと述べている。にもかかわらず、実際には、彼は今日のリベラリズムを強く批判し、ほとんどリベラリズムに絶望しているかのようにみえるのだ。確かに、書名の通り「リベラリズムへの不満」がこの本を貫いている。
彼は、自らを「古い伝統的なリベラリスト」と規定してその立場を擁護する。いや、そこへ回帰しようとさえする。
しかし、今日のいわゆるリベラリズムが、たとえばポリティカル・コレクトネス(もともと、人種や宗教、性別などについて、偏見を含まず中立に立とうとする立場をさすが、実際には、差別的言説や権力的行動を、政治的、法的に「誤り」とする左翼リベラル派の主張をさす)のような主張に行き着いた様をみてみよう。
そこには、あまりに過激な自己主張、異なった意見への不寛容、事態の性急な政治化という殺伐たる光景が広がっている。
確かにこれはもはや、多様な意見と寛容を旨とする古いリベラルとは決定的に違っている。日系人でありながらも、健全なアメリカ的リベラルを信奉するフクヤマからすれば、たとえばトランプ現象に賛否の応酬をする左右両派の思想的様相そのものが、アメリカのよきリベラルの伝統からのただならぬ逸脱にみえるであろう。
だがここで、相互信頼と寛容にもとづく古いリベラルの復活を求めても仕方ない。なぜなら、今日の過剰なまでの政治的で不寛容なリベラリズムを生みだしたものは、まさしくフクヤマがかつて描いた「歴史の終わり」に実現される「リベラルな価値」だったからである。
新旧のリベラルを区別することはできない。フクヤマは、今日のリベラリズムとして、新自由主義とポストモダン等の哲学思想をあげているが、この両者ともに、「リベラルな価値」を母体にしているからである。
この矛盾は何も特別な考察を必要とするものではない。つまり、承認や尊厳を求める闘争、つまり「自由を求める闘争」というリベラルの思想は、やがては、自由に対するいっさいの障害を排除し、あらゆる抑圧や不合理からの解放を主張し、いかなる差別的取り扱いにも苦情を申し立てるという一種の狂気じみた自動運動に行き着くであろう。
「抑圧からの解放」は永遠に続く。しかしこの解放の自動運動は、その車輪を回すのに、多大なエネルギーを必要とし、潤滑油が切れてくれば車輪はきしみ、社会的な支持を失ってゆく。
実際、70年代前後から、家族であれ、学校であれ、共同体であれ、企業等の集団であれ、社会慣習であれ、生活上の規律であれ、個人の自由に対する制約に対してはそれをたえず批判し続けるという徹底した批判主義がでてきた。それは、社会秩序を構成する既存の制度的枠組みを自由への抑圧として批判した。かくて批判主義はリベラルの鬼子(おにご)である。
確かに批判が有効な局面もあり、そういう時代もあったし、むしろ批判こそが建設的である状況もある。批判そのものが間違っているわけではない。
しかし、その前に、批判主義は決定的な欺瞞を内包している。それは、批判主義は、その批判を、決して自らへは向けないということである。自由や平等や権利といった「リベラルの価値」のものへ批判を向けることはない。批判とはいわずとも、懐疑の目を向けることもない。
批判主義は、常に「敵」を外部に求め、自らのあり方を問おうとはしない。こうして、それは、自らの批判のみを正義とみなし、批判に対する批判を受け付けなくなる。その結果、批判主義こそがリベラルを裏切ることになる。だがその理由は、もともとリベラリズムが胚胎した自家撞着にあった。内に潜む矛盾のゆえに、「リベラルな価値」がその内部から崩壊していくのである。
あらゆる言説は「権力への意思」を有す――フーコー
このことを示す典型例としてミシェル・フーコーほどの適材はいないであろう。フーコーは次のようにいう。
あらゆる言説は、決して中立的な事実を述べたり真理を述べたりするものではない。なぜなら、いかなる言語表現も、必ず他者に何かを伝え、一定の効果をもたらし、場合によれば社会的効果を生みだそうとするからだ。
その場合、いかに中立的で正当にみえるような言説であっても、その背後を覗けば、その表現者の利益や特殊な感情や、もっと端的にいえば「権力への意思」がある。自分を正当化したり、自己を引き立てようとしたり、他人を味方に引き入れたり、というわけである。無色透明な蒸留水のようなサラサラした言説はありえない。
こうして言説は必ず一定の「権力作用」をもたらす。それは、科学的真理といった場合にも当てはまる。「真理」という言葉に騙されてはならない。ある言説を真理だといったとき、それに対する反論を寄せ付けないのであり、そこに真理の絶対化が生じ、その真理を述べたものの権威化が生じているのである。「真理」につくことによる自己特権化である。
「科学」にせよ「真理」にせよ、無垢な客観性を装っているだけで、それは実は、ある意図を秘めた「権力」を隠しもっているのだ。
今日、「真理」はしばしば「事実」や「エビデンス」として表現される。たとえば政策の評価基準としてしばしばいわれるエビデンス主義においても、「事実が大事だ」「エビデンスが大事だ」という。だが、このいかにも中立的で客観的で科学的な言辞じさえも、考えてみれば、「科学中心主義」のイデオロギーを隠しもっている。
エビデンスを操り、それを握ったものの優位を隠している。これこそが「エビデンス」だといえば、誰もが容易には反論できない。これは「権力作用」にほかならないのである。
「リベラルな価値」も一見しごくもっともにみえる。抑圧からの解放、偏見からの解放、人権の尊重、こうしたリベラルな価値を正面切って批判するのは難しい。
リベラリズムは、人間の条件である性や能力や家庭の境遇や国など、生まれの偶然的属性を取り去ってしまえば、根本的にはあらゆる人は平等・対等であり、何ものにも従属しないという意味で自由だという。だから、様々な意匠も衣装も取り払って丸裸にすれば人間はまったく同じだという。
この根源状態を想定すれば、自由と平等は、普遍的な人間の本質であり、その実現は、道徳的正しさをもつという。それは科学法則のような真理ではないにしても、カントが述べたような普遍的な道徳的真理なのである。
しかし、フーコーの権力論をここに当てはめれば、「リベラルな価値」も一種の権力作用にほかならない。これもまた実に巧妙に隠された「権力」なのではないのか。自由や平等を永遠に求める運動は、永遠に続く権力作用だということになろう。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月18日 00:05
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第1回)
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること

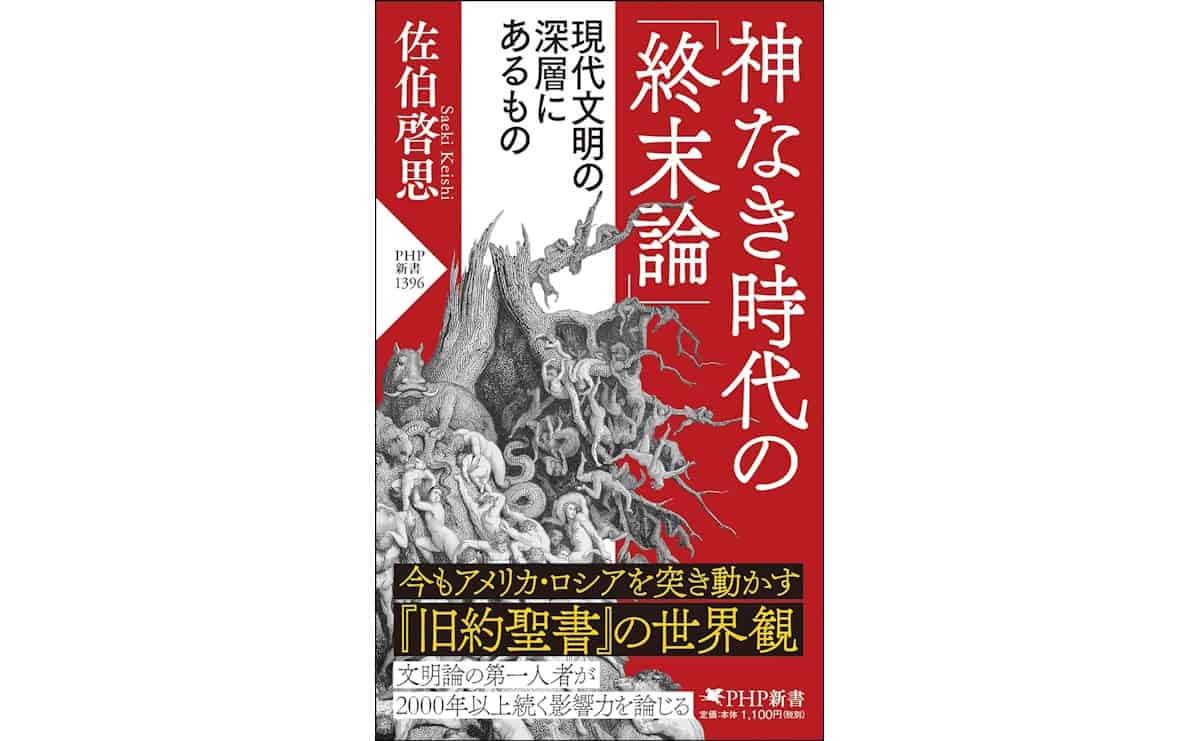
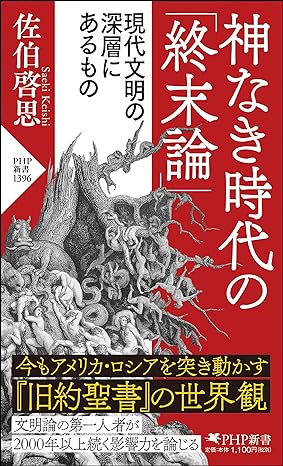

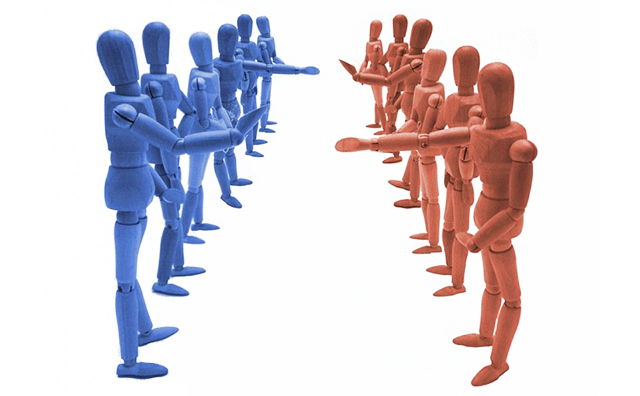



.jpg)
