揺れる「元徴用工」判決 韓国が狙った“請求権の枠外“
2018年12月25日 公開
2024年12月16日 更新

韓国大法院(最高裁判所に相当)が新日鐵住金に韓国人の「元徴用工」への賠償を命じた判決をめぐり、原告側弁護士は12月24日、期限までに同社が協議に応じる意思を示さなかったとして、資産差し押さえの手続きを近く開始すると明らかにした。一連の判決を紛争解決の専門家はどう見るのか。東京外国語大学の篠田英朗教授が説く。
※本稿は『Voice』2019年1月号、篠田英朗氏の「教条的な国内法学者の異常さ」を一部抜粋、編集したものです。
私企業に「植民地支配」の責任を問う矛盾
大法院判決は、「植民地支配は不法で強制的な占領だった」と断定し、「植民地支配と直結した不法行為などは請求権協定の対象に含まれていない」と述べ、「個人の請求権も協定に含まれたと見るのは難しい」と断定した。
反対意見を出した裁判官は、1965年「請求権協定が大韓民国の国民と日本国民の相手国およびその国民の請求権まで対象としているのは明らか」で、「請求権協定で規定された『完全かつ最終的に解決されたことになる』という文言は、韓日両国はもちろん、国民もこれ以上の請求権を行使できなくなったという意味だと見るべきだ」と述べたという。
請求権協定は、その前文で、「日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決」することをめざしていると宣言している。
そのうえで第2条において、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が……完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と書かれている。
文言を見れば、反対意見が妥当であるように見える。
そもそも日本政府は、「植民地支配と直結した不法行為」という認定を認めない。そのうえで、包括的に「個人請求権」も請求権協定で扱われた、と理解している。
歴代の韓国政府も、少なくとも個人請求権も請求権協定で扱われた、という立場を取っていた。
しかし今回の韓国大法院の判断は、両国行政府の伝統的な協定理解を否定した。文言上の解釈論のレベルを超えて、そもそも「植民地支配と直結した不法行為」に対する「個人の請求権」を、二国間協定で消滅させることはできない、という法理論を提示した。
賠償請求を命じた相手が新日鐵住金という私企業だったことは、「請求権協定は政府間協定なので、個人が私企業を相手に民事訴訟を起こす権利を侵害しない」という姿勢も示す。
私見では、この姿勢は、大きな矛盾を孕んでいる。「植民地支配」はいずれにせよ国家行為である。したがって、その責任を私企業に帰して、損害賠償を命じるのは、矛盾している。
ただし、その点を論じるには、韓国統治下の国家総動員体制での企業の位置付けの評価という難しい問題を孕んでいる。
日本が、今回の判決を請求権協定と矛盾したものと考える理由は、韓国併合時代の国家による労働力の動員を、私企業の責任に負わせることはできない、私企業による強制徴用はなかった、と考えるからだろう。
ただし、請求権協定は、日韓両国による将来の係争案件の処理の方法に関する合意であり、個人救済の妥当性を完全に消滅させた、と宣言したものではないことにも、注意を払っておく必要がある。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債





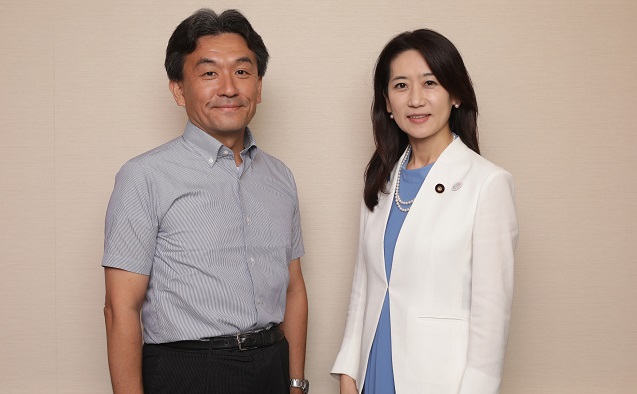



.jpg)
