Voice » 日下公人 「情」と「考え」が足りない経営者
日下公人 「情」と「考え」が足りない経営者
2018年05月14日 公開
2024年12月16日 更新
「情」と「考え」が足りないからうまくいかない
日本企業の組織のあり方を変えなければならなくなったとき、あまりにも愚かだったのは、アメリカ型の組織論を称揚する人びとをもてはやしたことであった。日本の経営者や人事担当者たちからすれば、たしかに、「アメリカでやっている合理的経営」などといえば、もっともらしいし、自分たちが「リストラ」に手を染めることを正当化できる。
しかも、何も考えなくていいから、楽だったのであろう。
だが、アメリカはそもそも奴隷をこき使っていたような国である。そんな国の「使用人をこき使うための組織論」を、少し自分たちの経営が悪くなったからといって、ろくな考えもなしに導入するのは、あまりにもご都合主義的だし、ただただ木に竹を接ぐような話である。
これまで「仲間」意識で働いてきた日本の組織構成員は、心の底から納得できない。これまで「仲間」だと思って働いてきたのに、急に「使用人」のように扱われるのだから、たまったものではないし、憤懣やるかたない。
アメリカ伝来の成果主義を単純に移植したような浅はかな会社は、すでに2000年代前半の段階でガタガタになった。そのせいもあって、超一流などと評されていた企業が倒産したり外資に買われたりするような、かつてでは考えられなかった事態がどんどん起きるようになった。
昔の日本軍なら、優秀な上官は「お前たちの命を俺にくれ」といったものである。そして自分が先頭に立って突撃した。促成教育で学卒を見習い士官にして、さらに小隊長か中隊長にすることが行なわれたが、その人たちは勇敢に戦ったので、戦死・戦傷率が高かった。
だが、いまの経営者は、自分たちの地位は守りながら、かつて「仲間」であった従業員たちを「使用人」的な地位に叩き落としてしまった。経営状況が悪いことを錦の御旗にして、組織をいじり、役職を上げたり下げたり弄ぶことに余念がない。それで仕事をした気になっているのであろう。
しかも、それを正当化するのに「合理的経営」などと嘯くのだから、下の人たちはまことに救われない。
日本のこれまでの組織文化を考えるなら、組織や事業を整理したり、降格人事などをしたりしなければならないときこそ、「情」を働かせなければならなかった。「仲間」に対してどう対応すべきかという視点で考えるべきであった(私の友人は、「人事部長に……」といわれたとき、NHKを退社した。仲間の人員整理をやらされるのはイヤだったのである)。
まずは明確な基準を設け、客観的に判断する。将棋や囲碁ならば勝ち星の数で判断できるからたやすいが、会社経営の場合はなかなか難しいから、そこは真剣に考えなくてはいけない。日本の組織改革が下手くそなのは、そこに変な恣意が入るからである。
そのうえで、しっかりと「情」を添えて、説得しなければならない。そして何より、まずは自分が腹を切ることを考えなければならなかった。
間違えてほしくないが、私は会社で格差をつけるのがダメだといっているのではない。温情主義に流されて会社を潰したら、よほどそのほうが恨まれるであろう。企業である以上、活力を維持するために格差が必要であるならば、経営者は明確にその道を選択しなければなない。
だが、そのときに「仲間であった社員」を「使用人」に叩き落とすような「情」のないことをするのは、あまりにバカげていませんか、という話をしているのである。
たとえば先ほど述べたような、中心部に小さな正社員グループがいて、その周辺に高給高能力の専門家集団やルーティンワーカーが集うような組織体に変えるにしても、「情」を働かせて考えてみれば、いくらでもやりようはあるはずである。
うまくいかないとしたら、それこそ「『情』と『考え』が足りない」というしかない。
(本記事は、日下公人一著『「情の力」で勝つ日本』<PHP新書>を一部抜粋、編集したものです)
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:12月21日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- なぜ弾圧? 知っておきたい中国政府と「ウイグル族」の歴史
- 「国民に覚醒を呼び掛けてほしい」元衆議院議長が高市早苗首相に求めること
- 「1月解散」の可能性は...?「高市長期政権」に向けたグランドデザインと戦略を語る
- 「台湾有事は日本有事」の意味とは? 地政学で読み解く危機の現実
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- アメリカ軍は弱体化している...世界トップに躍り出た「中国海軍の軍事力」
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 習近平の「暗殺未遂数」は歴代トップクラス
- 【天才の光と影 異端のノーベル賞受賞者たち】第18回 リチャード・ファインマン(1965年ノーベル物理学賞)

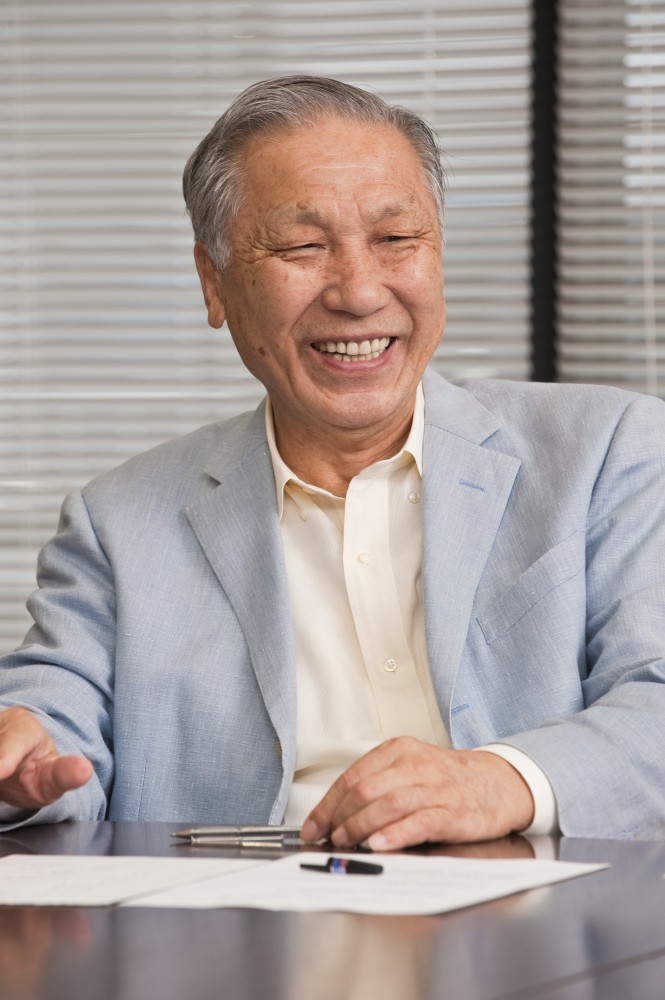
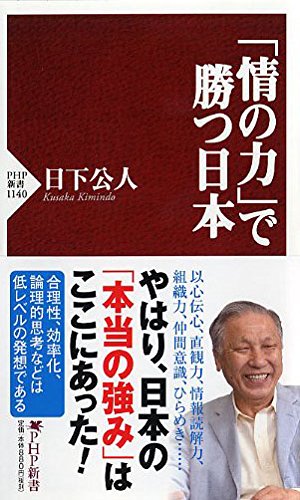



.jpg)
