少年法は改正すべきか
2015年04月10日 公開
2024年12月16日 更新
《『Voice』2015年5月号より》

川崎中一殺害事件について考える
未成年による残虐な犯行に対する扱い
2月に起きた川崎市の中学1年生殺害事件で、世論が沸き返りました。さんざん報道されてきたので、事件の概要については、ここであらためて述べるまでもありますまい。主犯格の少年(18)は、まったく高校に通っていず、どうやら札付きの非行少年だったようです。新聞やテレビでは少年法61条遵守の観点から実名、顔写真などを報道していませんが、週刊誌やネットでは、虚実取り混ぜて過熱した情報が思うさま飛び交っています。しかしこうした情報公開をめぐる媒体間のギャップは、べつにいまに始まったことではありません。
18年前に起きたいわゆる「酒鬼薔薇事件」では、残虐極まる犯行手口だけでなく、警察やマスコミを手の込んだかたちで嘲弄した犯人が14歳であった事実に世間が驚愕し、逮捕後、某出版社の2つの週刊誌がいち早く実名と写真を公開しました。この出版社は当時、法務省の回収勧告にも頑として応じませんでした。
もちろん売らんかなの週刊誌のことですから、私たち誰もがいくらかはもっている下卑た野次馬根性や好奇心を当て込んでの目論見であったのは事実です。しかし公平に見てこのときは、この出版社の編集方針に、加害者の人権には過剰なほど配慮するのに被害者遺族の心情を考慮しない当時の空気に対する義憤のようなものが働いていたことも確かだと思われます。一種の確信犯的な試みで、支持者もけっこう多かったようです。
今回の場合は、18年前に比べてインターネットの飛躍的な普及という情報環境の変化があり、そのため、SNSやブログなどを通して、やたらとプライベートな情報が全国、いや全世界に露出し、物事を慎重に考えないコメントや画像が氾濫する結果となっています。しかも、もうそんなことは当たり前だという雰囲気が共有されており、マスコミの自粛などほとんど何の意味ももたないといってもいい。これはまたこれで行き過ぎの感が否めません。かの「イスラム国」も、こうした情報環境を巧みに利用したといえるでしょう。
本稿では、これらの情報洪水のなかから聞こえてくる声のうち、次の二つの問題点をあぶり出し、それについて少し掘り下げてみようと思います。この問題点は、じつはいま述べた某出版社の「決断」の意思のうちに孕まれていたものと同じです。
(1)未成年(少年法で規定された20歳未満)だからといって、残虐な犯行を犯した者をかばうような扱いはおかしいのではないか、実名や顔写真を公表することによって、加害者に社会的な制裁を受けさせるべきではないかという議論。
(2)何か大きな事件があったときに、そのディテールを知りたいという好奇心は人間の本能的な感情であり欲望であって、それを抑えることは不可能だから、技術的に可能な限りでやってしまえばよいという感覚。
(1)の議論は、推し進めていくと、いまの少年法の年齢規定を18歳未満にまで下げるべきだという主張に連続していきます。この主張の是非について考えてみましょう。
結論からいうと、私は、この主張にほぼ賛成です。ただしそれは、被害者への同情心とか、被害者になり代わって応報や復讐や制裁をしてやりたいといった感情的な理由からではありません。また、札付きのワルには厳罰を科してやらなくては更生できっこないのだ、といった単純な厳罰主義から出た考えでもありません。
まず国家の法というものは、被害者の報復感情の代行をするためにあるのではありません。それは、いかにして社会の公正な秩序を維持し、すべての国民に安寧を保障するかというところに眼目が置かれています。だからそれぞれの法律には独自の趣旨というものがあり、それらが組み合わされて、総体としてその眼目を満たしうるような体系性を具えていなければなりません(実態はそううまくできてはいませんが)。
少年法の趣旨はといえば、非行少年に対して性格の矯正と環境の調整のために「保護処分」を行なうというところにあります(1条)。これと対になるかたちで、刑法41条の「14歳に満たない者の行為は罰しない」という規定があるので、14歳以上20歳未満の「少年」は、明らかに刑罰の対象になります。しかし同時にその目的は成年と異なり、懲戒よりはむしろ矯正に重きが置かれるというように、バランスがとられているわけです。「少年」は「成年」に比べて未熟だからこそ可塑性を残しているという考えに立つものでしょう。この考え方は基本的には妥当なものですから、「少年法など廃止してしまえ」などと乱暴なことを言ってはいけません。
しかし一方、この年齢は肉体的には大人顔負けの力をもち、性的にも成熟しており、しかも家族による庇護・管理からの自立途上にあって精神的に不安定な時期に当たります。社会人としての責任意識は十分に身に付いていず、親や教師の目を逃れていくらでも悪いこと(社会規範に反すること)、粗暴なことに手を出す可能性のうちに置かれています。血気にはやるのは昔から若者の常です。まして今回の事件のように、学校という囲いからすっかりはみ出てしまっていて、早くから勉強に興味も抱かず仕事にも就かず、親もその事態にお手上げ状態になっているような「少年」の場合には、そういう可能性がもともと大きかったといえるでしょう。
少年の凶悪犯罪は減っている
さて問題は、「少年」と「成年」との法的な境目をどこに置くかということなのですが、これを考えるには、いくつかの問題を押さえておくポイントがあります。
まずこうした少年事件が起きるたびに厳罰化の声が上がるのですが、少年の凶悪犯罪(殺人、強盗、強姦、放火)は減り続けているという事実に皆が気付かなくてはなりません。たとえば、平成24年における少年凶悪犯の検挙人数は135人、25年では77人、殺人に至っては、24年8人、25年はわずか3人です(警視庁生活安全部資料 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/hikou/hikou25.pdf)。
最近はだいぶこの事実が気付かれ始めているようですが、たまにマスコミでこの種の事件が大々的に報じられると、これを見た人はすぐに感情的反応を示して、「増えている」と思い込んでしまいます。むしろ事態は逆で、めったにないからニュースとして大きく取り上げられるのです。ですから、ある個別の事件があったからといって、それを根拠に厳罰化しろというのは短絡的思考です。
次に、厳罰化には犯罪の抑止効果があるという考え方がありますが、これは実証されていません。原田隆之氏の『入門 犯罪心理学』(ちくま新書)にはそのことが詳しく書かれています。また私も以前、『なぜ人を殺してはいけないのか』(PHP文庫)という本の「死刑は廃止すべきか」という章で、その実証不可能性を論じたことがあります。私は死刑存置論者ですが、その立場を取るのは死刑に抑止効果があるからではありません。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月07日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点
- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由



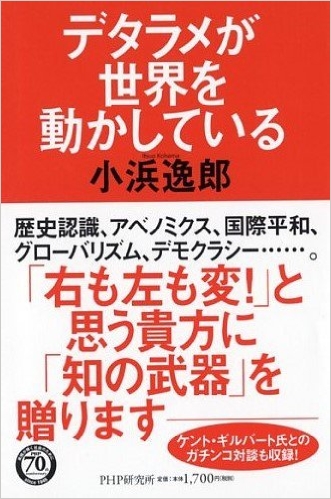
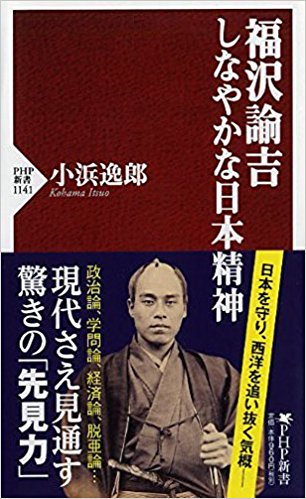




.jpg)
