『日本外史』は反徳川の書物ではない...吉田松陰が陥った“推論の罠”

頼山陽の『日本外史』は司馬遼太郎の小説に匹敵するほど面白い本である。一方で偏った読み方をされやすい一冊でもあり、例えば吉田松陰の読み方には大きな問題があったと言わざるをえない。松陰の読み方は、古代のギリシア人歴史家・プルタルコスが説いた「ヘロドトスの悪意」の第三に当たると言えよう――。
※本稿は、山内昌之『歴史を知る読書』(PHP新書)の一部を再編集したものです。
江戸時代こそ現代の「重要な参照軸」
私たちが生きる社会とは異なる世界を知ることは、「平和」を築くうえで大きなヒントを与えてくれる。そこで紹介したいのは、頼山陽の『日本外史』である。個人的には、司馬遼太郎の小説に匹敵するほど読んでいて面白い本である。
『日本外史』はしばしば、書かれている内容の根拠を疑問視する向きもあるが、頼山陽は基本的に史実に忠実な人物であり、たとえば『坂の上の雲』のように人物を文学的に脚色したり創造したりはしていない。
それでいながら叙述にすこぶる迫力があるのが印象的で、その迫力が何に依拠しているかを考えたとき、頼山陽は日本史上の合戦などを取り上げていても、大前提として平和とは何かを追求していることと無縁でないことに気づいた。
歴史が好きな日本人は、たとえば戦国時代に代表される中世史、あるいは幕末から日清・日露戦争にかけての近代史に魅力を感じる人間が多い。
ところが私に言わせれば、そのあいだの江戸時代にどうして人気が集まらないのか、甚だ不思議である。これだけ平和を尊ぶ国民が、太平の世を築いた徳川幕府やその祖である徳川家康よりも、暴力や粛清にあけくれた信長や秀吉を賛美するのはなぜだろうか。
信長や秀吉は、戦国時代という過渡期を終えるために現れた、従来の日本にはいなかったタイプのリーダーだと私は考えている。彼らが凄まじい暴力を辞さなかったからこそ、たしかに時代は切り拓かれたのかもしれない。
しかし他の時代や人物に見向きもせず、信長や秀吉の活躍ばかりを追いかけていては、現代に活かせる学びの射程は限られてしまう。
むしろ、秀吉が関係を悪化させた朝鮮や中国との関係を修復し、東南アジアに平和貿易という概念を用いた徳川家康にも目を向けて然るべきだろう。
270年の徳川の太平の世はたしかに「血湧き肉躍る」時代ではないかもしれない。しかし、平和や持続可能性がテーマになるこれからの時代を考えるうえで、間違いなく重要な参照軸となるはずだ。
頼山陽『日本外史』への誤解
頼山陽の『日本外史』に話を戻すと、私には本書が誤解されているように思えてならない。というのも、幕末に勤王の志士に影響を与えた印象が強いからか、現代の日本人の多くが「反徳川」「反江戸幕府」の書物と捉えているように感じるのだ。しかしじつのところ、その見方はまったく正しくない。
その冒頭には「例言」として本の要旨が書かれているのだが、そこでは「我が徳川氏」という表現が用いられているばかりか、徳川幕府が平和と繁栄の統治をもたらしたと明言されている。
そのうえで、かつて徳川氏が戦乱を終結させた意味や、当時の日本人が平和な時代を生きる有難みをわかっていないと厳しく指弾する。
『日本外史』はつまるところ、源平二氏から徳川氏までの武家盛衰史であるが、頼山陽は最初から順を追って読んでほしいと語っている。歴史を一カ所のみ切り取ることは、大きな危険性をはらんでいる。
たとえば、関ヶ原の戦いでは徳川家康と石田三成に限らず、毛利家や前田家、あるいは上杉家などそれぞれの立場を満遍なく読んでいかないと、どの家が正しくてどの家が悪いかという話になりかねない。
もしも毛利家の視点だけを追いかけてしまえば、必然的に「徳川家に領土を奪われた」という怨みのエピソードになってしまう。
『日本外史』を最後まで順を追って読めば、平和な時代の尊さがわかると頼山陽は語る。結びの言葉はとくに印象的で、「衣類も荷物も無防備のまま、つまり甲冑などを着ることなく、食料をもたずに旅をできるのは誰の力であろうか」と尋ねている。
答えは当然ながら、兵乱が多かった歴史に終止符を打った徳川家康の功績こそ大きいということを、彼は一貫して主張した。以上をふまえれば、『日本外史』を素直に読めば倒幕を促す本ではないことがわかるはずだ。
そして、歴史の一部分だけを切り取って学ぶことの危うさを、頼山陽の言葉から窺える。
頼山陽は『日本外史』で乱世の中世を描くことで、逆説的に平和の重要性を説いた。「人命至重」という言葉を用いているように、そもそも何よりも人命に重きを置く思想の持ち主であったし、海外への侵略や膨張も否定するような人物であった。
ところが、そうした考え方と相容れなかった人物が幕末に存在した。誰もがその名を知る、長州藩の吉田松陰である。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

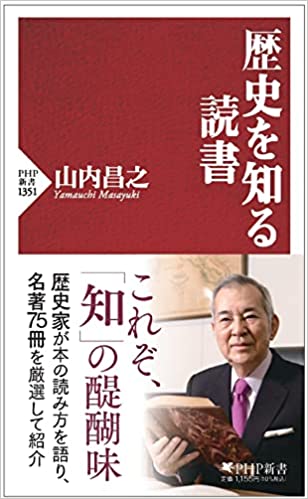


.jpg)
