日本は同胞を救わない国のままでいいのか!
2015年12月15日 公開
2024年12月16日 更新
エルトゥールル号の教訓
時を超えた恩返し
櫻井 門田さんが書かれた『日本、遥かなり——エルトゥールルの「奇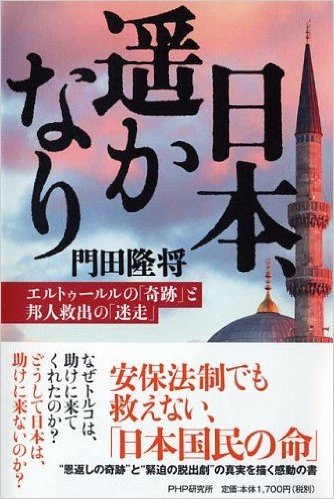 跡」と邦人救出の「迷走」』(PHP研究所)は本当に素晴らしい内容でした。関係者に徹底した取材を行ない、なおかつ、一連の取材には血が通っています。多くの人の感動を呼ぶのは間違いないと思います。私も読んでいて、幾度も涙がこぼれました。
跡」と邦人救出の「迷走」』(PHP研究所)は本当に素晴らしい内容でした。関係者に徹底した取材を行ない、なおかつ、一連の取材には血が通っています。多くの人の感動を呼ぶのは間違いないと思います。私も読んでいて、幾度も涙がこぼれました。
門田 ありがとうございます。
櫻井 1890年のエルトゥールル号遭難事件は、知る人ぞ知るエピソードです。和歌山県串本で難破したトルコ軍艦エルトゥールル号の乗組員を日本人の漁民たちが懸命に救助し、69名のトルコ人の命を救いました。いちおう知っている話でありながら、門田さんが詳細に掘り起こしたことで、ある意味、新しい大きな感動を与えてくれます。
門田 しかもこの事件に先立つ1886年に、ノルマントン号沈没事件が発生しています。エルトゥールル号と同じ紀伊大島沖で、イギリス船籍の貨客船ノルマントン号が座礁し、沈没した事件です。欧米人は船長以下、26名が救助されたのに対し、日本人の乗客25名は誰1人、助からなかった。にもかかわらず、当時、日本は欧米列強と不平等条約を結んでいて治外法権だったため、有色人種を見殺しにした船長は職務怠慢罪でわずか禁固3カ月、他の船員は無罪、という軽い判決でした。「人種差別」という言葉が、衝撃とともに日本中に広がったのです。
「もう2度と、外国船など助けるものか」という風潮が広まっても不思議ではない状況です。しかし、そのノルマントン号沈没事件からわずか4年後、傷だらけで崖を登ってくる見知らぬ異国人を、同じ紀伊大島の人びとはなおも必死で助け出した。なぜなら、彼らにとっては「難儀したときに互いに助け合うのは当たり前のこと」だったからです。
そんな日本人の姿はトルコ人たちの胸を打ちました。エルトゥールル号のエピソードは、トルコでは小学校の教科書にも紹介されてきたのです。
そのような日本人への感謝が1985年、イラン・イラク戦争のときに報われます。サダム・フセインのイラク軍がイラン上空を戦争空域に指定し、日本からの救援機が来ないため出国できない200名以上の邦人に対し、トルコが航空機2機を派遣して救出した「時を超えた恩返し」の実話です。
櫻井 本書の優れた点は、エルトゥールル号遭難事件の分析から1歩も2歩も進んで「邦人救出」というテーマに深く切り込んでいることです。おっしゃったテヘランの邦人救出のみならず、1990年、イラク軍クウェート侵攻に伴うクウェート在留邦人人質事件、94年のイエメン内戦に伴う邦人脱出など「海外にいる日本国民の生命をいかに守るか」というテーマを据えてノンフィクションに新たな地平を切り拓いた点で、たいへん意義深いと思います。
門田 ご指摘のとおり、本書に私が込めた問題意識は「国家が『命』を守るとはいかなることか」というものでした。
あらゆる先進国は、戦争やテロ、事件や事故に巻き込まれた自国民がいれば、世界のどこであろうと民間航空機や軍用機を飛ばして自国民の救出に来ます。ところが、日本だけは「来ない」。いうまでもなく、自衛隊の海外での邦人救出が戦後、禁じられてきたからです。
「自衛隊は憲法違反」と口走るような現実無視の人びと、言い換えれば「自国民の命」を守るという最も大切な「本質」を見失った法解釈や観念論に固執する“内なる敵”ともいうべき存在によって、戦時下のテヘランから邦人を脱出させるためには、他国に「お願いする」しかない、という奇態が生じてしまったのです。それは、自国民を救出するという行為が、「究極の自衛」であるという「基本」すらわかっていない人びとが、いかに日本に多いかを物語っています。
在外邦人の救出に「条件」が必要なのか
門田 そして残念なことに、その状況は、今般の安全保障関連法改正でも本質的には変わっていません。
じつは2014年5月15日、内閣総理大臣の諮問機関である安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)が報告書を出しました。この段階では、「国際法上、在外自国民の保護・救出は、領域国の同意がある場合には、領域国の同意に基づく活動として許容される」「領域国の同意がない場合にも、在外自国民の保護・救出は、国際法上、所在地国が外国人に対する侵害を排除する意思又は能力を持たず、かつ当該外国人の身体、生命に対する重大かつ急迫な侵害があり、ほかに救済の手段がない場合には、自衛権の行使として許容される」とありました。
とりわけ重要なのは、以下の箇所です。
櫻井 ここまで明確に国民の生命を守ることを打ち出す内容の報告書は、かつての日本にはありませんでしたね。
門田 まったく申し分ない内容です。度重なる自衛隊法の改正を経て、安保法制懇の報告書では在外邦人救出に前提条件など必要ない、というところまで踏み込んだ。私もその後、安全保障関連法案での邦人救出の進展に大いに期待しました。
しかしその後の国会審議を経て、内容はずいぶん後退してしまいました。たしかに今回の改正で、従来の邦人「輸送」だけでなく「救出」も可能となったわけですが、在外邦人の「救出」を行なうためには「領域国の同意」「秩序の維持」「関係当局との連携」の確保が必要だという要件が設定されました。「救出」「輸送」いずれの場合でも、自衛隊は「戦闘行為が行なわれることがない」と認められるところにしか派遣できない。これでは今回、私が書かせていただいた各々のケースのいずれも、邦人救出のために自衛隊を派遣できるかは非常に不透明です。
櫻井 海外にいる日本人の身に危険が及んだ際は自力で対処しなければならない、というのは国際社会の現実であり、どんな国にとっても常識のはずです。それなのに門田さんの期待が裏切られてしまった背景には、安全保障関連法案を「戦争法案」と称する共産党や市民運動の存在があったと思います。さらに罪深いのは、与党内にあって自民党の足を引っ張る公明党の存在でしょう。
門田 「踏まれても蹴られても/付いて行きます下駄の雪」との都都逸があるように、公明党が自民党にぴったりと吸い付いた結果、両党が渾然一体となりすぎて、もはや見分けがつかないほどです。いまや自民党・公明党の候補者は互いの応援の見返りに、選挙区の後援会名簿を交換してさえいます。
櫻井 私は、自民党のなかに「選挙区は自民党、比例区は公明党」と連呼する選挙活動に恥や違和感を覚えなくなった人が増えていることに驚きを禁じえません。
門田 本来なら公明党との連携で得るもの、失うものを比較検討しなければならない。にもかかわらず、いまや選挙が唯一のメリットとなってしまい、両党が離れられない関係になってしまっているのではないか。加えて「自民党は右寄り」という国民の印象を和らげる「緩衝剤としての公明党」が便利だというのも、自民党の側が重宝がる理由でしょう。
櫻井 自民党と公明党は本来、合併が難しい政党です。綱領も信条も政策も相容れない2党ですから、連立を組んでいることのほうがむしろ不自然です。にもかかわらず、選挙対策のためだけに離れられなくなっているのだとしたら、その先に待っているのは両党の埋没です。それは両党と両党を支持する有権者にとって、不幸以外の何物でもありません。
それでも私は、自民党が公明党を切り離すことは不可能ではない、と考えています。公明党から離縁を切り出すことはおそらくないでしょうから、主体性が問われるのは自民党の側です。
公明党が政権に深く食い込んだ結果、私たちはメディアが報じる政府の考えや政策が安倍首相の本意によるものなのか、公明党の意見の反映なのかが見えづらくなっています。また、自民党といっても1枚岩ではありません。党内力学によって自民党の政策が形づくられるのは当然でしょう。安倍政権の打ち出す政策を、こうした要素を踏まえてより丁寧に見ていく必要があります。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月22日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 【日本文明研究会】文明史のなかの日本のリベラル・デモクラシー(第2回)



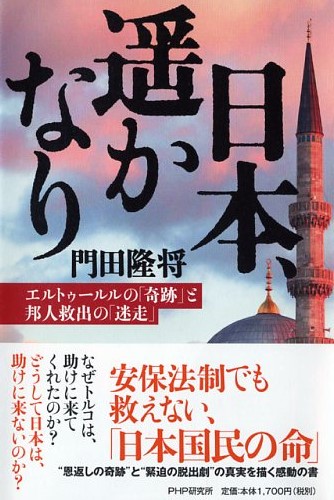
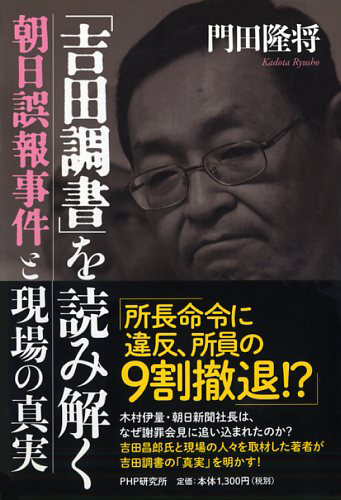


.jpg)
