現場力が活きる「ライト・フットプリント(LFP)経営」とは
2015年02月23日 公開
2024年12月16日 更新
じつは日本企業が最先端を走っている
しかし、ここでわれわれは一つの疑問に突き当たる。ブエが記したライト・フットプリント経営の4つの成功条件である「自律分散」「協働協創」「相互信頼」「隠密行動」は、そもそも日本企業が長年にわたり重視し、実行してきたことではなかったか。
その証拠に、目まぐるしい変化を続ける現在のVUCAワールドのなかで、日本企業は輸出企業を中心にかつてないほど業績を拡大している。2014年4―9月期の決算では、上場企業約1500社は経常利益を約1兆5000億円増やし、過去最高を記録した。2015年3月期の通年でもリーマン・ショック前の過去最高益にほぼ並ぶ見通しである(『日本経済新聞』2014年12月4日付朝刊)。
私の見るかぎり、日本企業の好調の要因は、円安やアメリカ経済の好調などの外部要因だけではない。これまで日本企業が積み重ねてきた構造改革や「選択と集中」の決断、「現場力」の強化、脱自前主義による外部連携の強化などにより、世界に先駆けてライト・フットプリント経営を実践し、新しい環境のなかで「稼ぐ力」を高めてきたからである。
「稼ぐ力」を発揮する日本企業の象徴は、2015年3月期の純利益2兆円が見込まれるトヨタ自動車である。トヨタがVUCAワールドのなかで展開する経営は、まさに世界の最先端というべきものだ。
実際に、ブエの挙げたライト・フットプリント経営の成功条件をトヨタに当てはめてみよう。
「(1)自律分散」に関して、トヨタが改善(カイゼン)に代表されるボトムアップを長年重視していることはよく知られている。さらに、現在ではグローバル地域別での自律経営を実践している。2014年に北米本社機能をダラスに集約して権限移譲を行ない、豊田章男社長が進める「地域の自律」をさらに加速させている。
「(2)協働協創」について、トヨタは商品開発の分野で自前主義を取りながらも殻に閉じこもらず、国内外の他社と緩やかなコラボレーションを図っている。たとえばBMWとのディーゼルエンジンの調達と燃料電池における提携、フォードとのハイブリッド車(HV)の共同開発、PSAプジョー・シトロエンによる欧州向け小型商用車のOEM供給、パナソニックとのテレマティクス(自動車に通信システムを組み込んだ情報サービス提供)提携、マイクロソフトとの同じくテレマティクスやスマートグリッドでの提携などである。国内外を問わず外部と迅速な連携を行なう身軽さは、ライト・フットプリントの一語に尽きる。
「(3)相互信頼」の典型は、いわずと知れた「系列」である。トヨタにとっての系列企業とは、運命共同体のようなものである。さらにトヨタは系列を強化するため、デンソーとアイシン精機のブレーキシステム事業を統合する方針を固め(『日本経済新聞』2014年11月28日付)、2016年1月には開発子会社のトヨタテクニカルディベロップメントを再編し、従業員約5000人をトヨタ本体に取り込む予定だ。
「(4)隠密行動」の例として、トヨタは2014年12月、燃料電池車(FCV)「MIRAI(ミライ)」に200億円を投資し、2015年末までに年間生産能力を現在の3倍に引き上げる、と発表した。いま振り返ると2000年代、各社が電気自動車に傾注しているあいだにトヨタは燃料電池車に活路を見出し、迅速かつ隠密に研究開発を重ねていた。そして「いったいいつの間に」と他社が驚くほどの生産ラインを一気に築き上げ、2014年のタイミングで発表したのである。
もう一つのライト・フットプリント経営の好例は、合成繊維で知られる東レである。粘り強い取り組みで、炭素繊維をものにし、世界をリードする。さらに、ユニクロとのコラボにより、「ヒートテック」という大ヒット商品を生み出した。東レはユニクロを展開するファーストリテイリングと「協働協創」を図るため、異業種コラボレーションを担当する30人の精鋭部隊「GO(グローバル・オペレーション)推進室」を事業部に昇格させ、予算執行や人事の権限を強化した。
ファーストリテイリングと合弁会社をつくらず、「バーチャルカンパニー」の形態を維持する理由について、東レの日覺昭廣社長は「合弁会社にすると、互いに相手の懐に手を突っ込みたがるでしょう。(中略)せっかくの関係が崩壊してしまいます」(『日経ビジネス』2014年10月27日号)と「ライトな関係」の強みを強調している。
「Gemba Power」の強み
トヨタや東レのような柔軟な発想は、なかなか従来のトップダウン型の経営から生まれるものではない。ライト・フットプリント経営を実現するには、大きなパラダイムシフトが不可欠である。
「安定期の経営」と「乱気流の経営」はまったく別物であり、両者の経営を比較すると、次のような対立項が浮かび上がる(括弧内はライト・フットプリント経営における要諦を指す)。
(1)本社vs現場(現場が主役であり、本社はサポート役に徹する)
(2)規模vs能力(やみくもな規模の追求よりも、質の高い組織能力で勝負する)
(3)戦略vs戦術(不確かな戦略よりも、現場での機動的な戦術を重視する)
(4)革新vs改善(いつ生まれるかわからないイノベーションを追い求めるよりも、足元の地道な改善・改良を積み重ねる)
(5)個人vsチーム(卓越した個人に依存するのではなく、チームワークで勝負する)
いかがだろうか。「現場」「能力」「戦術」「改善」「チーム」という項目はいずれも、これまでの欧米型の「経営の常識」と正反対の発想であることに気付くはずだ。
じつは、先述のブエは前掲書のなかで「Gemba(現場)」という言葉を20回、「Gemba Power(現場力)」を10回近く使っており、「現場経営」を提唱している。私と面談するたびに、ブエは現場力についてさまざまな角度から質問してくる。ほかに「Bottom-up(ボトムアップ)」という単語や「Learn to trust people to manage themselves(自主管理しようとする人たちを信頼することを学ぶ)」という文章も見られる。
日本人経営者の書いた本であれば、「現場」という語が頻出するのは理解できる。しかし、フランス人コンサルタントであり、ハーバードMBAであるブエが日本的な「現場力」の強みに気付き、それこそがいま求められていると主張することに意味がある。
そう、「現場力」「ボトムアップ」は、世界最先端のライト・フットプリント経営そのものなのだ。
たとえば「無印良品」(中国など海外ではMUJI)のブランドで知られる良品計画は、10年以上にわたり現場からの業務改善提案を行なっている。2013年度下期の改善提案は約2200件。そのうち168件が採用され、実際に業務改善に結び付いている。そして改善の結果は、確実に良品計画の業績に表れている。2014年度の営業収益は対前期比17.1%増の2206億円。経常利益230億円、当期純利益171億円は過去最高を記録した。
日本企業の現場は、たんなる業務遂行ではなく、継続的な業務改善を行なう人びとの集まりである。トップの指示を待つのではなく、自ら問題点を発見し、自発的に改善策を提案、実行する。人材育成の指針においては、他律的なマニュアルワーカー(単純労働者)でなく、自律的に動くナレッジワーカー(知識労働者)を育てることに力点を置いてきた。
ナレッジワーカーは現場で育つ。いや、現場でしか育てることができない。トヨタ自動車の製造現場では「自主研」と呼ばれる取り組みが長年、行なわれている。自主研究会の略であり、現場では「自主研究」と「自主研修」の二つの意味が込められているという。若手もベテランも泥まみれ、汗みどろになりながら一緒に知恵を絞り、業務の改善を図る。こうした現場が、いったい欧米企業にいくつあるだろうか。
その意味で、日本企業がもつ潜在力とアドバンテージはすこぶる高いといってよい。先述の東レ・日覺社長は東レが日本的な企業であることについて、「それが強みだと思っています」(同前)と断言している。CEOのトップダウンという伝統をもつ欧米企業が、ライト・フットプリント経営を学んだとしても、日本企業の従業員のように現場で「自律分散」や「協働協創」をどれほど実践できるかどうかは正直、未知数である。だからこそ、われわれは内なる経営資源を見詰め直し、欧米に真似のできない道を貫かなければならない。日本企業の競争力の柱であった「現場力」に一段と磨きをかけることこそ、VUCA下の熾烈なグローバル競争に勝ち抜く道である。
 遠藤 功
遠藤 功
(えんどう・いさお)
早稲田大学ビジネススクール教授、〔株〕ローランド・ベルガー会長
1956年、東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機〔株〕、米系戦略コンサルティング会社勤務を経て、現職。
著書に『日本企業にいま大切なこと』(PHP新書)など多数。最新刊は『現場論』(東洋経済新報社)
<掲載誌紹介>
2015年は戦後70年の節目の年。6月23日は沖縄戦終結から70年、8月6日は広島原爆投下、9日は長崎原爆投下、15日は70回目の終戦の日である。今年は本誌でもさまざまなかたちで先の大戦と戦後を考えてみたい。
その第一弾が、2月号総力特集「戦後70年 日本の言い分」。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月13日 00:05
- 「私が長官を撃ちました」 國松長官狙撃事件の真犯人は誰か
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- なぜ日本だけが「目の敵」にされるのか 習近平政権が台湾問題で絶対に譲らない理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点
- イギリスでさえも二大政党制が融解 ヨーロッパに見る従来型政党政治の限界と模索
- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か

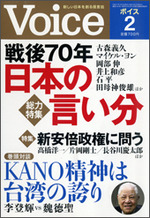 2015年2月号 (戦後70年日本の言い分)
2015年2月号 (戦後70年日本の言い分)




.jpg)
