「ポーランド孤児」を助けた日本人 70年後、阪神・淡路大震災で果たされた恩返し

ワルシャワの街並み
激動の歴史の中で、独立への道を歩み続けたポーランド。実は、日本との間に深い絆が結ばれた出来事がある。日本が海を越えて手を差し伸べた「ポーランド孤児救出」。この善意の行動は、70年以上の時を経て、あるかたちで日本へと返ってくることになる。ノンフィクション作家の早坂隆氏の著書『世界の旅先で、「日本」と出会う』より紹介する。
※本稿は、早坂隆著『世界の旅先で、「日本」と出会う』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです
ポーランド孤児救出とその恩返し
ポーランドは過去に何度も「地図上から消えた」という歴史を持つ国家だが、その歩みの中には日本との深い友情の物語も存在する。ポーランドではそれなりに知名度のある話だが、日本ではあまり知られていない。
それは日本による「孤児救出」の逸話である。
18世紀以降、「領土分割」という暗黒の時代が続いたポーランドでは様々な独立運動が試みられたが、そのような蜂起は常にロシア軍などによって鎮圧された。独立派やその家族の多くは、厳しい取り締まりの末、酷寒のシベリアに送られた。
第一次世界大戦の際には、ポーランドの大地においてドイツ軍とロシア軍が衝突。荒廃した国土から、多くの難民がシベリアに流入した。シベリアに住むポーランド人の数は、計20万人近くにも及んだと言われている。
ここに追い打ちをかけたのが、1917年のロシア革命である。革命によってボリシェヴィキ政府が誕生したが、旧ロシア帝国領内は内戦に突入。国土は凄惨な破壊と混乱に見舞われた。
このような事態を受けて、シベリアで暮らすポーランド人の生活はいっそう苛酷なものに転じていった。日々の食糧や医薬品にも不足するような困窮生活の中で、多数のポーランド人たちが無念の思いを抱えたまま息絶えた。
1918年、ポーランドはアメリカが提唱した「十四カ条の平和原則」に基づく形で独立を回復するが、シベリアにいるポーランド人たちの惨状は変わらなかった。
そんな中で迎えた翌1919年、遂にウラジオストク在住のポーランド人たちが力を合わせ、「ポーランド救済委員会」を設立。特に両親を失った孤児たちを救済するための運動を開始した。
ポーランド救済委員会はまず欧米諸国に働きかけ、孤児たちの救済を懇願。しかし、同委員会の期待に応える国はなかった。1920年の春にはポーランドとソビエト(ロシア)との間で戦端が開かれ、輸送手段としてシベリア鉄道を使うことも不可能となった。
結局、最後に同委員会が頼った先が日本であった。同年6月、同委員会会長のビエルキエヴィッチ女史が来日し、外務省に対してシベリア孤児の救援を懇請。この要請を受けた日本政府は速やかに救済を決断し、孤児たちに救いの手を差し伸べたのである。
救済に関して中心的な役割を担ったのは、日本赤十字社であった。これをシベリア出兵中の日本陸軍が支援。結果、同年7月に孤児たちの第一陣が、敦賀経由で東京に到着した。この第一回救済事業は翌年まで継続され、計375人もの孤児がシベリアを脱して東京の地を踏んだ。
日本側は収容所を用意して孤児たちを受け入れ、必要な医療処置などを施した。国民の関心も高く、日本中から多くの支援金が寄せられた。今で言う「ボランティアスタッフ」も大勢集まったというから、当時の日本人の高い献身性が窺える。
しかし、孤児たちの間で腸チフスが蔓延し、看護婦の松沢フミさんが感染、殉職するという悲劇も起きた(享年23)。それを知った多くの孤児たちが、涙を流したという。
それでも、日本側は救出事業を継続した。大正11(1922)年には第二回となる救済事業が実施され、390名の孤児たちが今度は大阪に到着した。第一回と合わせて、計765名の孤児が救出されたことになる。
日本側のこうした対応により、来日当初は衰弱し切っていた孤児たちの体力は徐々に回復。その後、全員が無事にポーランドまで送り届けられることになったのである。
日本を発つ船に乗り込む際、孤児たちはお世話になった日本人たちとの別れを心から惜しんだ。中には乗船を泣いて嫌がる子もいたという。孤児たちは口々に、「アリガトウ」と覚えたての日本語で感謝の気持ちを表し、多くの日本人関係者らと共に『君が代』を斉唱して別れたという。
そんな救出劇から70年以上を経た1995年、「阪神・淡路大震災」の折にポーランドでは「孤児救出の恩返しを」という運動が速やかに広まり、被災地に対する多額の支援金が集められた。
両国が互いに見せた善意の交わりは、日本人が知っておくべき史実の一つと言えよう。
高い人気を誇るワルシャワ大学「日本学科」
そんな歴史を持つポーランドだが、首都のワルシャワは第二次世界大戦の際に壊滅的な打撃を受けた。
1944年、ナチス・ドイツの占領軍に対する大規模な民衆蜂起(ワルシャワ蜂起)が起こったが、これが失敗に終わった結果、報復として街は徹底的に破壊された。一連の戦闘により、20万人前後の市民が犠牲になったとされる。
それでも、終戦の後、ワルシャワ市民たちは、「建物のヒビ一つまで再現しよう」と街の復元に尽力。旧市街はかつての美しい街並を取り戻し、1980年にはユネスコの世界遺産に登録されるにまで至った。
旧市街の中心に位置するのが旧市街広場である。広場には「ワルシャワのシンボル」として市民に愛される人魚像が建っている。
この像は、悪人に捕われた人魚をワルシャワの漁師が助けたため、それ以降はこの人魚が御礼として街を守り続けているという伝説にちなむものであるという。ゆえにこの人魚像は、剣と楯を手にしている。
旧市街広場の南部には、ポーランド国内で最大の規模を誇るワルシャワ大学のキャンパスが広がっている。創立は1816年と古く、この街の出身である音楽家のフレデリック・ショパンもかつて在籍していたという伝統校である。
同大には日本学科が設けられており、高い人気を誇っている。ポーランド人の親日的な意識に支えられ、合格倍率は実に毎年20倍前後という狭き門であるという。
同学科には、3年生終了時までに約2000字もの常用漢字を覚えなければ転科や退学の対象になるという規約がある。日本の大学生には耳の痛い厳しさである。
このワルシャワ大学以外にも、50以上の日本語教育機関がポーランドにはある。ワルシャワには、ポーランド日本情報工科大学という大学も創立されている。
優秀な学生たちの中には、日本への留学という希望を叶えた若者も少なくない。日本の文部科学省が実施している日本語・日本文化研修留学生の試験には毎年、20名前後のポーランド人が合格しているが、これは非漢字圏の中ではアメリカやフランスを上回って第一位という極めて優れた成績である(2015年)。ポーランドにおける日本語教育のレベルが、いかに高いかを物語る数字と言える。
日本への関心の高いポーランドだが、その理由としてはアニメや漫画の影響の他、空手や柔道、合気道といったスポーツの人気も挙げられる。このような状況は他の東欧諸国でも見られるが、とりわけポーランドでは独特の熱を帯びている。
ポーランドでは相撲も人気で、特に「女子相撲」の競技人口が多い。ポーランドで相撲をする女性の数は、日本以上とも言われる。近年、日本では相撲観戦を趣味とする女性が増えているが、自ら土俵に上がるタイプの「相撲女子」は、未だ少ない。
女子相撲特有のルールとしては、「顔への突っ張り」や「ぶちかまし」の禁止があるという。もっと見てみたいような気もする競技ではあるが、大柄な女性の多いポーランド人のことを思うと、大和撫子に勝ち目はあるのかといささか不安である。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

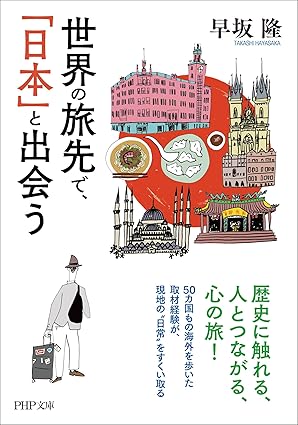


.jpg)
