厳しく罰せば、更生できるのか? 見直すべき「受刑者」との向き合い方
2024年06月19日 公開
2024年12月16日 更新

今年(2024年)2月、都内のとある劇場に映画『プリズン・サークル』を観ようと多くの人が集まった。公開から5年を経ても各地で追加上映されるこの作品を製作したのは、ドキュメンタリー映画監督であり、NPO法人out of frameの代表を務める坂上香さん。
メガホンをとるのは『ライファーズ 終身刑を超えて』『トークバック 沈黙を破る女たち』につづく3作目で、舞台は島根あさひ社会復帰促進センターという新しい刑務所。
この刑務所の最大の特徴は、受刑者同士の対話をベースに更生を促すプログラムを、日本で唯一導入していることである。刑務所でのワークショップなども長年行なっている坂上さんに、日々の活動の背景や『プリズン・サークル』に込めた思い、問題意識について伺った。
聞き手:Voice編集部(田口佳歩)
※本稿は『Voice』(2024年5月号)より抜粋、編集したものです。
助けながら、助けられる
――さまざまな活動を展開されている坂上さんですが、まずはNPO法人out of frameの事業内容について教えていただけますか。
【坂上】大きく分けて2つあって、1つは罪を犯した人や、依存症などの生きづらさを抱える人たちの映画を製作して配給すること。もう1つは、彼ら彼女らが自分の思いを表現するためのワークショップや対話の場をもつことです。
私が撮影する映画に映し出されるのは、あくまでも「私の目から見た彼ら彼女ら」です。苦しさの真っただ中にいる当事者は、自分から発信するのは難しい。でも、何かのきっかけでその段階を経たあとには、自分自身の力で思いを表現することができるかもしれない。それが彼ら彼女ら自身にも、また社会にとっても大事だと思って映画をつくっています。
ただし一方的に助けるとは思っていません。私自身、ワークショップなどで話を聞くなかで多くの気づきがあり、時には助けられてきたという実感がありますから、お互いに「助ける/助けられる」関係性です。
――『プリズン・サークル』の製作にあたって、刑務所から取材許可が下りるまで6年かかったそうですね。
【坂上】前例がないことなどを理由に、なかなか刑務所内で映画を撮影する許可が下りませんでした。それでも、受刑者の姿をしっかりと捉えて、なおかつ劇場などで長く公開され続ける作品をつくりたいと思い、映画にこだわりました。
幸いにも許可が下りたあとも、困難はありました。撮影は1カ月に1回、計3日間程度と限られていましたが、その1カ月のあいだに何があったかは教えてもらえません。毎回必死に、目の前の彼らと向き合うほかありませんでした。
私は1作目の『ライファーズ』でアメリカの刑務所の更生プログラムを取材していたのですが、それが今回の刑務所でも使われているプログラムのベースであったため、何とかある程度の状況は読めました。
また、ワークショップの講師として受刑者と交流した経験もあって、面識のある受刑者からは撮影の理解が得られやすいという側面もありました。もしもこの2つの経験がなければ、今回の映画はつくれなかったですね。
――追加上映ではいまでも満席が相次ぐ本作ですが、手ごたえはいかがでしょう。
【坂上】これほどの反響には正直驚いています。私はこれまでに、生きづらさを抱えている当事者を主人公として描き、多くの人が「私のことでもある」と感じられる映画をつくりたいと思ってきました。その思いは『プリズン・サークル』でも変わりありませんが、初めて日本を舞台に選んだことで、日本の皆さんにより「自分事」として伝わったのかもしれません。
――刑務所では行動の1つ1つに厳しい決まりがあります。受刑者が置かれている環境については、どのようにご覧になりますか。
【坂上】刑務所に行くこと自体、罪を犯した人びとに対する「自由を奪う刑」です。これは海外では十分に罰として納得されている考え方ですが、日本では、その上さらに懲らしめるべきと思われているのは事実でしょう。
しかし、懲らしめれば更生できるという根拠はありません。むしろ、その経験が「こんな目に遭わされた」という思いを強めたり、精神的に病ませたりするケースも少なくない。
罪を犯した人に対して、どのように対応するかは、社会が彼ら彼女らをどう見るかという問題でもあります。日本ではさまざまな事件が日々報じられますが、そうしたニュースが現実社会をそのまま表しているとは限りません。
そして、多くの人にとって罪を犯した人は「彼ら」「彼女ら」であり、「自分は違う」という無意識の思い込みがある。でも『プリズン・サークル』をご覧いただければ、じつはごく普通の人だったと分かるはずです。
たとえば、受刑者のなかには過去にDVや育児放棄、いじめなどを受けた人も珍しくなく、『プリズン・サークル』でも受刑者が打ち明けています。加害者の多くは、かつて被害者だったのです。あのとき、社会が手を差し伸べられていれば、彼ら彼女らの未来は変わったかもしれない。その意味でも、私は貧困や差別などあらゆる弱者への支援がまったく足りていないと感じています。
私たちは変わっていく
――『プリズン・サークル』で印象的なのが、受刑者が互いの過去をじっくりと聞きあう姿でした。
【坂上】受刑者に限った話ではなく、私たちの多くが自分の言葉をしっかり聞いてもらったという経験は少ないのではないでしょうか。私の場合は息子に多くを教えられました。
時には息子のためを思ってアドバイスしたくなるのですが、「お母さん、僕はただ話を聞いてほしいんだよ」と言われて、「ごめんなさい!」と謝ったことも(笑)。話を聞く側に思い込みがあると、相手の成長を妨げてしまう可能性があります。
また、私たちと同じように、罪を犯した人たちも時とともに変わっていきます。映画に登場した元受刑者のうち2人とはいまもよくやり取りしますが、刑務所内で映画を撮影しているときと出所後の現在では、考えが大きく変わっていることを実感します。ですから、話を聞くたびに「いまはそう思っているんだ」「昔はこう言っていたよね」と確認していく作業を大事にしています。
――いまは少年院でのラップのワークショップを撮影し、やがては映画として発表することをめざしているそうですね。
【坂上】『プリズン・サークル』を公開したあと、「刑務所について無知だった」「もっと関わりたい」という反応をいただき、背中を押されました。そして、当事者が社会と繋がることが社会を変えるきっかけになると思って始めたのが、ラップを用いた少年院でのワークショップです。子どもたちがつくったラップに対して、外の大人に応答してもらうのです。
ラップを受け取る大人たちは、最初は子どもたちが吐露する悪事にショックを受けますが、必死に受け止めようと歌を返します。すると、次第に大人たちが自分の弱さや失敗を吐き出し始める。それを受け取った子どもたちは「大人たちも自分たちと変わらないんだ」と驚き、社会への認識を変えていきました。
ワークショップは5カ月間でしたが、その短期間で子どもたちのみならず、参加した大人も大きく変わりました。
現実問題として、出所してまた罪を犯す元受刑者も存在します。それでも私が思うのは、一度罪を犯したとしても、人は何かのきっかけで変われるということ。ただし、変わるペースはひとそれぞれ。そうであるならば、どう罰するかだけではなく、社会として彼ら彼女らの現実とどう向き合うかを考えるべきではないでしょうか。
私だって無力さを感じて、落ち込んでばかり。それでも、すぐに起き上がります。人は立ち直れるということを、刑務所の更生プログラムなどで目の当たりにして、多くを学ばせてもらってきたからです。
彼ら彼女らの傷を消すことはでき得なくとも、その経験を何かに活かすことはできるかもしれない。そのためには、自分が傷ついた経験、そして人を傷つけた経験をしっかりふり返り、変わる場が必要不可欠です。いま社会に欠けているのはその機会であり、刑務所とは本来、そういう場でもあるべきなのではないでしょうか。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債



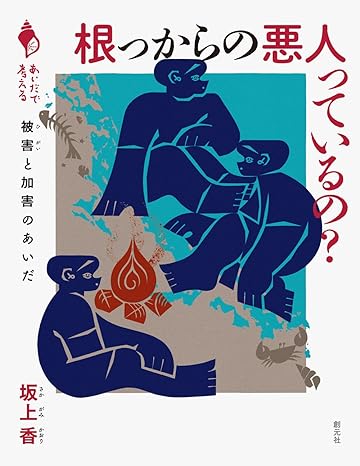



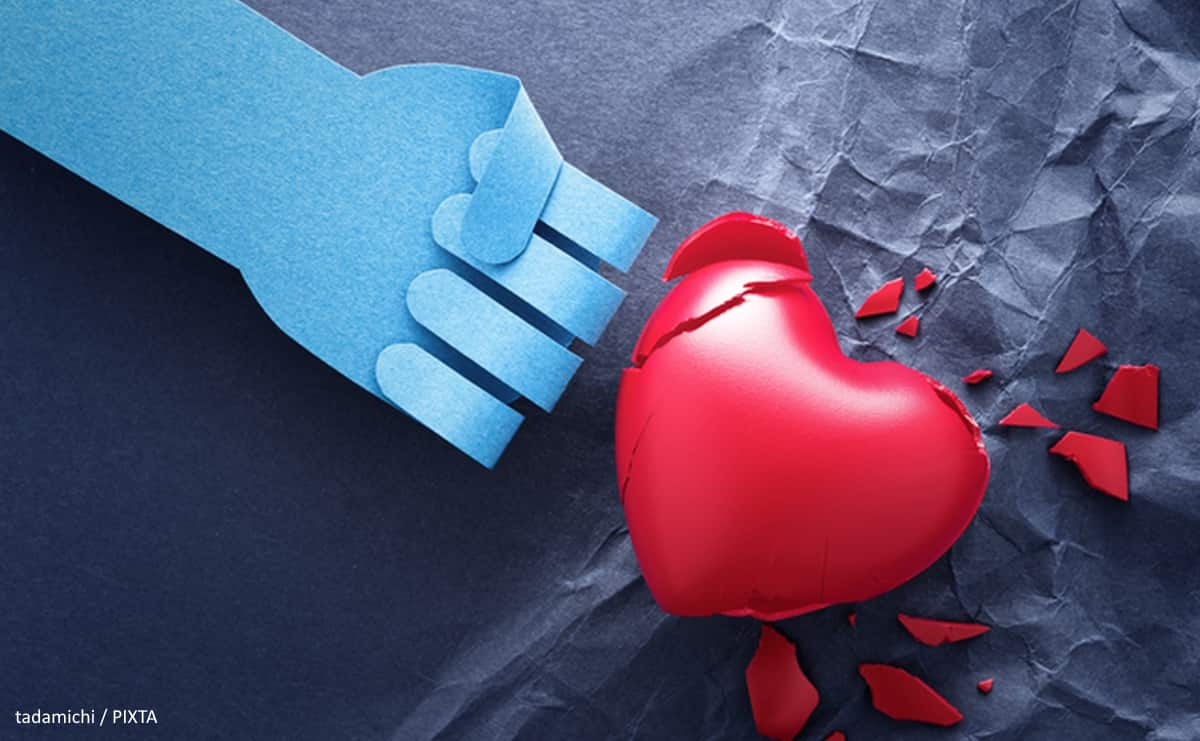

.jpg)
