小浜逸郎 誤解されている福沢諭吉
2018年05月08日 公開
2024年12月16日 更新
福沢にまとわりつく「誤解」
福沢諭吉は「武士」でした。そして真正のナショナリストでした。
その心は、彼が、あの動乱と建設の時代における公共精神を代表しており、当時の日本国民の幸福獲得について、終生、力を尽くして考え抜いた人だったという意味です。福沢は、欧米列強の脅威に取り巻かれる中で、日本の独立を真に成し遂げるには何が必要かを一心に考え抜いた人でした。
しかし福沢にはいくつもの誤解がまとわりついています。
この誤解の種は福沢自身にあるというよりも、福沢読者の側にあります。つまり、読者たちのイデオロギー的立場から来ている部分が大きいのです。
たとえば福沢は、しばしば欧化主義者のように見なされます。このイメージはリベラル左派の人からは歓迎され、右寄りの人からは苦々しいものとしてとらえられます。
しかし『学問のすゝめ』(明治5年~9年)や『通俗国権論』(明治11年)、『民情一新』(明治12年)その他を見ればわかるとおり、彼は一貫して欧化主義者に批判的でした。彼らを「西洋心酔者流」と呼んで至る所で痛快な揶揄を飛ばしています。
また、後に初代文部大臣を務めた森有礼が、『学問のすゝめ』発刊とほぼ同じ時期に、英語公用化論を唱えた時、福沢は同書の中で、暗に森を指して次のように罵倒しています。
《あるいは書生が、日本の言語は不便利にして、文章も演説も出来ぬゆえ、英語を使い、英文を用るなぞと、取るにも足らぬ馬鹿をいう者あり。按ずるに、この書生は、日本に生れて未だ十分に日本語を用いたることなき男ならん。国の言葉は、その国に事物の繁多なる割合に従て次第に増加し、毫も(少しも)不自由なき筈のものなり》(『学問のすゝめ』十七編)
森有礼は福沢にとっては弟子筋に当たります。その森をこのように罵倒するのですから、当時の知識人たちの容赦ない論争風景とその必死の身構えとが偲ばれるというものです。
それはともかく、ここで福沢は、文明が進めば必然的にその社会も複雑多様化するので、それに応じて母語も複雑に分化し、逆に母語が複雑に分化すれば、日本の文明化もさらに進むという好循環を指摘しています。だから、国語政策として急務なのは、文明化を促進し、母語である日本語を「繁多」にしていくことだ、と。
福沢がいち早く西洋近代文明とその背後にある進取の気象に触れ、これをとりあえずのお手本として積極的に摂取すべきだと唱えたことは事実です。けれども同時に彼は、たえず外に進出していこうとする西欧の強大な力の脅威を人一倍強く感受し、これに対抗する必要性を繰り返し訴えていました。
そのためには、一時、公家や長州がハマった感情的な攘夷思想などに走らず、まず「敵」をよく知ること、「敵」の優れた点を換骨奪胎してわがものとすることこそ大切だと説き続けたのです。いまの言葉で言えば、グローバリズムの浸透に対して、ただ精神論的に強がって見せるのではなく、国を守るために、現実的に有効な施策を真剣に模索したわけです。
長く続いた鎖国と封建制度によって日本が西洋文明に遅れを取り、国際社会への感度を鈍らせていたことは確かですから、まず何よりもその遅れと鈍りから速やかに脱却しなくてはならない──これが福沢の基本戦略でした。
彼はまた単純な国権主義者と見なされることがあります。この場合は逆に左寄りの人から顰蹙を買い、右寄りの人からは好意的に迎えられます。
しかし、主著『文明論之概略』(明治8年)や『通俗民権論』(明治11年)その他を見ればわかるとおり、彼の胸中にあったのは単なる国家権力の人民に対する強化ではなく、人民の自主独立の精神を育てることによって、国権と民権との間に常に相互抑制と均衡の関係を築き上げることでした。それが日本の近代化(文明化)にとって不可欠と考えられたのです。
政府は人民によって支えられる。幕末維新の政変も、一部権力者や討幕勢力の力によるものではなく、人民の気風がそれを引き起こすほどに高まっていたからである。為政者の賢愚は人民の賢愚の反映であるというのは福沢の持論でした。
民権と国権とはどちらが強すぎてもダメで、両者が車の両輪のように作用してじっくり協力体制を築いていかなくてはならない。それによって初めて実質的な国力を富ませることができる──これが、福沢の国家建設のグランドデザインだったのです。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月07日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 苦渋の解雇通告で味わった無力感…本田圭佑氏らとファンドを設立した元CEOの原点
- 量子コンピュータ開発における日本の勝ち筋 周回遅れの現状を覆す4つの戦略
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- 誰が常任理事国の横暴を止めるのか? 大国が裁かれない「構造的矛盾」
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- 安野貴博氏が目指す「デジタル民主主義」 テクノロジーでいかに分断を解消するか?
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由


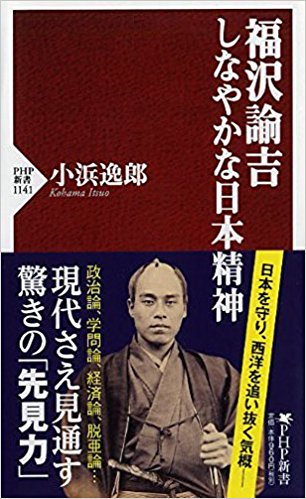
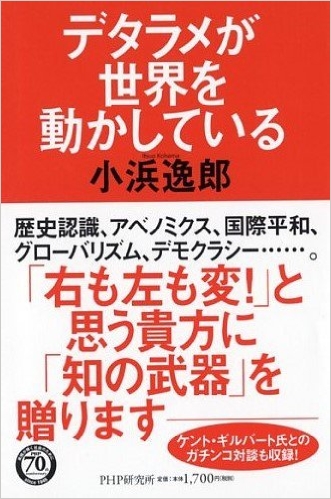




.jpg)
