シュンペーターが説く「イノベーションを起こせる人・現状維持に留まる人」の違い

イノベーションの理論で知られるシュンペーターは、イノベーションを起こせるのは「行動の人」だと主張した。本稿では「行動の人」が持つ特徴や、イノベーションがどのように生まれるのかを書籍『入門 シュンペーター』より解説する。
※本稿は、中野剛志著『入門 シュンペーター』から一部を抜粋・編集したものです。
「快楽主義的」な人と「精力的」な人
「イノベーションの理論の父」シュンペーターによると、イノベーションを起こせるのは、社会的な抵抗や心理的な抵抗に屈することのないような、特異な人格の持主です。
シュンペーターは、人間行動の類型を、「快楽主義的」と「精力的」に分けます。
快楽主義的な人間というのは、自分の欲求を満たすためだけに働き、それ以上のことはしないような人たちです。快楽主義的な行動は、「静態的」な経済における行動であるとシュンペーターは考えました。
--------------------------------------------------
「静態的」な経済では、「ほとんど誰もがその視野の及ぶ範囲で経済合理的に行動している。例外はほとんど重要ではない。誰もが自分の財の利用可能性のなかで正しい選択を確実に行い、深く考えることなしに、慣れ親しんだ市場で自信をもって適切なことを行う (※1)」。
--------------------------------------------------
このように、「快楽主義的」とは、「経済合理的」とも言い換えられています。
「快楽主義的」な人間は、自分を拘束する条件を受け入れ、それに逆らおうとはしません。与えられた条件の下で、自分の欲求を満たすように合理的に行動するのです。「さらに快楽主義的な動機は、決断力に乏しく、旧来の軌道にとどまる人の特徴ともなっている (※2)」とシュンペーターは付け加えています。
要するに、「快楽主義的」=「経済合理的」な人間は、イノベーションを起こすような者ではないということです。
(※1) J・A・シュンペーター著、八木紀一郎・荒木詳二訳『シュンペーター 経済発展の理論』(初版)(日経BP/日本経済新聞出版本部)2020年、P127-8
(※2) シュンペーター(2020,p132)
「行動の人」
それでは、「快楽主義的」な人間と対比される、「精力的」な人間とは、どのような人なのでしょうか。
シュンペーターによれば、「精力的」な人間とは、自分を拘束する条件に抵抗し、新しいことをやらずにはいられないようなタイプの人です。それは、「行動の人」です。「精力的」な人間あるいは「行動の人」は、「快楽主義的」な人間とは異なり、社会の同調圧力や習慣といった拘束にはとらわれません。
--------------------------------------------------
「行動の人」(Mann der Tat)は、経済の分野でも、既存の軌道の外にあっても、その内にある場合と同じ強さで決然と行動する。今までなされたことがないという事実は、彼にとって行動をためらわせる理由とはならない。通常の経済主体にとって行動を規制する固い枠となっている障害は、彼には感じられない。彼が予見するさまざまな可能性も、それがすでに実現されているかどうかという基準で区別されることはない。彼はすべての可能性を同じ明瞭さで見て取り、そのなかからこだわりなく選び取るのである。すべての可能性が、彼にとって同じように現実的なのである。(※3)
--------------------------------------------------
シュンペーターは、「精力的」な人間は、「快楽主義的」な人間のように、与えられた環境に適応しようとはしないことを強調します。
シュンペーターは、精力的な「行動の人」がやることは、「偉大で創造的な芸術家たちが彼らの技芸にある伝統的な要素を使ってそうするのと同じ (※4)」だと述べています。
このことから分かるように、「行動の人」こそが、既存の物や力をまったく新しい形で組み合わせる「新結合」すなわちイノベーションを行なう者だとシュンペーターは考えているのです。
(※3) シュンペーター(2020,p135)
(※4) シュンペーター(2020,p136)
自分で需要を創造する
さらにシュンペーターは、イノベーションの担い手である「行動の人」には、精力的であることに加えて、もう一つ、重要な特徴があると指摘します。
「行動の人」は、需要に応じて供給するのではなく、自ら需要を創造するというのです。「市場の声を聞く」などという受け身の姿勢ではなく、自分で市場を創造すべく、行動するのが「行動の人」なのです。
--------------------------------------------------
私たちの「行動の人」は、既存の需要やすぐに期待できるような需要に単純に応じるのではない。彼は自分の生産物を市場に押し付けるのである。もっともこうしたやり方は、実業家なら誰もがよく知っていることである。新製品を市場に導入しようとするなら、重要なことは、それを使うよう人々を説得し、場合によっては強制することである。最初は利益を上げるに遠く、損失が出るが、それでも製品の重要な要素に関心をもたせるように努力するのである。(中略)どんな新しい機械もどんな新しい嗜好品も、既存の需要の圧力によって生み出されたものではない。例外的にはそういうこともあるが、その例外もすでに存在する経済発展によるものである。(※5)
--------------------------------------------------
なるほど、言われてみれば、そのとおりです。
企業は、新しい製品を市場に投入する時は、盛んに広告・宣伝を行なって、消費者の購買意欲をかき立てようとするのが一般的です。企業は、新製品を供給した後で、その需要を作り出そうとするわけです。
確かに、画期的な新製品というものは、これまで世の中に存在しなかった製品なので、それに対する需要も世の中には存在しないという場合が多い。
例えば、スティーブ・ジョブズ率いるアップル社がiPhoneを初めて市場に投入する以前に、iPhoneのような製品が欲しいという需要が明確にあったというわけではありません。iPhoneが登場した後で、人々はそれを見て欲しくなり、そこでiPhoneの需要が生まれたのです。つまり、スティーブ・ジョブズという「行動の人」が、iPhoneの需要を作ったのです。
(※5) シュンペーター(2020,p136-7)
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債

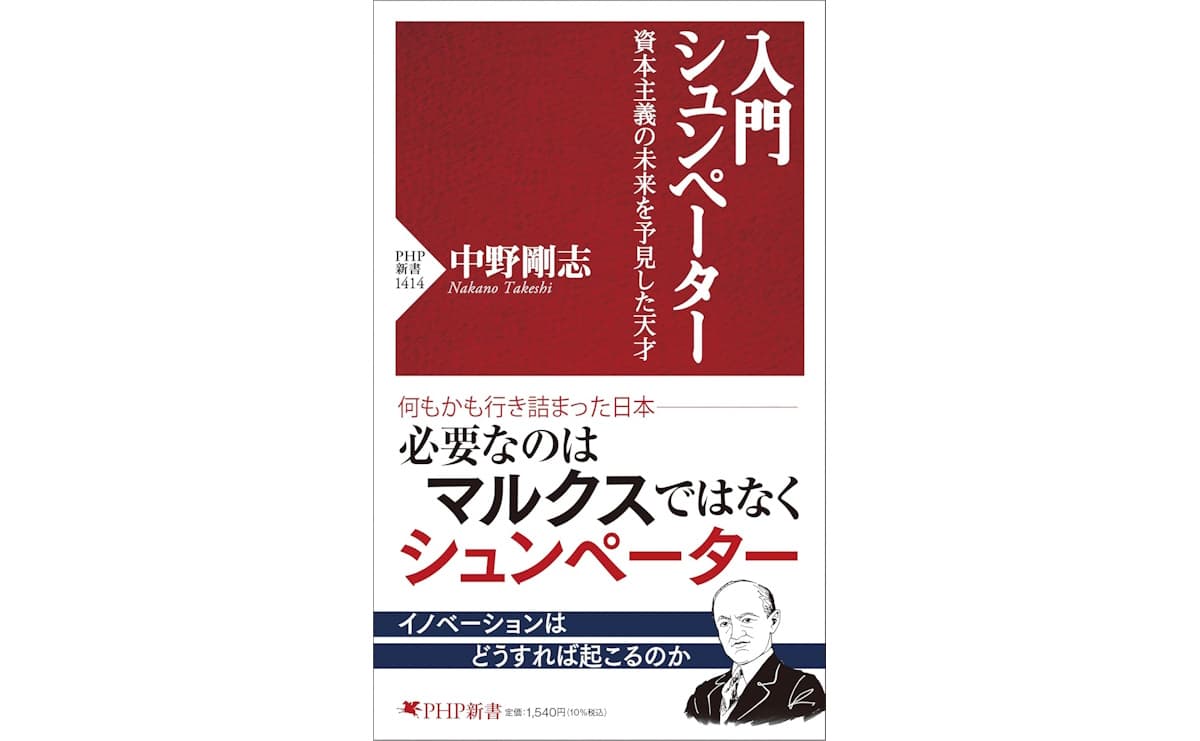
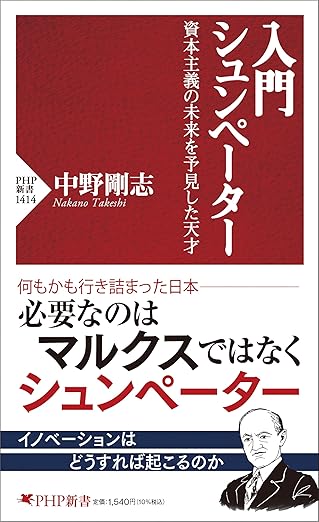





.jpg)
