赤ちゃんは言語をどう学ぶ? 研究者が語る「オノマトぺ」の重要性
2024年04月22日 公開
2024年12月16日 更新

「新書大賞2024」の大賞に輝いた『言語の本質』(今井むつみ/秋田喜美著 中公新書)。同書の共著者と気鋭の哲学者・小説家が、本書の内容をもとに白熱議論。赤ちゃんはなぜ、大人たちが話す「言語」を理解し、習得できるのか。その謎の鍵を握るのが、言語学で長年軽視されてきた「オノマトぺ」だった――
※本稿は昨年9月の代官山 蔦屋書店のトークイベント「言語の本質を探す旅」の内容をまとめた『Voice』(2024年1月号)の記事より抜粋、編集したものです。
【今井むつみ】(慶應義塾大学教授)
1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。94年ノースウェスタン大学心理学部博士課程修了。慶應義塾大学環境情報学部助手などを経て、2007年より現職。専門は認知科学、教育心理学。著書に『学びとは何か』『英語独習法』、共著に 『言語の本質』など。
【秋田喜美】(名古屋大学大学院准教授)
1982年愛知県生まれ。神戸大学大学院博士課程修了。博士(学術)。大阪大学大学院講師を経て、現職。専門は認知・心理言語学。著書に『オノマトペの認知科学』、共著に『言語類型論』『言語の本質』 など
【千葉雅也】(立命館大学大学院教授)
1978年栃木県生まれ。東京大学大学院総合文化 研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は哲学・表象文化論。著書に『動きすぎてはいけない』(紀伊國屋じんぶん大賞、表象文化論学会賞)、『勉強の哲学』『現代思想入門』(新書大賞2023)、『デッド ライン』(野間文芸新人賞)、『センスの哲学』など。
「本質」は一つではない
【千葉】私は哲学、文学の観点から、「言葉の実践」に関心をもち続けています。『言語の本質』(中公新書)も刊行後すぐに拝読し、本書への推薦文も寄稿しました。本日は著者の今井むつみ先生、秋田喜美先生と本の内容についてお話しできればと思います。
早速ですが、両先生にお聞きしたいのは、『言語の本質』というタイトルについてです。この本がベストセラーになったのは、内容はさることながら、タイトルで「本質」と言い切った点にあったのではないでしょうか。
実際、タイトルに「本質」とはっきりと書かれていることで、「おっ」と驚き、反応を示した人は多かったはずです。仮に「言語とは何か」というタイトルであれば、これほどの注目は集められなかったと思います。
【今井】言語の「本質」という言葉が、言語学の専門家の間で議論を起こすことは、私も予想していました。人間は生まれながらにして文法知識を持っているとする生成文法の専門家からすれば、本書はとんでもない内容と言えるでしょう。ただ、少なくとも私としてはそんな大それたことを書いたつもりはありませんでした。
一人の科学者として、データとして確認できたものは肯定しますし、データと乖離する見解にはノーと否定します。
また、研究者の立場や考え方によってデータの解釈は異なりますから、そもそも「普遍的な本質」があるとは考えていません。「普遍の本質」ではなく、「my view of essence」、すなわち「マイ・本質」くらいの認識で、秋田先生との共同研究で得た仮説を世に提示したつもりです。
【秋田】私も同じ思いです。「本質」と言うと一つしかないというニュアンスがありますが、私はそうは考えていなくて。『言語の本質』で提示した内容は、あくまでも本質の一部だと考えています。それぞれの立場によって、別の「言語の本質」が議論されてもいい。
見方によって、いろいろな側面があるのが「本質」です。「これが真理だ」と断定するのではなく、よりオープンな議論をめざすべきです。
言語に「身体」は必要か
【千葉】『言語の本質』というシンプルなタイトルとは裏腹に、本書はいくつかのユニットが複雑に組み合わさって成り立っています。オノマトペの研究をベースに、オノマトペの言語学的な評価や正当性、アブダクション推論(仮説形成推論)にまで射程を広げている。決して単純な本ではないですが、あえて言うならば、どこに力点があったのでしょうか。
【今井】いくつかありますが、一つは「記号接地問題」でしょうか。認知科学での、未解決の問題です。1960~90年代までの人工知能は、現代のような「人間の脳細胞」を模したものではなく、人間がコンピューターに記号を与えて問題解決をさせる「記号アプローチ」が主流でした。
しかし、この問題を最初に提唱した認知科学者スティーブン・ハルナッドは、人工知能の「記号アプローチ」を批判し、人工知能が言葉の意味を真に理解するためには、基本的な一群の言葉の意味はどこかで感覚と接地(ground)していなければならないと指摘しました。
つまりは、最初に覚える言葉が、嗅覚や触覚などを含む「身体に根ざした経験」と紐づかなければ、言語を真の意味で理解できないということが彼の論点です。
ハルナッドが提起した記号接地問題は、まさに子どもの言語学習にも当てはまります。たとえば、私たちは外国語を学ぶときに、外国語の辞書(外国語を外国語で定義した辞書)しか情報がなければ、永遠に何かの「意味」にたどり着くことはできません。
同じように、幼児がはじめに「感覚」に接地した言葉を何一つ知らなければ(外国語学習の例で言えば「感覚に接地」した母語を介さなければ)、言語学習は不可能であるということです。
しかし、ハルナッドの指摘が正しければ、子どもはどのように言葉を覚え、巨大な言語システムを獲得していくのでしょうか。
この問いの鍵となるのが、秋田先生と共同で研究してきた、「オノマトペ」です。オノマトペは、音形が感覚につながっているという点で、「身体的」な言語と言えます。
「アメーバ」はなぜ「アメーバっぽさ」があるのか

【秋田】オノマトペは、「もぐもぐ」などのように、皆さんも馴染みのある言葉です。じつは、言語学の世界では長らく、オノマトペは取るに足らない周辺的存在と考えられてきました。ソシュールやホケットといった近代言語学の大御所が主張した「言語の恣意性」という概念に反するものと考えられてきたからです。
たとえば、日本語で「イヌ」と呼ぶ動物は、英語の「ドッグ(dog)」やフランス語の「シャン(chien)」とは、まったく違う音形で呼ばれていますね。
このように、言語記号の音声と意味の結びつきには必然性がない(=恣意的)と考えるのが、「言語の恣意性」を含むソシュールの理論です。
他方で、オノマトペには、言語間で音の類似性が認められており、だからこそ「言語の恣意性」に反する言葉として、言語学では軽んじられてきたわけです。
この傾向は、オノマトペの発達していない英語圏やフランス語圏で顕著で、音で概念を真似るオノマトペは幼稚に映り、それに反発する感覚として、「言語は恣意的だ」という刷り込みが強化されたのかもしれません。
【今井】たとえば、英語のオノマトペは、未発達ではありますが、動詞や名詞の多くに、オノマトペ的な「音象徴性」が組み込まれていますね。中国語は音自体がオノマトペ的ですし、形態は違っても、「音象徴性」はどの言語にもある現象と言えるでしょう。
【秋田】たとえば、英語であれば、「スケルトン」。すごく骨格って感じがしないでしょうか? あるいは、「アメーバ」は、すごくアメーバっぽいですよね。
【千葉】たしかにしますね。本当にそうなのかと、なぜか身構えてしまいますが(笑)。
【秋田】あるいは、螺旋を意味する「スパイラル」。この単語を知らない人に「ジグザグと螺旋、どちらの形がスパイラルという感じがするか」と実験で尋ねると、ほぼ当たります。
日本語でも、「硬派(こうは)」と言うと、硬い感じがするし、「軟派(なんぱ)」の「なん」という音は柔らかい感じがする。言語記号と音声の相関は、オノマトペ以外の言葉にもたくさんあるはずなのに、この話をすると皆さん笑うんです。
【千葉】本書でも引用があったタケテ/マルマ効果ですね。尖った図形と曲線的な図形を2つ見せて、「タケテ」と「マルマ」どちらかの名前かを判断させる実験です。
このように問うと、大多数の人が尖った図形に「タケテ」とつけ、丸みのある図形に「マルマ」とつけたという結果が出た。いまも反証はされていないのですか?
【秋田】言語によって割合が違うという説はありますが、反証した人はいません。
【今井】タケテ/マルマ効果が、言語を学習する前の赤ちゃんにも当てはまるのかどうか。それを知るために、実験を重ねました。
音と図形が対応した組み合わせと対応しない組み合わせを示し、赤ちゃんの脳波を調べたところ、反応が明確に分かれました。興味深かったのは、音と図形が対応していないと、赤ちゃんの脳が情報を統合することに苦労していたことです。
「言葉を理解する」ためには、聴覚と視覚の認知が統合されなければなりません。音と形が合致しない組み合わせの場合、両者を統合するための情報処理にかなりの負荷がかかっていたということです。
反対に、音と形が合致した組み合わせでは、脳に負荷がかからずにスムーズに言語学習が進むことがわかりました。
【千葉】つまり、言語の対象と音には生得的なマッチングがある、ということでしょうか。
【今井】そのとおりです。話を敷衍すれば、言語学習は文法のような「知識」ではなく、生物として生まれもった反射のような現象から始まるとも言えます。どの赤ちゃんでも同じ結果が追認されたのは、言語習得の入り口が人類普遍だからでしょう。
言語習得のグラデーション
【千葉】「言語習得の入り口は人類普遍だ」という話は、けっこうすごいことですね。少なくとも、哲学・思想や文化・社会理論を研究する分野では、これまで素直に認めることができなかった。
一方で、身体感覚から遠く、音象徴性が薄い記号同士の差異でつくられているような「デジタル的な言葉」もあります。そちらのほうがソシュールの言う「恣意性」で説明しやすいでしょう。
しかし、僕らが最初に覚えるのは、オノマトペの延長のような、アナログで身体感覚に根ざした原始的な語彙であり、そこからのグラデーションとして「デジタル的な言葉」が派生してくる――。本書では、そういうビジョンを提示しているわけですね。
【今井】そのとおりです。赤ちゃんは、アナログな「知覚」から言語習得をスタートさせますが、すぐに単語や文の意味を発見し、知識を構築します。その知識を使って、また次の学習をする。「何々とは何か」を推論によって、永遠に洞察していくことで、知識の再編成とアップデートを繰り返していくわけです。
つまりは、新しい言葉が入るたびにその再編成が加速する学習サイクルが起動しているわけですね。私はそこに、「記号接地」と同じように、「言語の本質」を見るわけです。
【千葉】言語の本質に迫る研究が成り立つことに、とても勇気づけられます。
【今井】ありがとうございます。本書を幅広い立場の方に、それぞれの興味の持ち方で読んでいただけたことは、本当にありがたいです。本日議論できたことも幸せなことでした。ありがとうございました。
Voiceの詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 「チクショー。やめろ」 オウム真理教・麻原死刑囚最後の日
- 「高市首相は強力な味方だ」トランプ政権キーパーソンが断言
- 「大阪都構想」が反対派からこれほど“毛嫌い”される理由
- “高学歴な人”ほど左派政党を支持する「先進国の現実」
- “日本の若者は右傾化”したのか? リベラル台頭の裏にある不都合な現実
- 自民党が生き残る唯一の道は「伝統保守」への回帰 なぜ所得再分配が必要か
- イーロン・マスクがトランプ支持に転じた「本当の理由」 保守派を超えた広がり
- 「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
- 橋下徹が解説する、日本で「国民が首相を直接選べない」理由
- 繰り返された「その場しのぎ」の政策...痛みを避け続けたメルケルの16年間が残した負債




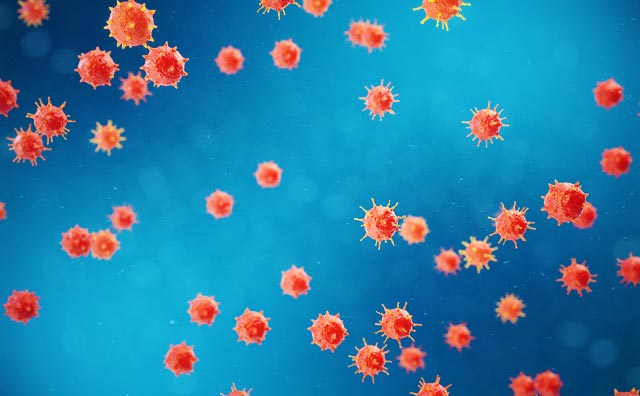
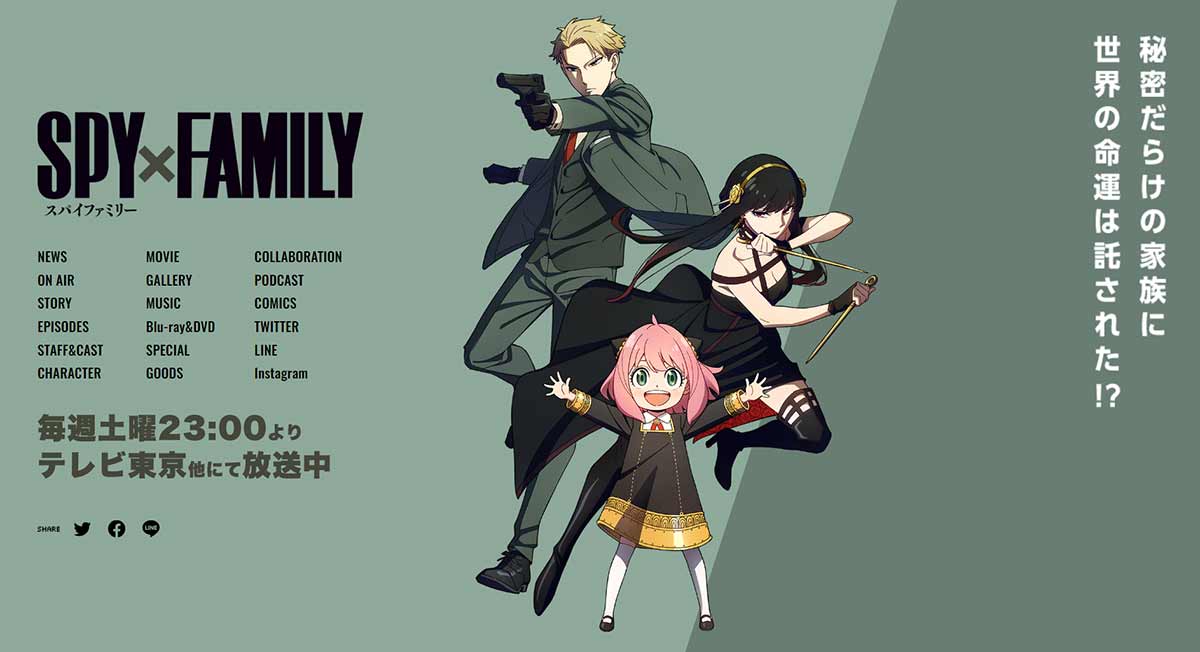

.jpg)
